東南アジア農業生態学学習イニシアチブ(ALiSEA)は最近、メンバー組織(ASINCV、SPERI)と連携し、ゲアン省フークイ果物・工業作物研究センターで農業生態学の発展における連携を強化し、知識と経験を共有するプログラムを組織しました。

ALiSEA代表団がフークイ果物・工業作物研究センターを訪問。写真:キエウ・チ
かつてタイヒエウ熱帯植物試験場として知られていたフークイ果物・産業用植物研究センターは、1960年4月に農業食品産業省によって設立されました。過去60年間、同センターは特にフークイ地域、一般的には北中部地域の生産のゆりかごとしてみなされ、多くの種類の産業用植物や在来果樹の試験、保存、開発において重要な役割を果たしてきました。
現在、センターは、柑橘類の品種、ゴムの木、サトウキビ、そして生態農業の原則に基づいた持続可能な農業モデルの研究開発に重点を置いています。センターは毎年、地域の農家や協同組合を対象に、柑橘類の栽培と管理技術に関する研修コースを10~15回開催しています。
同センター副所長のファム・ティ・サム氏は、「生態農業の開発において、私たちは特に地元の種子源の利用、化学物質の投入量の削減、間作モデルによる生物多様性の向上、土壌の被覆と適切な輪作を重視しています。これは、農家が土地を守り、持続可能な収入を増やすための解決策です」と述べました。

フークイ果樹・産業用樹木研究センターにおけるサトウキビとゴムの混作実験モデル。写真:キエウ・チ
サム氏によると、センターではゴムとサトウキビの混作モデルを実験している。「短期的な利益を得て長期的な利益を得る」というこのモデルは、雲南省ゴム研究所(中国)の経験を参考に、センターが1年間かけて試行したものだ。サトウキビは4mの畝間隔で混作し、ゴムの畝間は16~20mの帯状に植える。これにより土壌を覆い、雑草の抑制、水分の保持効果があり、同時に高い経済効果も得られる。
実際、センターにおける在来植物品種の保存と開発は、支援体制と資金の不足により多くの困難に直面してきました。しかし、研究チームは貴重な遺伝資源の保存と修復に粘り強く取り組んでいます。サム氏によると、センターの発展の方向性は、研究と実践、 科学と農家を結びつけ、環境と地域社会に責任ある農業を目指すことです。
センターは、生態農業の13原則の研究、移転、そして経営と生産における応用に重点を置いており、生態・経済・社会の3つの要素のバランス、地域資源と品種の活用、化学物質の削減、そして生物多様性の確保(間作)を重視しています。間作普及モデル、特にセンターの機械化を適用した90ヘクタールのサトウキビモデルは、労働コストと生産コストの削減に大きく貢献していることが実証されています。
ALiSEA代表団によるフークイ果物・工業作物研究センターへの訪問とワーキングセッションは、技術交流の機会であるだけでなく、地域における生態学的農業の実践イニシアチブを連携させる機会も創出します。これにより、加盟団体は気候変動に適応した環境に優しい農業モデルを学び、普及させることができます。
出典: https://nongnghiepmoitruong.vn/can-co-che-khuyen-khich-bao-ton-giong-cay-an-qua-ban-dia-d778696.html




![[写真] 深海の砂の堆積物、古代木造船アンバン号が再び埋もれる危機に](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/13/1763033175715_ndo_br_thuyen-1-jpg.webp)


![[写真] トゥオン族の仮面を描くユニークな芸術](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/14/1763094089301_ndo_br_1-jpg.webp)







































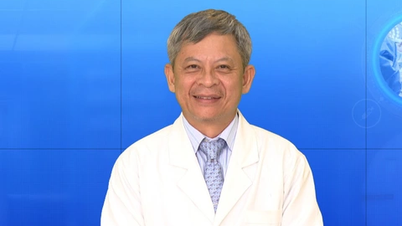























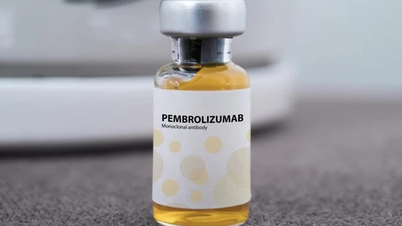























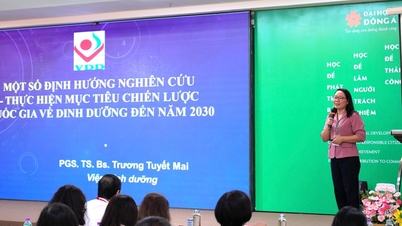





![ドンナイ省一村一品制への移行:[第3条] 観光と一村一品制製品の消費の連携](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/10/1762739199309_1324-2740-7_n-162543_981.jpeg)






コメント (0)