 |
| 国会議員代表のグエン・ティ・キム・トゥイ氏は国会で、積極的な人的資源と財源なしに教育改革をうまく進めるのは難しいと述べた。 |
大学の自治権は「制約的」か「非常にオープン」かという議論
ブイ・ティ・クイン・トー副学長( ハ・ティン氏)によれば、大学の自治の実施においては一定の成果はあるものの、財源の調達には課題があるという。
代表は、調査によって、自治制度によって大学間の競争が激化していることが示されたと述べた。大学は採用しやすい研修プログラムを追求する傾向があり、それが国家の人材育成戦略に不均衡をもたらしている。
「多くの大学では、特に修士課程の教育において、学生や研修生のインプットとアウトプットの質、教育と研修の質はもはや最優先事項ではなく、収入源と採用できる学生や研修生の数の方が重要になっています」とトー氏は述べた。
この代表は、高等教育法と高等教育を規制する他の多くの専門法との間に一貫性が欠けているため、自治を実施するための手段と政策は依然として限られており、多くの学校に困難をもたらしていると述べた。
人事管理に関しては、公立大学は採用、採用、人事異動、任用などを独自に決定することはできず、公務員法および管理機関の規定に従わなければなりません。そのため、職員の採用や、適切で質の高い人材の配置が困難になります。
財政に関しては、高等教育法と国家予算法、公共資産の管理および使用に関する法律が同期していないため、多くの障壁があります。公共サービス部門は5年ごとにロードマップに従って予算を削減する必要があり、教育機関の支出はますます厳しくなっています。
そのため、ブイ・ティ・クイン・トー代表は、高等教育機関ネットワークを早急に計画する必要があると提言した。このネットワークは、国家の社会経済発展戦略、経済地域および地方の発展方針と密接に連携する必要がある。
「高等教育機関の計画は学校の階層化に基づいて行われなければならない。国内のすべての学校に適用される一般的な規制はない。」
同時に、自治と自治の実施は高等教育機関の自己責任と並行しており、自治が強まれば強まるほど、責任も大きくなるという原則を徹底的に理解する...
国家予算の支出に関しては、教育分野への通常支出を開発投資支出として捉えるべきです。そうすることで、国家はより合理的な投資配分戦略を策定し、設定された目標と方向性に沿って、教育訓練分野、特に高等教育を発展させることができるでしょう」とトー氏は提案しました。
クイン・トー議員による、大学は規制によって制約されているため、自立することはできないとの発言についての議論で、ド・チ・ギア議員(フー・イエン)は、学校が適用すべき「独自の」規制が依然としてあると述べた。
「時に、それらは非常にオープンな政策となる」とングイア氏は断言した。
ギア氏は自身の主張を裏付けるように、法令第81号により、教育プログラムが認定されれば、各大学は独自の授業料を設定できるようになると述べた。これにより、授業料の値上げを狙った認定取得競争が激化している。実際、大学の授業料は現在非常に高騰しており、授業料を徴収するために、通常の専攻ではなく、質の高い専攻を開設している大学もある。
「BOT事業であれば、古い道路はそのまま利用でき、資金力のある人は新たな投資で新しい道路を利用できます。しかし、現状では多くの学校では、BOT道路しかないため、授業料が2,000万、3,000万、さらには6,000万ドンも値上げされている専攻があります。質の高い専攻もあるのに、入学時の点数は通常の専攻より低く、追加される科目もわずかで、検査が完了した後に授業料が値上げされるのです」とギア氏は比較した。
「間違いには解決策がある」
今朝の討論セッションでは、キム・トゥイ副大臣が、2018年度一般教育計画の策定と、新しい教科書の編纂・出版・配布を予定通り進める上での教育訓練省の多大な努力を称賛しました。また、トゥイ副大臣は、教育訓練省と教育界全体が単独で解決することが困難な人員と財政の課題についても言及しました。
「国全体が大きな期待を寄せている教育改革に取り組むには、人材と資金という2つの最も重要な要素があり、積極的に取り組まなければ、うまくやっていくのは難しいだろう」とこの代表は語った。
しかし、トゥイ氏によると、教育訓練省が綿密に調査し、速やかに地方指導者と協議し、首相に解決策を報告すれば、困難や障害、違反は解決できない問題ではないだろうという。
トゥイ氏はスピーチの中で、困難と問題点についてのみ言及し、具体的に3つの点を指摘した。
まず、「ベトナム教育出版社(省の管轄事業)における違反行為は、不適切な指導的人材の任命や綿密な検査・監督の欠如といった統治機関の責任もあって、刑事訴追されなければならない」
第二に、一部の教科書の誤りと、来年度における教科書不足の可能性について、トゥイ氏は、教育省と教育界の困難さは認識しているものの、「教育省と出版社が批判を容認する姿勢こそが、有権者の不安を招き、世論を揺るがしているのだと思います。現状では、ほとんどの批判や提言に対して、出版社や教育省は反応を示していません。場合によっては、その対応が現実に即していないこともあります」と述べた。
トゥイ氏は例を挙げた。「私の質問に対する書面による回答で、大臣は次のように断言しました。『ベトナム教育出版社は、知識と生命を結びつける省の書籍11万冊を回収・修復し、6年生の自然科学の書籍3万8000冊を破棄・再版しました。
しかし、多くの学校の先生方からのフィードバックによると、教科書は新しい教科書に置き換えられていないようです。どの情報が正しく、どの情報が間違っているかを知るには、教科書の査定記録を確認すればいいのです。教科書が改訂されたのであれば、いつ改訂されたのか、査定委員会の設置決定やその議事録は残っているのか、あるいは大臣の承認決定はあるのか…?
この件でロビー活動や裏切り行為といった現象を断固として摘発し、対処しなければ、教育分野における設備入札の刑事事件と同様の事態に陥るだろう。
第三に、トゥイ氏は、最も懸念されるのは、書籍選定における透明性と客観性の欠如だと述べた。これは「教科書の編集、出版、流通を行う組織や個人間の競争を阻害し、教科書の質を継続的に向上させることは教師と学習者の利益となるだけでなく、不健全な競争を助長し、社会化政策を徐々に歪め、この分野における社会化を消滅させ、かつての独占状態へと逆戻りさせる可能性もある」と指摘した。
上記の理由から、トゥイ氏は「政府は、検査、点検、摘発、そして違反の迅速な処理を組織的に行うよう指導すべきである。同時に、教育訓練省に対し、通達第25号の不合理な規定を早急に見直し、直ちに改正するよう要請すべきである」と勧告した。
そして2つ目の勧告は、「国会と政府は、中央委員会決議第29号に記された『学習教材の多様化』と国会決議第88号に規定された『教科書編纂の社会化』の政策を継続的に実施するため、教育法の改正を検討する」というものです。
[広告2]
ソース



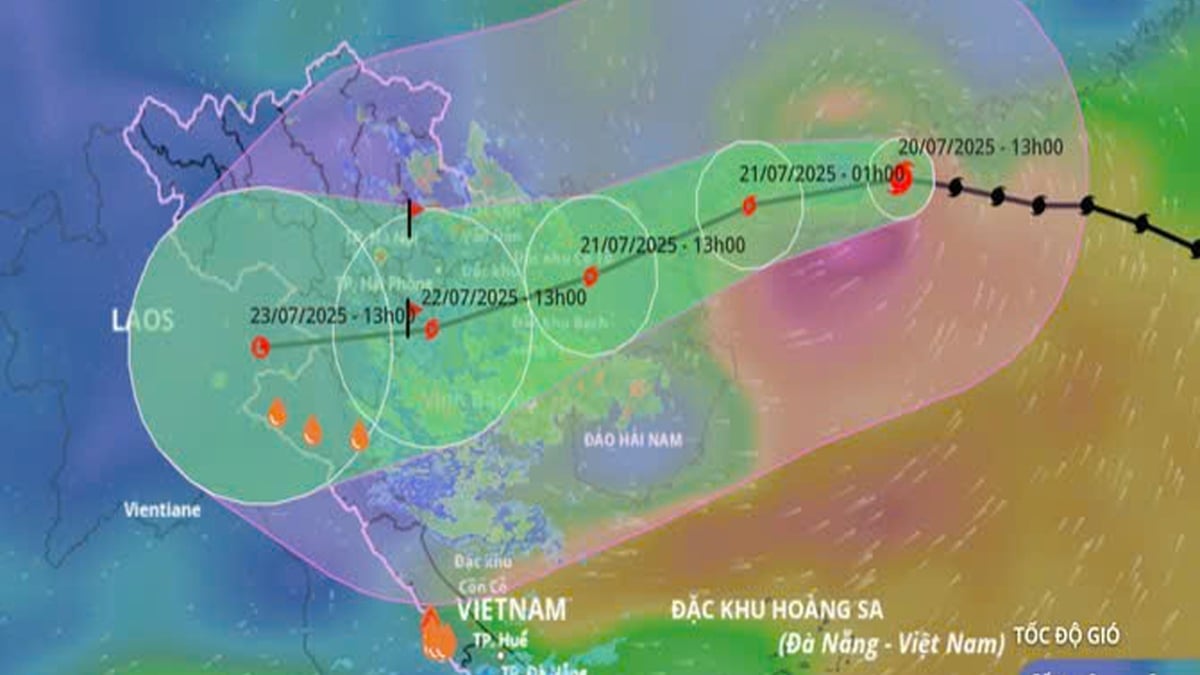





























































































コメント (0)