すべてがきちんと整頓されたモダンなアパートに漂う、馴染みのある新しい木材とコーヒーの香り。ロングにとって、この家はただの資産であり、処分するべきものだった。
彼はリビングルームに入った。そこは彼女が生きていた当時と全く同じだった。ソファはすり切れ、コーヒーテーブルは色あせ、壁には古い写真が飾られていた。彼は心が沈んだ。
「ロング、家を売らないで。古いのは分かってるけど、あなたの一部なんだから…」彼女の言葉が頭の中で何度も反響したが、彼はそれを無意味なノスタルジーとして無視した。
ロングは価値がないと思われた古い品々をちらりと眺めた。その時、電話が鳴った。骨董品商からのメッセージだった。「ロングさん、箱を買いに来ました」

長い間、彼は眉をひそめ、苛立ちを覚えていた。ただ全てを終わらせ、この重荷から解放されたかった。木箱を開けた。中には黄ばんだ写真と、優美な筆跡の手紙、そして小さなオルゴールが入っていた。彼はオルゴールを巻きながら、呟いた。
- 思い出はお金で売れるのでしょうか?
ロングがこれまで聞いたことのないようなメロディーが流れ始めた。その音は彼の心に染み込み、部屋の音が消え去った。
***
箱から奏でられる美しい音楽に、ロンの周囲の空間はガラスの破片のように砕け散った。冷たい風が吹き込んだ。ミルクフラワーの強く甘い香りが、あらゆる細胞に染み込んだ。ロンは深呼吸をし、胸が奇妙な感情で満たされるのを感じた。
遠くから、聞き覚えがありながらも心に響く「カラン」という音が響いた。電車の音は急ぎではなく、ささやくような響きで、彼を別世界へと誘った。
ロンは、苔むした瓦屋根と古木が並ぶ通りに立っていた。時は半世紀も遡り、若き日の祖母の姿が目に浮かんだ。優雅なアオザイをまとい、髪を三つ編みにし、バディン・バイクに恥ずかしそうに乗っている姿。そして、ハンサムな祖父が明るく微笑んでいる姿が目に浮かんだ。
父親の緊張を感じ、彼女の震える手が自分の手に触れたのを感じた。列車の「ガタン」という音は、初恋のサウンドトラックになった。ロングはまるで神聖な何かを逃したかのように、心が震えるのを感じた。
***
ロンの目がかすかに瞬いた。オルゴールの音楽が、より緊迫感があり、ノスタルジックな雰囲気へと変わった。辺りが突然暗くなった。ロンは、泥と雨の匂いを帯びた冷たく湿った空気が流れ込んでくるのを感じた。彼は彼女のもう一つの記憶、雨の午後のハンベ市場に「足を踏み入れた」。
雨が降り注ぎ、古いトタン屋根を叩く音は力強い歌のように響き、他のあらゆる音をかき消していた。ロングは、雨宿りをする人々と共に、みすぼらしいポーチの下に立っていた。その空間は狭苦しかったが、人の温もりに満ちていた。
「この雨じゃ、一日中野菜なんて誰も買えないわ」と、雨音に混じった声で若い女の子が文句を言った。髪はびしょ濡れで、既にびしょ濡れのシャツに水が滴り落ちていた。
霜のような銀髪をした野菜売りの女は、少女の髪を撫でながら優しく微笑んだ。
- じゃあ一緒に座りましょう。価値あるよ!
彼女は蓮の葉に包まれた、まだ熱々のもち米をそっと開けた。もち米の香りと蓮の葉の香りが混ざり合い、ロンの嗅覚の隅々まで染み渡った。彼女はもち米を一切れちぎり、少女に渡した。
- お腹を温めるために食べましょう!
少女はためらったが、野菜売りは譲らなかった。すると肉屋も包丁を握ったまま、ポケットから餅の袋を取り出し、皆に差し出した。皆は一緒に座り、餅米の袋と餅を一つずつ分け合った。笑い声、質問、愛する人への心配…すべてが雨音と混ざり合った。その日、市場の人々の間に生まれた愛は、ただ雨が降るだけで、とてもシンプルだった。
ロンはそこに立ち、人間の愛情の温かさを感じていた。そして、一見価値のないものに思えるものこそが、実は最も大切なものだと、ふと気づいた。
***
オルゴールのメロディーがより美しく、ゆっくりとなっていくにつれ、ロングは不思議な温かさに包まれるのを感じた。彼はもはや昔の部屋ではなく、笑い声に満ちた庭の真ん中に立っていた。
目の前には簡素な結婚式があった。豪華なテントも高級車もない。ただ、真っ赤な「Double Happiness(二重の幸福)」の文字が書かれたバディン自転車が待っていた。自転車は壊れやすかったが、ロンはその頑丈さを感じた。それは、シンプルでありながら確かな未来への約束のようだった。
結婚式の宴は緑茶とピーナッツキャンディ、そして緑豆のケーキだけで済んだ。しかし、会場は笑い声と歓声で溢れていた。人の愛情はどんなご馳走よりも温かいものだった。
その日、ロンは幸せいっぱいに祖父母を見つめた。彼は白いシャツを着て、きちんとボタンを留めていた。祖母はクリーム色のアオザイを着て、髪をきちんと三つ編みにしていた。彼の隣に立っていた彼女は、恥ずかしそうだったが、喜びに目は輝いていた。
彼らの傍らには、魔法瓶と綿の毛布という簡素な結婚祝いの贈り物がありました。ロングは、これらは高価な贈り物ではなく、愛と分かち合い、そして心からの祝福の象徴であることに気づきました。
***
オルゴールが突然止まった。ロンは目を覚まし、今いる部屋に戻った。部屋はもはや空っぽではなかった。思い出の香りがまだそこら中に漂い、祖母の遺品を、敬意と感謝の念に満ちた、これまでとは違う視線で見つめていた。
ちょうどその時、ドアをノックする音がした。骨董品商は興奮して言った。
- ロンさん、箱を買いに来ました。
「違います。この箱は骨董品ではありません。これは私の遺産です。私のハノイです!」ロングは考えもせずに答えた。骨董品商は当惑した表情を見せ、それから踵を返して立ち去った。
ロングの視線はもはや急がなかった。彼は静かに窓辺に腰を下ろした。彼女がよく座っているのを見かけた場所だ。部屋の冷たく不慣れな雰囲気は消え、馴染みのある温かさが取って代わっていた。
彼は窓の外を見た。ハノイは相変わらず、喧騒の交通と高層ビル群が続いていた。しかし今、彼はもはや距離を感じなかった。ロンの目には、街はもはやコンクリートと鋼鉄の塊ではなく、スローモーションの映画のように映っていた。もち米を売る老婦人の姿が見えた。彼女の屋台は小さいながらも、彼女の人生のようにしっかりとしていた。若いカップルが手をつないで通りを歩いているのが見えた。そして彼は、心からの真の愛は、時の流れに関わらず、いつまでも変わることなく残るのだと、突然悟った。
ゆっくりと目を閉じた彼は、どんなお金よりも大切なものを見つけた。それは、自分のルーツだ。ハノイは行く場所でも、到着する場所でもない。帰る場所なのだ。
出典: https://www.sggp.org.vn/gia-tai-cua-mot-tinh-yeu-post821280.html




![[写真] ラムドン省:トゥイフォン湖の決壊の疑いのある被害画像](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/02/1762078736805_8e7f5424f473782d2162-5118-jpg.webp)
























































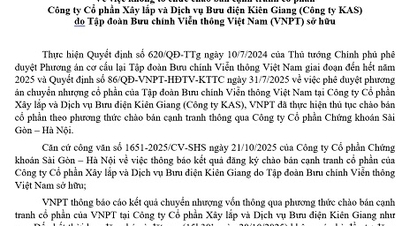















































コメント (0)