
サンは半月以上も病院で一人ぼっちだった。誰も食事を持ってきてくれず、飲み会にはいつもたくさんの友人を招いていたにもかかわらず、見舞いに来る友人は一人もいなかった。飲み仲間が褒めるように、サンは常に「フェアプレーヤー」であることを誇りに思っていたため、どれだけ仕事をこなしても、友人の好きなようにさせてあげていた。また、危険な時には友人を救う「ヒーロー」になることも多かった。ある時、借金を抱えた友人に施すため、母親が飼っていた牛を夜まで連れて行き、近所の人に売り飛ばした。雨季には雨漏りがひどく、ベッドさえ洗面器の上に置かなければならなかったが、サンは友人の父親がトタン板の葺き替えを手伝うため、2日間も屋根に登ることを厭わなかった。そのため、サンの母親が外に立って中を覗くと、息子が何度も屋根を登り降りしているのが見えた。サンが蘇生したら、他の誰かの子供を家に連れて帰ることになるのかどうか、彼女は混乱していた...
サンの友達は困った時はいつもサンのところに駆けつけてくれた。夜になると、サンの両親は「親友」たちの大きなノックの音に何度も驚かされた。「クソったれ」の息子は飛び起き、服を着て逃げ出した。空が轟音を立てても、両親の忠告など気にも留めなかった。しかし、人生には「でも」というものがある。サンが病気で困っている時、どの友達も「おい」と返事をしてくれなかった。尋ねても、一人は家を留守にしていたり、一人は忙しく話していたり、母親の牛を売って借金の返済をしてくれたり、雨が降ると飛び上がって家の屋根を葺いてくれたりした親友たちは、様々な理由で姿を消した。
外では、川の波が打ち寄せる音が、サンの父親が船を桟橋に係留する足音に似ていた。ある日、今日と同じようにどんよりとした空で、父親はゆったりしたレインコートを着て、水瓶の横にまだ身をよじっている魚の束を投げ入れて、波止場から帰ってきた。父親はサンに火をつけて粥を炊くように言い、自分は急いで魚を捌いた。父と息子が夕食をすすりながら食べている頃には、すでにあたりは暗くなり、壁には父親の影が映り、エビのように反り返った背中がサンの目を刺した。湯気の立つ魚粥の鍋からも煙が少し出ており、サンはこっそりと濡れた目をこすった。
今夜、シロアリに食われている家の中に横たわりながら、サンは突然父親が恋しくなり、喉が詰まるほどだった。父親が胡椒を振りかけ、水差しからコリアンダーの茎を数本摘み取ってくれた、熱々の魚粥が恋しかった。満天の星空の下、ポーチに座り、棘だらけの道を眺め、足をざらざらしたレンガの床につけ、道を渡る川風の音を聞きながら、サンは父親がタバコを吸いながら、遊んだ後は早く家に帰り、田舎の友達の後をついて人生を無駄にするなと呟いているのが聞こえた。父親の額にはしわが寄っていたが、目と笑顔は大地のように穏やかだった。
サンの父親がご飯を炊くためにゴザを敷いていた敷居には、今ではシロアリが山積みになっている。母親が生きていた頃、サンが夕暮れ時に帰宅するたびに、母親が慌ただしくご飯を炊いているのが見えた。米とトウモロコシの鍋は蓋まで溢れかえっていた。母親は座ってトウモロコシの粒を一つ一つ椀にすくい入れ、玄関の前を通るたびにかがまなければならない背の高い息子に、綿のように白いご飯の入った椀を押し付けていた。毎食、魚醤に浸したサツマイモの芽の茹で汁と、父親が叩かなければならないウコンの葉で煮た魚の山があった。母親はそばに座り、ご飯をすくう暇もなく、汗だくになりながらも、まるで家族全員が宴会をしているかのように幸せそうに笑っていた。父は、母が結婚してから4年後には家を建てるお金を貯めてくれたが、今はシロアリが家屋を倒壊させようとしているので、もう少ししっかりした家を建てたいと願っただけだと言った。まず、サン氏が結婚した時に、花嫁をきちんと迎え入れられる場所があること、そして、そこに座る先祖たちが見下ろして誇らしく思えるように。しかし、サン氏が亡くなるまで、その願いは遠い夢のままだった。
サンが丸くなって横たわる窓辺に、満月の影が落ちていた。月は地面を覆い、枝葉一枚一枚を銀白色の層で覆っていた。夜と風が彼を包み込み、まるで不毛の地から引き上げようとするかのようだった。両親の影が心に残り、目がかすむ。鶏が鳴いた。外では、空と大地は霧のようで、川からの風が吹き荒れ、畑を駆け抜けて庭へと追いかけ合っていた。夏の向こう側では、ボロボロになったバナナの葉が数枚ひらひらと揺れていた。サンは急に寒さを感じた。寒さはまだ残っていた。
サンは、父が年を重ねるごとに孤独になっていったことを思い出す。家に帰るたびに、父が杖をつき、埠頭へとゆっくりと歩いていくのがサンには見える。父は川岸に停泊している船を物思いにふけりながらゆっくりと歩く。父は恋人の目を見つめる若者のように、物思いにふけるように川を見つめる。川は無数の急流から下流へと流れていく。父の影は、広大な海の中で不安定で孤独で、形のない孤独が果てしなく川へと流れ込んでいく。父はただじっと立ち尽くし、ただ見つめている。そして静かに振り返る。闘病の日々、父はただじっと横たわり、何も言わず、しおれた顔にはもはや何も映っていない。ハンモックは依然として優しく揺れ、小さな窓から空をぼんやりと見つめる父の視線には、サンの不確かな未来への不安が宿っていた。
夜は徐々に朝に変わった。星々が密集し、暗い空にかすかな青い光を放っていた。サンは、まるでそこに十万の目があるかのように思った。しかし、現れる目は一つだけで、サンはコートを着たまま飛び上がった。サンは川へ向かった。父親のボートは、海へ、果てしない生命へと果てしなく流れる川の脇に斜めに立てられた柱に、まだ錨を下ろしていた。柱には、茶色の三つ柱シャツがまだ残っていた。サンは手探りで川から出た。風がシャツを吹き抜け、冷たい音を立てた。これほど寒い冬が、この細長い土地を襲ったことはなかった。サンはシャツのフラップを引っ張り、乾いた咳が止まらない首を覆った。今までになくサンは、今は母親の薪ストーブだけが自分を温めてくれるのだと理解した。両親が昼夜を問わず薪をくべて燃やしているストーブだ。
サンは、水面に戯れるように揺れる船をじっと見つめたまま、そこに立ち尽くしていた。霧の向こうに、竿の横で懸命に働く男の影が見えた。男は錨のロープを手に持ち、船が座礁しないよう浅瀬を探すかのように水面を見つめていた。「お父さん!」サンは心の中で呼びかけた。男は顔を上げた。力強い額にはまだしわが寄っていたが、笑顔は温かく親しみを込めたものだった。波が激しく打ち寄せていた。向こう岸から流れてきた霧があっという間にこちら岸を覆い、川面に薄く軽い毛布を広げていた。サンは水辺まで歩いた。足が川面についた。水はかじかむほど冷たかったが、それでもサンは前に進んだ。水は足首まで、そして膝まで達した。サンの手が船に触れた。父親の面影は霧のように突然消えた。サンは立ち止まり、ゆっくりと後退し、ホテイアオイの間に漂う月の影を見つめていた。サンの涙がこみ上げてきた。
「息子よ、家に帰りなさい!寝なさい!夜は寒いぞ!」お父さんの声が遠くから聞こえてくるように聞こえました。
上空では、幾千もの小さな星が、千万の粉々に砕け散る川底にきらめきながら落ちていった。サンは父親の目が微笑んでいるように見えた。父親の後ろでは、母親も水に浸かり、砂の中に埋もれたムール貝を掻き集めながら後ろ向きに歩いていた。サンの脳裏に、かすかに燃えさしのついた薪ストーブと、縁側の畳の上に置かれたお盆が突然浮かんだ。どこからともなく、ご飯が炊ける香りと、薪ストーブで煮込まれたウコンで煮込まれた魚の香りが漂ってきた。サンは目を閉じ、息を吸い込んだ。再び藁の香り、薪の煙の香り、そして雨上がりの草の香りが漂ってきた。サンは息を詰まらせ、父親が籠に置いていった古いシャツに顔をこすりつけた。シャツは夜露で冷たく濡れていたが、それでも父親の汗の匂いが残っていた。おそらく何十年経っても、サンは忘れられない匂いだったのだろう。愛の匂い、苦難の匂い…
サンは涙を拭い、静かに決意した。サンはここに残る!やり直す!両親が結婚したとき、彼らには何もなかった。サンは今、小さな家を持っている。それでも多くの人にとって夢のような家だ。そして向こうでは、漁網は毎晩魚やエビでいっぱいだった。サンはここに帰ってきて、田園の息吹と川風を胸いっぱいに吸い込む。サンは父親のように、村の力持ちのように、一生懸命働く。遅かれ早かれ、サンにも両親のような温かい家族ができて、両親を愛し、生まれた場所を愛せるようになる子供たちが生まれる…サンはきっとやり直す!
朝、鶏が鳴いた。両親が帰ってから初めて、安らかに眠ることができた。
VU NGOC GIAOによる短編小説
出典: https://baocantho.com.vn/giac-mo-ve-sang-a195072.html





















































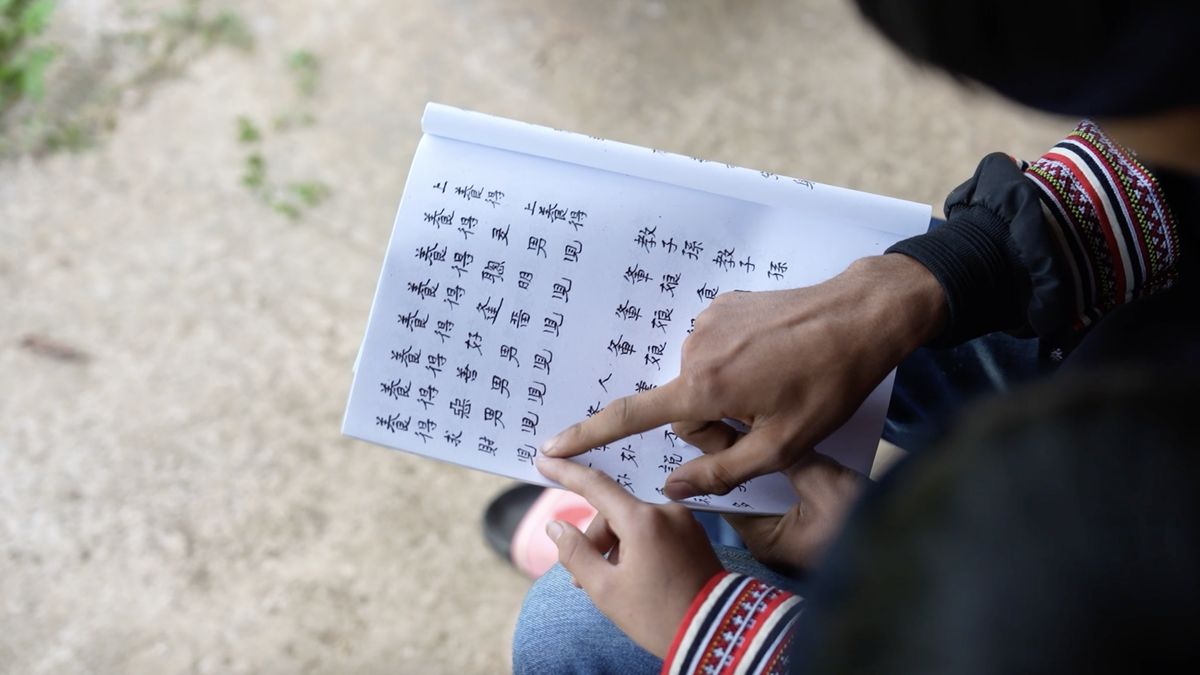




















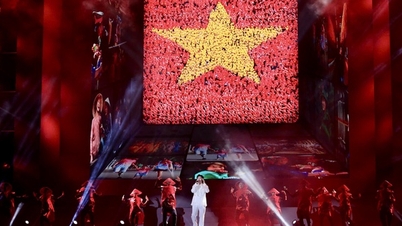




























コメント (0)