州政府の管理機関と独立調査機関のデータはいずれも、企業や個人が依然として債務返済に苦労している2024年第2四半期に不良債権比率が上昇することを示している。

証券化は、既存の解決策の一つである。 不良債権 日本、韓国、中国などの国々では、専門家はベトナムがこの解決策の導入を検討できると示唆している。
不良債権はどのくらい増えるのでしょうか?
2024年第2四半期の上場銀行27行の財務報告に基づくトイチェ統計によると、不良債権残高は2023年末と比較して約45兆ドン(22%相当)増加した。
上記の数値は絶対的な増加率です。金融データ専門会社WiGroupの算出によると、不良債権比率(総未払い債務)は2024年第2四半期末で2.22%に達し、2024年第1四半期の2.18%、2023年第4四半期の1.96%を上回りました。
統合金融ソリューションズ株式会社の創業者、レ・ホアイ・アン氏はトゥオイ・チェ氏に対し、国家銀行のデータを挙げ、第2四半期末時点でシステム全体(上場企業と非上場企業の両方)のバランスシート上の不良債権が5%近くまで増加し、その他の潜在的債務を含めると6.9%になると述べた。
アン氏はまた、上記の比率は全銀行の不良債権水準ではなく、平均水準であると指摘した。そのうち、上場銀行セクター(未払い融資の約80%を占める)は依然として3%を下回っており、残りは主に非上場セクター、あるいは再編中の銀行である。
「これは国内の弱い企業による不良債権であり、経済が困難な状況にあるとき、このグループの企業はさらに不良債権の発生源となる可能性が高く、実際、国立銀行による処理対象に指定されており、現在も指定され続けている」とアン氏は語った。
ベトナムの外資系銀行の幹部は、企業の資本吸収力が弱いため信用の伸びが依然として低い一方で不良債権が増加していると述べた。
同氏は「最近、国内外のマクロ経済状況は厳しく、失業率は高く、生産と事業は衰退しており、借り手が債務を返済できない状況に陥っている」と述べた。
そのため、債務再編メカニズムと債務グループの維持にもかかわらず、不良債権は依然として増加しています。特に、社債市場と不動産市場の悪影響により、不良債権は依然として大手・中堅商業銀行に圧力をかけています。
レ・ホアイ・アン氏によると、現在の不良債権の状況は、全体的な状況に関係しているだけでなく、各銀行のリスク許容度にも左右されるという。
WiGroupのデータもこれを反映している。国営銀行グループの平均不良債権比率は約1.5%、大手民間銀行は2~3%、中小民間銀行は4~6%で、ここ数四半期で急激に増加する傾向にある。
アン氏は、多くの中小銀行が常に高い不良債権を抱えているのは、大手銀行に比べて融資先の顧客基盤の選定能力が低いためだと説明した。中小銀行は顧客基盤の質が高く、経営能力も優れているにもかかわらず、厳しい経済状況の影響で、大手商業銀行や国有銀行の不良債権は依然として増加している。

債務返済猶予の終了に備える必要がある
一方、多くの銀行関係者は、通達02号の期限が切れると債務が適切なグループに再編成され、不良債権が増加するのではないかと懸念している。
解決策については、銀行アカデミーの銀行学部のハ・ティ・ハイ・リー氏が、債務取引市場の開発を推奨した。
また、各銀行自身も、実態に応じて貸倒引当金を積極的に積み増す必要があり、収益の減少も受け入れなければなりません。
銀行アカデミー財務学部の講師、レ・ティ・ビック・ンガン氏は、証券化は日本、韓国、中国、タイなどの国々における不良債権処理の既存の解決策の一つであり、ベトナムも参考にできると述べた。
しかし、そのためには、担保や住宅ローンが売買や交換が可能な証券に変換される流通市場のための明確な法的枠組みを確立することが重要です。
さらに、一部の専門家は、銀行部門や経済に影響を及ぼす不良債権の急増を回避するために、不良債権リスクを迅速に検知して対処するための早期警報システムの開発を提案した。
Tuoi Tre 氏によると、現在、一部の銀行はいくつかの市場データ パーティと連携して、さまざまなレベル、業界、地域に応じた早期リスク識別モデルを備えた独自の警告システムを構築しているとのこと...
ソース










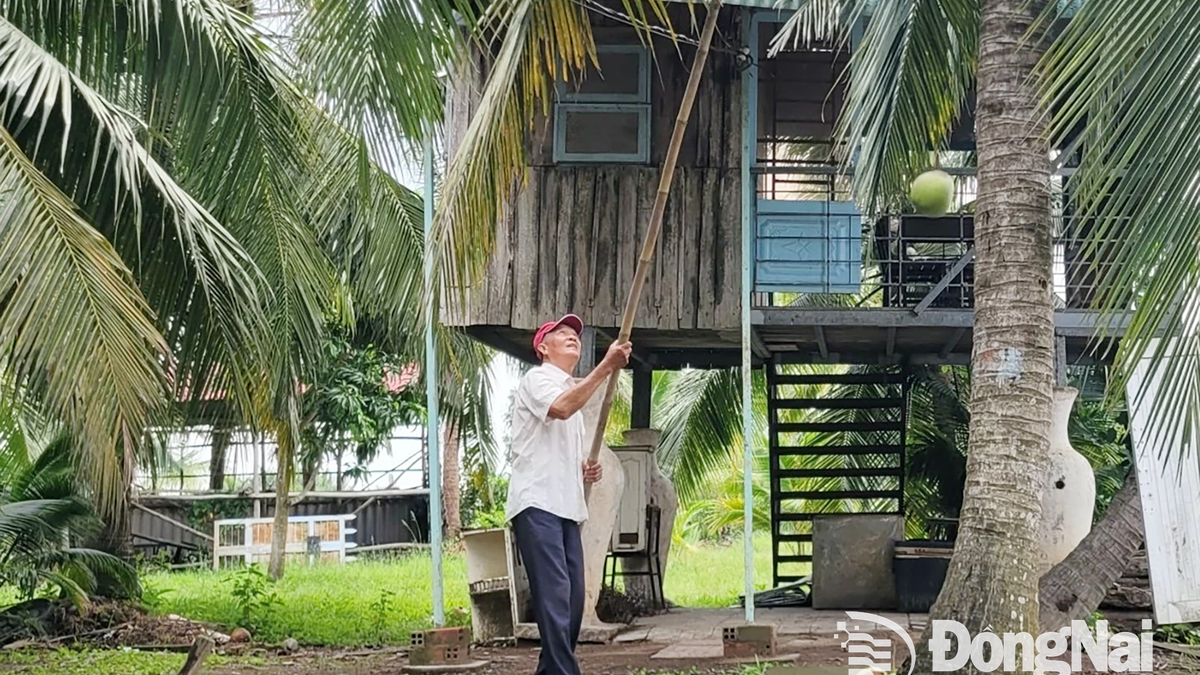



































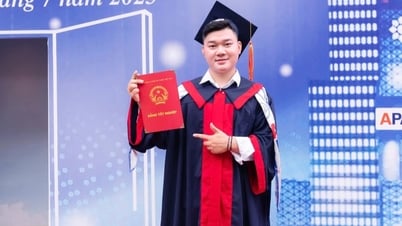



















































コメント (0)