修士課程のフイン・ニ氏は、読書は読者に豊かで豊富な潜在意識の言語資本を育むと信じています。(写真:NVCC) |
自宅読書室・図書室「スイートトマト」の創設者であり、ホアニン高等学校(ロンホー地区、 ヴィンロン)の文学教師であるMSc. Huynh Nhi氏が、ベトナム図書・読書文化の日(4月21日)を機にGioi紙とベトナム新聞にその様子を紹介した。
フイン・ニー先生は、ミエン・ヴオン図書館の共同設立者でもあります。ホアニン学校の生徒たちは、毎月「Touching Books」プログラムに参加しています。「Touching Books」のセッションでは、ニー先生は作家や講演者を繋ぎ、この川沿いのコミューンの生徒たちに読書への情熱を掻き立てています。これは、多くの地域が交流し、実践するモデルケースとなっています。
ニ先生によると、現在、学校では「図書館読書時間」と「図書館授業」を実施しています。これは全教科を対象とした学校全体の方針ですが、やはり文学が最優先です。残りの教科は、生徒たちが図書館で自習する習慣を身に付けられるように、散発的に実施される予定です。
この学校のモットーは、生徒たちに本への愛着を育み、読書の仕方を教えることです。さらに、読書をよくする人たちが「読書体験」セッションを企画し、生徒たちの本への興味を刺激しています。
これらの体験セッションでは、教師たちが頻繁に会合を開き、生徒が本の著者や、読書への刺激を与えてくれる人々と交流し、学習過程における困難を解決し、将来を見据えた学習にも役立つスキルを身につけられるような環境を整えています。同時に、ニ先生の文学グループは「ブックタッチ」セッションも企画し、生徒が交流し、学び合い、経験を共有し、好きな本や読んでいる本を紹介し、議論する機会を提供しています。
フイン・ニさんの「スイートトマト」図書館は若い読者を魅了しています。(写真:NVCC) |
読書をするとき、まず最初に必要なのは、適切な種類の本を選ぶことではないでしょうか?
読書はまず喜びをもたらさなければなりません。もちろん、喜びの定義は人それぞれですが、本は人々が読むための興味を掻き立てるものでなければなりません。そして、読書は人生における問題や困難に対する解決策を見つけるためのものであり、つまり、読者に思考力の向上、共感、そして直面する問題への関心を感じさせるものなのです。
読書の目的に応じて、適切なジャンルやタイトルの本を選定します。例えば、娯楽目的であれば、あまり難解なものではなく、楽しい本を選びます。また、難しい課題を克服する必要がある場合は、それぞれの課題に応じて適切な本を紹介します。したがって、読書文化の発展を促すには、読書年齢、ニーズ、そして読書の目標を明確にすることが非常に重要だと私は考えています。
彼女が発案し、20回近く実施した「ブックタッチ」活動は、生徒たちの興味を惹きつけているのでしょうか?
この活動は、学生が接触空間を広げ、優れた専門資格を持つ人々にアプローチする経験をするのに役立ちます。これにより、共有に加えて、学生が問題を解決できるように方向付け、サポートすることにも貢献します。
私にとって、この活動は読書文化にとって非常に意義深いものです。「ブックタッチ」セッションを企画するために、学校は通常、月に一度実施します。生徒に読んでもらうテーマの本を事前に選び、内容を準備し、そのテーマに適した講師を招いて、生徒と円滑に交流できるようにします。
講演者は通常、教師の友人、あるいは知人を通して依頼されます。実際、学校には大物講演者を招聘する予算があまりありません。これは地域活動でもあるため、招待講演者の多くは、同じ情熱を持ち、地域発展の精神を推進する友人であり、学校のこの活動を熱心に支援してくれることが多いのです。
「タッチブック」は、子どもたちが退屈しないよう、様々な形で行われます。例えば、あるセッションでは、講師が子どもたちの頭上に立ち、具体的な内容について語り、子どもたちが質問をします。また、別のセッションでは、「リビングライブラリー」や「ヒューマンライブラリー」のように、子どもたちを5~6人程度の小グループに分け、講師1人につき子どもたちが直接それぞれの体験談を語り、講師が子どもたちの質問に答えるといった形式も取られます。
生徒たちに読書への愛を育む経験を語るセッションに参加するニ先生。(写真:NVCC) |
あなたの自宅の図書館も、読書文化のかなり良いモデルだと思いますか?
この小さな図書館は、様々な要素が組み合わさって誕生しました。まず、私の本への情熱と、すでに豊富な蔵書が揃っていたことがきっかけでした。その後、学生向けの読書会を企画する中で、地域の方々がより多くの本を支援してくださるようになりました。
実は、我が家の図書館は主に幼児、特に幼稚園児と小学生を対象としています。というのも、私自身も小さな子供がいるからです。子供が少し成長し、これらの本が読まなくなったため、無駄にしておくわけにはいかなくなり、読書の機会に恵まれない他の若い読者と共有できる図書館を設立しようと考えました。
当初は、コミュニティからの積極的な支援や書籍の寄贈など、多くの利点がありました。おかげで、豊富で多様な書籍を入手できる機会に恵まれました。さらに、様々な親御さんに教え、アプローチしていく中で、子どもたちの様々な状況、例えば現代の社会問題の影響による言語能力の低下、集中力の低下、携帯電話への依存などについて、子どもたちが抱える様々な問題を共有してもらいました。彼らも不安を抱え、解決策を見つけたいと願っていました。
本は私たちの生活に役立つ手段です。だからこそ、読んだ内容をどう伝え、生活に活かすかを見つけなければなりません。豊かな人生を送ることは非常に大切であることは誰もが知っていますが、理論を行動に移すのは容易ではありません。ですから、もし私たちが読書家であり、本を愛し、その重要性と価値を理解しているなら、その価値観を積極的かつ大胆に、日々の実践へと落とし込んでいきましょう。 |
それを踏まえ、私は親御さんたちにも、お子さんに読書を奨励するようアドバイスしています。読書は外的要因による悪影響を軽減するのに役立つからです。親御さんが自宅に図書館を設けることに同意し、お子さんに読書の仕方を学ばせ、健全な生活空間を創造するという様々な要素が重なり、このような図書館が設立されました。
家庭の図書館や読書室は、私たちが持っているものや社会のニーズ、子供たちへの愛情、そして社会の多くの悪影響に悩まされている大人の子供たちの癒しから生まれたものであると言えます。
私の読書室のタイトルは「スイートトマト」です。これはベトナム女性出版社が出版した本のタイトルです。この本は、母親がまだ13歳の時に過ちを犯し、母と息子ではなく姉妹と呼び合うようになった少年の物語です。その後、少年は成長し、人生と向き合う中で、母親に教え返す必要に迫られ、成長して母親と共に生きるための生計を立てる方法を探します。
私にとって、これはとても人間味あふれる作品で、人生における多くの美しい価値観を喚起してくれます。何よりも重要なのは、登場人物全員が欠点を抱えながらも、同時にそれぞれの美しさも持っていることです。その美しさに気づけば、人生をより良く生きることができるでしょう。そこで、自宅の書斎、つまり図書館を「スイートトマト」と名付けることにしました。
現在、幼稚園から小学生までの子供向けの本を約1,500冊所蔵しており、ティーンエイジャー向けの本もいくつかあります。大人向けの本については別途分類しており、具体的な統計は取っていません。
粘り強く、若者に読書への愛を育んでください。(写真:NVCC) |
厳選された内容の本のほかに、若者を図書館に惹きつけ、本にアクセスさせる秘訣は何ですか?
実際、本の内容自体がすでに大きな魅力となっていますが、さらに講師の要素にも注目すべきです。これも非常に重要です。講師は触媒のような存在であり、子どもたちが心地よく感じ、交流を受け入れ、読書にどんどん積極的になるよう促すからです。
本を読むことは、一人ひとりに豊かで豊富な潜在意識の言語資本を与えます。そのため、読者の言語による思考力とコミュニケーション能力は飛躍的に向上します。優れた言語能力は、人生の様々な側面を支配するための手段であり、強みとなるでしょう。 |
人生におけるあらゆるニーズにおいて、子どもだけでなく大人も、安心して快適に、そして愛された環境で過ごしたいと思っています。そのため、指導者は子どもたちが安心して、愛情を持って社会と交流できる安全な環境を作る必要があります。
これらは人間の非常に基本的な欲求であり、マズローの欲求段階説(5段階ピラミッドモデルに基づいて人間の一般的な行動と心理を描写した心理モデル)が非常に明確に説明しています。具体的には、安全性、交流、社会的つながり、愛といったすべての要素が揃った環境に住む人々は、幸福感と刺激を得て、常にその環境に住み続けたいと思うようになります。
ですから、子どもたちにふさわしい本を選ぶだけでなく、真に安全な読書環境、そして真の愛に満ちた繋がりと交流を育む環境を子どもたちに提供していきたいと思っています。子どもにお菓子を買ってあげたり、甘い言葉で甘やかしたりすることが愛だと考えるわけではありません。むしろ、特に現代においては、子どもたちと触れ合い、語り合うことこそが、愛を体現する最も実践的な方法なのです。なぜなら、現代の子どもたちは、特に学業成績のプレッシャーにさらされている時など、親と話したり、共有したりすることがほとんどないからです。
読書室に来ると、子どもたちは困惑していることや聞きたいことを率直に話し、共有することができます。例えば、子どもたちに本を紹介し、読んだ後に内容を要約するように促した時、子どもが「できない」と拒否するような場合は、無理強いするのではなく、疑問に思っていることや共有したい内容があれば、それを話し合ってもらうようにしています。
そうすることで、子どもたちが特定のパターンを押し付けることなく、段階的に交流し、成長していく環境が作られます。読書とは、これを知ること、あれをする方法を知ること…その快適さ、安全性、そして理解されることは、子どもたちが最もよく成長するための基礎であり、その中で理解されることは、子どもたちが本を読む場所を見つけて選ぶための鍵となります。
出典: https://baoquocte.vn/gioi-tinh-yeu-doc-sach-cho-nguoi-tre-bang-su-kien-tri-311734.html








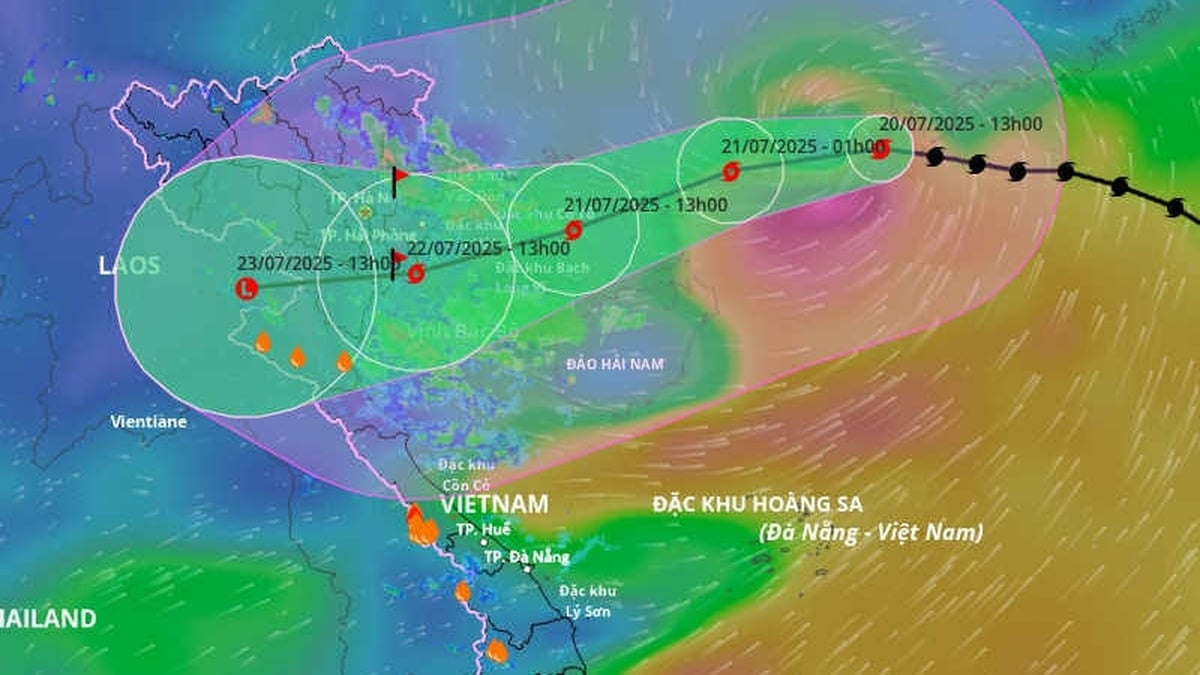




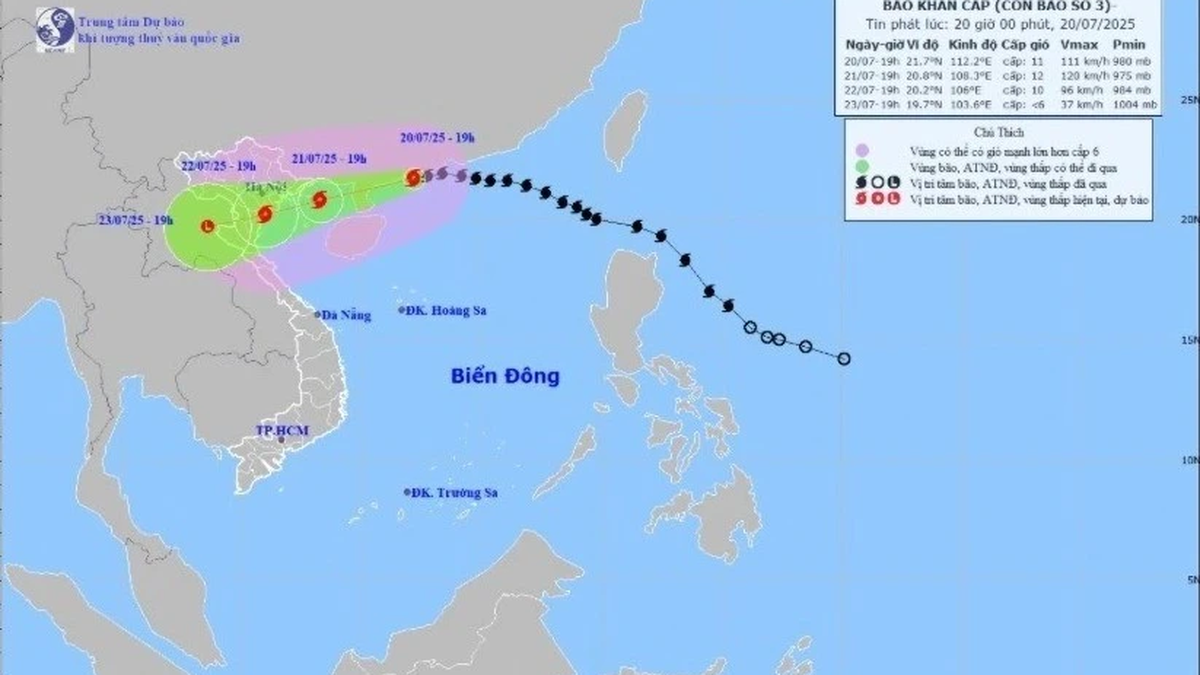

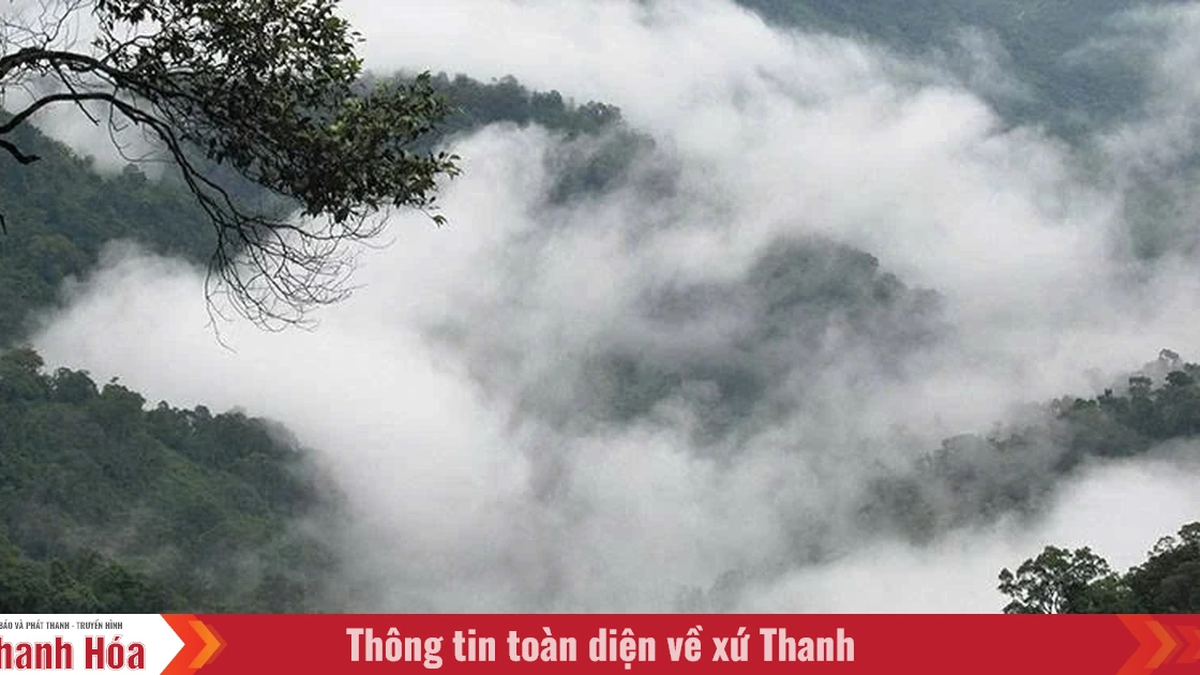





















































































コメント (0)