日本の6月のコアインフレ率は3.3%で、米国より0.3ポイント高く、2015年10月以来の高水準となった。
新たに発表されたデータによると、日本の6月のコアインフレ率(生鮮食品を除く)は、5月比0.1%上昇の3.3%となった。主な要因は電気料金の急騰である。この上昇率は、日本銀行(BOJ)の予想(3.5%)を下回った。
一方、米国の6月のインフレ率は3%でした。つまり、日本のインフレ率は8年ぶりに米国を上回ったことになります。
日本政府は7月20日、今年のインフレ率が日銀の示した2%を上回る2.6%に達する可能性があると予測し、同時に成長目標を1.5%から1.3%に引き下げた。
過去30年間デフレが続く日本では、2022年後半から物価上昇圧力が高まり続けており、その勢いはますます強まっている。最近の円安傾向は、日銀が年後半に金融緩和政策のスタンスを変更せざるを得なくなるのではないかという憶測をさらに強めている。
今週、日本銀行の上田一男総裁は来週の会合でも金融緩和策を維持する意向を示唆したが、この動きにより、過去1週間の円高の兆候にもかかわらず、円はドルに対して下落した。
第一生命経済研究所のチーフエコノミスト、新家芳樹氏は、3~4%のインフレ率は「もはや低くない」と述べた。「企業が消費者にコスト負担を転嫁する意向を示しているため、当局は慎重に対応する必要がある」と同氏は述べた。
日本は現在、世界で唯一マイナス金利を導入している国です。しかし、記録的な低金利を維持していることは、世界的な金融引き締めの波と相容れない状況です。現状では、インフレ指標は日銀が金融政策を調整する可能性を高めており、世界金融に一定の影響を及ぼす可能性があります。
ミン・アン(フィナンシャル・タイムズによると)
[広告2]
ソースリンク


















































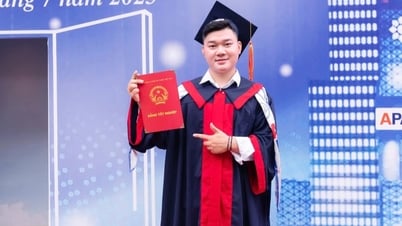



















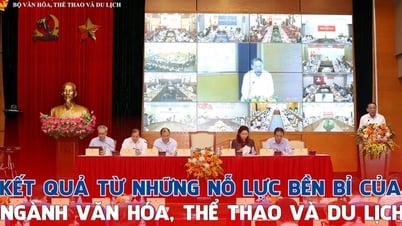

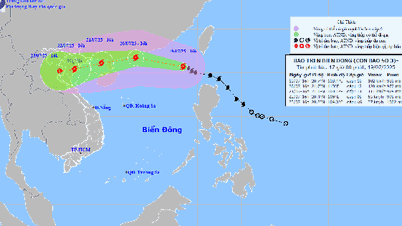

























コメント (0)