2023年11月5日 7時57分
昔、私の家は畑の端にありました。収穫が終わると、畑を焼く煙が辺り一面に広がり、息苦しさを感じました。鼻や耳に吸い込まれるような濃い煙の匂いが怖かったのです。
しかし、長い時間が経つと、ふと、遠く漂うあの強い煙の匂いが恋しくなる。野焼きの煙だけでなく、心の奥底に漂う落ち着かない煙も、小さな台所から立ち上る。薪ストーブ、藁ストーブ…が遠くへ遠ざかるたびに、毎朝、毎昼、毎晩。
冬の朝、母はいつも家の中で一番早く起き、そっと台所へ行き、学校までの道が遠かったので私を揺り動かして支度をさせてくれました。でも、母が作った料理の味が漂い、温かく残る煙の匂いが漂ってくるまで待たなければなりませんでした。そして、懐かしさに駆られ、温かい毛布から這い出る勇気が湧いてきました。そして、最も記憶に残る甘い煙の匂いは、母が朝もち米を炊く時の煙の匂いでした。ああ、炊きたてのもち米の香ばしい香りが冬の朝の霧と混ざり合い、なんとも魅惑的で不思議な温かさでした! ゴマ塩の脂っこく濃厚な味も風に溶け、母の叩く手のリズムに合わせてリズミカルに変化していました。私はドアのそばに立ち、目を半分閉じたり開いたりしながら、壁に揺れる人の影と、赤く揺らめく火を見ていました。そして、煙の糸がこっそりと立ち上り、冷たく空虚な空間を消し去っていく。あの香ばしく温かい煙を吸い込みたくて、立ち去りたくなかった。
 |
| イラスト:トラ・マイ |
焼けつくような夏の午後も覚えています。畑から帰ると、父は台所へ向かいます。庭では、まるで灼熱の太陽と競争するかのように、藁の火が燃え上がります。煙が静かに揺らめきます。カニスープの鍋は、レンガ、ムクゲ、そして青いカボチャのスライスが重なり合って、煮え立ちます。甘く爽やかな香りが漂います。食事の時間、スープを椀に注ぐと、畑の爽やかな香り、汗の塩辛さ、そして強烈な風を感じます。しかし、料理をする時は、火を丁寧に、風通し良く、素早く起こさなければなりません。煙が鍋にこもって風味を失わないように。父は私に、昼食を作る時、暑すぎると兄弟たちは藁を投げ込み、棒切れで灰をかき混ぜるだけであっという間に火が終わると、台所から煙が逃げる暇もなく、ひどく悲惨な思いをしたと教えてくれました。父は言った。「急げば急ぐほど、時間はかかるし、熱くなる。静かに藁を押せば、ご飯とスープが炊けるだけの火力になる。煙は渦を巻かず、静かに上昇して上に積み重なった物にくっつく。あるいは、壁に布を一枚重ねて覆い、目や耳に入らないようにすればいい。」
慌ただしく、遊びに忙しく、慌ただしい日々を送っていた私たちは、煙を嫌ったり怖がったりすることもありました。美味しい料理の多くが煙に頼っていることを知らなかったのです。母が寝る前に籾殻をかぶせた、スターフルーツ入りのスズキの煮込み鍋。籾殻の炭はゆっくりとくすぶり、やがて消えていき、翌朝には干し魚の出来上がり。脂の乗った魚の濃厚な味とスターフルーツの酸味、そして籾殻の煙の香りが混ざり合い、言葉では言い表せないほどの絶妙なハーモニーを奏でていました。涼しい日には、近所のおじさんたちが粘り気のある稲わらを積み上げて焼き菓子を焼くと、長い路地の端から端まで、香ばしい煙が漂ってきました。子供たちはその芳醇な香りを吸い込み、鼻腔の中で懐かしさと漠然とした距離感を掻き立てました。
しかし、今でも一番思い出に残っているのは、古くてこげ茶色の台所の屋根から立ち上る夕焼けの煙です。当時は、周囲は瓦葺きの家々で、台所も瓦葺きで、時には茅葺き屋根でした。夕暮れが静かに沈むと、コウノトリは巣へと舞い戻り、水牛や牛は村へと続く凸凹道をゆっくりと数えながら、最後の陽光にきらめきながら歩いていました。風が、かすかに揺れる筋を空に描き始めました。それぞれの繊細な煙の房は、暖かく穏やかな香りを空へと放ちました。それは平和と豊かさの香り、そして再会と家族の香りでした。夕焼けの煙を眺めていると、人々はその日の疲れや苦労をすべて忘れてしまうようでした。煙は優しく、優しく、そして優しく広がっていました。風が強く雨が降る午後の真っ只中に立ち上る煙か、それともかすかに静かな煙か… 一日の終わりにキッチンからゆっくりと立ち上る煙を突然目にすると、見知らぬ土地でまだ戸惑っている人のことを気の毒に思った。
そして、現代のキッチンから煙の香りが消え去った時、ふと懐かしさがこみ上げてくる。薪と陽光の間に秘めた愛の静寂と情熱は、一体どこに見つけられるというのだろう?煙は消え去り、遠い日々へと永遠に漂い、懐かしさの雲に混じり合っている。儚く、そして果てしない。過去を振り返る時、ほんの少しの悲しみだけが残る。
最後の香り
ソース

















































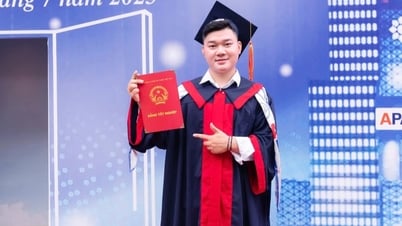












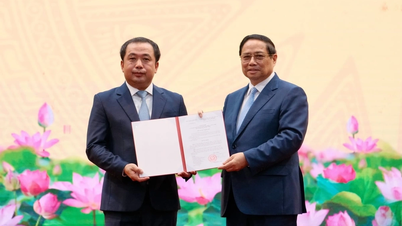




































コメント (0)