
ハノイには現在、約1,600棟の古いアパートが存在します。写真:VGP/Thuy Chi
本当の「後押し」を20年以上待っていた
ハノイ市は2025年7月1日より二層制の地方自治モデルを正式に運用開始し、都市統治へのアプローチにおける転換点となります。同期した法的回廊、徹底した地方分権化メカニズム、そしてコミューンレベルと区レベルの積極的な参加により、市は老朽住宅の改修における長年の「ボトルネック」を解消し、持続可能で近代的、そして人間中心の都市開発へと前進することを目指しています。
2000年代初頭以来、ハノイでは老朽化したアパートの改修が大きな課題となってきました。しかし、過去20年間の成果はごくわずかで、約1,600棟のうち、改修が完了したのはわずか1~2%にとどまっています。また、グレードDの建物は80棟以上あり、依然として住民にとって潜在的な安全上のリスクとなっています。
主な障害は、柔軟性に欠ける法的メカニズム、煩雑な行政手続き、そして不十分な補償メカニズムにあり、多くのプロジェクトが停滞しています。しかし、2025年7月1日から二層制地方政府モデルへの移行が新たな機会を切り開きます。これは単に制度を合理化するだけでなく、経営理念の根本的な転換、草の根レベルへの強力な地方分権化、そして地方自治体が自ら積極的に障害を根本から取り除くための権限を与えるものです。
住民に最も近い行政機関として、区政府は指示を受けるだけでなく、老朽化したマンションの改修の各段階において住民を積極的に支援するようになりました。ジャンヴォ区、キムリエン区、フオンリエン区、タンコン区、クインマイ区といった区は、住民が直接組織化して意見を収集し、集計を支援し、計画案や再定住住宅基金の導入を進めるなど、明るい兆しを見せています。
区役所職員は、住民との密接な接触と住民の気持ちを理解することで、従来の硬直した行政手法よりもはるかに効果的に政策を説明し、信頼関係を築き、合意形成を図ることができる。
二層制政府 - 都市変革のてこ入れ
区は、アドボカシー活動に留まらず、計画建築局および建設局と連携し、古い住宅地の1/500計画を策定・提案する役割も担っています。このプロセスはかつては数年かかっていましたが、行政機関の仲介者を削減することで、わずか数ヶ月に短縮できるようになりました。これは、改修の進捗を加速させるための重要な基盤となります。
さらに、2025年から施行される土地法、住宅法、2024年資本法を含む3つの改正法により、より調和的でオープンかつ実用的な法的回廊が構築されました。そのうち、特に注目すべき5つの変更は、改修プロジェクトの困難を直接的に解消するものであり、以下の通りです。100%の合意ではなく、プロジェクトの危険度に応じて住民の70~80%の合意が必要となること。技術インフラに過負荷がかからないことを条件に、TODモデルに基づく合理的な階数増加を承認すること。地上への圧力を軽減するため、地下空間の開発を奨励すること。請負業者を指名するのではなく、PPPメカニズムに基づく入札により投資家を選定すること。住民の権利が確保される限り、プロジェクトの範囲外で移転資金を調達することを許可すること。
そのおかげで、20年以上にわたって何百ものプロジェクトを「棚上げ」にしてきた最大の法的障壁が徐々に取り除かれつつあります。
ハノイ建築家協会常任会員である建築家トラン・フイ・アン氏は、老朽マンションの改修をより効果的に行うには、新たな発想が必要だと述べた。インフラから居住空間に至るまで、地域全体を再計画する必要がある。さらに、区に権限が与えられれば、住民を動員し、企業と調整し、問題を現場で解決できるようになる。しかし、権限を与える際には、明確な責任分担と綿密な監督が不可欠だ。
ベトナム都市計画開発協会副会長の建築家ダオ・ゴック・ギエム博士も同様の見解を示し、古いアパートの改修を、再建が必要な断片として捉え続けるのではなく、各エリアを生活機能が充実した小さな都市圏として捉えるべきだと述べた。それぞれの改修プロジェクトは、20~30年先を見据えた地域全体の都市計画の中で捉える必要があり、特に交通、学校、医療といったインフラ整備を最優先に考える必要がある。
建築家ダオ・ゴック・ギエム博士によると、ハノイの二層制政府への移行は制度上の画期的な進歩ではあるものの、厳格な管理メカニズムが伴わなければ、問題を引き起こすリスクもある。例えば、付随する技術・社会インフラへの投資を怠り、階数の増加に重点を置きすぎると、交通システムの過負荷、住宅紛争、利害衝突といった問題に容易につながりかねない。
建築家ダオ・ゴック・ギエム博士は、各区は住民を動員するだけでなく、計画策定、実施状況のモニタリング、事後検査に直接参加する責任を持つべきだと考えています。地方自治体が透明性と決意を持って、そして公共の利益のために行動しているのを目にすれば、人々は喜んで協力するでしょう。
ベトナム建築家協会事務局長のファム・タン・トゥン氏は、現状において、住民に最も近い場所である区レベルの役割が極めて重要になっていると述べた。区レベルは、住民間の対話を組織し、改修計画を明確に提示し、移転の進捗状況を約束し、新たな住宅基準や補償価格を発表する「指揮者」としての役割を担う必要がある。住民が耳を傾け、具体的かつ実践的な情報によって納得すれば、彼らは反対するのではなく、共に歩むだろう。
董氏は、実質的な双方向の協議メカニズムを作るために、各アパートの団地に、区当局、住民グループ、弁護士、計画専門家の代表が参加する「コミュニティ対話グループ」を設立することを提案した。
国会議員で、元国民経済大学副学長のホアン・ヴァン・クオン教授は、ハノイは制度改革の黄金期を迎えていると述べ、二層制地方自治モデルへの移行は、単に制度の合理化を図るだけでなく、地方分権化の突破口となり、草の根レベルに実質的な権限をより多く与えることになると強調した。しかし、「権限委譲」は「手段の権限委譲」と並行して行われなければならず、幹部職員の体系的な研修が不可欠である。
さらに、すべての改修計画が監視および比較できる透明なデータ プラットフォーム上で実行されるように、デジタル インフラストラクチャ、特に人口、住宅、技術インフラストラクチャのデジタル データベースを構築する必要があります。
クオン氏は、真の変化を生み出すためには、ハノイ市がアパートの改修を進めている主要区でデジタル政府モデルを試行すべきだと考えている。そこから経験を学び、それを再現することで、各区を効果的で近代的、そして住民に密着した「都市改革の運営ステーション」へと変貌させていくべきだ。
20年以上にわたりハノイの「ボトルネック」となっていた老朽マンションの改修は、二層制の地方自治モデルによって今、「解放」の大きなチャンスを迎えています。区が指示を受けるだけでなく、アドボカシー、サポート、監督といった形でプロジェクト運営プロセスに実際に参加することで、アプローチ全体も変化します。行政主導から対話、合意形成、そして調和のとれた発展へと。
新たな法的回廊、現代的な計画思考、透明な権利、そして明確な地方分権化を組み合わせることで、ハノイは、古くて劣化したアパートが文明的で安全かつ持続可能な都市エリアに取って代わられる画期的な時代を十分に期待できる。
トゥイ・チ
出典: https://baochinhphu.vn/ha-noi-ky-vong-dot-pha-trong-cai-tao-chung-cu-cu-103250716184314043.htm






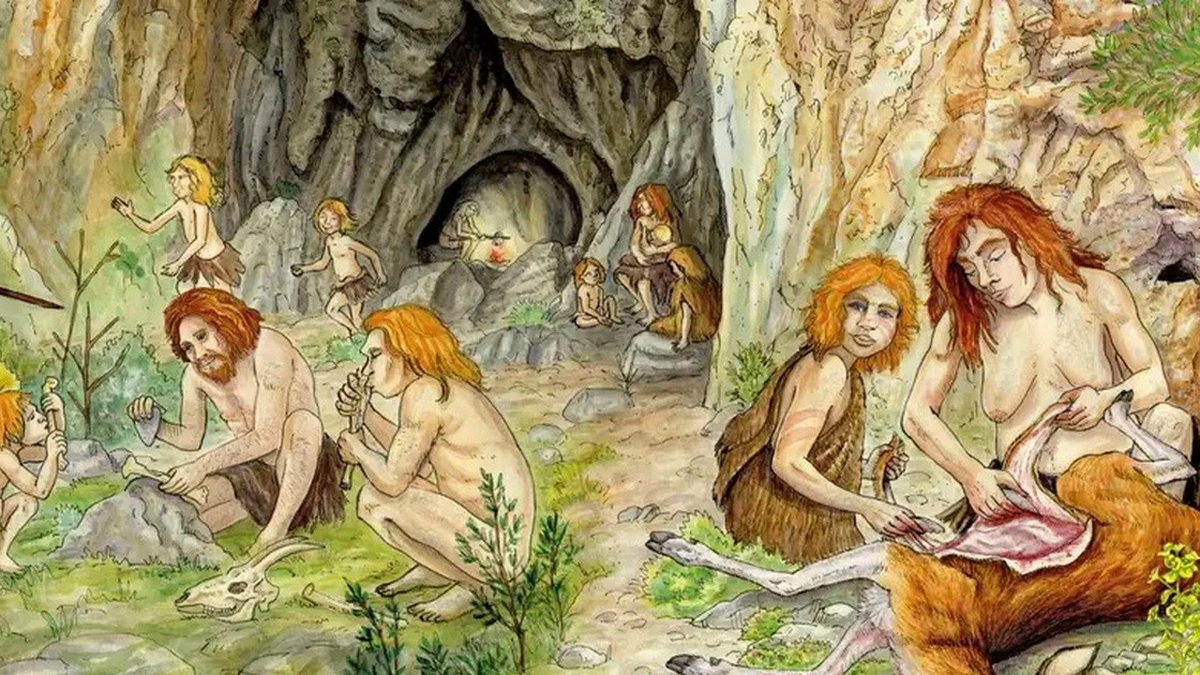




















































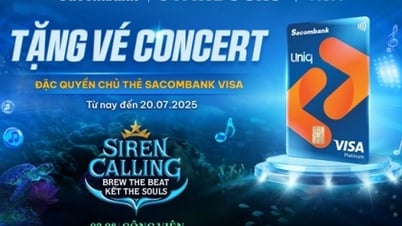












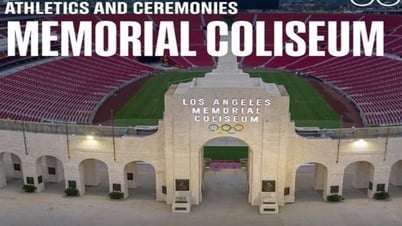


















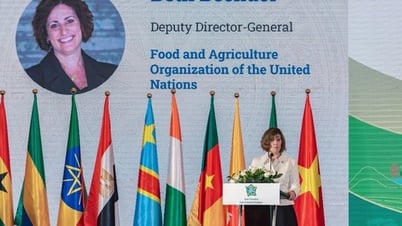










コメント (0)