以下の記事は、 ハノイで教師が髪をつかまれた事件に対する7年生の反応を説明するために、独立した心理学者であるダン・ホアン・ガン博士によって共有されており、親、学校、地域社会が、生徒を「無神経」と性急に結論付けるのではなく、生徒の心理状態を正しく理解するのに役立っています。
動画の映像には、教師の髪を掴み、頭を押さえた生徒のすぐ後ろに座っていた二人の生徒が、明らかにショック反応を示していたことが映っています。一人の生徒は驚いて後ずさりし、長い間口を覆い、もう一人はじっと立ち尽くし、しばらく顔を壁に向けたままでした。麻痺状態は、ショック反応の非常に明確な兆候です。このような麻痺状態では、カメラを通して冷静に事件を観察している人間が通常期待する行動をとるという判断を下すことは非常に困難です。
テーブルの前方に座っていた少年の一人は、ほとんどの時間、両手で目を覆い、隣の人の方を向いて注意を集中させようとしていました。もう一人の少年は立ち上がり、両手を目に当てて自分自身を見つめていましたが、これもストレスの多い状況から逃れようとする反応だったのかもしれません。
最も誠実とは正反対の行動でさえ、恐怖と麻痺の外見的な表現になり得ます。多くの子どもたちは状況を観察し、振り返って笑います。中には助けようともせずに通り過ぎる子もいます。外から見ると、これらの行動は無神経に見えます。しかし、思春期には、子どもの内面ははるかに鮮明になることがあります。「私は強いんだ。慌てる必要はない」「あの人は私の友達だ。好きだ」…

そして教室のカーテンが閉まります。カーテンが閉まると、恥ずかしさが湧き上がります。しかし子どもたちは、大人が恥に対処する際に見てきたことを知らないか、あるいは繰り返すだけです。つまり、恥を隠そうとするだけで、深く見つめて、助けや改善の方法を見つけようとしないのです。
「無関心」という言葉を使うことは、彼らの経験の複雑さを単純化しすぎています。予期せぬ状況に直面した際の孤立感や無力感だけでなく、(他の多くの社会環境において)問題解決のロールモデルとなる大人がいない、そして何が正しいのか、何が親切なのかを信じられないことも、彼らの経験の複雑さを物語っています。
あなたは感情がないわけではなく、自分の感情にとらわれ、まだ自分の感情を表現できずに、とても苦しんでいるのだと思います。
そう確信しているのは、衝撃的な出来事を至近距離で目撃したからです。当時16歳だった私がバスに乗っていた時、運転手がバスを停車させ、飛び降りて二人の女子高生を平手打ちしました。騒がしい集団だと思ったのです。
バスに乗っていた学生も社会人も、多くの人が息苦しい雰囲気の中で沈黙していました。私も完全に身動きが取れなくなり、二人の女子学生のうち一人が私の優しい親友だと分かった時、ようやく涙がこぼれました。後に一緒に苦情を申し立てましたが、あの時の心の傷は、自責の念と自信喪失とともに、何年も私を苦しめ続けました。
画面で見たり聞いたりしたときに自分たちにできると思うことと、実際に状況が発生したときに私たちが行うことは大きく異なることに気づいたのは、後になってからでした。
最近の7年生の事件に戻りますが、精神的なケアが2人の主人公だけに向けられるわけではないことを願っています。
教師という道徳的なプレッシャーや、許しを促し、人間性を称賛する風潮に、その教師が圧倒されないことを願っています。教師として期待される基準を、不当な扱いを受けたばかりの人の自然な欲求よりも優先してしまうこともあるでしょう。それは難しい、理性的な選択です。しかし、その教師が、無理に寛容で高潔な感情を抱かないように願っています。感情的に脆くなっていく過程を尊重し、彼女が抱える曖昧な感情を徐々に理解していく必要があります。教師としての立場への自信のなさ、何か悪いことをして守られていないことへの罪悪感、そしておそらく感情的な経験について曖昧な思いを抱いている子どもたちの中で感じる孤独感などです。

不正行為を行った生徒が、徐々に内面の葛藤を解決し、起こった出来事を真に反省していく過程を共に歩むことが期待されます。しかし、 教育においては、不正行為を行った生徒が、可能な限り高いレベルの理解力をもって、自らの行動に責任を負わなければなりません。
これを目撃した生徒たちが忘れ去られないことを願います。ショックを受けた生徒こそ、自分が耐えてきたことを言葉で表現できたのです。外見上は麻痺しているように見えた生徒は、内なる自分と再び繋がるための導きを必要としています。しかし、言葉にできない感情を抱えながらも、麻痺した状態を保てるよう安全な状態だった生徒は、心理的ケアを受けられなければ、自分自身と人生について混乱と疑念を抱くことになるかもしれません。
私たち大人が子どもたちに「あれを見た時に、どうして介入しなかったの?」「大人を呼んだ方がいいの?」「どうしてカーテンを閉めたの?」などと尋ねるとき、子どもたちが少しずつ心を開いてくれるように、十分に理解し、耳を傾けるよう努めたいものです。「あの友達は体が大きくてナイフを持っているから怖い」「あの友達が好きだから」「子どもは守られるべきだと思うし、先生は大人だと思っているから」「クラスの競争で点数が減るのが怖いから」「大きなことに動じない、かっこいい人間だと友達に思われたいから」「わからない、そのときは何も思いつかなかった」…
これらの告白の言葉は、子どもたちが経験してきた複雑な過程を凝縮したものです。もし耳を傾け、解釈しなければ、その凝縮は告白そのものの漠然とした感情と合理的な信念にとどまってしまいます。感情の複雑さははるかに鮮明で、直接目撃した大人でさえ耐え難いほどです。だからこそ、その複雑さは言葉で伝える必要があるのです。
学校や家庭には、この問題が複数の関係者による行政的な努力だけで解決できると考えないよう願っています。新たな経験の一つ一つに目を向け、寄り添うことこそが、教育がその使命を果たすための基盤なのです。
ハノイで中学1年生が教師の髪を引っ張り頭を押さえた事件
「生徒が教師の髪を掴んで頭を押さえると、教師はクラス全員にじっと座るように言った」
2025年9月20日生徒が教師の髪を引っ張ったり頭を押さえたりしたことについて校長が発言
2025年9月21日生徒が「教師の髪を引っ張ったり頭を押さえたりした」という事案は深刻であり、公平に扱われなければならない。
2025年9月19日出典: https://vietnamnet.vn/cac-em-hoc-sinh-lop-7-trong-vu-co-giao-bi-tum-toc-khong-vo-cam-2444713.html







![[写真] ファム・ミン・チン首相が住宅政策と不動産市場に関する中央指導委員会の初会合を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/22/c0f42b88c6284975b4bcfcf5b17656e7)





























![[写真] ベトナム国家エネルギー産業グループに一級労働勲章を授与するト・ラム書記長](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/21/0ad2d50e1c274a55a3736500c5f262e5)















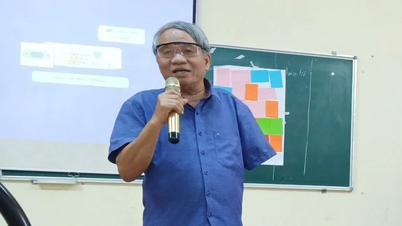













































コメント (0)