第78回国連総会ハイレベル週間の2日目、ロシアが常任理事国である国連安全保障理事会(UNSC)の緊迫した会合に出席したウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領に再び多くの注目が集まった。
ウクライナは現在、国連安全保障理事会の理事国ではないが、東欧諸国の長引く紛争に関する国連最高権力機関の会合に出席するよう招待された。
結局、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相とウクライナ大統領の会談は実現しなかった。ゼレンスキー氏は演説を終えてすぐに退席し、ラブロフ氏が到着する前に会談が終わったためだ。
「スズメバチの巣を突く」
ゼレンスキー氏は9月20日の会合での比較的短い発言で、戦場の厳しい現実には言及せず、制裁の発動や軍事力の派遣など最も強硬な措置を取る権限を持つ国連機関である国連安全保障理事会の構造を批判した。
米国、ロシア、中国、フランス、英国の5カ国は国連安全保障理事会の常任理事国(P5)であり、拒否権を有しています。残りの10議席は、170を超える加盟国の間で持ち回りで選出され、任期は2年で、拒否権は持ちません。
ゼレンスキー大統領は、9月19日の総会での演説とは異なり、今回は母国語で話すことを選択した。

2023年9月20日、ニューヨークで開催された第78回国連総会中の国連安全保障理事会(UNSC)会合に出席するウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領。写真:ナショナル・ニュース
ウクライナ大統領は、193カ国すべての加盟国が参加する総会が3分の2の賛成で安保理の拒否権を覆せるよう、国連規則を改正することを支持している。しかし皮肉なことに、この改正自体が導入されれば、P5の拒否権に直面することになる。
注目すべきは、自国の権力が弱まることを望まない米国のアントニー・ブリンケン国務長官も英国のオリバー・ダウデン副首相も、演説の中でゼレンスキー氏の提案に言及しなかったことだ。
しかし今週、他の数カ国が国連安全保障理事会の再編問題を提起し、同機関はより幅広い代表性と公平性を持つ必要があり、少なくとも拒否権は廃止されないまでも制限されるべきだと主張している。
「ゼレンスキー氏は、国連改革について語ることによって、ウクライナ戦争を世界的な大義に変えようとしていると考えていると思う」と国際危機グループ(ICG)の国連ディレクター、リチャード・ゴーワン氏はインタビューで語った。
「多くの国連加盟国が安保理は時代遅れで改革が必要だと考えていること、そして特に拒否権制度は不評だと考えていることは、彼の言うとおりだ。しかし、安保理改革は外交的にスズメバチの巣を突くようなものであり、安保理改革や拒否権制度の変更には手続き面でも政治的な障害も非常に大きい」とゴーワン氏は述べた。
ゼレンスキー氏はまた、1990年代にソ連が崩壊した後にロシアがソ連の特権を継承することを国連が許したのは間違いだったと述べ、「何らかの理由で、その特権は今も国連安全保障理事会の常任理事国の中に残っている」と語った。
ウクライナの指導者が話している間、ロシアの国連常駐代表であるワシリー・ネベンジャ氏は携帯電話に目を落とし、画面をタップした。
国際関係における「法的手段」
ウクライナ大統領は演説後すぐに会議室を退出したため、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の外交トップであるラブロフ外相との間に対立はなかった。

2023年9月20日、ニューヨークで開催された第78回国連総会における国連安全保障理事会(UNSC)会合のパノラマ風景。写真:Shutterstock
ロシアのラブロフ外相は国連安全保障理事会での演説で、西側諸国が自国の地政学的ニーズのみを重視していると非難した。彼は、これが「世界の安定を揺るがし、新たな緊張のホットスポットを悪化させ、誘発している」と述べた。彼によれば、世界的な紛争のリスクは高まっている。
ロシアの外交政策を20年近く指揮してきたラブロフ外相はまた、国連安全保障理事会におけるモスクワの拒否権行使を国際関係における「正当な手段」として擁護した。
常任理事国5か国のうち、ロシアはこれまで120回と最も頻繁に拒否権を行使している。次いで米国が82回である。中国は複数回拒否権を行使している一方、英国とフランスは1989年以降拒否権を行使していない。
「拒否権は、組織の分裂を招く可能性のある決定の採択を防ぐために国連憲章で定められた正当な手段だ」とラブロフ外相は主張した。
同氏は「西側諸国は拒否権の濫用問題を提起し、一部の国連加盟国を標的にしている」と述べ、これは明らかに自国への言及だと主張した。

2023年9月20日、ニューヨークで開催された第78回国連総会期間中の国連安全保障理事会(UNSC)会合に出席するロシアのセルゲイ・ラブロフ外相。写真:ニューヨーク・タイムズ
ロシア外交官は、国連安全保障理事会の制裁を受けている第三世界の国々に同情を表明するコメントで演説を終えた。
「制裁の人道的限界が考慮されるべきだ。つまり、国連機関は西側諸国のポピュリスト的な言説ではなく、こうした制裁の人道的影響を考慮すべきだ」とロシア外相は述べた。
ラブロフ外相は具体的な国名を挙げなかったが、制裁対象となっている国の多くはシリア、イラン、北朝鮮、キューバ、ベネズエラ、マリなどロシアの同盟国である。
ラブロフ外相はまた、ウクライナ戦争についても長々と語り、ゼレンスキー大統領の政権はロシア語話者を差別し、虐待しているとの主張を繰り返し、モスクワはキエフとの協議を無条件で支持していると述べた。
Minh Duc (EFE/La Prensa Latina、NY Times、DWによる)
[広告2]
ソース

























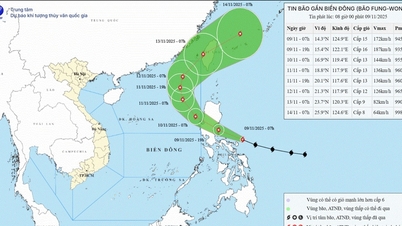







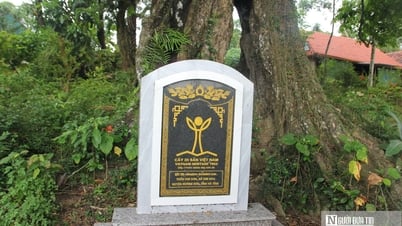
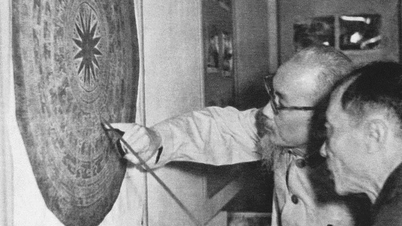





























































![ドンナイ省一村一品制への移行:[第3条] 観光と一村一品制製品の消費の連携](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/10/1762739199309_1324-2740-7_n-162543_981.jpeg)












コメント (0)