従業員が定年退職時に、年金の最高額受給資格期間(男性35年、女性30年)を超えて社会保険に加入した場合、超過納付年数ごとに一時金が支給され、制度を享受できます。
2014年社会保険法の現行規定によれば、男性労働者が35年間、女性労働者が30年間拠出した場合、最大の年金(75%)を受け取ることができます。
社会保険加入期間が超過し、給与の75%を受け取る場合、1年あたり平均社会保険給与の0.5か月分として計算されます。
しかし、2025年7月1日から施行される新しい社会保険法(社会保険法2024)では、引き続き就労し社会保険に加入する退職者に対する一時金の増額に向けた規定が追加されました。

新しい社会保険法では、定年退職しても引き続き働き、社会保険に加入する人に対して、より高い調整が行われます。
具体的には、年金受給資格者でありながら社会保険料を納付し続けている従業員の場合、所定納付年数(退職年齢から)を超える年数ごとに、社会保険料の納付の基礎となる平均給与の2倍に相当する額が支給されます。
退職者一時金の計算方法
2024年社会保険法の規定に従って一時金の額を計算できるように、 労働・傷病兵・社会省は具体的な計算式の指示を出しました。
例えば、退職一時金の具体的な計算例は以下のとおりです。
Aさんは通常の労働条件で働いており、定年退職時点で社会保険料の納付期間は39年です。定年退職と同時に退職した場合、社会保険料の納付期間が4年分超過することになります。
社会保険料の超過納付期間が4年間の場合、Aさんは毎年、平均社会保険料納付額の0.5ヶ月分に相当する一時金を受け取ることができます。この場合、Aさんの一時金は、4年間×0.5=平均社会保険料納付額の2ヶ月分となります。
しかし、Aさんがすぐに退職せず、退職前にさらに3年間就業し、社会保険料を納付した場合、Aさんは合計42年間の社会保険料納付期間を有することになります。そのため、Aさんは年金に加えて、以下の一時金も受け取ることになります。
社会保険料の納付期間は、定年退職年齢の35年以上前の4年間で、1年当たりの納付額は、社会保険料の基準となる平均給与の0.5倍に相当します。つまり、4年×0.5=2.0となります。
退職後の社会保険料の納付期間は3年間で、1年あたり社会保険料の納付基準となる平均給与の2倍となります。つまり、3年×2=6となります。
したがって、このケースでは、A 氏は、社会保険料の基礎として使用される平均給与の 8 倍に相当する金額を退職時に一時金として受け取る権利があります。
労働専門家は、引き続き就労し社会保険に加入している退職者への一時金の増額は、労働者、特に優秀な労働者(専門家、 科学者など)が退職条件を満たした後も就労を続け社会に貢献する意欲を高めることになるだろうと述べた。
[広告2]
出典: https://vietnamnet.vn/truong-hop-ve-huu-duoc-huong-them-khoan-tro-cap-mot-lan-rat-cao-2347615.html




![[写真] トゥオン族の仮面を描くユニークな芸術](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/14/1763094089301_ndo_br_1-jpg.webp)

![[写真] 深海の砂の堆積物、古代木造船アンバン号が再び埋もれる危機に](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/13/1763033175715_ndo_br_thuyen-1-jpg.webp)















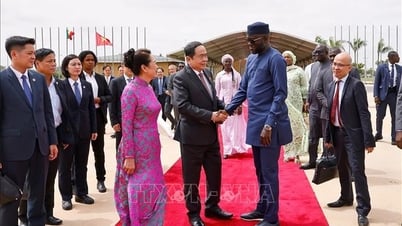




























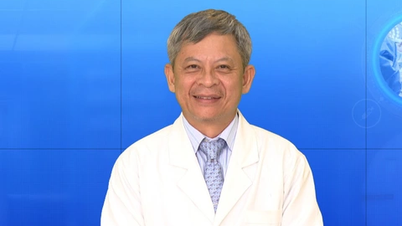




















































![ドンナイ省一村一品制への移行:[第3条] 観光と一村一品制製品の消費の連携](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/10/1762739199309_1324-2740-7_n-162543_981.jpeg)






コメント (0)