「小さい頃は、早く大きくなって村の門から出られたらいいのにって思ってた。でも今は週末が待ち遠しくて、故郷に戻って村の道を歩けるんだ」と友人は懐かしそうに話した。きっと子供の頃は、村の子供たちは皆、村を出て外の広い世界へ行きたいと思っていたんだろう。そしていつしか、故郷を遠く離れた同じ子供たちも、故郷の村へ戻りたいと願うようになったのだろう。

当時、私の故郷であるバウ・トロン村には村門がなく、クアンナム省のほとんどの村にも今日のような立派な門はありませんでした。歓迎の門は村と田畑を繋ぐものでした。歓迎の門は小さなものでしたが、村人たちにとって、少なくとも当時の子供だった私にとっては、それは非常に特別なものでした。
例えば、母が仕事に出かけている間、私が家の番をしている日は、お昼頃か夕暮れ時に外に出て母を待ちます。母が鍬を担いだり、籠を二つ抱えて門まで戻ってきたりするのを見ると、母は…家に帰ってきたということになります(!)。
母が市場に行く日も同じでした。30分ほど経つと、私はバナナの葉が敷き詰められた路地に出て、門の方を見ました。母が籠を腰に担ぎ、門に向かって歩いていくのを見て、「まるで市場から帰ってきた母のように嬉しくなりました」。門はいつも村の目印でした。雨季になると、村の人々はよく「水は門まで来たか?」と尋ね合ったり、「門まで水が来た」と報告したりしました。
その後、私と友達が成長して遠くへ旅立つようになってからも、門に着くたびに、何も言わずとも、まるで「家に帰ってきた」という気持ちになりました。あの興奮と緊張は言葉では言い表せないほどでした。なぜなら、村の門の向こうには、近所の人、親戚、友人たちの温かい心が溢れ、村の子供たちをいつでも温かく迎えてくれることを知っていたからです。同じように、誰かが村を離れ、遠くへ――主に南部へ――勉強や仕事に出かけるたびに、親戚たちは別れを告げる前に、名残惜しそうに門まで見送ってくれました。
建築家ホアン・ダオ・キンは著書『人生の路地』の中で、村の門についてこう記しています。「村の門は単なる里程標ではなく、歩哨でもありません。村の門は、それぞれの村の名前であり、『私』なのです。」
実際、それぞれの村の門の向こうには、それぞれ独自の生活様式、習慣、そして活動を持つ、静かで質素な家々が数多くあります。だからこそ、二つの村は隣り合っているにもかかわらず、異なる文化が息づいているのかもしれません。
都市化によって田舎は狭く、ますます縮小していますが、村人たちの心は常に開かれ、村の子供たちの足跡を温かく迎えています。そして村の門――それが単なる「歓迎の門」であろうと、荘厳で堅固な「門」であろうと――は、今もなお村の「目印」であり、特別な「里程標」であり、一人ひとりの心に刻まれた愛の「証」なのです……
[広告2]
ソース









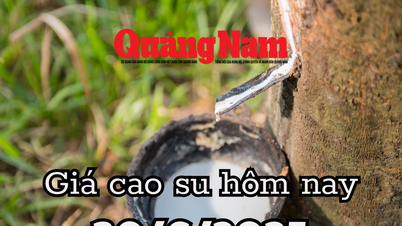


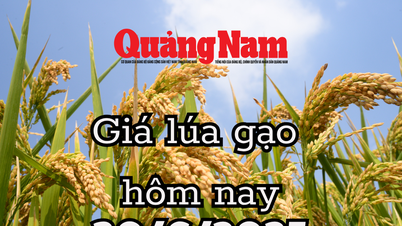






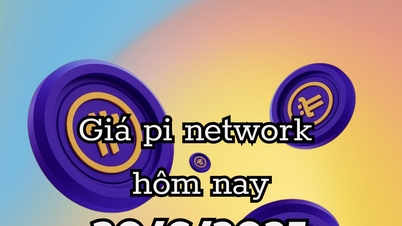











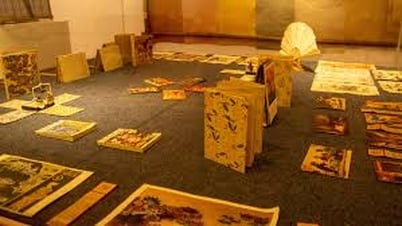




































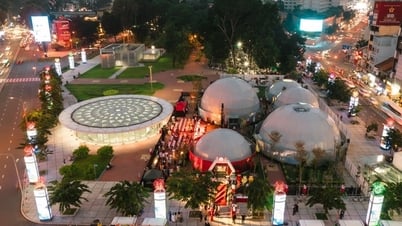













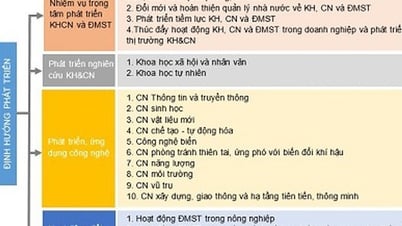









コメント (0)