貧富の格差は社会問題であり、どの国でも現実です。貧富の格差を縮小することは、常に党と国家の最優先事項です。しかし、第四次産業革命と急速なデジタル化の進展の中で、デジタルデバイドの縮小は困難な課題であり、早急に解決策が見出されなければ、社会における貧富の格差は拡大する一方です。人民軍新聞の記者は、この問題について、タイ・タン・ハ准教授(貿易大学上級講師)にインタビューを行いました。
PV:タイ・タン・ハ教授、ベトナムにおけるデジタルデバイドの測定に関する研究グループを率いていらっしゃると伺いました。この研究テーマは、実用的価値が非常に高いです。なぜなら、デジタルデバイドの問題にタイムリーな解決策がなければ、社会における貧富の差がさらに拡大してしまうからです。先生と同僚の方々が、このテーマを研究対象に選ばれた理由をお聞かせいただけますか?
タイ・タン・ハ准教授:貧富の格差は、 世界中のすべての国にとって非常に複雑で多面的な、そして困難な問題です。特に、新型コロナウイルス感染症の「嵐」とその恐ろしい影響の後、貧富の格差はさらに拡大しているように見えます。しかし、さらに困難で熾烈で長期化する戦いがあります。それは、デジタルデバイドを縮小するための戦いです。第四次産業革命と現在の急速なデジタル化の進展を背景に、デジタル変革へのアクセスを持つグループと、アクセスがほとんど、あるいは全くない恵まれないグループとの間のデジタルデバイドは、非常に大きな影響を及ぼし、社会における貧富の格差をさらに拡大させるでしょう。
 |
| 准教授、タイ・タン・ハ博士。 |
我が国では、貧困撲滅と貧富の格差是正を常に最優先課題としてきました。これは党と国家の政策指針、特に国会で承認され、政府が精力的に実施している少数民族・山岳地帯の社会経済発展のための国家目標計画、新興農村建設のための国家目標計画、持続可能な貧困削減のための国家目標計画といった重要な決定に明確に反映されています。貧富の格差是正に向けた我が国の努力における成果は実に目覚ましいものがあります。国連基準による多次元貧困率は2022年に4.3%まで減少しました。この成果は国際社会から認められ、高く評価されています。
しかし、世界の他の多くの国々と同様に、ベトナムも新たな、そして困難な世界的課題に直面しています。それは、デジタルデバイドの解消です。ベトナムは世界でも有数のデジタル変革率を誇る国であり、あらゆるデジタル経済分野、特に電子商取引において二桁の成長率を誇っています。こうした状況において、貧困層や脆弱層がデジタル製品、サービス、プラットフォームへのアクセスをほとんど、あるいは全く得られない場合、貧富の格差はさらに拡大するでしょう。例えば、オンラインショッピングは社会において新たな消費トレンドとして急速に普及しているため、貧しい農家が電子商取引プラットフォームで農産物を販売できなければ、彼らの収入は減少するでしょう。
 |
| ニンビン省行政センターは住民に奉仕している。写真:NAM TRUC |
こうした現実を踏まえ、私と貿易大学、クアンビン省ベトナム祖国戦線委員会、そしてパイロット研究対象地域の職業訓練機関の同僚たちは、このテーマに深く関わってきました。幸運にも、オーストラリア大使館から「オーストラリアの研究枠組みに基づくインクルージョン指標の開発を通じた、ポストコロナ時代のベトナムにおけるデジタル格差の測定」というテーマの研究資金を得ることができました。オーストラリアはすでにこのテーマについて綿密な研究を行っており、現在も研究を続けています。さらに、2023年は両国間の外交関係樹立50周年にあたり、私たちの提案テーマは特に意義深いものとなりました。ハノイのオーストラリア大使館に提出された68件の応募の中から、11件に選ばれたのです。
PV:あなたの意見では、今日のデジタル時代において、どのようなグループが脆弱になる可能性が高いでしょうか?
タイ・タン・ハ准教授:世界的な一般的な調査結果によると、ジェンダーも課題となっています。先進国では、男性の方が女性よりもスマートフォンを所有し、インターネットにアクセスする機会が多いのに対し、世界では約12億人の女性が携帯電話を持っていません。そのため、世界中の女性は男性に比べてデジタル技術にアクセスする機会が少ないのです。
社会において、インターネットに頻繁にアクセスする人々は、共通の興味を持つ人々の間で人間関係やソーシャルネットワークを構築します。そのため、インターネットへのアクセスが少ない、あるいは全くアクセスしない人々に比べて、収入を得たり仕事を見つけたりする機会が増えます。貧困層や発展途上地域の人々は、インターネットにアクセスする機会が少なくなります。
障害のある人のインターネットアクセス率も低いですが、これは、必要な手段が提供されたとしても、身体的な制約により、それらの手段を使ってインターネットにアクセスすることが非常に困難になるためです。
PV:では、社会における情報格差の原因は何でしょうか?
タイ・タン・ハ准教授:社会におけるデジタルディバイドの発生には、主にいくつかの要因があると考えています。例えば、低所得者はインターネットへのアクセスが少ないこと、発展途上地域ではインターネットへのアクセス機会が少ないこと、優れた知識、スキル、外国語能力を持つ人は、学習や日常生活においてインターネット上の豊富なリソースを効果的に活用できること、そして例外的なケースとして、十分な資金を持つ人々がインターネットを全く、あるいはほとんど利用しないことなどが挙げられます。さらに、国家間の軍事紛争も、紛争当事国と紛争の影響を受けていない国との間にデジタルディバイドを生み出しています。
PV:あなたの意見では、社会におけるデジタル格差をどのように埋めることができるでしょうか?
タイ・タン・ハ准教授:国際電気通信連合(ITU)と国連教育科学文化機関(UNESCO)が提唱する「デジタルデバイド縮小戦略」によると、この問題に対処するための10の解決策が示されています。これには、ブロードバンド計画におけるデジタル包摂の促進とデジタル経済の役割拡大への取り組み、デジタルリテラシーとスキルの向上、脆弱層向けの政策支援、インターネットアクセス政策と世界との連携、インターネットとインフラのニーズへの重点化、オンライン上の児童の保護、環境への影響の抑制、情報技術とイノベーションの促進、そしてブロードバンドインターネットの低価格化などが含まれます。
PV:ありがとうございました!
勝利(実行)
※関連ニュースや記事をご覧になるには経済セクションをご覧ください。
[広告2]
ソース











































































































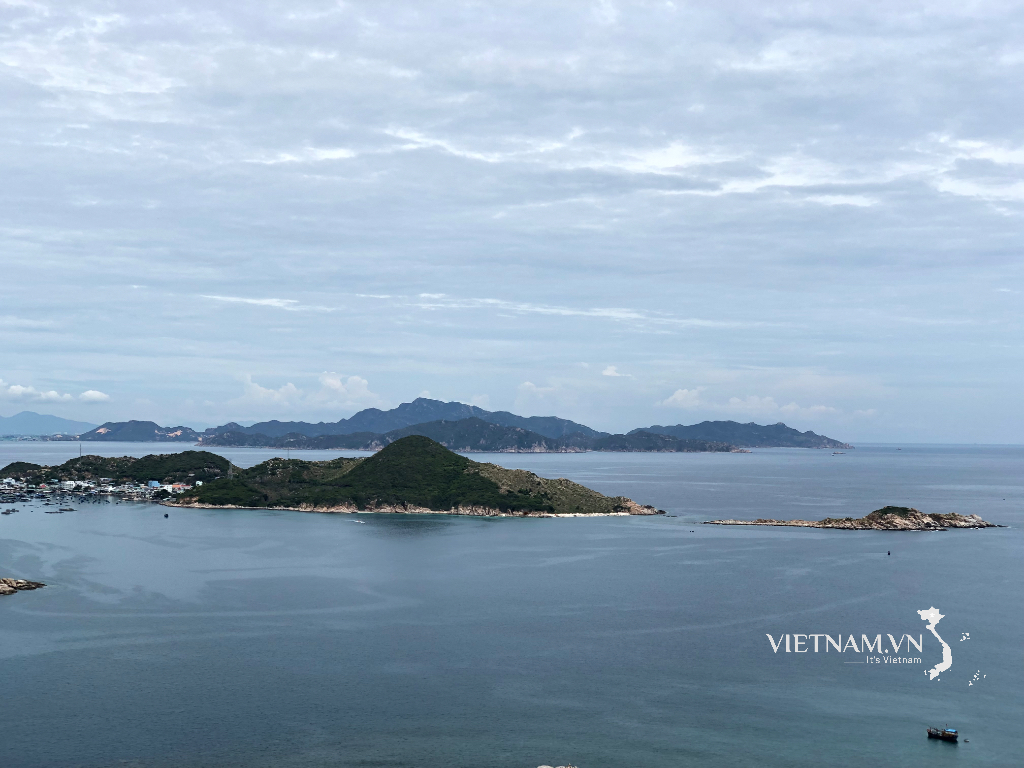


コメント (0)