両親へ、愛の言葉を二つ。
民俗学者のナット・タン氏によると、「父」と「母」という言葉は古代から存在していた。『リン・ナム・チッチ・クアイ』に記された「ホンバン」の伝説には、人々が助けを必要とするたびにラック・ロン王に「父上よ、どこへ行っても、なぜ私たちを助けに来ないのですか?」と祈ったことが記されている。その文の下に、著者は「南の人々は当時から父親を『ボー』(父)と呼ぶようになった」と記している。「ボー」(「ボー」と同音異義語)という言葉は今日でも使われており、「ボー・ラオ」(老人)は老人を指し、これは年老いた父親に相当する。
『カム・ディン・ヴィエット・スー・トン・ジャム・クオン・ムック』という書物には、次のように記されている。「タン・ヴィ(791年)、ドゥオンラム(現在のソンタイ省フックトー郡)出身のフン・フオンは、唐朝の占領政府に対して蜂起を起こした。彼の死後、兵士たちは彼の息子を後継者に即位させた。彼らは彼を敬愛し、寺院を建て、彼を偉大な恩人であり父親のような存在とみなし、ボー・カイ・ダイ・ヴオンと称した。」
「『父』と『母』という言葉は何世紀にもわたって使われ続け、今もなおベトナム語とベトナム文学においてその力強さを保っています」と研究者のナット・タン氏は断言する。ベトナムのことわざには、「愚かな子は母に恥をかかせる」や「9月にはミカンの実が下に実り、3月には野生のマンゴーが芽を出し、母が戻ってくる」(「母」は子を指す)などがある。
紅河デルタ地域の多くの地域では、両親を「お父さん」や「お母さん」と呼ぶだけでなく、「先生ブー」、南部では「ティアマ」、 フーイエンでは「バメ」と呼ぶこともあります。研究者のナット・タン氏は著書『田舎の習慣と伝統』の中で、両親は「いとこ」や「叔母さん」とも呼ばれていると述べています。これは、封建時代から20世紀初頭の西洋化運動に至るまで、ベトナムで流行した流行でした。「昔は、官僚の家庭で働く人々だけでなく、一般の人々でさえ、この階級の息子や嫁を『従兄弟』『叔母』と呼ぶ習慣がありました。そして、若い旦那様や奥様の子供たちもそれに倣い、両親を『従兄弟』『叔母』と呼ぶようになり、そうした家庭では人々はそれを誇りとし、好んでいました。この習慣は徐々に広まり、最初は公務員(フランス植民地時代には、多くの公務員が高官に劣らない地位を占めていました)から始まり、都市の商人へと広がっていきました。」
「『叔父』『叔母』という言葉は凧のように勢いを増し、『父』『母』を覆い隠し、取って代わろうとしたが、1945年8月に官僚体制が終焉を迎えると同時に、ひっそりと、そして恐ろしく沈黙の中に退いた。それ以来、『叔父』『叔母』という言葉は、本来の純粋な意味に戻った。『叔父』は母の弟、『叔母』は叔父の妻を意味するようになった」とナット・タン氏は自身の意見を述べた。
ナット・タン氏はまた、両親への愛情のこもった呼びかけは、地域によって表現の仕方は異なるものの、ベトナムの家庭では今も深く大切にされていると強調した。都会で学び、キャリアを築くために実家を離れた子どもたちは、両親のもとに戻り、温かい抱擁を受けられる日を今でも待ち望んでいる。たとえ髪が白くなっても、親は子どもを世間知らずで愚か者だと決めつけるのだ。
「数え切れないほどの紆余曲折を経ても、『父』と『母』という言葉は依然として正式な言葉であり続けている。民謡、ことわざ、文学、詩には、他の言葉が使われる余地はほとんどない。『息子が父を超えると、家族に祝福がもたらされる』『父は塩辛いものを食べ、息子は水を渇望する』『母は限りない愛情で子を育て、子は日を数えて母に報いる』『息子、嫁は他人の嫁のようなものだ』(『レ・クイ・ドン』―夫の実家へ行く息子への母の忠告を題材にした詩)などである」とナット・タン氏は締めくくった。
「八月は父の命日、三月は母の命日」という諺は今日まで受け継がれ、今もなおその価値を保っています。この諺は、太陰暦八月にバトハイ王とフン・ダオ・ヴオン王、三月にリュウ・ハン王女を偲ぶ毎年の儀式を、私たち一人ひとりに思い起こさせてくれます。これは、母と父、そして女神と神々の両方を人々が心から崇敬する、文化と宗教の美しさを反映しています。
 |
映画『自転車泥棒』のワンシーン。(出典:ST) |
「偉大な野望を果たせなかった父を悼みます。」
「昔、父は座ってワインを飲み、母は座って編み物をしていました。/冬の外では、ガジュマルの木が葉を落としていました…/昔、母は父の枕元に遠く離れて座り、父の大きな野望が果たされなかったことを哀れに思っていました…」(トラン・ティエン - 私の母)
この歌詞は私にとってとても馴染み深いものです。父が東欧行きを計画していた頃のことを思い出します。父はハノイに行き、長い間待ち続けていましたが、その後、EUが崩壊し、父は失業して実家に帰って農業を始めました。当時の生活は大変で、母は教師の仕事に加えて、物販の仕事もこなさなければならず、父は元官僚で、農業には全く馴染みがありませんでした。当時の家族の苦難を考えると、「大志を果たせなかった父を悼む」という歌詞の意味が本当によく理解できました。
作曲家トラン・ティエンの歌は母親を歌っていますが、父親の姿はより陰鬱です。絵に描かれているのは、不運に見舞われた父親が酒を飲みながら座っている姿です。隣にはセーターを編む女性がいて、彼に温もりを与えています。大きな野望は打ち砕かれましたが、それでも家族の支えになりたいという思いは変わりませんでした。しかし、境遇は彼を迷わせます。タン・ダが歌ったように、「才能は高く、地位は低く、野心は抑えられ、故郷を忘れて彷徨い続ける」のです。この歌は、不運に見舞われた父親が、家族への深い愛情を持ち、困難な時にも互いに寄り添い支え合う姿を描いています。
ヴィットリオ・デ・シーカ監督による1946年の傑作映画『自転車泥棒』は、古典作品とみなされながらも、今日に至るまで観客の心を揺さぶり続けています。ローマに住む失業中のリッチという男が、長い年月を経て、ようやく求人広告で仕事を見つける物語です。ただし、仕事に通うための自転車を持っていることが条件です。
そのため、妻は車を買うためだけに多くの家財道具を売り払わざるを得ませんでした。しかし、彼が路上でポスターを貼っている間に、彼の生活の糧は盗まれてしまいました。彼と息子のブルーノは、自分たちと同じように何十万人もの貧困層が暮らす広大な街で、必死に車を探さなければなりませんでした。
そしてついに、泥棒が捕まった時、群衆に守られていたため、自転車を取り戻すことができませんでした。絶望と混乱の中、彼は別の自転車を盗もうとしましたが、失敗しました…。リッチ一家が自転車を探し、盗み出すまでの旅は、当時のイタリアの歴史と社会の一端を物語っています。この映画に登場する自転車は世界を魅了し、常にリアリズムの真髄とされ、1949年にはアカデミー外国語映画賞を受賞しました。そして、史上最高の映画に選ばれています。
この映画は、行き詰まり、見捨てられ、未来を失った彼らの不幸な境遇に、深く胸を締め付ける悲しみを残します。しかし、心の奥底では、父と息子は互いへの信頼、愛、そして希望を抱き続けています。
最近観た映画は、中国の霍建奇監督の『あの山、あの人、あの犬』です。父と息子の関係を描いた感動的な作品です。1980年代、中国湖南省の山岳地帯で郵便配達員として働く父と息子の、しなやかで愛情深く、そして感動的な物語です。
 |
映画『自転車泥棒』のワンシーン。(出典: ST) |
山腹にある自宅の玄関に、孤独な老婦人が座っていた。彼女は孫からの手紙を持ってくる郵便配達員を待っていた。孫はずっと前に家を出て、なぜか帰ってこなかったのだ。彼女は孫を恋しがり、悲しみで目がくらむほど泣いていた。しかし、実際には孫からの手紙はなかった。郵便配達員は彼女の思いを汲み取り、白紙の手紙を書き、彼女に読み聞かせた。老婦人はその手紙を聞くたびに涙を流し、手紙を胸に抱きしめた。郵便配達員と息子が去った後も、老婦人はそこに留まり、いつか彼らが戻ってくることを願っていた…。それは私にとって忘れられない光景だった。
父親は引退の準備をしており、息子は父親の跡を継ぎました。初めての郵便配達の旅は父親に同行し、そして最後の旅でもありました。ラオ・ニーという名の愛犬は、彼の常に寄り添う存在でした。3日間、彼らは村々を通り、野原、森、小川、そして険しい斜面を越え、郵便を配達しました。父親は息子に、仕事の仕方、人々との出会い方、挨拶の仕方、そして郵便物の配達方法を教えました。物語は一見単純なようですが、父親の足跡を辿ることで、若者は多くのことを学びました。
「郵便ルートは郵便ルートでなければならない」という原則があり、バスに乗ることはできず、正確には歩かなければなりませんでした。手紙一つ一つは受取人の熱意と反応を表していたため、決して紛失したり忘れられたりしないように、細心の注意を払って扱わなければなりませんでした。映画には、手紙が風に飛ばされ、父親がパニックに陥るシーンがあります。彼は、手紙を紛失すれば、受取人との連絡、繋がり、そしてお互いから情報を受け取ることへの期待が失われることを理解していたのです…。
息子は父の経験から学び、父は息子と山娘の戯れに自身の青春時代を投影した。そして、偶然の出会いをきっかけに山娘と結婚した。仕事で家を空けていたため、一生をかけて待ち続けた妻を気の毒に思ったという。そして、息子が成長し、自分が人生を捧げてきた仕事を引き継ぐ姿も見届けた。
彼は昇進を求めることなく、この仕事を辛抱強く続け、息子にもこの仕事を続けてほしいと願っていました。息子には仕事に喜びを見出すようにと語りかけました。「この仕事は大変だけど、たくさん旅をして人と出会うと、仕事が当たり前のことに気づき、人生はとても穏やかに感じられるんだ。」
これらは父親を描いた素晴らしい芸術作品です。成功者でも、裕福でも、有名人でもない父親たち。人生のピークを過ぎ、貧しく、失業中で、あるいは平凡な仕事に就いている男性たちです。しかし、家族への彼らの愛と犠牲は常に計り知れず、完全なものです。だからこそ、「お父さん!」という呼びかけは、どんな状況であっても、家族の中で常に響き渡るのです。
出典: https://baophapluat.vn/nghi-ve-cha-trong-doi-song-va-van-nghe-post551754.html





























































































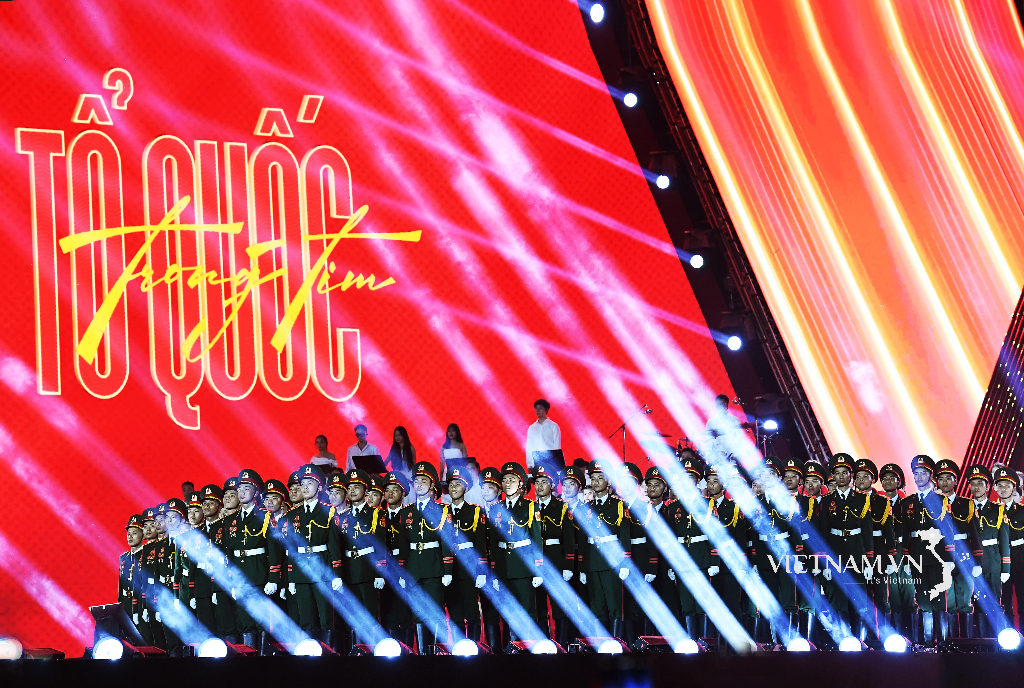

コメント (0)