 |
| 震災記念館から見た神戸ポートタワー |
私たちのグループを神戸へ案内してくれたのは、グエン・マイン・ゴックさんです。ハノイ出身で法律を学び、1990年代初頭から日本に留学し、最近はVietravelのツアーガイドをしています。ゴックさんによると、1995年の震災後も神戸には2つの建造物が残っていたそうです。それは神戸ポートタワーと、明石海峡を渡る明石海峡大橋です。
1963年に建設された高さ108メートルの神戸ポートタワーは、優美でありながら力強い佇まいをしています。震災後、神戸市民の新たなシンボルとなりました。技術の粋を集めた明石海峡大吊橋は、日本の象徴となっています。
明石海峡大橋は全長約4キロメートル、1988年に3径間にわたって建設されました。建設当時の主径間はわずか1,990メートルでしたが、地震後、 1メートル延長されました。最新の技術に加え、マグニチュード7.2の地震にも耐え、286km/hの強風、マグニチュード8.5の地震、そして水流の影響にも耐えられるジョイントを備えた2本の剛桁システムのおかげで、明石海峡大橋は無傷のまま残っていたことに、世界は驚嘆しています。
何年もの再建努力を経て、若く美しいコービーが誕生した。
今日神戸にお越しの皆さん、震災の痕跡を探したいならマリケンパークがおすすめです。現場では、被災した埠頭跡が保存されています。しかし、最も集中的かつ多様な展示が見られるのは、中央区海岸通1-5-2にある防災科学技術研究所・ヒューマンイノベーション(DRI)の地震ミュージアムです。2002年4月に開館したDRIは、1995年の神戸地震に関する資料やデータを展示・保存し、人々が震災から学ぶための場となっています。また、日本の地方自治体の人材育成や、震災対応の経験を共有する場でもあります。私たちのグループは、建物の西側にある、階段の多いかなり大きな講堂に案内されました。全員が立ち上がり、大きなスクリーンを見つめました。簡単な説明の後、突然照明が消えました。3D技術による音、映像、そして照明によって、「5時46分の震災」を目の当たりにすることができました。
一瞬にして、神戸の無傷の建物は崩壊した。電気はショートし、家屋は焼け落ち、高速道路は曲がりくねり、傾いた。なんと恐ろしい光景でしょう!
阪神・淡路大震災がもたらした7分間の視覚体験は、多くの人々に涙をこらえることのできない体験をもたらしました。なぜなら、わずか20秒だったからです。そう、たった20秒ですが、阪神・淡路大震災は6,433人の命を奪い、そのうち4,600人が神戸で亡くなりました。街は壊滅的な打撃を受けました。交通、電気、水道、病院、学校、オフィス…そして数十万戸の家屋が倒壊または甚大な被害を受け、物的損害は1,000億ドルと推定されています。その瞬間は、1995年1月17日午前5時46分(日本時間)でした。
私たちは「地震」で神戸は崩壊してしまうだろうと思っていましたが、もっと広い別の講堂で、ある少女の悲劇を題材にしたドキュメンタリーを通して、神戸の復興を目の当たりにしました。
家が倒壊したとき、彼女はそこに留まり、妹を救う方法を見つけたいと考えました。しかし、不運な妹は「逃げて!」と彼女に懇願しました。妹の言葉に耳を傾け、彼女は生き延びました。そして、神戸の他の被災者たちと同じように、家も電気も水もなく、寒さの中で暮らすという困難に立ち向かい始めました。
「街と共に永遠に生きる」と題された15分間の映画を観ると、神戸が奇跡的に復興した理由が深く理解できます。まず第一に、それはボランティアの善意から始まりました。軍隊が出動し、多くの緊急救助隊が瓦礫に閉じ込められた人々を救出し、その場で応急処置を施し、病院に搬送しました。残された建物は仮設住宅として接収され、仮設住宅や再定住地が急遽建設されました。神戸が混乱に陥らなかったのは、市民と日本政府の保護のおかげです。食料、衣類、生活必需品は直接配達されたり、無料で郵送されたりしました。そのおかげで、何十万人ものホームレスの人々が困難を乗り越え、手を携えて荒廃と廃墟から神戸の復興に貢献することができました。
神戸の復興から得られた教訓は、建物を建てる際に基礎を深く埋めたり、滑り台で転がる鉄球の上に置いたりすることでした。これにより、地震発生時に地盤が鉄球とのみ相互作用し、建物が倒壊することなく残ったのです。
現在、神戸の各家庭では、家が倒壊したり、電気や水道が止まったりした場合でもすぐに使えるように、薬や懐中電灯、飲料水、食料など、多くの必需品が入ったバッグを常備しています。
日本は地震や津波に見舞われる国です。ベトナム、特に中部沿岸地域は、しばしば暴風雨や洪水に見舞われます。1999年には、フエで歴史的な大洪水が発生し、甚大な人命と財産の損失がありました。しかし、現在そして未来の世代がその被害を理解し、自然災害に積極的に対応できるよう、修復・展示する場所が不足しています。歴史博物館は、この責務を担うことができる機関なのでしょうか?
自然災害は人類に同じ苦しみを与え、それを克服できるかどうかは人間の可能性、決意、そして意志にかかっています。
神戸の震災でそのことに気づきました。
ソース










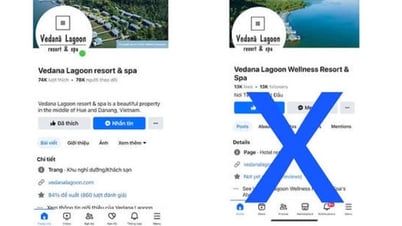






















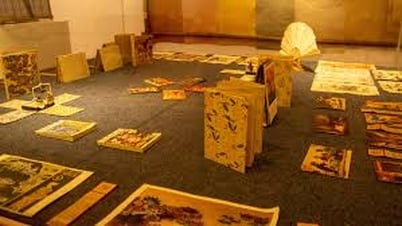


































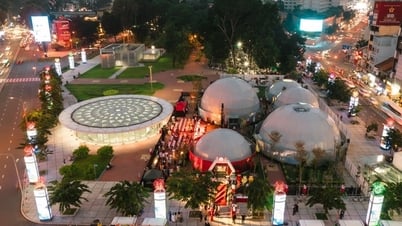












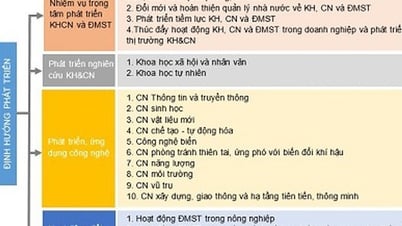









コメント (0)