先週、米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences)に掲載された研究によると、科学者たちはメガロドンの歯の化石を分析した結果、この絶滅したサメが部分的に温血動物であったことを発見した。CNNによると、メガロドンの体温は当時の推定海水温よりも約7℃高かったという。
「オトドゥス・メガロドンは他のサメに比べて体温が著しく高かったことが分かりました。これは、現代の温血動物と同程度の体内熱産生能力を持つことと整合しています」と、UCLA海洋科学・生物地理学教授で研究共著者のロバート・イーグル氏はメールで述べた。この研究結果は、この特徴がこの古代の捕食者の恐るべき体格に重要な役割を果たし、絶滅の原因となった可能性を示唆している。
アザラシを飲み込もうとするメガロドンのイラスト。写真:ロイター
体長が少なくとも15メートルあるオトドゥス・メガロドン(メガトゥース・ザメとしても知られる)は、中生代以来の海で最大の捕食動物の一つであり、約360万年前に絶滅した。
これまで科学者らはメガロドンは温血動物だったという仮説を立てていたが、この新たな研究は、この仮説を裏付ける具体的な証拠を提示した初めての研究である。
研究者たちは、この古代のサメの歯の化石に含まれる炭素13と酸素18の同位体が密接に並んでいることを発見しました。これは、体がどれほど温かかったかを示すデータポイントです。この発見から、メガロドンの平均体温は約27℃と推定されました。
現代のホホジロザメやアオザメと同様に、メガロドンは内温性で、体の特定の部分の温度を調節することができたと研究は述べています。一方、他の冷血捕食動物の体温は周囲の水温に左右されます。
シカゴのデポール大学の古生物学者で本研究の主任著者である島田健秀氏によると、このサメの巨大な体と強力な狩猟能力の主な要因の一つは温血動物であることかもしれないという。
「体が大きいほど、より広い範囲で獲物を捕獲する効率は高まりますが、それを維持するには多大なエネルギーが必要です」と島田氏はメールで述べています。「化石記録から、メガロドンは鰭脚類やクジラ目などの海棲哺乳類を捕食するために巨大な切断歯を持っていたことが分かっています。今回の研究は、温血動物への進化がメガロドンの巨大な体格の主な理由であり、高い代謝要求に対応できたという考え方に一致しています。」
これほど大型の動物が体温調節のために常に膨大なエネルギーを消費していたことが、環境の変化に伴う衰退の一因となった可能性がある。研究者たちは、メガロドンの絶滅は地球の気温低下と同時期に起きたと述べている。
「メガロドンの失踪は、高い代謝を維持するために継続的な食料供給を必要とする温血動物の脆弱性を示しています」と島田氏は述べた。「気候の寒冷化によって海洋生態系に変化が生じた可能性があります。」気候の寒冷化は海面低下を引き起こし、海洋哺乳類などメガロドンの食料源の個体群の生息地を変化させ、種の絶滅につながった。
研究論文の主執筆者でニュージャージー州ウィリアム・パターソン大学の古生物学者マイケル・グリフィス氏は、メガロドンは他の頂点捕食者に比べてはるかに大きく、そのため獲物の個体数の変化に対してより脆弱だったと述べた。
この古代のサメについてより深く知ることは、科学者が現代の同様の海洋生物が直面している脅威をより深く理解するのに役立つ可能性があります。「この研究の大きな意義の一つは、現代のホホジロザメのような大型捕食動物が、メガロドンとの生物学的類似性のために気候変動の影響を受けやすいことを明らかにしたことです」とグリフィス氏は述べています。
VNA/ティン・トゥック新聞によると
[広告2]
ソースリンク





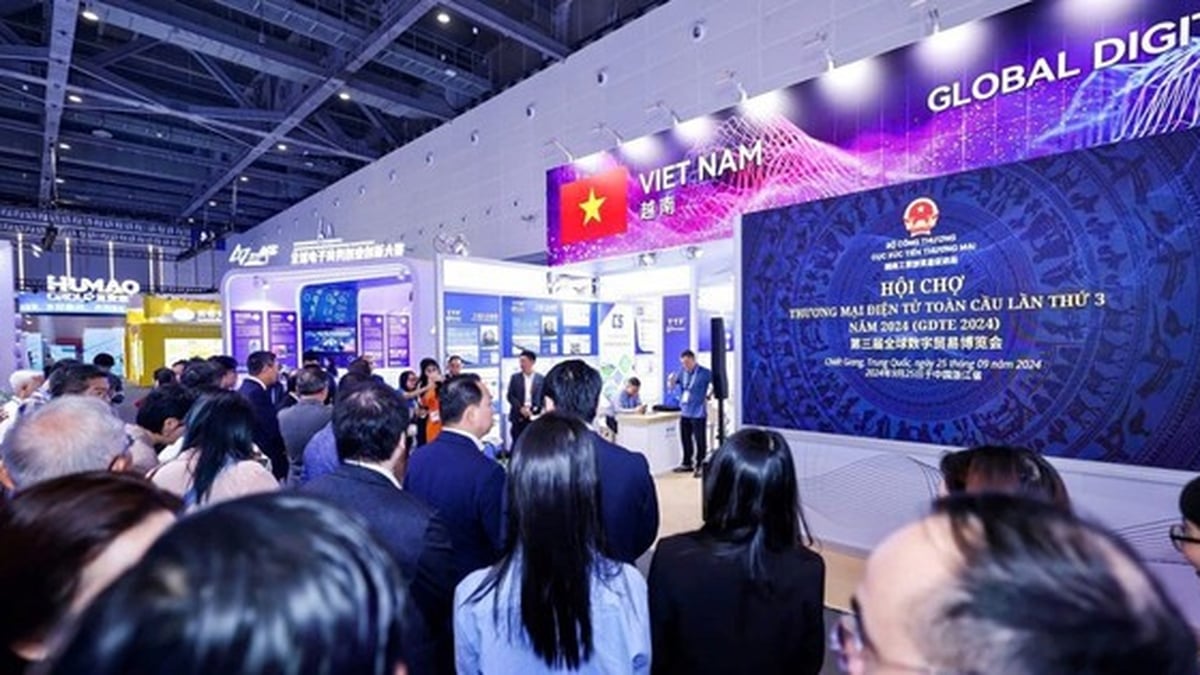






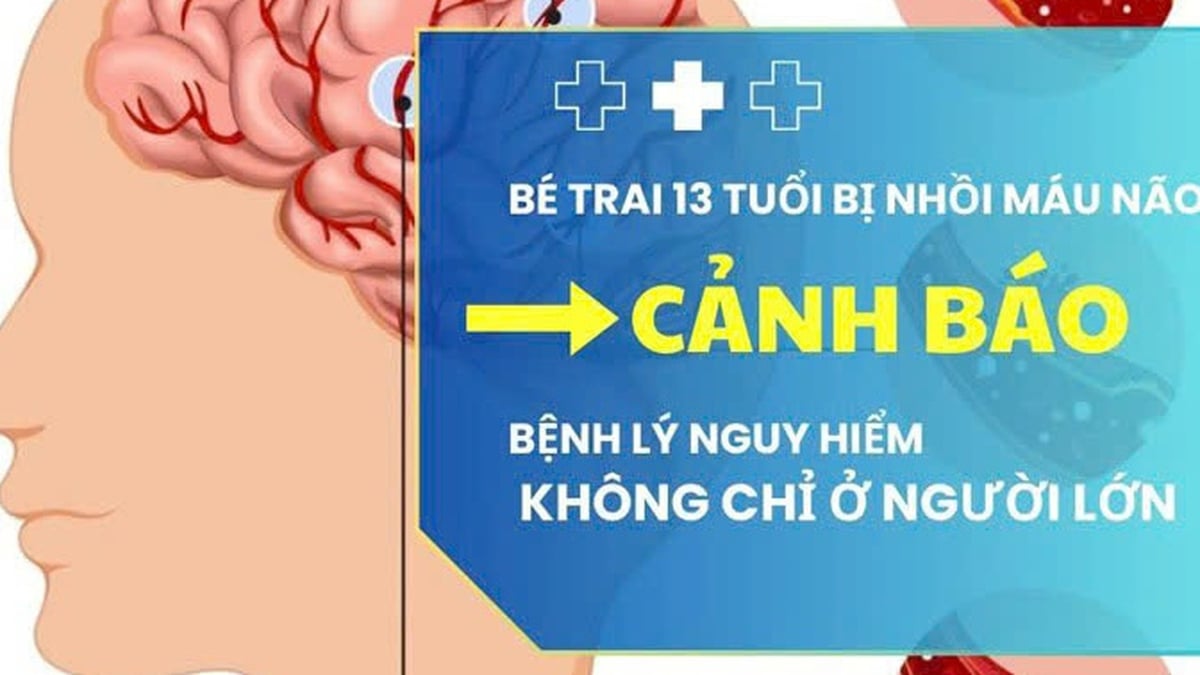









































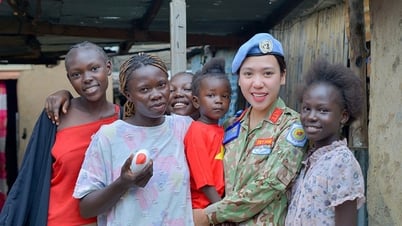


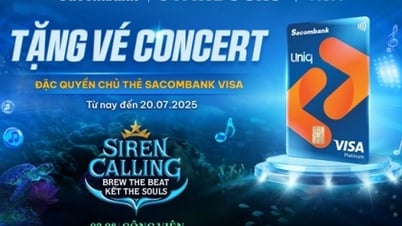




























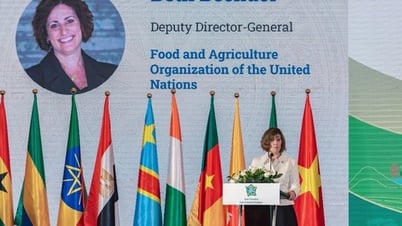















コメント (0)