2025年2月13日、日産とホンダは、12月23日に締結された覚書に基づき2024年末から開始されていた合併交渉の終了を発表した。主な理由は、双方が合意点を見出せず、特に日産がホンダの子会社になるという提案に反対したことが、交渉がすぐに行き詰まる原因になったと言われている。
両社は電動化やソフトウェア開発といった分野で協力関係を維持してきたものの、合併のような大きな進展については合意に至っていないことは明らかだ。専門家らは、今回の合意決裂は日産社内の不安定さを浮き彫りにするとともに、日本の自動車メーカーが電気自動車の潮流への対応、研究、生産にかかるコストを分担するよう求める圧力が高まっていることを浮き彫りにしていると指摘している。

この動きが確認されれば、電動化やソフトウェア変革の圧力を受けて大きな変革期を迎えている日本の自動車業界に激震が走る可能性がある。
これに関連して、毎日新聞はトヨタ幹部が日産と何らかの協力関係を築くため会談したと報じた。この情報は後にオートモーティブ・ニュースにも引用されたが、トヨタと日産は公式コメントを控えた。
トヨタの豊田章男社長は1月のコンシューマー・エレクトロニクス・ショー(CES)で、独占禁止法上の懸念を理由に、日産が関与する大規模な合併にトヨタが関与する可能性を否定した。しかし、日産とホンダの協議が決裂したことで、この姿勢は変化した可能性がある。

トヨタは長年にわたり、国内自動車業界において広範な影響力を築き上げてきました。スバル(20%)、マツダ(5.1%)、スズキ(4.9%)、いすゞ(5.9%)といった大手自動車メーカーの株式を保有しています。そのため、日産との提携や株式交換といった動きは、非常に戦略的で、複雑なものになる可能性があります。
実際、豊田章男社長は、日産とホンダの合併覚書調印後の共同プレスリリースに失望した。「製品に関する具体的な内容はなく、『成長エンジン』や『モビリティにおける世界リーダー』といった漠然とした言葉だけでした」と豊田社長は述べ、ライバルである両社の合併計画の中身のなさを暗に批判した。
日産は、長年にわたる製品ラインアップの不一致とグローバル戦略の不一致を受け、現在、大規模なリストラを進めています。前会長のカルロス・ゴーン氏の下で、日産は2020年までに年間販売台数800万台という野心的な目標を掲げました。しかし、同社の発表によると、2024年度(2025年3月31日終了)の販売台数は330万台にとどまり、以前の目標の半分にも満たない見込みです。

製品責任者のイヴァン・エスピノサ氏は、ゴーン氏の「急速すぎる、激しすぎる」成長戦略が弊害をもたらしたことを認めた。日産は効率性回復のため、コスト削減を進めており、世界で2万人の雇用削減、7つの工場の閉鎖、部品の複雑性の70%削減、そして6つのシャシープラットフォームの生産停止などを進めている。しかし、同社は高級ブランド「インフィニティ」への投資を継続する方針を堅持している。
現在、日産はルノー、三菱との戦略的提携を計画しており、同じシャーシと部品を使用した車種を共同開発し、ブランドのみを変更して製品を市場に投入するまでのコストと時間を最適化する予定です。
トヨタと日産の協議の具体的な内容は不明だが、アナリストらは、電気自動車プラットフォームの共有、ソフトウェア開発の協力から海外市場での合弁事業の合併まで、あらゆる形態の協力が双方に大きな利益をもたらす可能性があると指摘している。

しかし、法的障壁、企業文化の違い、そして両社間の伝統的な競争関係により、交渉プロセスは長期化したり、具体的な結果に至るのが困難になったりする可能性があります。トヨタは現在、売上高、利益、技術力において圧倒的な優位に立っていますが、日産は依然として長期的な発展の方向性を見出せずに苦戦しています。
世界の自動車産業が電動化とソフトウェア技術へのシフトを加速させる中、日本の自動車メーカーが競争力を維持するためには「単独で」進むことはできない。今問われているのは、「協力するか否か」ではなく、「誰が主導権を握るか」である。
出典: https://khoahocdoisong.vn/toyota-bat-ngo-tiep-can-giai-cuu-nissan-post1542891.html





























































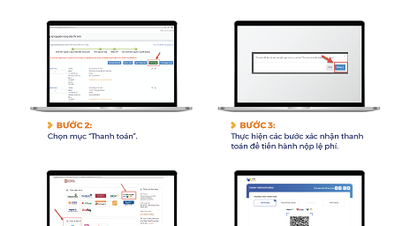



































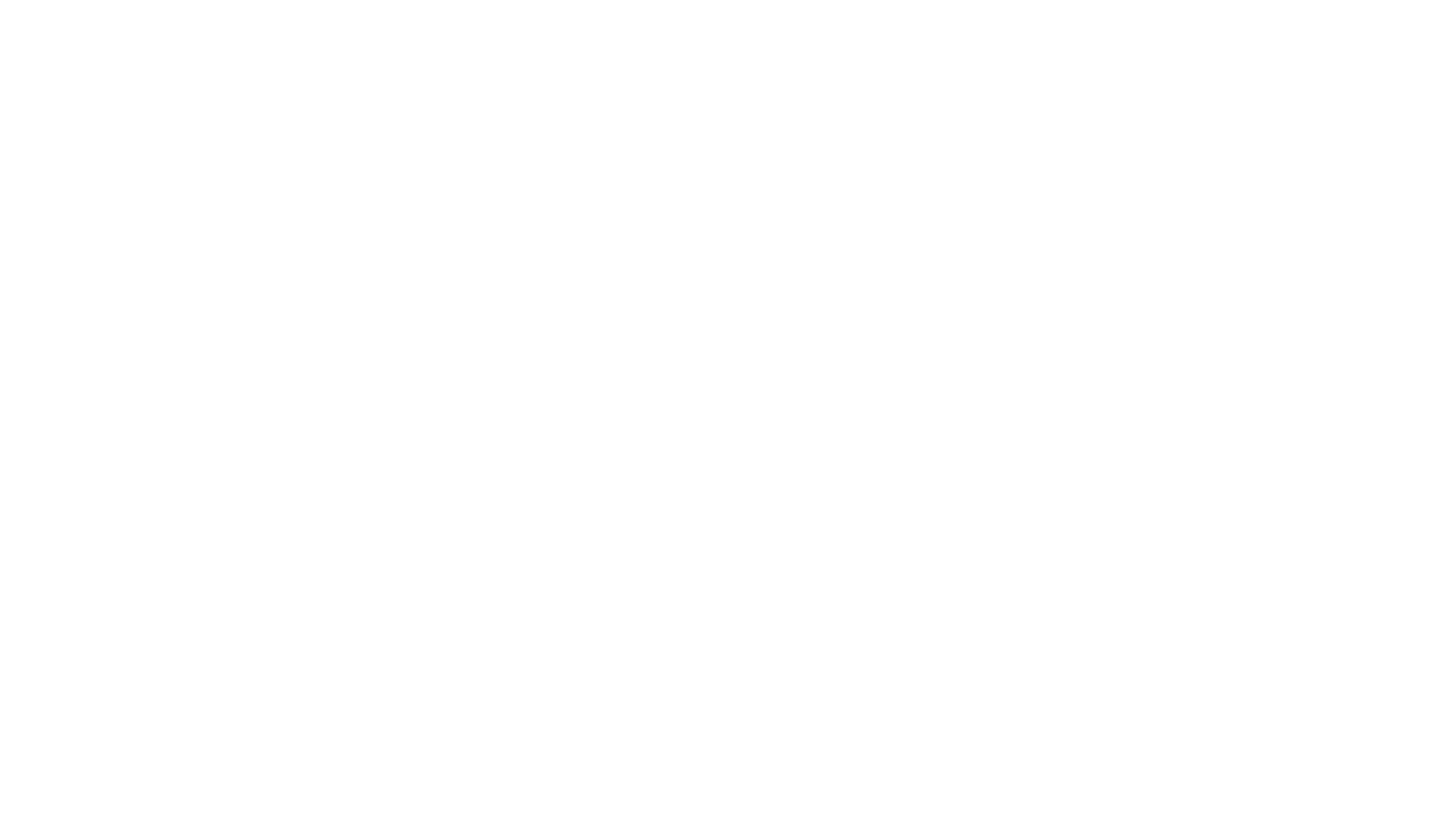


コメント (0)