背中に光背を持つ釈迦牟尼仏像は、おそらく1世紀にベレニケ市に住んでいたインド人によって作られたものと考えられています。

仏像の高さは約71センチ。写真:エジプト観光考古省
紅海沿岸の古代エジプトの港町ベレニケで発見された1900年前の仏像は、南アジアからの移民の持ち物である可能性が高いと、ライブサイエンスが5月2日に報じた。この仏像は、2550年前に南アジアに住んでいた釈迦牟尼仏を描いている。釈迦は元々は王子であったが、後に贅沢な生活を捨てて僧侶になった。
デラウェア大学の歴史学教授で、ベレニケ・プロジェクトの共同責任者であるスティーブン・サイドボサム氏によると、新たに発見された仏像は西暦90年から140年にかけてのものだ。エジプト観光考古省の担当者によると、高さ71センチのこの仏像は、仏陀が立ち、左手に衣の裾を持っている様子を描いている。仏陀の後ろには光背がある。この仏像は、ローマ帝国がエジプトを支配していた時代に遡る。当時、エジプトとインドは活発な貿易を行っていた。エジプトからの船は、象牙、胡椒、織物などの製品をエジプトに頻繁に運んでいた。この仏像は、ベレニケに住んでいた南アジアの人々によって作られた可能性がある。
考古学者たちは、ベレニケでこの像に加え、サンスクリット語の碑文も発見しました。この碑文は破壊されたものの、244年から249年まで在位したローマ皇帝マルクス・ユリウス・フィリップスの治世中に作成されたものです。サイドボサム氏とその同僚たちは、この発見を学術誌に掲載する準備を進めています。
リチャード・サロモンによると、サンスクリット語の碑文は、古代エジプトに貿易のためではなく、定住したエジプト商人のコミュニティが存在したことを示している。また、歴史記録はアレクサンドリアにインド人が住んでいたことを示している。
アン・カン( Live Scienceによると)
[広告2]
ソースリンク




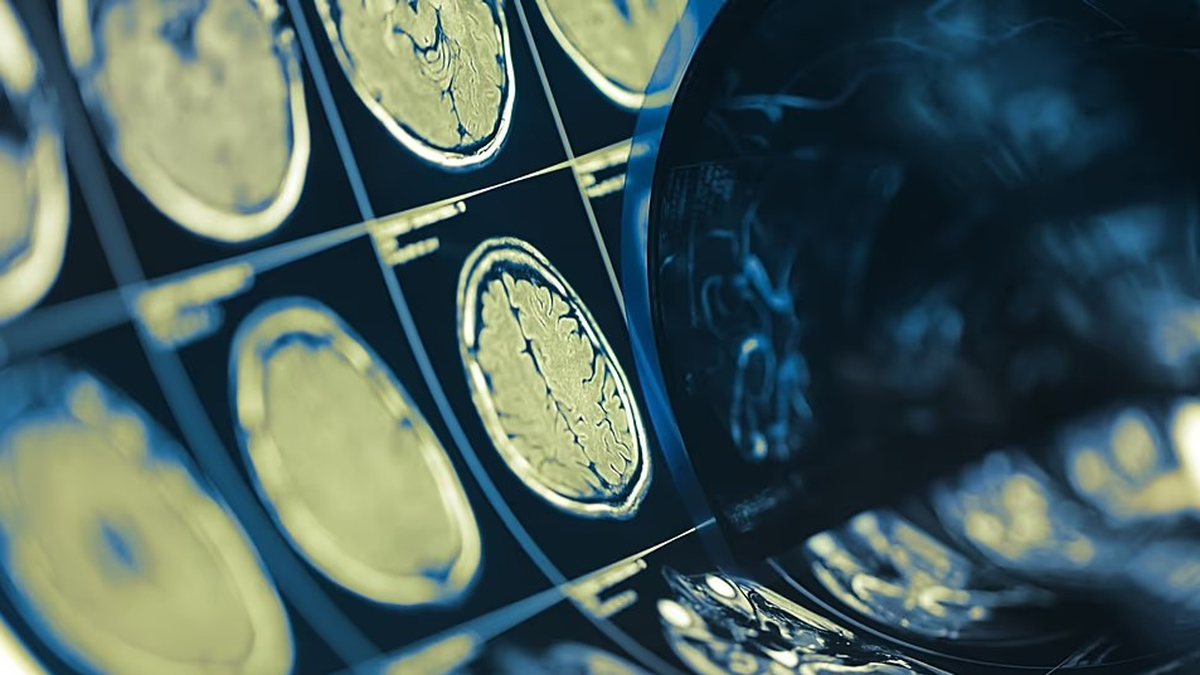




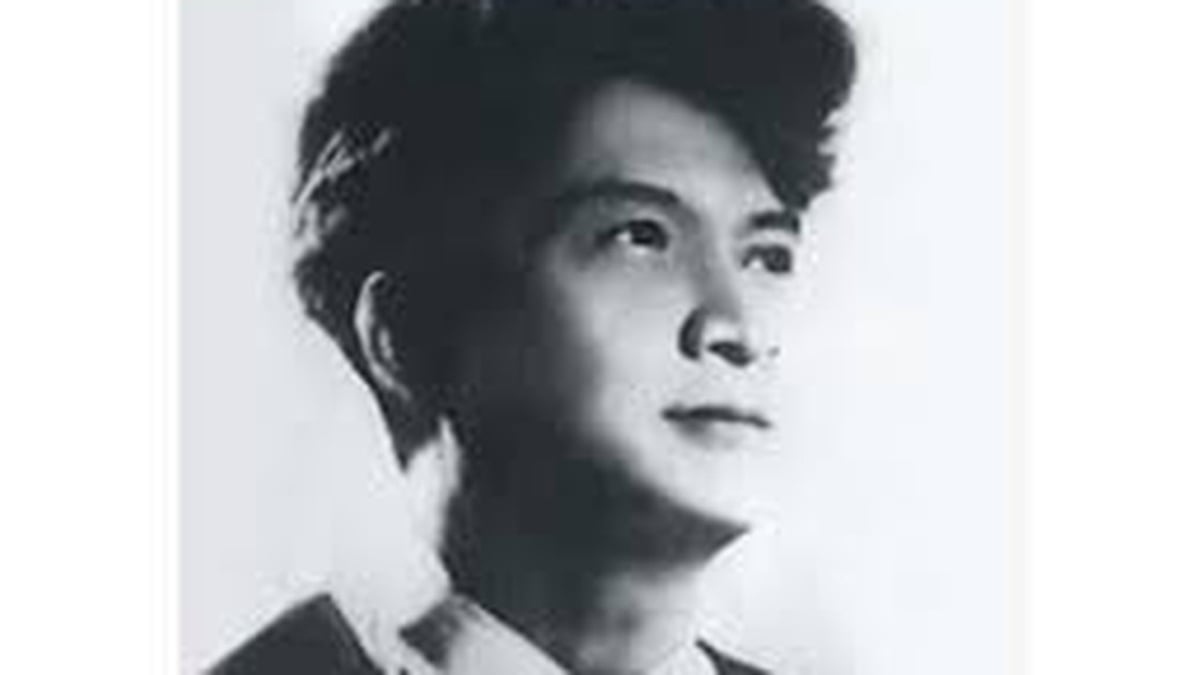












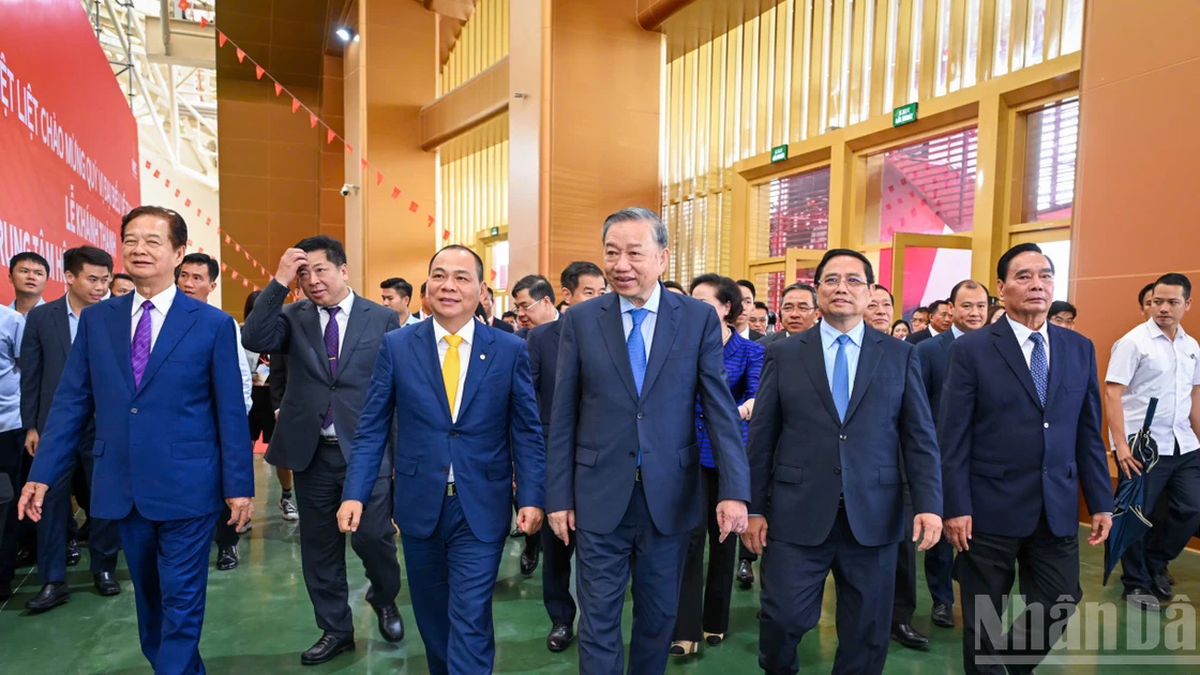


![[写真] ト・ラム事務総長が建国記念日を祝う250のプロジェクトの開所式と起工式に出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/19/3aa7478438a8470e9c63f4951a16248b)

![[写真] 政治局はダナン市党委員会常務委員会とクアンニン省党委員会と協力する](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/19/b1678391898c4d32a05132bec02dd6e1)



![[写真] ホーチミン市初の国際金融センタービルのクローズアップ](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/19/3f06082e1b534742a13b7029b76c69b6)













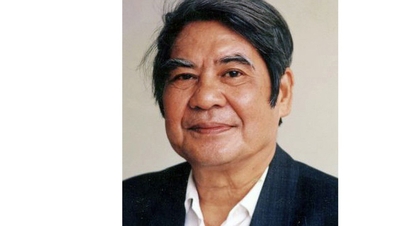






















































コメント (0)