日経アジアによると、最近公開された日本映画『おいしい給食3』では、デートを待つ10代の若者のように、熱心に給食を楽しみにしている30代の中学校の数学教師が主人公だという。

最近公開された映画『おいしい給食3』は、日本の学校給食における子どもたちの幸せを、視聴者に深く理解させてくれます。写真:2024おいしい給食製作委員会
先生(ハンサムな日本人俳優、市原隼人演じる)は、喜びに満ちた表情で登場した。昼食が始まると、先生は飛び上がってクラス全員で校歌を歌い、そしていよいよ食事の時間となった。
1980年代は、学校給食に大きな革新が起きた時代でした。日本版給食では、スパゲッティやチキンティッカといったエキゾチックな料理が中心でした。生徒たちは白いエプロンと帽子をかぶり、調理場からテーブルまで食べ物を運び、給食を楽しみました。食事が終わると、食器や調理器具は調理場に戻され、エプロンとマスクは保護者が洗うために家に持ち帰られました。
日本の学校では、毎日正午になると教室が「レストラン」に早変わり。「いただきます」という掛け声が響き渡ります。これは、食事を作ってくれた人への感謝の気持ちを表す、丁寧な日本語です。
「給食」は1947年に日本の公立学校給食制度に登場しました。当時、給食で育った子どもたちは今や70代、80代です。1950年代には牛乳は贅沢品だったと言われていますが、1960年代には全国の学校給食で牛乳が提供されるようになりました。
最近では、乳糖不耐症の人向けに水やお茶の代替品が用意されているほか、留学生向けにベジタリアン向けのメニューも用意されています。しかし、ほとんどの日本人にとって「給食」は、牛乳、パン、野菜、そして前菜という、これまでと変わらないものです。

1955年頃の日本の小学生の昼食の様子。写真:ゲッティイメージズ
昼食は十分な栄養を確保する
味はこれまであまり問題ではありませんでした。メニューは常に創意工夫を凝らし、成長期の体に必要なカロリー、タンパク質、栄養素を摂取できるように工夫されています。東京の小学校の給食費は平均255円(1.58ドル)で、10 年間のインフレの中でも比較的安定しています。
牛乳と並んで、手頃な価格でタンパク質を豊富に含む食品は、何世代にもわたって日本の小学生の食卓にありました。「おいしい給食」シリーズで人気を博した当時、学校給食では豚肉、鶏肉、卵といった主食の代わりとして鯨肉がよく提供されていました。しかし、2010年頃に大きな議論が巻き起こり、鯨肉は学校給食のメニューから姿を消しました。しかし、ここ5年ほどは頻度こそ減ったものの、再びメニューに登場しています。
日本では、学校給食は適切な栄養を提供するだけでなく、 教育の不可欠な要素とみなされています。2005年以降、政府は学校に対し、子どもたちに食品の起源や原材料について教えることを義務付けました。また、子どもたちは食べ物を最後まで食べきることも教えられています。
現代の子供たちは、ソテーした野菜やフライドチキンといった料理を好みます。白パンの代わりにクロワッサンを食べることも珍しくありません。また、フルーツゼリーやジャムを添えたヨーグルトといった軽めのデザートも人気です。食のトレンドは、国や世界の発展とともに変化します。
20世紀当時、学校給食のトレーはそれほど「生徒に優しい」とは思えませんでした。生徒たちは常温の牛乳や鯨のフライを好まないかもしれません。しかし、誰も文句を言いませんでした。食事を断れば、空腹に陥ることになります。さらに悪いことに、教師は家に手紙を送ることもあり、その場合、保護者は校長室に呼び出されることになります。
学校給食の代わりになるものはありますか?私立学校では、生徒は自分で弁当を持参する必要があります。
公立学校でも、高校生になると弁当は必須となります。それでも、多くの日本の家庭は標準的な学校給食で十分だと考えています。さらに重要なのは、今では8割近くが外で働いている母親の負担が軽減されることです。学校給食は日本の家庭にとって特別な楽しみとなっています。
過去 70 年にわたり、「給食」は日本人の驚異的な長寿に貢献し、子どもと大人の肥満率が経済協力開発機構 (OECD) 加盟国の中で最も低い水準にとどまることに寄与してきたと評価されてきました。
[広告2]
出典: https://toquoc.vn/bua-trua-truong-tro-thanh-niem-vui-thich-cua-hoc-sinh-nhat-ban-20240718101804393.htm



![[写真] ファム・ミン・チン首相がIUUに関する運営委員会の第14回会合を議長として開催](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/23/a5244e94b6dd49b3b52bbb92201c6986)
![[写真] ニャンダン新聞編集長レ・クオック・ミン氏がパサクソン新聞の代表団を迎えた](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/23/da79369d8d2849318c3fe8e792f4ce16)

![[写真] ト・ラム書記長がハノイ市で有権者と面会](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/23/d3d496df306d42528b1efa01c19b9c1f)
















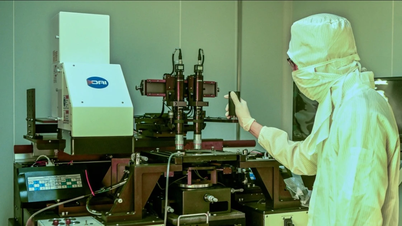








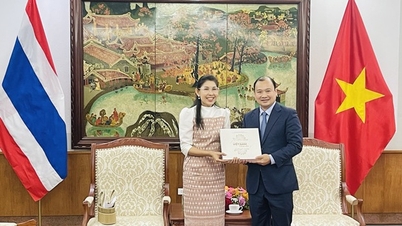
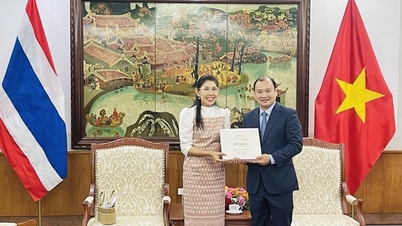



















































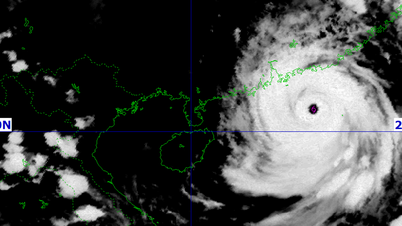



















コメント (0)