 |
| イラスト:ファン・ニャン |
70年近く前の春、私の祖母は南へ向かう途中、曽祖母の娘として生まれました。当時、列車、船、そしてボートでの旅はまだ容易ではなく、貧しい人々にとって飛行機に乗ることは空の星を拾うのと同じくらい困難だったでしょう。ゴックさんは、曽祖父母が故郷から何千キロも離れた場所を歩き、ましてや曽祖母が妊娠7~8ヶ月のお腹を抱え、知り合いというよりは見知らぬ人々の群れに混じって、想像もしていなかった約束の地に辿り着くことなど、想像もできませんでした。誰もが、満腹になるよりも空腹になる日々が続いた過酷な旅の後では、曽祖母がこんなに早く出産する苦しみを乗り越えられるはずがないと考えていました。曽祖母自身も、乗り越えられるとは思っていませんでした。しかし、その日、遠くの山からラック族の鳥の群れが空を飛び交い、曽祖母を救ってくれたと、ゴックさんは言います。群れをなす鳥たちの深い鳴き声は、彼女の強い本能を呼び覚ます歌のようだった...
- ラック湖の鳥たちの鳴き声は、まるで何千年も前から聞こえてくるかのよう。これほど深く、温かく、誇り高い声を持つ鳥は他になく、誰も真似できません。高く遠くへ、共に飛びたいと願う鳥だけが、あの魔法のような音を出すことができるのです。- 祖母は何度も、ラック湖の鳥たちのことを熱く語ってくれました。
「あの叫び声を聞きましたか?」ゴックは疑わしそうに尋ねた。
少年が疑念を抱くのも無理はなかった。ラック鳥の写真を見たり、先生たちがラック鳥について話しているのを聞いたことはあったが、その鳥の鳴き声についてはっきりと教えてくれた人はいなかった。祖母がいつも熱心に語ってくれたように、その鳥の鳴き声は伝説やおとぎ話の中にしか存在しないようだった。
「あなたは聞いていないかもしれませんが、ご先祖様はきっと聞いていたはずです。私たちの故郷は、かつてラック鳥が住んでいた場所です。そして時々、曽祖母が言っていたように、私が生まれた日に、ラック鳥の群れが戻ってきてくれたこともあったんです…」
- では、なぜあなたの本では鳥の鳴き声について誰も触れていないのですか?
- 私たちの祖先のように、それを見た人や聞いた人は文盲だったので、鳥のような鳴き声を描くことができる人は誰もいませんでしたし、それを教えてくれる作家や教師に会うこともできませんでした。
おばあちゃんはゆっくりと言った。ゴックは笑った。「もしかしたら、おばあちゃんの言う通りだったのかもしれない。昔は、読み書きができる人はほとんどいなかったのよ」
* * *
曽祖父母が北から南へ運んできた荷物の中には、蕾がいっぱいの小さな桃の木と、ラック族の鳥の群れが刻まれた青銅の太鼓がありました。桃の木は道中で花を咲かせましたが、ファンランに着くと、暑さと家族が増えたせいで徐々に枯れてしまい、曽祖父は道端の住民の庭に植え替えを頼まざるを得ませんでした。定住地を決めると、彼は一人で家を建て、木や竹で作ったドアや窓、トタン屋根の屋根を建てました。…家の中央右側の棟は、フン王の慰霊碑として残しました。彼が持っていた唯一の「資本」は、何代にもわたって受け継がれてきた青銅の太鼓で、北から南へ運んだのです。旅は予想以上に困難で長いものでした。道中、米と食料が尽きた。彼は空腹を満たすために太鼓と食料を交換することに同意する代わりに、残って耕作や鍬を雇った。家族全員の食料と引き換えに、重労働や危険な仕事も厭わなかった。銅の太鼓は家宝であり、食料と交換するなど到底受け入れられるはずがなかった。
曽祖父の家の近所の人たちも田舎の友人で、一緒に大工をしていたため、フン王、ティエン・ズン王、チュー・ドン・トゥ、タン・ジョン王などの像を手分けして彫り、祠に安置しました。ゴックが書物や教科書の中にしか存在しないと思っていたフン王時代の人物たちは、実は彼女の家族の中でずっと昔から存在していたのです。毎年、祖先の命日であるテトが近づくと、ゴックは祖母と一緒に木像を清めました。ゴックは彼らの顔を何度も見返しましたが、見覚えのある顔が何度も現れました。
* * *
ゴックは祖母から、フン王寺の建立の物語、遠い山から目覚めの歌を運んで飛んできたラック族の鳥たちの群れの物語を、何年も前にこの世界に生まれるために何度も何度も聞かされてきた。父親は時々彼女に「一度だけ話せばいい。あの子は覚えているよ」と念を押した。彼女は何度も何度もその話を聞かせた。それは彼女の記憶に深く刻み込まれ、年老いて記憶は徐々に薄れていったが、物語は残った。祖母が話すたびに、ゴックは熱心に耳を傾けた。認知症のため、祖母は時折、言葉を止め、戸惑った様子でゴックに尋ねた。「あら、お名前は?誰の息子なの?」と。初めて尋ねた時、ゴックは祖母以上に混乱していた。最も愛する者が自分のことを知らないという事実を受け入れられず、息子は泣き崩れた。少し成長すると、ゴックは祖母への怒りは消え、むしろ彼女を深く愛するようになった。
「おばあちゃん、歴史の先生も美術の先生も、ラック鳥は伝説の中にしか存在せず、現実には存在しないと言っていました。」 - 青銅の太鼓の表面にラック鳥を描く授業の後で、ゴックさんはそう言った。
「いいえ、私の故郷にもかつてラック鳥が現れたんです。ほら、この銅製の太鼓の表面の装飾はすべて実物から描いたものです。そして、私の曽祖母を出産から救ってくれたのはラック鳥の群れだったというのは紛れもない事実です。だからこそ、祖父、父、息子、そして私がいるのです。」
ゴックは静かに「はい」と答えた。科学と歴史の観点から見れば、あの伝説の鳥は存在しないかもしれない。しかし、祖母をはじめとする祖先の土地の子孫たちの間で代々伝えられてきた物語や証拠から判断すると、ゴックは今でもあの鳥は太古の昔から存在していたと信じている。もしかしたら、千年後には科学者たちがラックの鳥の化石骨を発見し、かつてこの地球上に存在していたことを証明してくれるかもしれない。先生も言っていたが、科学と歴史には常に予期せぬ変化がある、そうだろう?
* * *
おばあちゃんはまさにゴックの親友です。両親は忙しく働き、ゴックを一人で育てているので、世界中の誰よりもゴックのことを理解しています。頭の中にはおとぎ話や面白い話の宝庫があり、暇な時や眠れない時にはいつもゴックに聞かせています。このわずか数十平方メートルの庭園と寺院の敷地には、長年かけて数え切れないほどの物語が積み重ねられてきました。家のはるか裏手に流れる運河の物語。かつてはサイゴン川から流れ出る大きな川でした。人口はどんどん増え、土地は埋め立てられ、川は徐々に遠ざかっていきました。飢饉の時代に法外な値段で売りつけられた木像の話。しかし、公共物だったため誰も売ってくれませんでした。言うまでもなく、長年にわたり花と線香を捧げ、孫たちの願いと信念を込めたフン王、ティエン・ズン王、チュー・ドン・トゥ王の瞳と笑顔は、まるで木片一つ一つに魂が宿っているかのように温かかった。そして、王道の脇に植え直された桃の木の話。それは、とっくの昔に雲に変わってしまったはずなのに、彼女は今でも何度も語り続ける。毎年旧正月になると、父は美しい桃の枝を見つけてフン王の祭壇に飾る。それは祖先を祀るためであり、祖母が何年も前の桃の枝を思い出すことで故郷への郷愁を和らげるためでもある。
最近、あまりにも暑かったので、祖母の「親友」が体調を崩してしまいました。ゴックは祖母が起きている時はそばに座り、元気づけようと過去のことを思い出してはよく話していました。祖母は黙ったまま、時折目にキラキラと涙を浮かべていました。
医者は父に、おばあちゃんの病気はあと何ヶ月、何日と数えるしかないと告げました。父と母は、この時期の薬はただ症状を軽くするだけのもので、起き上がって食事をする力さえない祖母を救うには万能薬しかないことを皆が理解していたにもかかわらず、すべてを脇に置き、お粥と薬をスプーンですくって祖母の世話をしました。時々、おばあちゃんは突然目を覚まし、故郷が恋しくなり、家に帰りたがりました。昨夜、あるいは今朝の夢の中では、病院のベッドに横たわる老人の時間が、彼女のあらゆる思考のように混乱し、ラック鳥がハンモックで祖母を運んでくれる夢を見ました。また、祖父母がラック鳥の翼の先にいて、色とりどりの素晴らしい雲に向かって飛んでいくのも見ました。故郷に戻れば、薬は必要なくなります。父はおばあちゃんに少しずつお粥を食べて体力を回復するように勧め、祖母と孫を連れて故郷へ帰ると言いました。母は祖母が可哀想で、その夢は悪い前兆だと思い、涙を隠すようにこっそり背を向けた。故郷への旅は、月日とともに消えていく石油ランプのように遠いものだと、母は知っていた。
* * *
教室で描いたラック鳥の絵と全く同じものを見て、ゴックは何か違うものを描きたくなった。無意識のうちに、ラック鳥の翼にぶら下がった小さなハンモックを描き、その上に幸せそうに座るおばあちゃん、そしてその隣に小さくて微笑んでいるゴックを描いた。
しかし不思議なことに、2羽のラック鳥は祖母と孫に微笑んでいるように見えました。眼下にはピンク色の桃の花が咲き誇る山岳地帯が広がっていました。彼女は絵を見て喜んでいました。厳格な画家であるゴックの父が、先生はもちろんのこと、この作品を批判するはずがありません。そしてベルが鳴るほんの数秒前、彼女は自分が間違った依頼を描いてしまったことに気づき、本当にショックを受けました。それは、銅の太鼓にラック鳥を描くことでした。彼女と祖母が毎年磨いて傷や汚れに慣れるまで磨いてきた銅の太鼓に描かれたラック鳥の絵なのに、どういうわけか彼女は間違った題材を描いてしまったのです。
ゴックさんが描いたラック族の鳥は予想外に高得点を獲得し、週初めの国旗掲揚式で披露されました。先生は、銅の太鼓に描かれたラック族の鳥の形と完全には似ていないものの、翼にたくさんの愛を宿した特別なラック族の鳥であり、満点に値すると述べました。画家の父親は何が起こったのかを理解し、涙を浮かべながら息子を見つめました。「ありがとう」。息子に「ありがとう」と言って学ぶのは久しぶりでしたが、ゴックさんはまるで息子の言葉をもう一度聞いたかのようでした。
その晩、仕事が終わると父は絵の具を買い、ポーチの向かいの壁に絵を描き始めた。そこには毎朝朝日が差し込んでいた。父は徹夜で、ただの遊び好きな子供だと思っていた息子の絵を描き直した。絵を描けるようになるなんて、父は夢にも思っていなかったのだ。
今朝も、いつものように母とゴックが彼女を起こしてお粥を食べさせてくれました。母は父とゴックの絵を見せました。数ヶ月ぶりに、彼女は庭で車椅子に座って日光浴をしながら絵を眺めたいと言いました。病院のベッドに寝ていた時以来、珍しく震える唇の端に笑みが浮かびました。彼女はゴックを見つめました。「ここが私の故郷よ。故郷に帰れるの。こんな風に私を理解してくれるのは親友だけよ。」
ソース




























































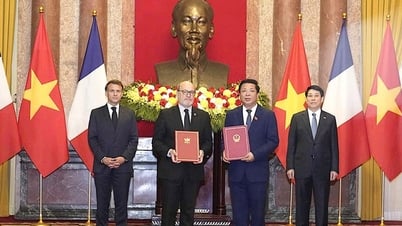
































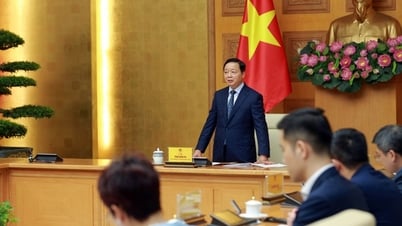






コメント (0)