数年前、中国には帰化選手が多く、この国の代表チームにも彼らが殺到していたが、これは現在の東南アジアのインドネシア、マレーシア、カンボジアのチームの様子と似ている。
しかし、上記の帰化選手(ほとんどがブラジル出身)は、人口10億人の国の代表チームを強化することに貢献できないばかりか、逆に中国チームを弱体化させている。
2002年のワールドカップ本大会に出場した中国代表は、主力選手が国内選手でした。長年にわたり帰化選手起用方針を貫いてきた中国代表ですが、それ以来、ワールドカップ本大会に出場していません。実際、彼らはもはやアジアサッカー界の強豪ではありません。
中国サッカーと日本サッカーの対比
かつて日本サッカー界は、ブラジルに帰化した選手たちを擁することで代表チームの質を向上させることを検討した。しかし、この方針を推し進めれば進めるほど、その欠点に気付くようになった。

多くの帰化選手を擁する中国チームも、2022年ワールドカップ予選でベトナムチームに敗れた(写真:ド・リン)。
本当に質の高い選手は、極東に行くためにサッカーのルーツを捨てたりはしないが、日本代表チームでプレーするために帰化を望む選手は、純然たる国内選手と質的に同じである。
勝利への意欲、規律、そして日本サッカーが目指したい主なプレースタイルとの適合性という点でも、純粋な日本人選手は帰化選手よりもはるかに優れたパフォーマンスを発揮します。
その結果、日本はアジアを代表するサッカー大国となり、着実に世界トップクラスのグループに加わりつつあります。近年のワールドカップ本戦における日本のサッカー成績は非常に安定しており、毎年決勝トーナメント進出の権利を獲得しています。
これらはすべて、日本サッカーの優れたユース育成のおかげであり、それがこのサッカーに才能の継承と継続をもたらしているのであり、帰化選手のチームのおかげではない。
これは中国サッカーにはないものです。中国サッカーは日本サッカーとはほぼ正反対です。人口10億人の国では、ユースの育成はそれほど重視されていません。帰化選手が効果的にプレーできないと、後継者不足のため、中国チームはすぐに敗北を喫します。
帰化選手の問題について、元U23ベトナム代表監督、元U20ベトナム代表監督でユース育成の専門家であるホアン・アン・トゥアン氏は次のように語った。「帰化選手の起用問題に関しては、これは一時的な解決策に過ぎず、特定の時期に、限られた人数で採用しているだけだと思います。」

ベトナムのサッカーは、優れた青少年育成のおかげで着実に発展している(写真:フオン・ドゥオン)。
「近年ベトナムサッカーが着実に発展し、今後もその発展が続くと予想される理由は、我々がタイに次いで東南アジアで最高のユーストレーニングを行っているからだ。」
インドネシアよりも安定しています。インドネシアはこの時期に多額の投資をしたかもしれませんが、インドネシアサッカーは長年同じ状況が続いており、安定していません。インドネシア人サッカー選手の大量帰化は、一時的な打開策に過ぎず、持続可能な方法とは言い難いでしょう。
一方、マレーシアサッカーについては、ラジャゴパル監督が2010年のAFFカップで優勝して以来、同国のサッカーは大きく衰退し、それ以来ずっと下り坂を続けている」とホアン・アン・トゥアン監督はさらに分析した。
「死の綱渡り」に挑む東南アジアサッカー
マレーシアサッカーについて言えば、中国サッカーと同様に、マレーシアには現在、帰化選手が溢れています。そして、中国チームと同様に、長年帰化選手を起用してきた結果、マレーシアチームは強くなるどころか、弱体化しているのです。
ホアン・アン・トゥアン監督が述べたように、ラジャゴパル監督がマレーシアチームの2010年AFFカップ優勝に貢献して以来、チームは東南アジアサッカーのトップの座に復帰していない。
近年、マレーシアチームは帰化選手が効果を発揮できていないことから、AFFカップやSEAゲームズの決勝戦からますます遠ざかっている。
マレーシアの帰化選手の問題について、元VFF副会長のドゥオン・ヴ・ラム氏は次のように分析している。「FIFAの規則によると、母国出身でない帰化選手は、帰化してその国の代表チームでプレーする前に、各開催国で少なくとも5年間連続してプレーしなければならない。」
彼らが発掘され、帰化候補に挙がった時は、若く、活力に満ち、意欲に満ちていたかもしれません。しかし、5年も経つと、彼らは年齢を重ね、体力を失い、同時にチームに貢献したいという意欲も徐々に薄れていきます。

カンボジア代表の南アフリカ生まれのセンターバック、カン・モ選手(写真:コア・グエン)。
開催国で5年間継続的に競技に出場した後、その国の代表チームに合流しても、彼らのパフォーマンスは向上するどころか低下するばかりです。地元にルーツを持たない帰化選手を起用したチームが弱体化する理由の一つはそこにあるのですが、帰化選手を起用したチームが強くなることは稀です」とラム氏は続けた。
マレーシアサッカー協会(FAM)が最近、マレーシアにルーツを持たない選手の帰化を中止すると発表したのも、まさにこのためです。FAMは、マレーシアにルーツを持たない選手の帰化を内務省および青年スポーツ省に提案したり、保証したりするつもりはないと述べました。これにより、マレーシア代表チームでのプレーが認められることになります。
若い才能の育成機会を維持する
FAMがマレーシアにルーツを持たない帰化選手を起用しない理由は、国内クラブが一時的な成果を追い求めるのではなく、若い選手の育成に注力できるようにするためだ。
ヨーロッパ出身選手の代表チームへの流入を目の当たりにしたインドネシアの専門家やメディアも、この点を指摘しています。インドネシアの専門家やファンは、帰化選手の代表チームへの流入によって、インドネシアのサッカー界の才能が活躍する機会が奪われていると公言しています。

もし帰化選手が代表チームに殺到していたら、今日のようなクアンハイは存在しなかったかもしれない。(写真:ティエン・トゥアン)
インドネシアとマレーシアに続き、今度はカンボジア代表が帰化選手を優遇する番です。しかし、カンボジア代表の東南アジアサッカーへの影響力はまだ大きくないため、仏塔の国出身のこのチームへの注目はそれほど高くありません。
しかし、元ベトナムサッカー連盟(VFF)副会長のドゥオン・ヴ・ラム氏は、何の経歴もない帰化選手を起用しながらも、強さと持続性を維持しているチームを見たことがないと述べている。したがって、カンボジア代表チームが帰化選手を起用する方針を推し進めているという事実は、必ずしも楽観的な兆候とは言えない。
一方、国内サッカーを運営する関係者は、「もしあらゆる場所で帰化選手を急いで起用したら、ベトナムサッカー界はコン・フオン、クアン・ハイ、コン・ヴィンといった選手をどこで獲得することになるのでしょうか?彼らはサッカーを愛し、サッカーを通じて有名になる若者の台頭の象徴なのです」と語った。
「帰化選手をあまりに多く起用することは、地元のサッカーの才能が成長する機会を奪うことを意味し、若い選手たちの成功への情熱と願望を奪うことにもなりかねない」と彼は付け加えた。
出典: https://dantri.com.vn/the-thao/cau-thu-nhap-tich-tran-ngap-dong-nam-a-bai-hoc-tu-bong-da-trung-quoc-20250319142104737.htm

















































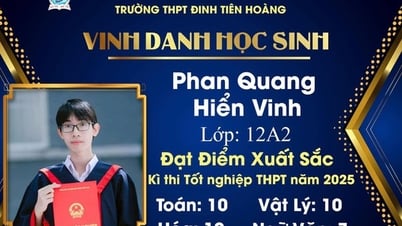



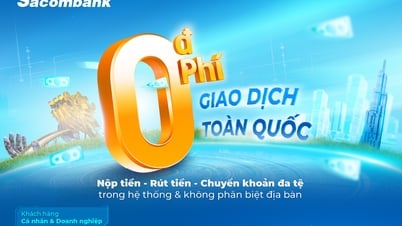










































コメント (0)