日銀は2日間にわたる金融政策決定会合の終盤、短期金利をマイナス0.1%に据え置き、10年国債利回り目標を0%に据え置くことを決定した。ただし、利回り上限の1%は固定的な上限ではなく、柔軟な上限となる。さらに、日銀は過去の会合で約束していた、無制限の国債買い入れによって利回り上限を守るというコミットメントも放棄した。
10月31日のニューヨーク証券取引所(米国)の取引では、円相場が一時1ドル=151.74円まで下落した。2022年10月に151.94円を突破すれば、1990年7月以来33年ぶりの安値となる。また、対ユーロでも2008年以来となる1ユーロ=160円の大台を割り込んだ。
11月1日の取引では、円は小幅に持ち直し、一時1ドル=151.27円まで下落しました。これは年初来で13%、新型コロナウイルス感染症のパンデミック中に記録した高値からは38%の下落です。対ユーロ為替レートは1ユーロ=160円を超える水準で推移しました。昨年も、円は対ドルで約13%下落しました。
1年前、円が1ドル=152円近くまで大幅に下落したことを受け、日本の財務省は20年以上ぶりに円の為替レートを守るため為替市場に介入した。
投資家は米国と欧州の金利上昇余地をみている一方、日本では根強い経済の弱さによって金利上昇は抑制されている。現在、米国の長期金利は4.9%前後、日本の長期金利は0.95%前後である。2022年10月21日に円が最安値を記録した時点では、米国と日本の金利はそれぞれ4.2%前後、0.25%前後であった。両国の金利はほぼ同ペースで上昇しているため、金利差は変化していない。
アナリストは、日銀のイールドカーブ・コントロール(長短金利操作)の調整は、この状況にほとんど変化をもたらさないと指摘している。JPモルガンの為替アナリスト、大島勝弘氏は、日本の長期金利が0.1%上昇するごとに、円は対ドルで0.5~1.3円程度しか上昇しないと推計している。
11月3日に発表される米国の月次雇用統計は、米国金利とドルを再び押し上げる可能性がある。10月31日に発表された米国の雇用統計は好調で、円の急落につながった。
日本が介入を含めた行動をとる用意があるかとの質問に対し、日本の外為担当トップである神田正人氏は「待機状態にある」と述べた。これは、2022年9月に日本が24年ぶりに円買い介入を行う前に神田氏が使った言葉である。一方、三菱UFJ銀行の井野哲平氏は、市場は現在これを「口頭介入としては最高レベル」と見ていると述べた。財務省高官の発言後、円の下落は一時的に小康状態となった。
しかし、政府と日銀の間には乖離があるように思われる。神田氏の発言から約5時間後、日銀は予定外の国債買い入れを発表し、長期金利の上昇を抑制する可能性があった。その後、円は再び下落した。
円安が続けば、一部のアナリストは、東京が実際に介入して通貨を支えると予想している。
[広告2]
ソースリンク





![[写真] ト・ラム事務総長が文化部門伝統の日の80周年記念式典に出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/23/7a88e6b58502490aa153adf8f0eec2b2)
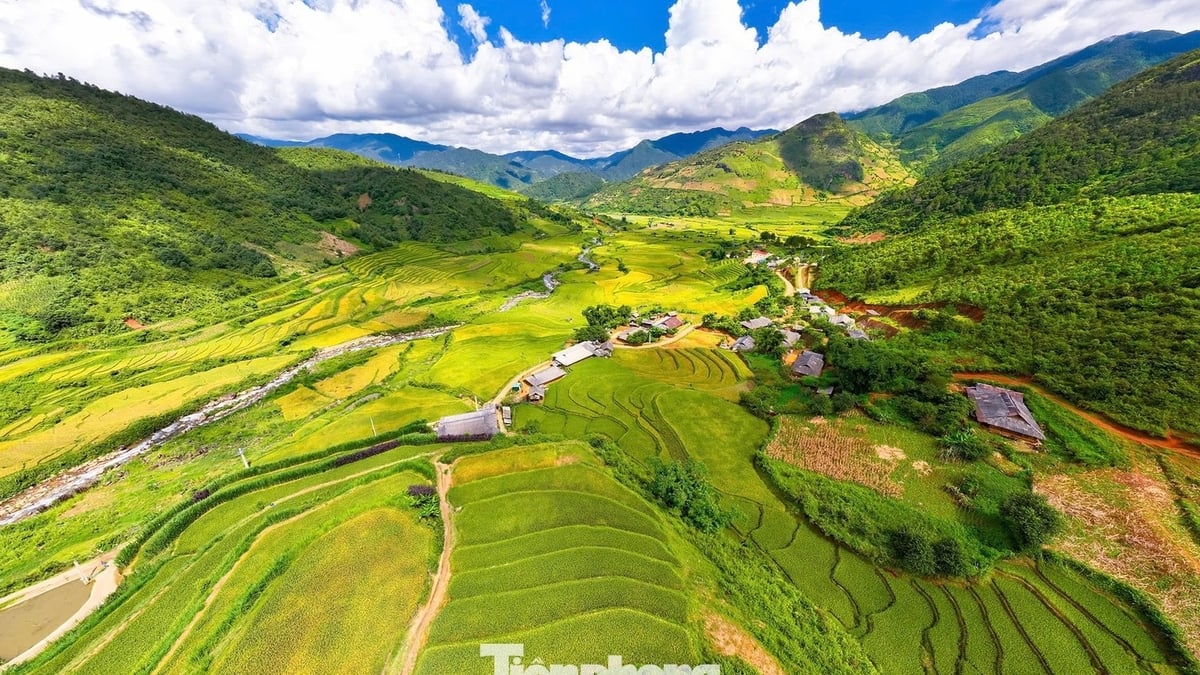
















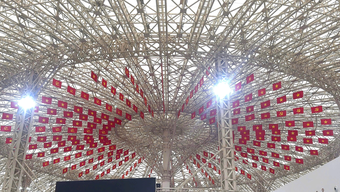

























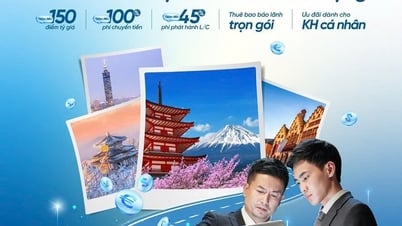

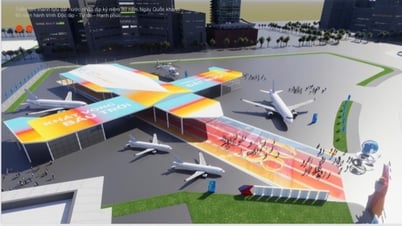







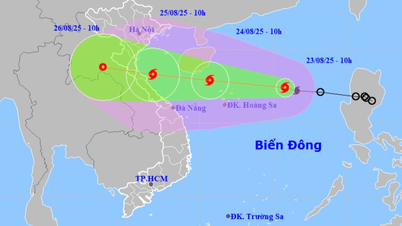
















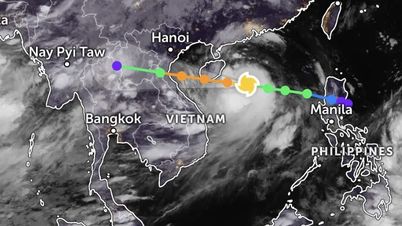













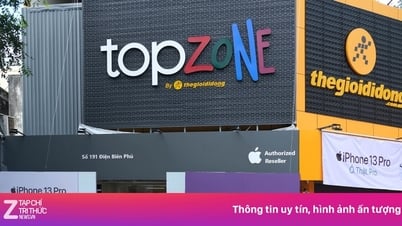






コメント (0)