今日の午後、 フエは雨が降りました。
「まだ以前と同じくらいお酒を飲んでいるの?」と、Trinh さんは優しく尋ねました。
フンは砂糖なしのブラックコーヒーを見ながら微笑んだ。「ええ。変わりませんよ。」
もはや若くはないが、二人の間には昔と変わらず穏やかな空気が漂っている。それはもはや愛でも、憧れでもない。ただ静かな繋がり、まるでかつて手をつなぎ、学生生活の最も輝かしい日々を共に歩んだ二人を繋ぐ、目に見えない糸のように。
イラスト:LE NGOC DUY
フエは、フンとチンの情熱的な愛が芽生えた肥沃な土地、まさに出発点でした。当時、フンは大学進学のためクアンチからフエへ移り、チンの家の近く、ヴィーダー橋のたもとにある小さくてみすぼらしい部屋に滞在していました。二人は学校の青年会活動で偶然出会いました。
チンはフエ出身で、優しく控えめな性格だ。彼女の美しさは眩しいほどではないが、穏やかで品格がある。声は柔らかく、瞳は優しく、手先は器用だ。毎日正午か午後、学校が終わると、チンはフンに温かい弁当を持ってやって来る。食事は心遣いと愛情に満ちている。チンは、不安定な青春時代を過ごすフンに安心感を与えてくれる少女だ。
二人は普通の人の愛し方とは違っていた。約束も、ドラマチックな出来事もなかった。ただ午後に香川の岸辺を散歩し、雨の夜には古いスピーカーからチンの音楽を聴きながら、チンはフンの肩に頭を預け、優しく言った。「これからはどこへ行っても、ちゃんと食べて、ちゃんと飲むのを忘れないでね、いい?」
卒業後、フンは政府機関に就職するためクアンチに戻り、チンは修士号取得のためフエに残った。地理的な距離、家族の期待の違い、そしてフンの両親からの「相性の良い年齢・悪い年齢」に関するアドバイス…こうしたことが、二人の関係を徐々に弱めていった。二人は別れを告げなかった。メッセージの頻度は徐々に減り、年月とともに不安も薄れていった。電話も途絶え、遠ざかっていくばかりだった。
年末のある午後、フンさんはチンさんに短いメッセージを送った。「もう一緒にいられない。元気で生きてね。」
チンはその文章を何百回も繰り返し読んだ。その夜、彼女は泣きじゃくった。自分を憐れみ、怒り、彼を憎むことさえした。なぜはっきりと言わなかったのだろう?なぜ理由を言わなかったのだろう?
そして、静かな日々が過ぎ去った後、トリンさんは悲しみを胸に抱きしめ、静かに立ち去った。いつかは終わる関係もあるのだと、彼女は理解していた。誰かのせいではなく、人生が別の道を選んだから。
2年後、チンは結婚した。最初の息子が生まれると、彼女は家でひっそりと「ナウ」という名前で呼ぶことにした。フンが泊まりに来るたびに、茶色のセーターを着て薄茶色の布で髪を結んでいるチンを見て、いつもその名前で呼んでいた親しみを込めた呼び名だ。誰もその理由を知らなかった。チンだけが、それがあの頃の優しさを少しでも自分のために残すための方法だと理解していた。
何年も経って、フンも結婚した。妻はドンハ市の小学校教師で、優しく有能だった。彼には男の子と女の子の二人の子供がいて、放課後の午後はいつもおしゃべりで楽しかった。生活は安定していて楽だった。家族や同僚にとって、彼は模範的な人物だった。しかし、誰にも気づかれない静かな時間もあった。雨の夜、彼は静かに座り、チンとの思い出を含め、過去を回想していた。
二人は頻繁に連絡を取り合うわけではない。しかし、チンが助けが必要な時は必ずフンに電話する。そしてフンも、騒々しい生活の中で穏やかな部分を保つために、自然な反射として、いつも静かに手伝ってくれる。
仕事でフエに行く機会があると、フンは時々チンをコーヒーに誘った。二人は過去のことは口にしなかった。ただ、お互いの子供のこと、仕事のこと、そして日々の生活について語り合った。二人は互いに理解していた。もうお互いのものではないと。しかし、相手が過去の深い部分を占め、忘れることも、戻ることもできない存在であることを、誰も否定できなかった。
今夜、フエ出張から戻ったフンは窓辺に座り、妻の隣でぐっすり眠る二人の子供を静かに見守っていた。妻は多くの悩みを黙々と耐え、背負ってきた女性だった。辛い時も食事や睡眠の世話をし、共に歩んできた人だった。
彼はため息をついた。彼の心は軽く、そして深くもあった。
愛は善悪で測ることはできない。記憶の一部として存在する。沈んだ月がまだ温かい水面に輝き続けるように。罪悪感も感じない。忘れなければならないとも思わない。なぜなら、すべてが純粋で、大切にする価値があるからだ。
電話が鳴った。それはトリンだった。
- もう家に着きましたか?
- 分かりました。ありがとう、チン。今日はフエはいい雨が降っています。
- はい。息子さんはお元気ですか?
― あっという間に大きくなってますね。妻も元気です。お体にお気をつけて。
- うん…わかった。早く寝るよ。妹さんと子供たちによろしく伝えておいて。
電話が切れた。フンは受話器を置いた。外では雨が静かに降り続いていた。もはや激しい動揺はなく、ただ長く深い雨が流れ、抑圧されていた思考の奥深くまで浸透していくだけだった。
彼はポーチに出た。クアンチの夜は穏やかで静かだった。裏庭のヤシの木々を風が吹き抜ける。三毛猫は椅子の足元で丸くなって横たわり、遠い時のため息のように規則的に呼吸していた。10年…傷跡が全て癒えるには十分な時間であり、見慣れたものが奇妙に思えるには十分な時間だった。
風の音に、フンはこれまでずっと考えないようにしていたことに突然気づいた。「昔」と「今」の距離は時間ではなく、充足感なのだと。もし再会したら、何百もの言葉を交わすだろうと思っていた。しかし、結局はただ「元気?」というだけだった。そして、かつて愛した人が安らかに生きていると知るだけで十分だと理解することが、成熟なのだと思える。もう私たちのそばにはいないけれど、いつも私たちの中にいる人がいる。秋の若稲の香りのように、冬の午後にタンズエン寺の鐘の音のように。優しく、穏やかに。
フンは微笑んだ。その瞬間、彼は安堵した。まるで思い出の引き出しを閉めたかのようだった。鍵をかけるのではなく、そっと押し戻し、そのままそこに置いただけだった。きちんと、そして優しく。チンは彼の青春時代の一部でありながら、もはや心配事ではない。家族、仕事、子育てで忙しい日々の中、時折、このような静かなひとときが、彼の心を見つめ直し、自分がどのように生きてきたのか、そして昔の恋を通してどのように成長してきたのかを思い起こさせてくれる。
トラン・トゥイエン
出典: https://baoquangtri.vn/giu-lai-mot-chut-dieu-dang-193696.htm





























































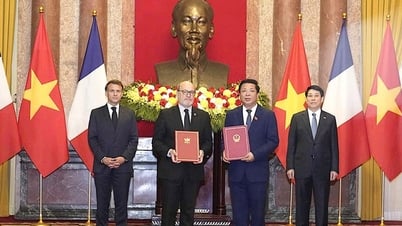
































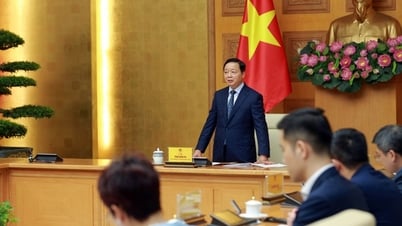






コメント (0)