彼らがからかうのも無理はなかった。古い自転車はもうこれ以上古くなるはずがない。自転車が一回転するたびに、賑やかなハーモニーが響いていた。壊れたブレーキレバーのカタカタという音、オイルが切れたボールベアリングのキーキーという音、へこんだ金床が車輪に擦れる音が入り混じっていた。最悪だったのは、自転車を止めるたびに、ブレーキをかけるために急いで側面に降りて、足を地面にこすりつけなければならなかったことだ。母が子供たちの安全を気にしていなかったわけではなく、ただ必要に迫られていただけだった。私たちはとても貧乏だった!まあ、私が乗ってカッコいいと思った前カゴ付きのミニバイクを買えないほど貧乏ではなかったが、母のモットーは、私が乗れなくなったら買うというものだった。新しい自転車もいずれ古くなる。あるいは、母のところに持って行って修理してもらい、見栄えを良くすることもできる。とんでもない、美しさや醜さを競うなんて考えもしないで!ペダルが動くならそれでいい。自転車に乗るのは歩くよりずっと辛い。母は悪くないと言うので、仕方なく泣き言を言うしかなかった。母の性格は近所中に知れ渡る「ブランド」になっている。使い古した物は、使い切って捨てる。つまり、母が捨てたものを…拾う術がないのだ。
2. 私は学校のトップの生徒とほぼ同じ点数でバカロレアに合格しました。社会科学・人文科学大学が気に入ったので、母にその大学への出願を勧めました。母はこう言いました。
- 地方の教育大学の試験は無料なので、自宅近くで勉強すると費用が安くなります。
母の希望で、行きたくなかったのですが、仕方なく教育大学で勉強することにしました。教育学を専攻していたにもかかわらず、友達からは「田舎者だね」とからかわれました。その言葉を聞いて、私はただ微笑むだけでした。悲しくも、怒りもありませんでした。なぜなら、私自身も漠然と田舎者であることを感じていたからです。
頭からつま先まで真っ黒に日焼けした少女。マスクの使い方も化粧もせず、口紅を塗ったことも一度もない。鏡の前に立って、自分が一年生だなんて信じられなかった。これは川遊びの日々の「成果」であり、「勉強すれば褒められる、競争すれば叱られる」という母の言葉の賜物でもあった。
ルームメイトたちは舌打ちして言った。「君には隠れた魅力があるのに、自分のケアの仕方がわからないから、まだ美しくないだけだよ」。それから、一人はTシャツとジーンズ、もう一人は石鹸を、そして裕福なホアは洗顔料とスキンクリーム(安物のやつ)を丸ごと一本くれた。
その週末、私は自転車で村の入り口まで帰りました。皆が町の様子が変わったと褒めていました。明るくて美しくなったと。でも、家に着くと母は私を頭からつま先まで抱きしめながら、文句を言いました。
- ママは僕を競争のためではなく学校に行かせてくれたんだ!
私はふくれっ面をして部屋に入った。彼女は美人だったが、褒めることはしなかった。ただ田舎娘に受け入れてほしかっただけなのだ。
3. 教師になり、最初の月の給料は炊飯器の購入に充てられました。私はガスコンロを買おうと言い張りましたが、母は拒否しました。母は庭のゴミや藁を掃き集めてコンロに火をつけ、煙が目にしみ込み、ご飯を炊いている間、汗だくになり、泣きそうに涙が流れました。母になぜそのお金で炊飯器を買わないのかと尋ねると、米を売って貯金し、半タエルの金を買ったのだと答えました。なんてことだ!母の唯一の望みは金を買うことだったのね、と私は母に聞かれるのを恐れずにつぶやきました。
家から遠く離れた場所で教師として働き、寄宿学校に住み、バスか車で家に帰らなければならず、とても不便でした。バイクを買うために給料からお金を借りたいと頼みましたが、母は断りました。毎月少しずつ給料を貯め、残りは家の準備をしたり、両親の洋服を増やしたりするために母に渡しました。母はどんな指示にも関わらず、金を買うためにお金を借り続けました。私は「皮肉屋」でした。
- お母さん、家を修繕して、ちゃんとした服を買って。もう金は買わないで!
- もうすぐ結婚するんだし、ずっと両親と暮らすわけじゃないんだから、わざわざ飾り付けたり準備したりする必要はないでしょ?服に無駄金を使う必要もないでしょ?私の膝丈は耳より上だから、ショートパンツとトップスはダメよ!
ある日、母が私にネックレスとイヤリングをくれて、それを着けるように言いました。私は言葉を失い、母は言いました。
- 女の子はこれを持たなければなりません。
- お母さんは家具を買おうとせず、ただ金だけを買い続けるので、本当にうんざりです!
- 家から離れて暮らすときは、身を守るために少しの金を身に着けてください。
貯金は1枚、2枚。母は、見張るべき場所があって、それが自分の身を守るためだと考えた。母は生まれてからずっとそうだった。お金を惜しまず、ケチケチと節約してきた。今になってようやく理解できたので、母は母を気の毒に思ったが、怒りをぶつけるのにも耐えられず、からかった。「お金が十分あったら、金を買うのよ」
4. 私は貧しい男性と結婚しました。友人や同僚は反対し、兄弟も躊躇していましたが、母は反対しませんでした。母は、結婚に金持ちか貧乏かは関係なく、お互いを愛し合えば一緒に豊かになれると言いました。娘のために結婚の準備をし、持参金として娘の手に金貨を添えました。義理の息子は貧しかったのですが、母は彼を心から愛していました。娘が給料をもらって、まだ仕事も見つかっておらず中卒の夫に失礼なことを言うのではないかと心配していたのです。母は何度も私に、「女性は水のようなもので、水は低い所に流れるものだ」と繰り返し言いました。夫婦が幸せになるには、忍耐強くあることが大切で、妻がまずそれを身につけるべきだと。
娘が夫の家族と茅葺き屋根の家で暮らすのに苦労しているのを見て、母は私に牛2頭を元手に与えてくれました。その後、夫は就職し、私は子供を産み、夫の土地にある小さな家に引っ越しました。ある時、娘を訪ねた時、娘は食事も買い物も何不自由なく過ごしていました。私が帰宅すると、母は何度も私に「10回のうち5回だけ働き、残りは子供のために貯金しなさい」と言いました。夫も私も公務員で安定した収入がありましたが、母は毎月誰かを家に米を運ばせていました。夫が戻ってくると、母に「もう送るな」と言いました。母はこう叫びました。
- お父さんとお母さんは農家なのに、お米を買うのはすごく高いのよ。それにしても、あなたたちは食べる量が少ないし、「不食」は得意だけど、お米はあまり食べないわね。
夫と私は安心して母の作ったお米を食べました。その年の稲刈りの頃、息子が祖父母の家に帰りたがっていたので、わら遊びに連れて帰りました。家には子供がほとんどいないのを見て、私は驚きました。
- ねえ!おばあちゃんはまだ稲刈りをしていないの?どうして家こんなに空っぽなの?
- はい!完成しました。小さなパッチが2つあるだけです。一気に仕上げました。
- おばあちゃんはどこ?
- 私たちがまだ寝ている間から、私はお米を拾い集めていました。
- あらまあ!あなたは年寄りなのに、家で休むこともないし、働きすぎだし、そんなにたくさんの「穀物」を食べた後で何を拾うの?
- おばあちゃんは、みんながそれをたくさん切るから、季節ごとに必ずそれを拾いに行くんだって。
娘の言葉を聞いて、私は愕然としました。娘は本当に冷酷でした。母は田んぼに出て天日干しをし、散らばった米粒を一つ一つ拾い集めているのに、娘はお金を無駄遣いしていました。困った時は、買ったイヤリングとネックレスを売り飛ばして、「私の命一つで娘の命三つ分になる」と言い張ったのです。
明るい陽光が差し込む野原を眺めながら、私は長い間探しましたが、野原にかがみ込む茶色のシャツを着た母の姿は見つかりませんでした。突然、目から涙が溢れ、胸が痛みました。
5. 壮年期に突然体調を崩し、顔色が青ざめてしまいました。母は私の病気が再発しているのを見て、病院に行くように強く勧めました。正直、若死にするのが怖かったので、母の言葉には本当にショックを受けました。入院、再検査、そしてまた入院しましたが、家族には蓄えがありませんでした。私も借金をし、夫も借金をしましたが、「家に入るお金は風が空家に入るほど難しい」のです。私は困窮していましたが、プライドも高かったので、友人に助けを求めることも、家族に頼むこともできませんでした。私は恥ずかしく思いました。仕事が安定していて、母や兄弟も皆農家だったので、家族の中で一番裕福だと思っていました。
ある日、母は娘を見舞うためバスに乗って病院へ行きました。夫の手に小さな布袋を渡し、開けてみると、中にはピカピカの金の延べ棒が5本入っていました。私は声を詰まらせながら、「何もできないけど、母に報告するのは得意だよ」と言いました。母は「気にしないで。貸してあげるから、しっかりしてね。後で返してあげるから」と言いました。
その後、私は別の病院に転院しなければならなくなりましたが、夫は仕事を辞めることができなかったので、母が付き添ってくれました。チョーライ病院からリハビリテーション病院、そして医科薬科大学まで、数ヶ月間、母は病院で私に付き添ってくれましたが、外食は一切しませんでした。食事の時間になると、母は私に食べ物を買ってきてくれたり、自分はチャリティフードを頼んだりしていました。私は母を気の毒に思い、きちんと食べるようにと強く勧めましたが、母は「危険な時は治療費を節約しないといけない。チャリティフードもとても美味しい」と言いました。母は毎食私に食べさせてくれましたが、私はスプーン数杯しか食べられませんでした。母は私の食べ残しを食べて、「こんなひどい食事だと太ってしまうわよ。猫みたいに食べていたとしたら、いつになったら治るのかしら…」と文句を言っていました。私は「腹が立って」、「もう食べないで。娘はもう大人よ。もう子供じゃないのに、どうして食べ残しを食べなければならないの?」と言いました。母は手を振って言いました。「子供の食べ残しを食べない母親がいるだろうか。それに、残ったものなんて…」
夜になると、痛みがひどくて何度も寝返りを打ちました。母は「頑張って」と私に言いました。母親である以上、娘のことを考えて早く良くなってあげなければならない、と。娘が夜中に動くたびに、母は起きて娘の全身をマッサージしてくれました。
ああ、母の骨ばった手と荒れた肌が、母の柔らかな肌に触れると、痛みは治まったものの、まだひどく不快だった。早く良くなって、母への「恩返し」がしたいと願うばかりだった。
NTBN
ソース



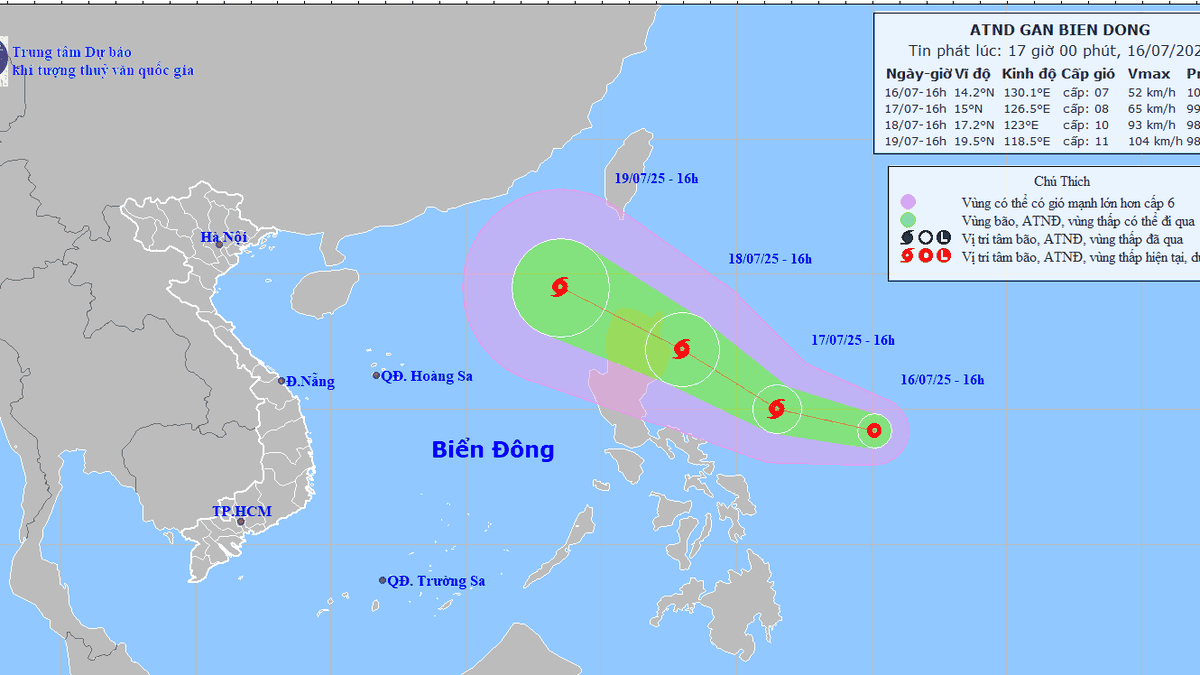













































































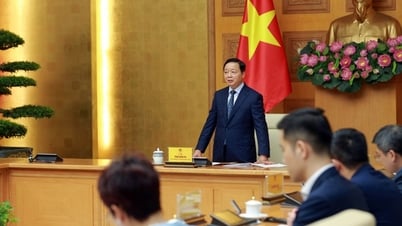
















コメント (0)