改正社会保険法の最新草案では、退職や一時金の脱退に関する多くの規制が調整され、保険料の最低賃金と最高賃金が引き上げられている。
2ヶ月以上にわたる意見募集を経て、社会保険法改正案は、省庁、地方自治体、企業、労働者、専門家から160件近くの書面による意見を受領しました。その後、労働・傷病兵・社会省は、退職給付、一時金社会保険(SI)、強制加入対象範囲の拡大などに関するいくつかの調整を加えた改正案を完成させ、 法務省に提出して審査を受けました。
社会保険撤廃の両案を一括して国会に報告
社会保険の一括脱退案については、3つの意見がある。第一グループは、社会保険加入期間が20年未満の従業員が1年経過しても社会保険に加入しない場合、一括脱退を認める現行規定を維持することに賛成している。この撤回は、拠出・給付の原則に基づき、従業員の権利を保障するためである。
2つ目のグループは、保険料の50%を払い出し、残額を将来の給付に備えて社会保険基金に積み立てるという選択肢を支持しています。このグループは、残額を労働者の「貯蓄」とみなし、社会保障制度に復帰する機会も残しています。
法務省は3番目のグループに属し、一時的社会保険制度は法案の根本的な変更であると考えている。もしこの制度が50%の削減に至れば、一時的社会保険給付額が現行の給付額よりも低くなる可能性がある。労働者からの反発を避けるため、法務省は起草機関に対し、 政府に提出する前に、各補足措置の影響を慎重に評価するよう提案した。
労働・傷病兵・社会省はコメントに応えて、選択肢の評価を補足し、統合して政府に提出するとともに、同時に国会に報告して両方の選択肢についてのコメントを求めると述べた。
社会保険料20年納付の条件を撤回
当初の草案では、年金受給資格の条件が厳格化されていました。そのため、社会保険料を20年間納付し、規定通り退職年齢に達した労働者は年金受給資格を得られました。しかし、多くの機関は、拠出者グループ間の公平性を確保するため、この規定を撤廃し、社会保険料を15年間納付し、かつ成人した労働者も年金受給資格を得るよう提案しています。
労働・傷病兵・社会省は、意見を踏まえ、最新の草案において上記の条件を削除しました。これにより、年金制度は、社会保険料を15年間納付し、規定の退職年齢(ロードマップに従って、男性は2028年に62歳、女性は2035年に60歳まで引き上げられる)に達した従業員に適用されます。

2022年末、ホーチミン市トゥドゥック市の社会保険庁で、一時社会保険の脱退手続きを待つ労働者たち。写真:タン・トゥン
社会保険料の計算における最低賃金の引き上げ
最新の草案では、強制社会保険料の基準となる給与は少なくとも半分とし、保険料の上限は政府が発表した地域の最高最低月額給与(現在、地域Iの最高水準は月額468万ドン)の8倍とすることを提案している。
これにより、3月の草案と比較して、最低賃金と最高賃金の両方が引き上げられました。現在、第1地域の最低賃金は月額468万ドンです。草案通りに適用される場合、現時点での最低賃金と最高賃金は234万ドンから3,744万ドンの間で変動しますが、地域別最低賃金は社会経済状況に応じて調整されます。
起草委員会は以前、社会保険料の最低納付額を200万ドン、最高納付額を3,600万ドンと提案していました。政府は消費者物価指数の上昇と経済成長に基づき、この額を調整しました。
起草委員会によると、幹部、公務員、公務員、軍隊員、企業職員の給与改革に関する中央委員会の2018年第27号決議では、「基本給」が廃止される。したがって、社会保険料の月額支給額を基本給に連動させるのではなく、地域別最低賃金を基準として最高額と最低額を決定する方向に変更する必要がある。
現行法では、企業部門の従業員の毎月の強制社会保険料の給与は、納付時の地域の最低賃金に、危険な職業の従業員の場合は5%、訓練を受けた労働者の場合は7%を加えた金額を下回ってはならず、最高納付額は基本給の20倍であると規定されています。
事業主への義務的支払い範囲の縮小
以前の法案では、事業主、経営者、無給の協同組合経営者、パートタイム労働者を強制社会保険制度の対象とすることが提案されていました。これらのグループは、退職金、死亡、出産、疾病、職業病、失業給付の全額を享受できるようになります。
意見を集約・吸収した結果、今回の草案では、強制加入の対象範囲を事業登録世帯主層に限定し、退職年齢の者には適用しないこととした。これにより、強制社会保険に加入する世帯主数は、当初計画の500万世帯から200万世帯近くまで減少する可能性があると予想される。
このグループの拠出金を計算する基準として使用される給与も、当初の草案のように200万~3,600万VNDの間で変動するのではなく、地域Iの最低賃金に応じた下限と上限のレベルに基づいて調整されます。

2021年の新型コロナウイルス感染症のピーク時、ハノイのクアナム通りにある「グリーンゾーン」路地の前に立つ地域職員。写真:ファム・チエウ
村や居住グループレベルで非専門家への適用範囲を拡大
新たな草案は、コミューンレベルの労働者と同様に、村落や居住集団の非専門職労働者を含む、強制社会保険料の納付義務を負うグループを追加している。統計によると、このグループに属する労働者は全国で約30万人に上る。一方、現行法では、コミューンレベルのフルタイム労働者のみが強制社会保険料の納付義務を規定している。
起草機関は、両グループの受給者制度と政策は類似しており、いずれも政府によって規制されているため、村落部落と居住部落のグループを強制加入の対象に含める必要があると説明した。この提案は、2030年までに労働年齢人口の60%を社会保障制度に加入させることを目指す中央委員会決議第28号にも合致している。
このグループの社会保険料の基礎となる給与は政府によって規制されており、最高地域(地域 I)の最低月額給与の半分である最低基準を下回らないことが保証されています。
葬儀手当を1,490万ドンから1,800万ドンに引き上げ
当初の草案では、社会保険に加入し年金を受給している労働者が死亡した場合、現行の基本給(月額149万ドン)の10倍にあたる1,490万ドンの葬儀手当が支給されると規定されていました。しかし、7月1日から基本給が月額180万ドンに調整されることを受け、起草委員会は最新の草案で葬儀手当を1,800万ドンに引き上げました。この額は、政府が年金制度を調整するたびに増額されます。
しかし、葬祭給付金の受給資格を得るには、社会保険料の納付期間が60ヶ月以上である必要があります。この規定を削除するべきだという意見が多くありましたが、起草委員会は、拠出・給付原則の確保、基金の均衡、そして特に自主セクターにおける政策的搾取の回避を目的として、この規定を維持しました。
社会保険法改正案は6月に政府に提出され、2023年10月の国会で審議のため国会に提出され、2024年5月の国会で承認され、2025年1月1日に発効する予定である。
ホン・チウ



![[写真] ファム・ミン・チン首相がタイグエン省の嵐後の洪水被害の克服作業を視察し、指導する](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/08/1759930075451_dsc-9441-jpg.webp)
![[写真] ファム・ミン・チン首相が国際貨物運送協会連盟(FIATA)の世界大会に出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/08/1759936077106_dsc-0434-jpg.webp)

















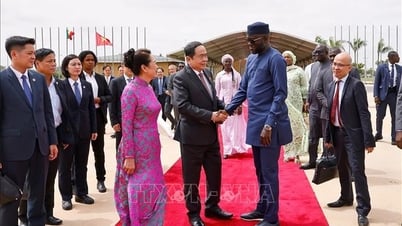









































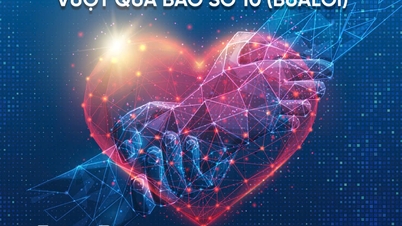








































コメント (0)