 |
| 塩水田でのエビ養殖の試験 |
多くの稲作地域は塩分の影響を受けています。
このモデルに参加しているクアンアン村(クアンディエン)アンスアンのチャン・ヴァン・クさんは、この地域の稲作地域は塩害と酸性化の影響を受けているため、冬春作しか生産できないと述べた。夏秋作は暑さと干ばつの影響を受け、水田も塩害と酸性化の影響を受けていることが多く、生産効率が悪い。田んぼを休耕させれば、水田は無駄になってしまう。作物と家畜の構造を変えることは、クアンアン、そしてクアンディエン全体の農民たちが長年検討してきたことだ。
崔さんは、塩分とミョウバンに汚染された水田でシロエビを養殖するモデル事業への参加に選ばれたことは、家族にとって大きな喜びだったと語った。水田でのエビ養殖はあまりにも新しい経験だったため、崔さんは当初、戸惑いと不安を抱えていた。しかし、農業普及員の指導と「手ほどき」によって、崔さんは技術を習得し、自信を深めた。現在、エビは順調に成長し、サイズも保証され、生存率も高く、収穫間近となっている。
省農業研究センターのチャウ・ゴック・フィ所長は、トゥアティエン・フエ省全体、特にクアンディエン県では、ラグーン地域に稲作地帯が多く、夏秋作期には塩害や酸性硫酸塩土壌の影響を受けやすく、経済効率が低いと述べた。多くの稲作地帯では冬春作のみを生産し、夏秋作期は休耕状態となり、「生産手段」の無駄が生じている。
クアンディエン県だけでも、塩害と酸性硫酸塩土壌の影響を受けた水田面積は最大560ヘクタールに及び、ラグーン沿いの8つのコミューンに属する10の協同組合に集中しています。一部の世帯は、適切な計画、圃場設計、技術プロセスを経ずに、自発的に水田の一部をシロエビ養殖に転換し始めており、養殖プロセスにおけるリスクにつながっています。
オショロコマエビは、pHが低く塩分がほぼゼロの環境でも生育できる種です。塩分や酸性硫酸塩土壌の影響を受ける稲作地帯での養殖に適しています。しかし、稲作が困難な稲作地帯でオショロコマエビ養殖を発展させるには、経済効率を確保し、養殖過程におけるリスクを軽減するための適切な養殖場設計と養殖プロセスが必要です。
複製の基礎
塩害と酸性化の影響を受けている稲作地帯をエビ養殖に転換するための基盤を築くため、農業研究開発センターは2ヶ月以上前、省予算を活用し、クアンアンコミューンのアンスアン協同組合において、5ヘクタール/2世帯規模の「塩害地におけるエビ養殖」モデルを実施しました。農業研究開発センターは生産ユニットと連携し、種子、飼料、病害予防薬剤を適時に適切に供給できるよう支援しました。規定に基づき、モデルへの参加が決定された世帯には、種子、飼料、病害予防薬剤の費用の50%が支援され、残りの50%は農家が負担することになっています。
放流前に、養殖センターの技術スタッフが各家庭に対し、正しい技術に基づいた圃場整備モデルを実施するよう直接指導します。収穫後は、田んぼの藁を取り除き、水を切り、冷却剤を用いて圃場に生息するエビや魚をすべて駆除します。その後、圃場に水を供給し、酸度を除去するために排水を行い、ミョウバンや化学残留物、圃場内の農薬などを洗い流します。その後、ろ過器を通して養殖池に水を供給し、石灰を加えてpHとアルカリ度を高めます。
養殖過程において、センターの技術スタッフはエビの成長と発育速度を定期的に監視・確認し、異常な兆候を早期に発見します。さらに、養殖現場での実践経験に基づいた予測・予測を行い、効果的な解決策を提案するとともに、各農家が技術を確実に実施できるよう指導し、損失を最小限に抑えます。
TTKNは、モデル事業に参加した農家と、塩水・ミョウバン汚染された水田を所有し、エビ養殖への転換を希望する農家を対象に、シロエビ養殖の技術手順に関する研修を実施しました。参加農家は、塩水・ミョウバン汚染された水田におけるシロエビの養殖手順をほぼ習得しました。
チャウ・ゴック・フィ氏は、養殖開始から2ヶ月近くが経過し、エビの平均重量は1kgあたり90匹、生存率は70~74%、平均収量は1世帯あたり800kgに達したと評価しました。淡水域におけるシロエビの成長速度は汽水域や塩水域よりも速く、養殖エビの生存率は基準を満たしています。養殖エビはまもなく収穫を迎え、推定収益は1ヘクタールあたり約3,000万ドンと、稲作よりも1,300万ドン高いと見込まれています。
初期の有効性は実証されているものの、チャウ・ゴック・フィ氏の提言によると、生産条件が十分でない場合に、人々は自発的に水田をエビ養殖に転換すべきではない。特に暑い時期に安定した温度を確保するために、水路を周囲に巡らせるか、適切な深さにする必要がある。放流前に、水田を注意深く改修し、酸抜きし、ミョウバンを洗浄し、化学残留物と農薬を洗い流さなければならない。養殖初期段階での生存率を確保するために、エビの種苗は塩分に十分に順応させる必要がある。塩分とミョウバンに汚染された水田でのメジロエビ養殖は、集約的または半集約的農業の方向ではなく、改良粗放的農業の方向で低密度で放流するべきである。なぜなら、これらの農法はラグーン池と砂池にのみ適しているからである。シラミ養殖は一期作の田んぼでのみ展開し、冬春作では稲作を継続するべきである。田んぼに塩水を注入したり、塩水を使用して田んぼの塩分濃度を高めたりすることは、田んぼの塩害を引き起こすので避けるべきである。
[広告2]
出典: https://baothuathienhue.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/nuoi-tom-tren-ruong-lua-nhiem-man-143265.html
































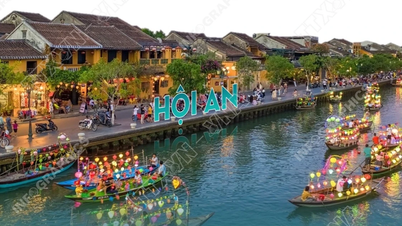


















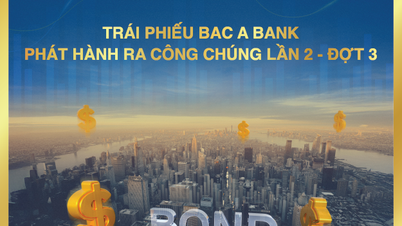








































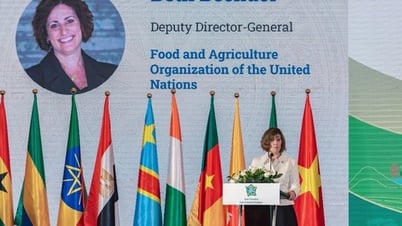







コメント (0)