討論の序文で示されたデータによると、現在、全国の都市化率は41%で、都市部は883カ所に及んでいる。2023年6月までに、全国で都市部と農村部を合わせて約4,500カ所の給水システムが設置され、最大約1,100万立方メートルの給水能力を持ち、1日あたり約830万立方メートルの給水が行われる。そのうち、87%は表層水源、13%は地下水源が主に利用される。
しかし、第13代国会議員(元)で天然資源・環境・コミュニティ開発研究所所長のブイ・ティ・アン准教授の声明によると、多くの都市部では生活用水の水質に関する懸念が生じている。水質基準はあるものの、これらの基準の遵守は依然として不透明である。
ファム・ゴック・チャウ准教授は、都市部の生活用水の水質について、特にハノイをはじめとする都市部への水供給は非常に困難であると述べました。生活用水システムにおける微生物汚染のリスクは、コレラや下痢などを引き起こすなど、極めて深刻な結果をもたらすでしょう。
ベトナム浄水環境協会のグエン・ヴァン・ヴェ副会長は、今後の都市部の生活用水の質向上策について、まず都市給水に関する現行の法的枠組みと政策メカニズムを見直し、補完し、都市給水に関わるあらゆる行為を規制する基盤とする必要があると述べた。そのためには、給排水法を速やかに制定・公布する必要がある。同時に、長期的には、都市給水計画は都市技術インフラ開発計画と連携する必要があり、現在の科学技術水準に基づいた規制、基準、技術経済規範の体系を研究・整備する必要がある。都市給水社会化のための財政・投資メカニズム、メカニズム、政策を整備し、地方への管理分権化を実施し、都市給水活動の検査・審査(事前検査、事後検査)を強化し、地域間給水技術インフラシステムの管理、情報共有、開発のための調整メカニズムを構築する。
「都市水質管理の現状」セミナーでは、環境資源と生活分野の管理者、科学者、専門家から多くのご意見をいただきました。セミナーでいただいたご意見は、管理レベルや専門機関に集約され、都市水質管理の現状を含む環境資源に関する仕組み、政策、法律の整備・改善に役立てられます。
[広告2]
ソース


























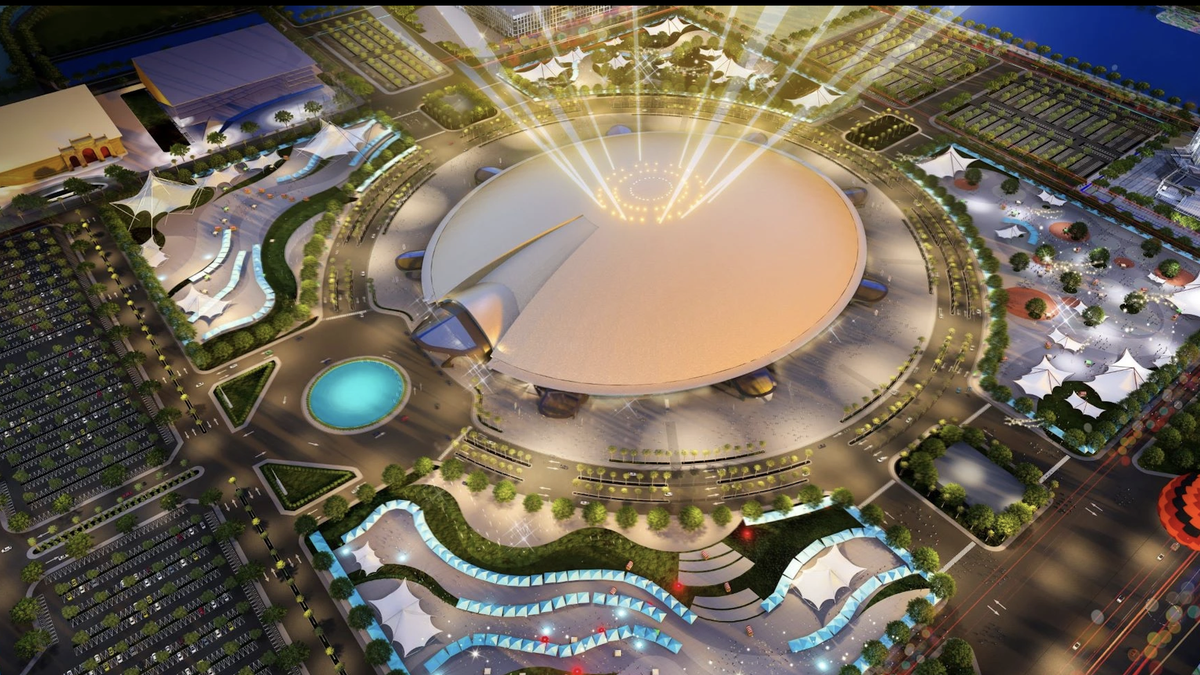







































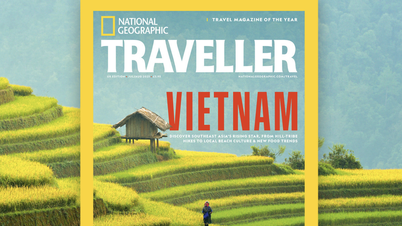

























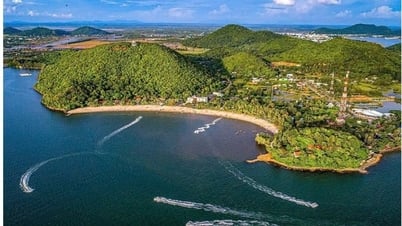






コメント (0)