ベトナム不動産協会(VARS)は最近、「出生率の低下と住宅市場への長期的な影響」に関する物議を醸す報告書を発表し、ベトナムは人口動態要因が不動産需要に影響を与え始める時期に入っていると指摘しました。しかしながら、短期的には住宅価格、供給、借入コストといった「ハード」要因の方が重要な要因であると考える人も多くいます。
VARSのデータによると、ベトナムの出生率は1989年の女性1人当たり3.8人から2024年にはわずか1.91人にまで低下しています。 ハノイやホーチミン市などの大都市では、出生率が「深刻な低出生率」の閾値である女性1人当たり1.3人未満に近づいています。これは、住宅市場の主な牽引役である新規世帯数が、特に大家族向けの大規模マンションセグメントにおいて、今後数年間で徐々に減少することを意味します。
VARSは、この状況が続けば、ベトナムは、人口の高齢化と極度の低出生率の影響を強く受けている韓国や日本と同様に、不動産の需給不均衡のリスクに直面する可能性があると予測している。
天然資源・環境研究所所長のファム・ヴィエット・トゥアン博士もこの予測に同意し、「長期的には、不動産の流動性は、法律、投入コスト、 経済危機、人口など、多くの政策の影響を受けます。人口増加、特に出生率の低下が続かなければ、住宅需要は徐々に減少し、流動性の低下につながるでしょう」と述べました。
プロピイン不動産金融テクノロジーアカデミーCEOのヴォ・ナット・リュウ氏は、別の視点から次のように強調しました。「出生率の低下は人口問題であるだけでなく、不動産市場の構造を変える重要な要因でもあります。私たちは金利、信用、合法性といった要素ばかりに注目しがちですが、人口動態要因こそが最も長期的かつ根深い変数なのです。」
しかし、統計総局のデータによると、ハノイとホーチミン市の新規世帯数は依然として年間2~3%の増加を続けています。これは、住宅需要が消滅したのではなく、経済要因によって「抑制」されていることを示しています。ベトナム不動産研究所(VARS IRE)のファム・ティ・ミエン副所長によると、流動性の低下の主な理由は新規世帯の不足ではなく、住宅価格が手の届かない水準に達していることです。ミエン副所長は、ハノイでは平均7,500万~8,000万ドン/㎡、ホーチミン市では平均8,500万~8,900万ドン/㎡のマンション価格を挙げ、20億~30億ドンのマンションは中間所得層には到底手の届かない価格だと述べています。
販売価格だけでなく、住宅ローンの金利も大きな障壁となっています。現在、平均金利は年間8%から12%の間で変動しており、一部の銀行は最初の数年間は6%から7%の金利優遇措置を設けていますが、それでも日本(1%から2%)やシンガポール(2%から4%)と比べるとはるかに高い水準です。15億ドンのローンを30年間、金利10%で返済する場合、購入者は毎月1,500万ドンから2,000万ドンを支払わなければならず、多くの若い世帯にとって負担が重すぎます。
さらに、多くの人が早く結婚したくないという事実も、住宅ニーズの変化につながっています。「彼らは生活と仕事の両方に使える多目的スペースを求めており、60~70平方メートルの固定されたデザインのアパートにはもはや興味がありません」とリュウ氏は言います。
専門家によると、ベトナム市場の活性化には、二つの課題に同時に取り組む必要がある。短期的には、手頃な価格の住宅供給を増やし、金利を引き下げ、融資手続きを改善する必要がある。長期的には、高齢化、出生率の低下、そして住宅ニーズの変化といったシナリオに備える必要がある。「人口動態だけを見て、政策や住宅製品を無視すれば、病気の診断を誤ってしまうでしょう。手頃な価格の住宅と、より低金利の融資メカニズムが必要です」と、ベトアンホア不動産会社のトラン・カン・クアン取締役は述べた。
出典: https://nld.com.vn/ti-suat-sinh-thap-va-nut-that-thanh-khoan-196250825201816875.htm






![[写真] ハノイ:当局は豪雨の影響克服に尽力](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/26/380f98ee36a34e62a9b7894b020112a8)

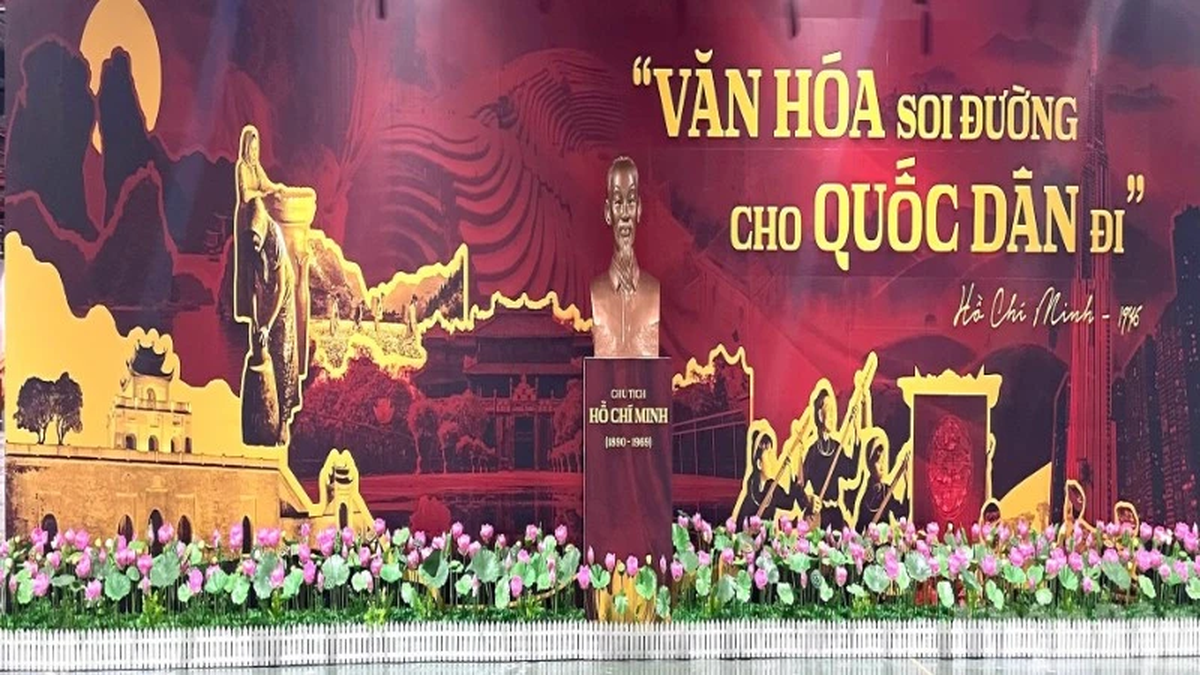





























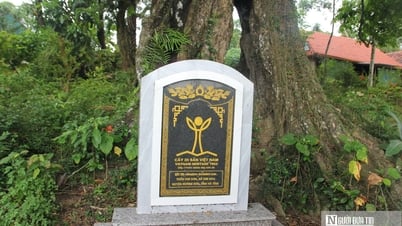


















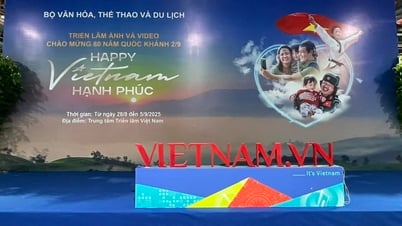







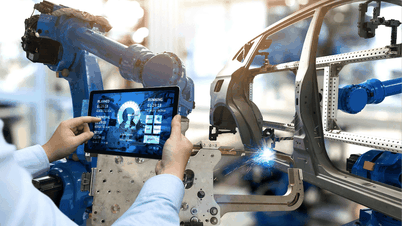































コメント (0)