
(ダン・トリ) - 2045年までに高所得国になるという目標は、ベトナムが直面しなければならない困難な道であるが、それはまた、ベトナム国民が団結して繁栄への願望を実現し、新しい時代に入るための原動力でもある。
2020年に金融アカデミーで学士号を取得したダオ・ホアさん(26歳)は、専攻分野での就職を諦め、観光業に就くことを決意しました。ホアさんの家族は反対しましたが、彼女はそれでもこの道でキャリアをスタートさせたいと強く主張しました。「人々の収入は増加しており、観光、特にラグジュアリーツーリズムへの支出も増えるでしょう」と、ホアさんはこの仕事を選んだ理由を語りました。3年経った今も、ホアさんはこの仕事に精を出しています。彼女のもとを訪れる顧客はますます増え、中には高級リゾートでの休暇に数億ドンを費やす人もいます。ベトナム国民がますます豊かになる中で、自分の仕事にもチャンスを見出しているとホアさんは語りました。 


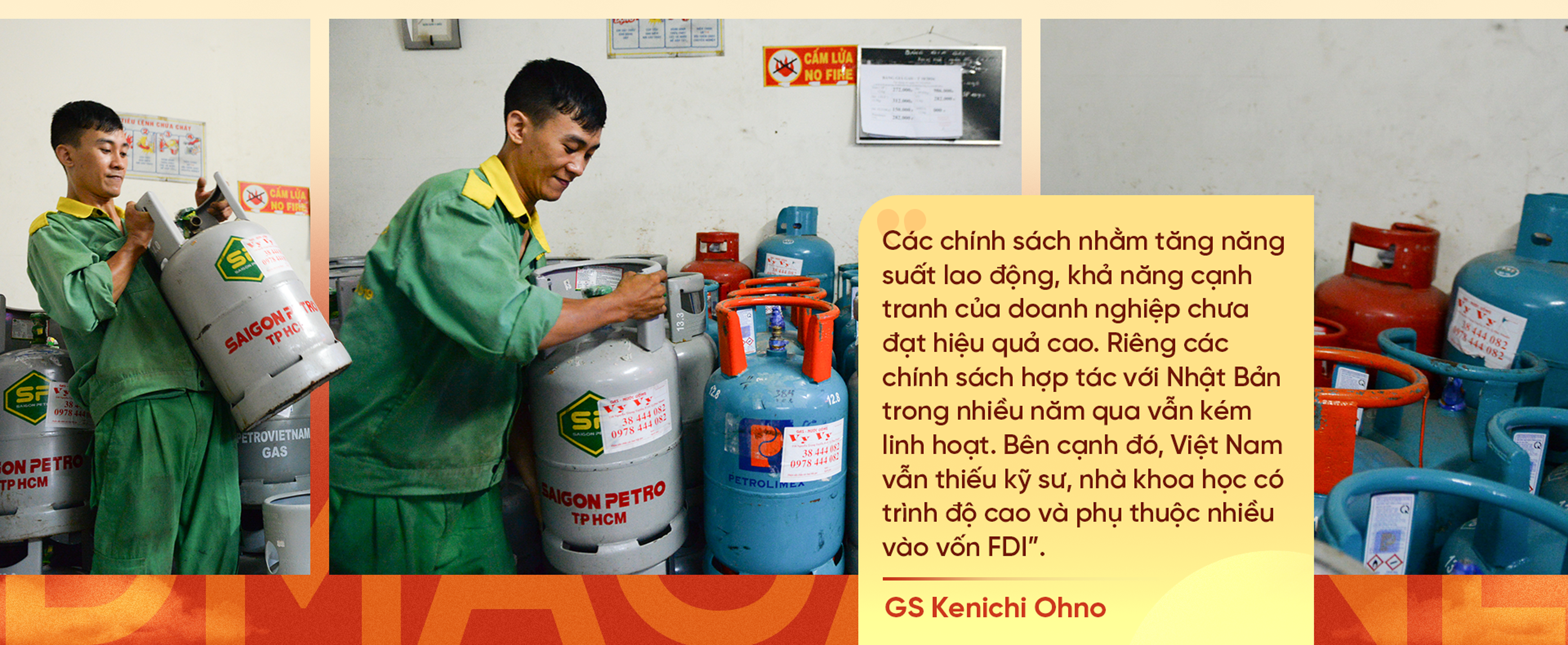
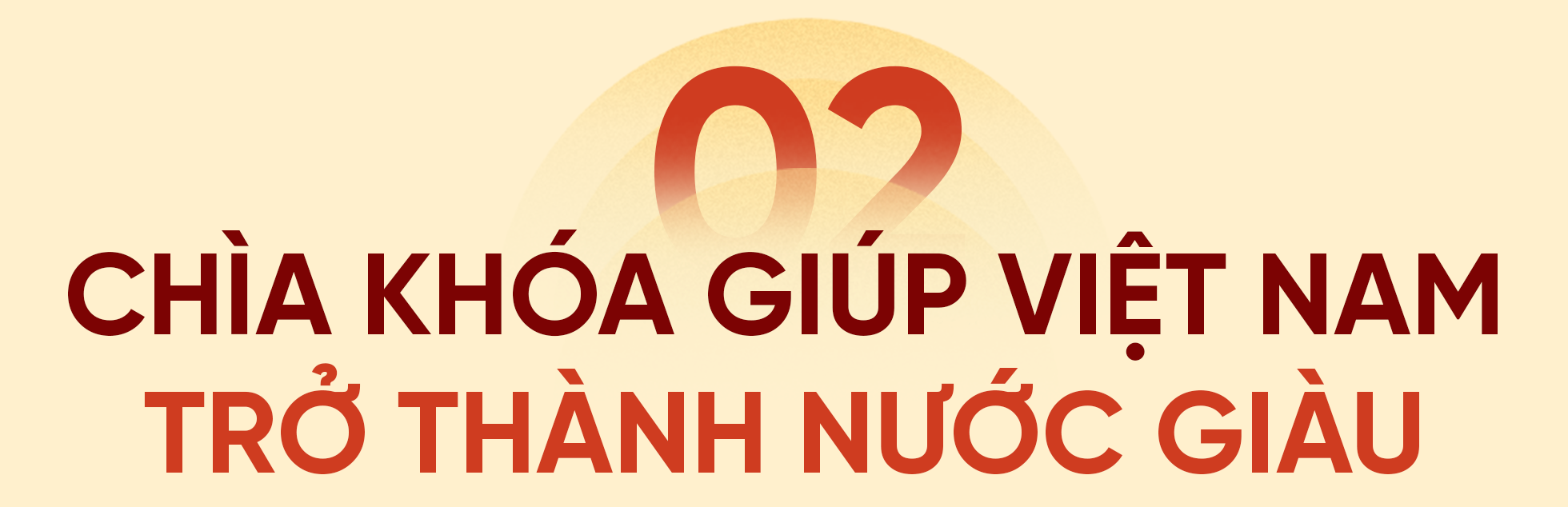
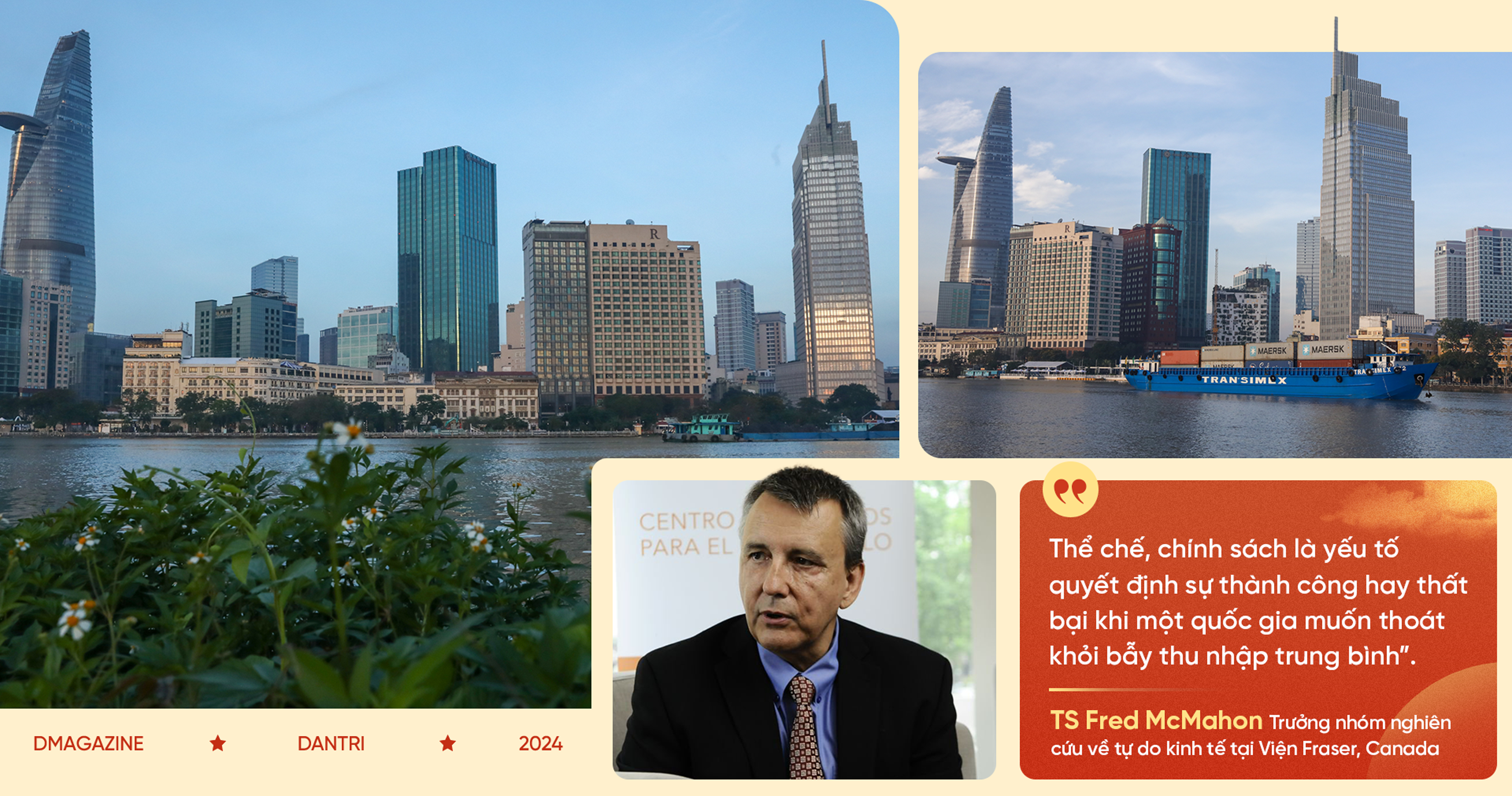

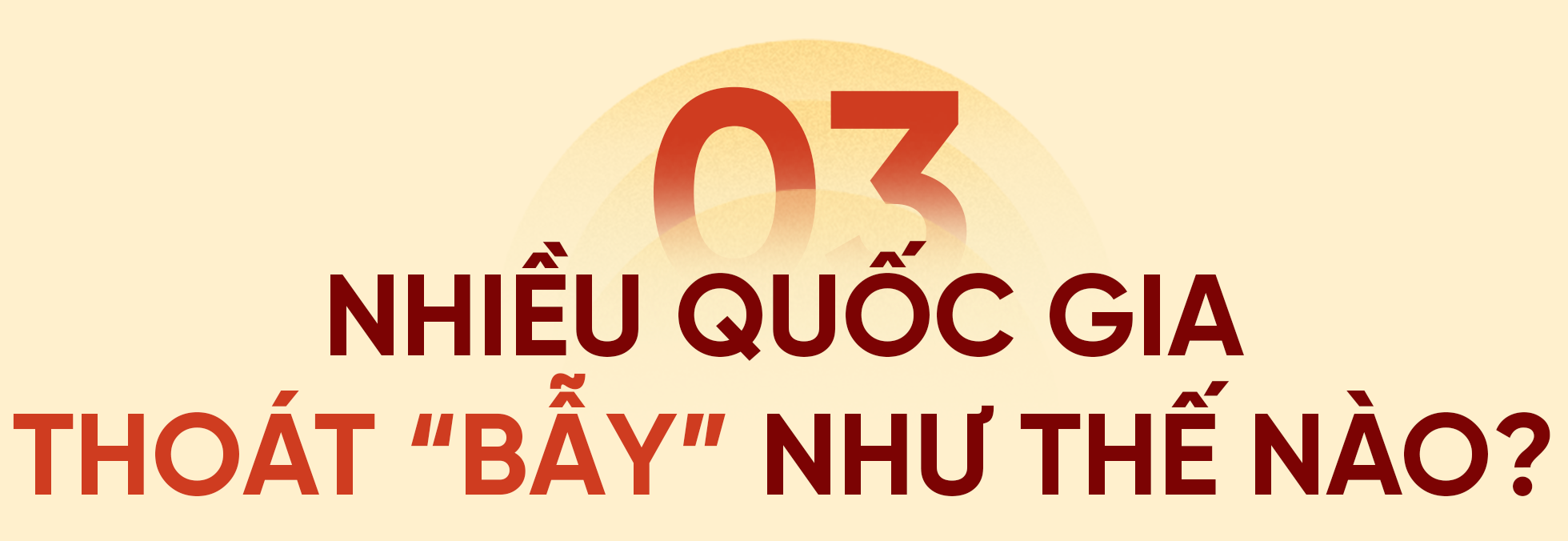





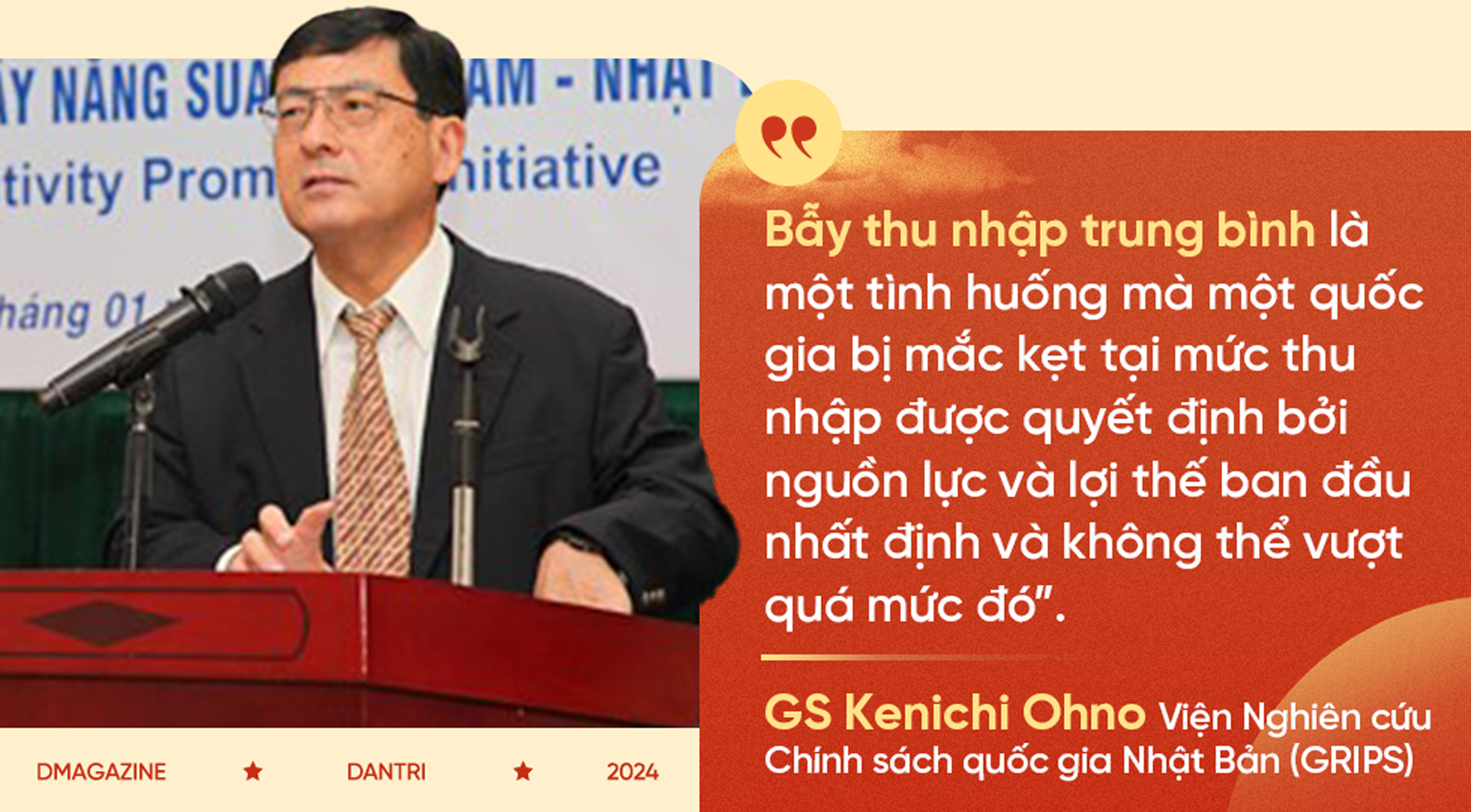
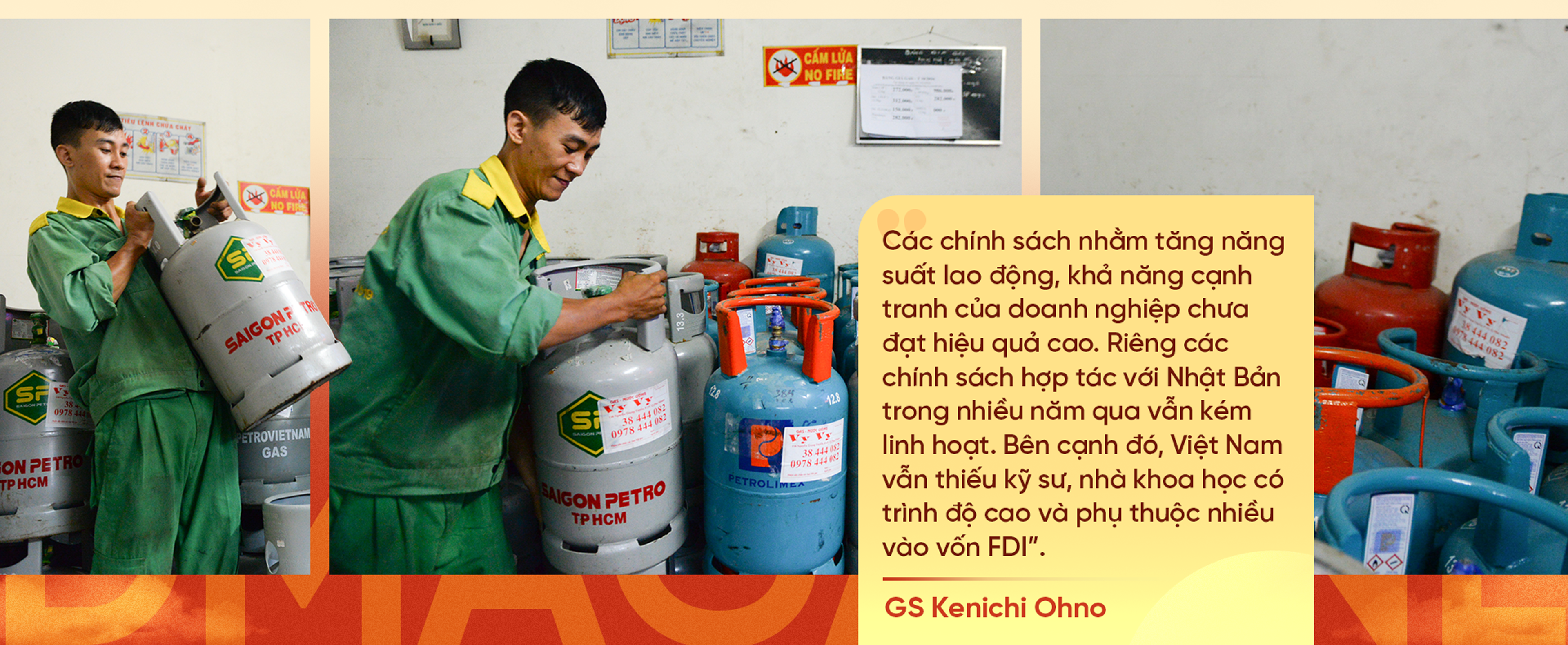
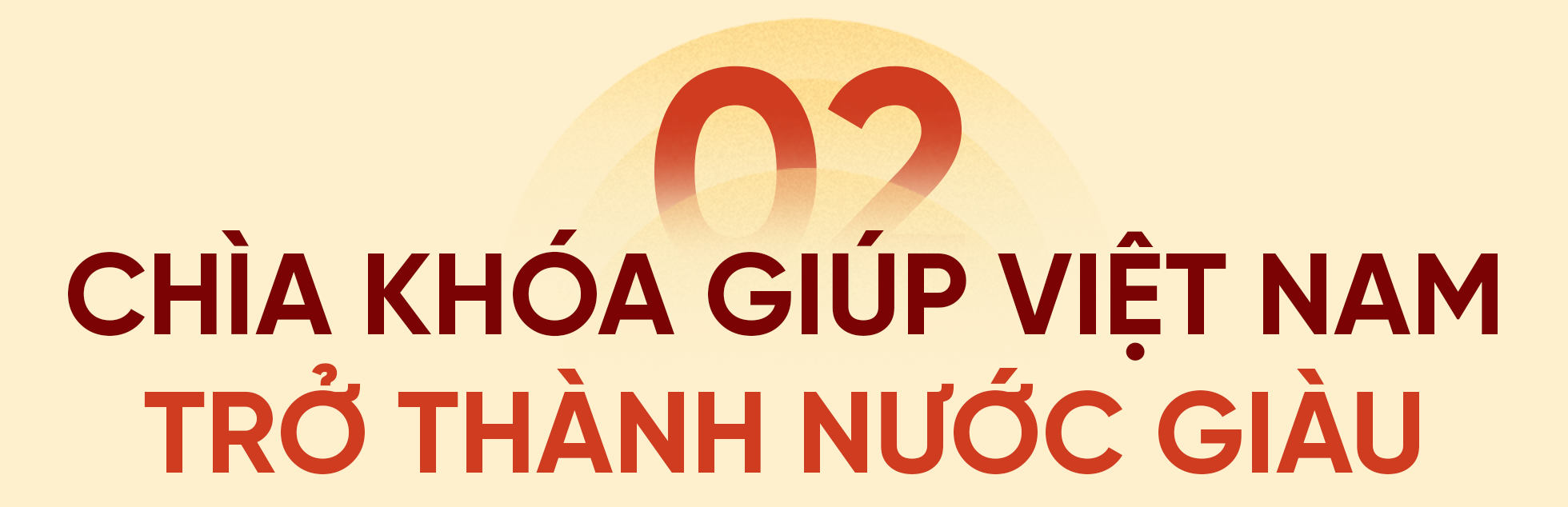
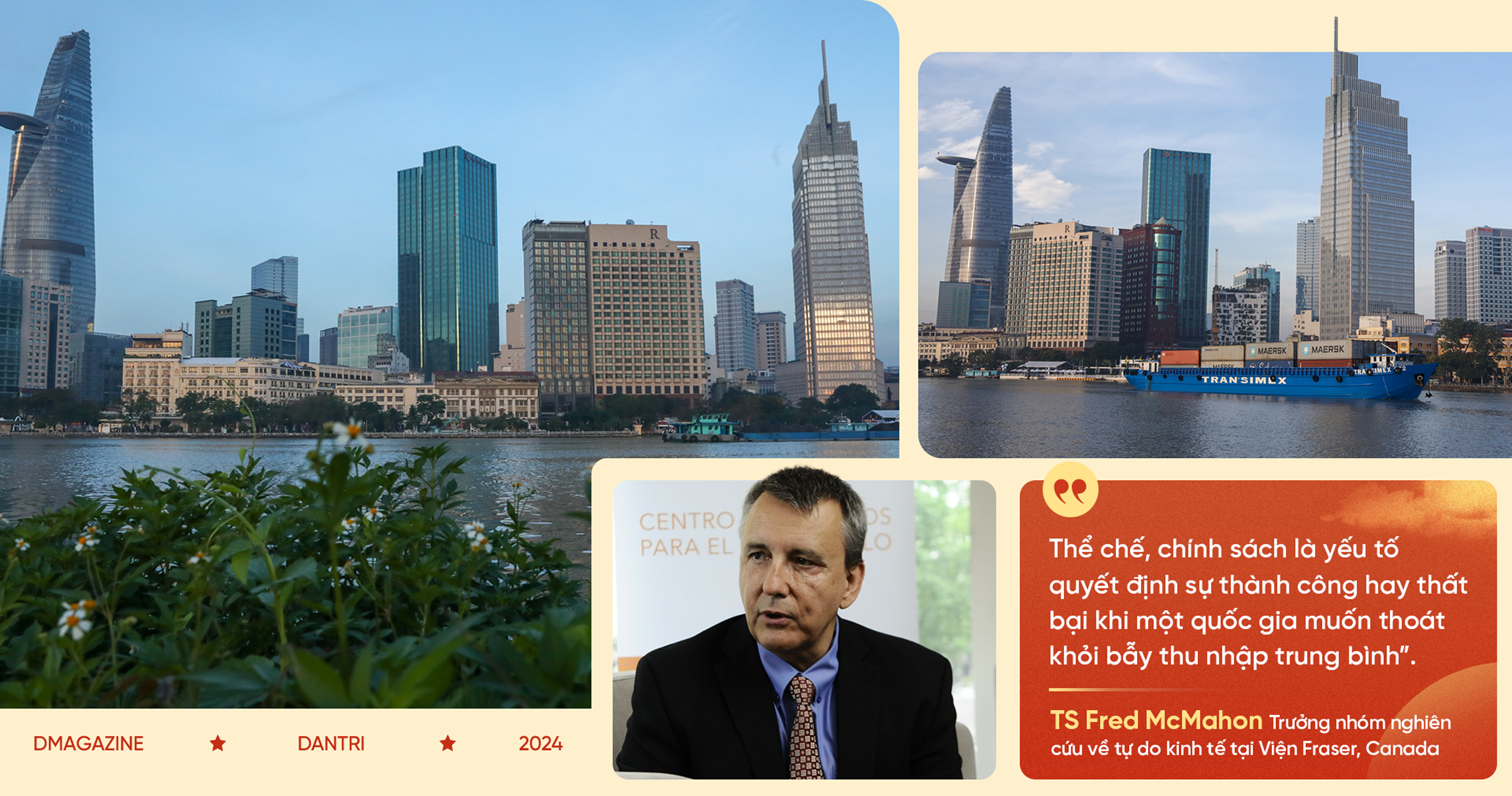

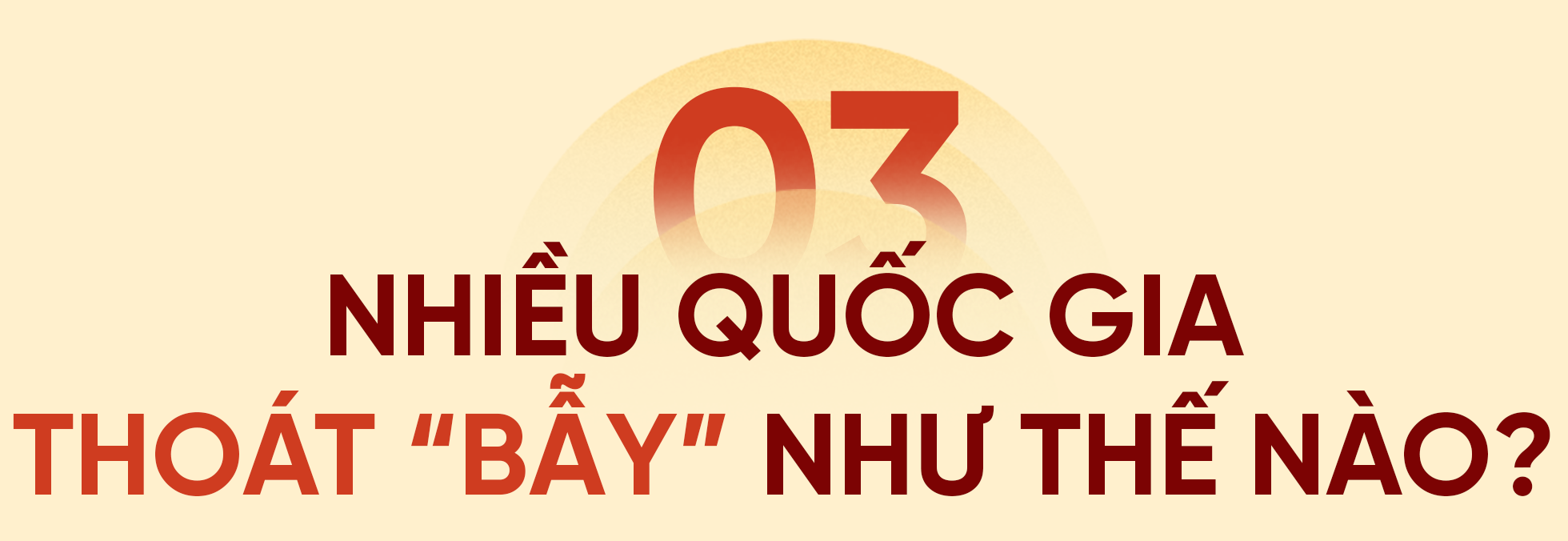



読者の皆様、ベトナムは新たな発展段階、そして機会と課題が複雑に絡み合う、希望に満ちた新たな時代を迎えています。35年以上にわたる改革を経て、ベトナムは大きな成果を収め、経済は目覚ましい成長を遂げ、人々の生活は大きく向上し、国際的な地位もますます向上しました。しかし、こうした成功の一方で、気候変動、熾烈な国際競争、貧富の格差、環境汚染、社会倫理への懸念など、多くの困難と課題にも直面しています。こうした状況において、新時代の特徴、機会、そして課題を明確に認識することが極めて重要です。ダン・トリ紙の連載記事「ベトナム国家の新時代」は、重要な問題を深く分析し、ベトナム国家の新時代をどのように理解すべきか、国の変革を象徴する重要な節目や出来事は何なのか、新時代におけるベトナムにとっての機会と課題は何なのか、機会を捉え、課題を克服し、迅速かつ持続的に国を発展させるにはどうすればよいのかといった重要な問いの解明に貢献します。新時代の国家建設において、あらゆる階層の人々、特に若い世代はどのような役割を果たすべきでしょうか。この連載記事が、国民全体の信念、立ち上がる志、連帯の精神、自立と自力更生の意志を喚起し、豊かで繁栄し、幸福なベトナムを共に築くことに貢献することを願っています。
コンテンツ: タン・トゥオン
デザイン:パトリック・グエン
Dantri.com.vn

































































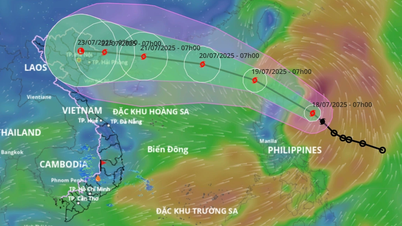



























![[インフォグラフィック] 2025年には47の製品が国家OCOPを達成する](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)





コメント (0)