研究によると、12種類の食品を含む日本の食生活は、脂肪肝を改善し、肝硬変や肝不全の発症を防ぐことができるそうです。
大阪首都大学病院が5月に発表した研究によると、米、味噌汁、大豆などの人気の日本食は、不健康な食生活の結果として太りすぎや肥満の人によく見られる肝臓への脂肪蓄積を防ぐのに役立つ可能性があることが判明した。
研究チームは136人の食事と脂肪肝の進行を追跡調査しました。12項目からなる日本型食事指標(mJDI12)の遵守状況に基づき、各個人の食事をスコア化しました。スコアが高いほど、肝硬変の進行率が低いことが示されました。
この食事に含まれる12種類の食品には、味噌汁、漬物、大豆製品、緑黄色野菜、果物、魚介類、キノコ類、海藻、緑茶、コーヒー、牛肉、豚肉が含まれます。これらの食品のうち、大豆、魚介類、海藻の3つは、肝硬変の進行を抑制する上で重要な効果があります。
専門家らはまた、大豆製品を多く食べる人は筋肉量が多く、線維症の進行率が全体的に低いことも発見した。
これまでの研究で、大豆は低脂肪食品であり、余分な脂肪の蓄積を減らすのに非常に効果的であることが示されています。海藻には、体内の毒素の吸収を防ぐアルギン酸と、肝機能を高め肝臓を保護するフコイダン化合物が含まれています。

大豆製品は肝硬変や脂肪肝を抑制する可能性がある。写真: Freepik
非アルコール性脂肪性肝疾患の症状
日本の国民健康サービスによれば、初期の脂肪肝は害を及ぼすことはありませんが、すぐに治療しないと深刻な肝障害や肝硬変につながる可能性があります。
脂肪肝疾患のリスクが高いグループは、50歳以上の人、肥満、太りすぎの人、2型糖尿病の人、高血圧、高コレステロール、喫煙習慣のある人です。
脂肪肝は初期段階では無症状であることが多いです。最も効果的な診断方法は血液検査です。線維化(脂肪肝の重症期)を呈する人は、右上腹部の鈍痛や疼き、極度の疲労感、原因不明の体重減少などの症状が現れることがあります。
肝硬変が進行するにつれて、皮膚や白目の部分が黄色くなる、皮膚のかゆみ、脚、足首、足の腫れ、腹部の浮腫などのより深刻な症状が現れます。
トゥク・リン(エクスプレスによる)
[広告2]
ソースリンク





































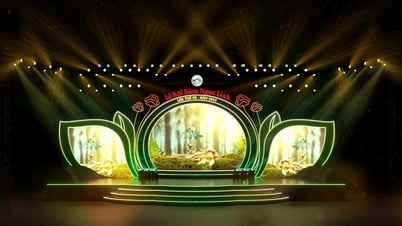
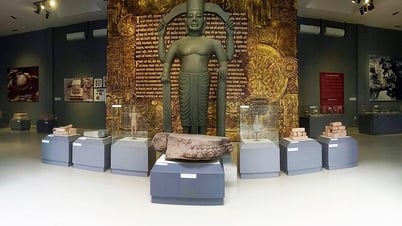





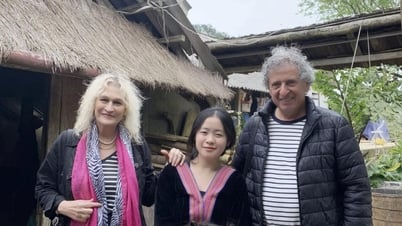

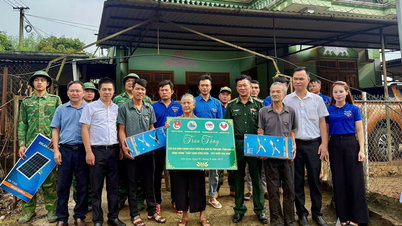




























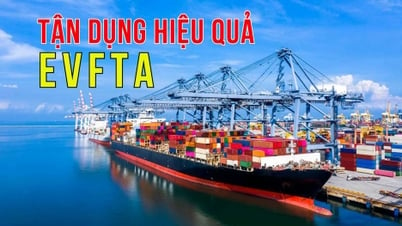


















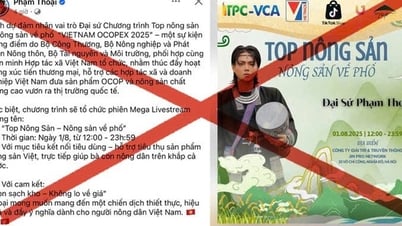






コメント (0)