約400年にわたり天皇の居城であった京都には、伝統文化の痕跡を色濃く残す、豊かで多様な食文化があります。ラーメンや寿司以外にも、京都にはぜひ試していただきたい料理が少なくとも5つあります。
湯豆腐

京都を代表する料理といえば、湯豆腐でしょう。豆腐、水、昆布だけで作られ、コンロで煮込まれます。豆腐は酢をベースにしたポン酢醤油などのタレにつけて食べます。
湯豆腐は京都で生まれた精進料理(栄養と精神のバランスを重視した日本の伝統的な精進料理)です。湯豆腐は僧侶の食事から生まれた精進料理です。1635年頃に南禅寺の近くに湯豆腐専門店が創業し、現在も営業を続けています。
ハモ(ウナギ)

京都では鱧は特に夏に人気の料理です。鱧は体全体に小さな糸状の骨が多数あるため、調理が大変です。鱧は煮たり、焼いたり、揚げたり、しゃぶしゃぶや鍋にも使えます。特に夏は、酸味のある梅のタレで味付けした冷製の鱧が人気です。
ハモは栄養価が高く、独特の風味があり、食べると舌の上でほんのりとした甘みを感じます。
漬物

京都の漬物の中でも代表的なものは、しば漬け、千枚漬け、杉漬けの3種類です。しば漬けは、千切りにしたキュウリとナスを赤紫蘇(シソまたはシソ科の植物)に漬け込んだ、酸味と歯ごたえのある漬物です。紫蘇の力で、食材が鮮やかな赤色に染まります。
千枚漬けとは、千枚の葉を漬け込んだ漬物です。大きく丸い聖護院大根を1mmの厚さに薄くスライスし、昆布と一緒に漬け込みます。
すぐき漬けには、すぐき菜と呼ばれる種類の大根が使われます。この小頭で葉の長い大根は、1世紀以上もの間、上賀茂神社周辺でのみ生産され、厳しく管理されてきました。
抹茶(緑茶)

茶道発祥の地である京都は、抹茶を味わうのに最適な場所です。寺院の境内や観光地には多くの茶室があり、抹茶の淹れ方を問わない、あるいは淹れ方を問わない、泡立ちの良い抹茶を味わうことができます。抹茶は日本の緑茶の中でも最高級品です。特別な環境で栽培された茶葉から作られ、色、風味、香り、そして栄養価を高めるために、厳密に管理された乾燥と粉砕工程を経て作られます。これらすべてが、古都京都で抹茶を味わう忘れられない体験となるでしょう。
京都では、抹茶はソフトクリーム、ケーキ、クッキー、クラッカーなど、さまざまな形で作られても美味しいです。
八つ橋(三角団子)

八つ橋は京都を訪れる人に最も人気のお土産です。米粉、砂糖、ニッキと呼ばれる国産のシナモンを原料として作られています。この生地を蒸し、半月形に平らに伸ばして焼き上げることで、サクサクとした食感と少し硬さのある、小さな茶色のタイルのようなクッキーに仕上がります。このタイプの八つ橋は1689年から存在しています。
1960年代には、京都で「生八つ橋」と呼ばれる新しいタイプの八つ橋が登場しました。このタイプの八つ橋は、焼き菓子ではなく、柔らかい生地を四角に切り、三角形に折り込み、中に甘い餡子を詰めています。オリジナルのシナモン味に加え、抹茶やゴマ味、そして最近ではチョコレートやバナナ味もあります。餡子が苦手な方は、皮だけを購入することもできます。
ソース








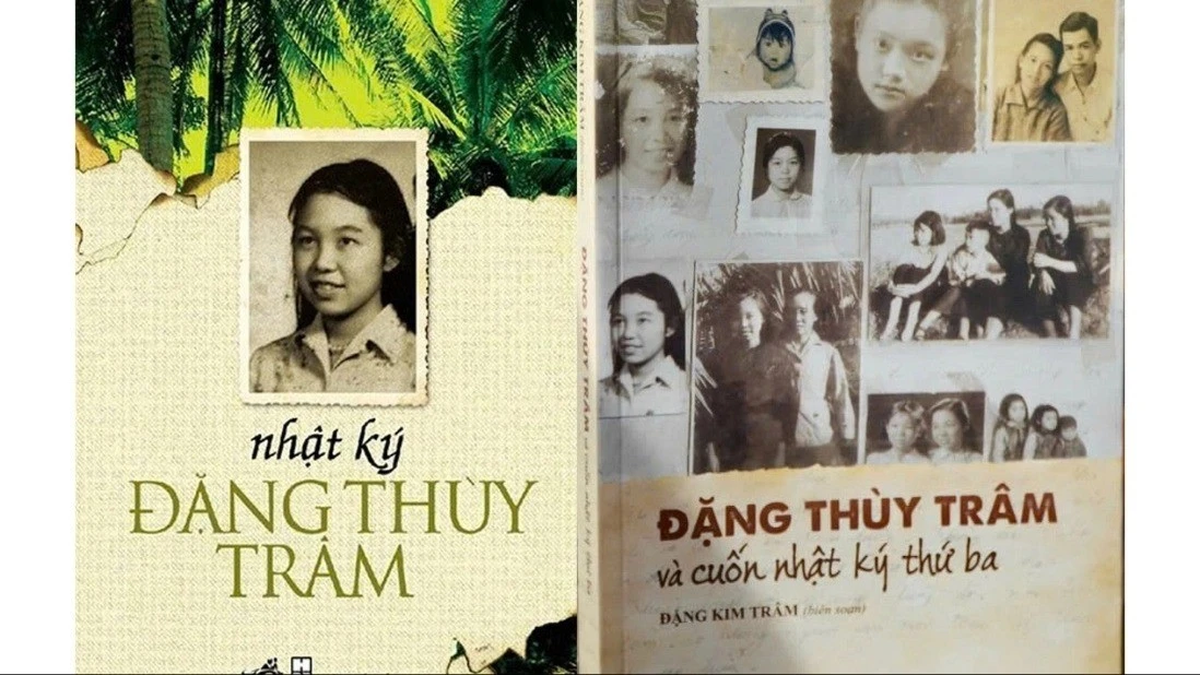























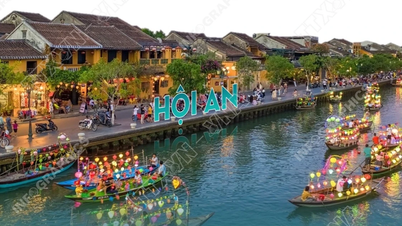


















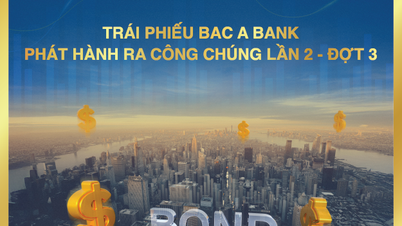








































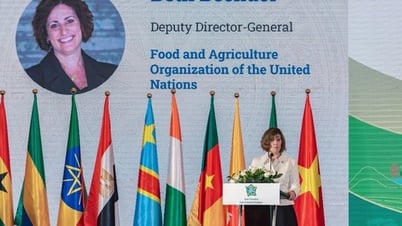







コメント (0)