高等教育に対する州の予算は少なく、継続的に減少しているにもかかわらず、公立学校の授業料は適切な形で引き上げられていないため、学校の収入は限られており、教育の質を維持・向上させるための収支バランスをとることが困難になっています。この困難に対する解決策は何でしょうか。
ファム・ド・ナット・ティエン博士 - 元教育訓練省次官:高等教育の社会化における資源に関する考え方の変革

これまで、教育の社会化は、国内外を問わず、組織、個人、企業、地域社会、そして一般市民からの資金動員に重点が置かれてきました。2019年6月4日付の政府決議第35/NQ-CP号「2019年から2025年までの教育・訓練開発への投資のための社会資源動員強化に関する決議」も同様のアプローチを採用しています。
この動員において、生徒・学生の授業料が大きな割合を占めています。高等教育市場の発展に伴い、この割合は増加し、高等教育における単位費用を徐々に補填していくでしょう。
これは、学習者が教育を受ける上での大きな障壁、すなわち経済的障壁につながるでしょう。これは、ベトナムが2030年までに目指す、すべての人々が生涯学習できる環境を整備し、開かれた大学教育システムを構築する上で、矛盾を生じさせるでしょう。
したがって、課題は、高等教育の社会化における資源に関する考え方を変えることです。つまり、財源に限定された考え方から、高等教育の発展に利用可能なあらゆる資源を含むオープンリソース(開かれた資源)への考え方へと転換することです。これらは、今日の世界における高等教育の発展において積極的に活用されている、アイデア、政策、そして技術といった資源です。
情報が指数関数的に増加し、人間の知識が日々倍増する今日、アイデアという資源は豊富かつ重要になっています。スタートアップは本質的に、アイデアという資源を基盤として事業を展開しています。
今日、世界の高等教育は、教育における経済的障壁の撤廃を目指す個人や学校からのアイデアの源泉によって、オープンな方向へ急速に発展しています。しかし、私たちはこの資源を真に評価しておらず、アイデアの発展に適した環境の構築に注力してきませんでした。
政策資源について:契約10号のような優れた政策は、画期的な資源となり、奇跡をもたらす可能性があります。我が国の教育の強みも、優れた政策資源に大きく依存しています。しかし、この資源が十分に評価されていないケースがあります。
テクノロジーに関しては、これは10年以上にわたり、世界の高等教育の発展における主要な資源となってきました。党の政策(政治局、2014年)から国家機関(政府、2015年)に至るまで、持続可能な開発と国際統合のプロセスにおけるICTの位置づけと特に重要な役割を確立することを目指していることから、私たちはこの資源の重要性を明確に認識しています。これは、我が国の高等教育がデジタル高等教育とオープンな高等教育へと変革する大きな機会をもたらします。
しかしながら、ベトナムのICT発展の現状は多くの課題に直面しており、地域および世界のICT分野全体の進歩と比較すると、ベトナムの進歩は遅いと言えます。
教育分野に限って言えば、技術リソースの開発は主に学校へのコンピュータとインターネットの導入に留まっています。オンライン研修に必要なICTインフラの構築にはほとんど注目が集まっておらず、オープン高等教育の主要な技術リソースとなるOERやMOOCプラットフォームの構築についても、目立った進展は見られません。
上記の資源の活用における欠陥により、公立高等教育機関は他の収入源の多様化が困難であるため、主に授業料に依存しています。世界銀行の調査(2020年)によると、収入源の多様化においては、技術移転活動による収入に過度に依存すべきではありません。ハーバード大学でさえ、この収入源は大学の募金活動による総収入のわずか1%を占めているに過ぎないからです。
国際的な経験から、公立の高等教育機関が活用すべき最も重要な収入源は、定期的な研修プログラムの提供、コンサルティングサービス、卒業生や企業からの募金活動の実施の3つです。
しかし、これは追加収益の創出を目的としたアプローチです。アイデア、政策、テクノロジーといった面で上記のリソースを活用し、効率性(コスト)を向上させ、ひいては単位コストを削減するアプローチに着目することが非常に重要です。今日、オープンサイエンス、オープン教育、オープンテクノロジーの急速な発展に伴い、ベトナムの高等教育機関は、学習者に低コストで質の高い研修プログラムを提供するために、豊富なリソースを活用する必要があります。
ヴォ・ヴァン・ミン准教授 - 教育大学(ダナン大学)学長:金融、資産、投資に関する法的枠組みの完成

2025年高等教育法改正案は、多くの根本的な革新を示しており、高等教育のガバナンスと発展に関する考え方において大きな前進を示唆しています。重要なポイントの一つは、財務、資産、投資、資源動員に関する規制が、国内の実務要件と国際的な動向に沿って、より明確に改訂されたことです。
まず、本草案は、財政的自立、資産の活用、合法的な利用を拡大し、高等教育機関が開発、管理、資源利用の効率化においてより積極的に活動することを可能にする。国内外の組織との投資協力に関する規定の追加は、市場メカニズムへの柔軟かつ効果的なアプローチに向けた政策思考の転換を示している。
特筆すべきは、高等教育分野において官民パートナーシップ(PPP)モデルが正式に合法化された初めてのケースであるということです。このモデルは、学校と企業、そして社会団体間の広範な協力の可能性を広げ、国家予算への圧力軽減と投資資源の多様化に貢献するというプラスの影響をもたらします。
同時に、草案は、戦略的課題のための資源を確保するとともに、社会資源の動員を促進するという国家の役割を明確に規定しています。この「二重」アプローチは、学校が自律的かつ革新的であるための条件を整備するとともに、新たな状況にふさわしい方向性を示す役割を果たします。
上記の規定が効果的かつ持続的に実施されるためには、草案において以下の点に留意すべきである。学校に更なる自治権が与えられることを条件として、公共資産の使用状況を監視するメカニズムを明確化すること。これは、透明性を確保し、損失を防ぎ、資産使用の効率性を向上させるためである。PPPモデルについては、定義には含まれているものの、形式化を回避し、実現可能性を確保するため、運用原則、実施条件、パートナー選定基準、リスク分担メカニズムをより明確に補足する必要がある。
高等教育への外国投資には、学術的安全性、知的財産権を確保し、国家の教育のアイデンティティを維持しながら、資本、技術、近代的な経営の誘致を促進するための独自の法的規制が必要です。
要するに、財政と投資の自立は、大学が持続的に発展し、地域および国際基準に到達するために不可欠な条件です。この改正法案は、そのプロセスのための重要な基盤を築きました。しかし、付与された権利を実践能力へと転換するためには、社会資源の監視、運用、連携、動員に関する具体的で透明性があり、効果的かつ実現可能な法的規制が必要です。
財政、資産、投資に関する法的枠組みの完成は、高等教育機関の持続可能な発展を支援するだけでなく、自律性、責任、効率性に向けた高等教育システムの構築にも貢献し、新時代の国家発展戦略に役立ちます。
ベトナム国家大学ハノイ校教育大学副学長 トラン・タン・ナム准教授:予算支出比率の引き上げが必要

現代の高等教育は、知識基盤型経済発展、イノベーション、そして国際統合の要求を満たす必要があります。第13回党大会では、「質の高い人材育成を戦略的突破口とする」ことが明記されました。党と政府は、教育訓練への投資が国家予算支出総額の少なくとも20%を占めることを繰り返し強調してきました。これに加え、大学の自治を促進し、国際的な質認証を強化する政策も推進されています。
実際には、ベトナムにおける高等教育への予算支出は依然として限られています。財務省によると、2020年の高等教育への実際の支出はGDPのわずか0.18%にとどまり、これは総教育支出の4.6%に相当します。一方、アジア太平洋諸国では、高等教育への支出は通常GDPの1~1.5%で、教育予算の20%以上を占めています。教育訓練省の報告書によると、現在、公立大学の収入の平均60%が国家予算に依存しています。これは、実際の財政的自立度が非常に限られていることを示しています。
高等教育法案(改正版)は、「国家は、国家の高等教育制度の発展戦略、計画、方向性に基づき、高等教育の発展への投資を優先する。高等教育機関が基準を満たし、施設、教育設備、科学研究、革新を近代化するための投資に重点を置く」と規定しているが、最低支出レベルや長期的な安定メカニズムについては明記していない。
実際、この法律は、持続可能性を確保するための最低料金や複数年にわたる配分メカニズムをまだ規定しておらず、奨学金、学生ローン、そして重要な活動を支援するための高等教育のための独立した基金の設立についても言及していない。特に授業料の枠組みが厳格化されている現状では、国家予算のみに頼り、社会を動員するだけでは不十分である。
高等教育法案は、予算外資金の動員と一般的な税制優遇措置の促進にとどまっています。こうした状況下では、現行の財政メカニズムは依然として長期的な持続可能性を欠いており、高等教育における財政不足の根本的な原因を解決できていません。
上記の実践を踏まえ、高等教育財政に関して私が強調したい第一の提案は、総教育支出および国家予算に占める高等教育予算の割合を高めることにより、高等教育への財源を拡充することです。具体的な目標としては、教育費をGDPの10%以上(一般教育20%政策に基づく)とすることを掲げ、高等教育への割合を現在の5%から地域水準(総教育支出の8~10%程度)まで引き上げることが挙げられます。
第二に、国立高等教育基金を設立する。中央予算と社会保障(企業や支援団体からの資金提供)を活用し、学生のための奨学金と単位取得のための全国基金を構築する。この基金は、学生による起業を支援し、質の高い認定(独立した認定機関への資金提供)を確保する。
第三に、安定した財政メカニズムが確立されています。高等教育法案(改正)の規定に基づき、学校には完全な財政的自治権が認められ、能力の範囲内で支出を決定する権利が与えられます。同時に、国は少なくとも3年に1回、成果(パフォーマンス)に基づいて研修と研究を命令します。この長期的な命令メカニズムにより、学校の安定した収入源が確保され、年間予算への依存度が軽減されます。
第四に、税制優遇措置:学校開発投資に充てられる授業料に対する免税・減免政策の拡充。例えば、施設投資に対する付加価値税の免税、高等教育支援サービス事業に対する法人所得税の免税など。
高等教育法案(改正案)では、高等教育に対する一般的な税制優遇措置について触れており、特に非営利の公的機関における教育・研究活動については明確な免税規定を追加する必要がある。
上記の提言は、科学的理論と国内外の実践に基づき、政策の充実とベトナムの高等教育発展の推進力となる法案に盛り込まれることが期待されます。予算支出比率の明確化、国家基金の設立、合理的な階層化、そして自治権の強力な推進は、画期的な改革となり、人材の質の向上とベトナムの高等教育の将来的な地位向上に貢献するでしょう。
出典: https://giaoducthoidai.vn/can-dot-pha-ve-chinh-sach-tai-chinh-cho-giao-duc-dai-hoc-post742673.html







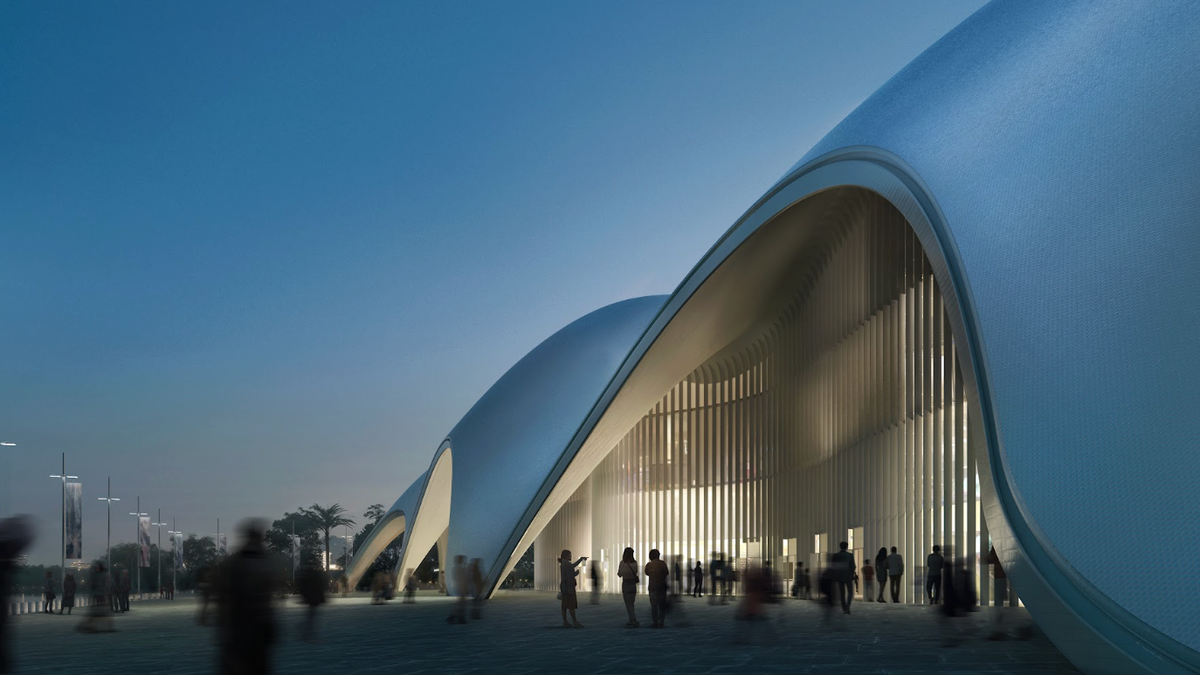




























































































コメント (0)