昨日10月22日、国会文化教育委員会(CEC)は、博士課程教育に関する政策および法律の実施状況のモニタリング結果に関する報告書を国会議員に提出しました。報告書では、博士課程教育の現状評価に加え、博士課程教育をエリート養成と捉えることや、博士課程教育に対する国家支援政策の提案など、国際的な統合の潮流に沿った新たな視点を反映した数々の提言も示されました。
報告書はまた、博士課程のトレーニングが構築し形成する必要がある要件として学術的誠実さの概念を繰り返し言及し、専門的な要件ではなく学位のために博士課程の動機を誤解させる傾向を批判した。
博士課程の費用は年間わずか1600万ドン
文化教育委員会によると、高等教育全般、特に博士課程への投資は依然として低い。過去3年間の高等教育への国家予算支出額は、教育訓練予算全体のわずか4.33~4.74%(国家予算支出全体の約1%)に過ぎない。
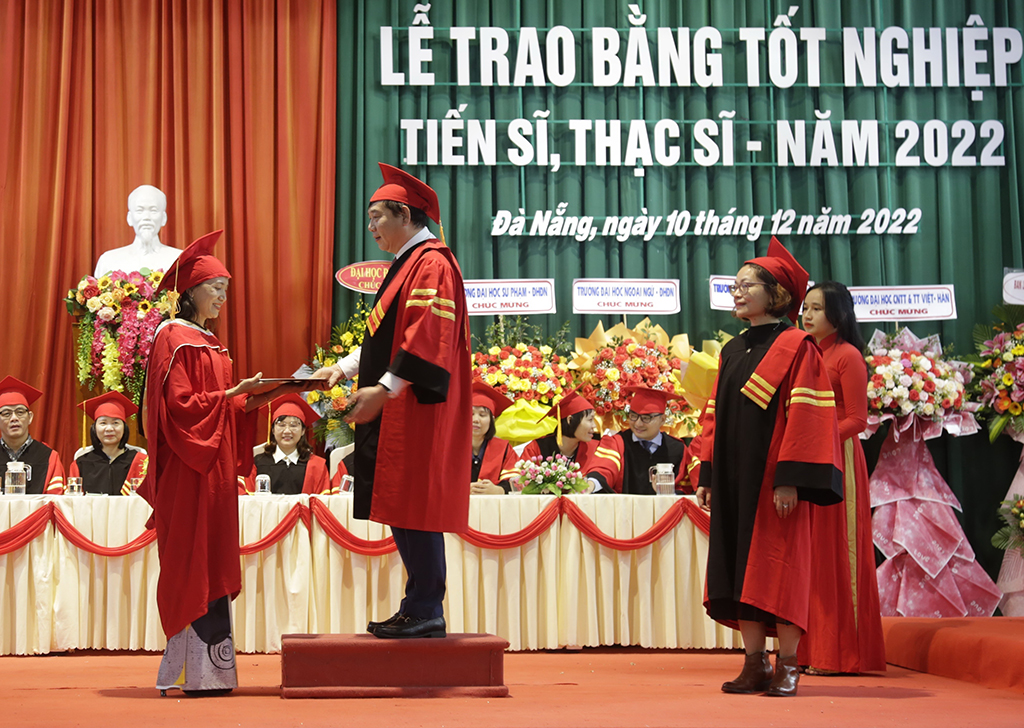
文化教育委員会は、博士号取得者チームをエリート集団として構築し、育成する上での戦略的目標と長期的ビジョンを導く規制を設けることを提案しています。
公立大学における博士課程の教育費用は現在、平均で年間約1,600万ドン(保健科学分野は約3,200万ドン)であり、地域や世界の一部の国における博士課程の教育費用よりもはるかに低い水準です。そのため、国内の博士課程教育機関は、博士課程の学生が研究を行い、文献や最新の科学論文を参考にし、論文の質を向上させるための好ましい環境を確保する上で、多くの困難に直面しています。
博士課程学生に対する奨学金や財政支援に関する仕組みや政策は、十分な注意が払われていない。一方、世界各国やこの地域では、博士課程学生は授業料を免除されるだけでなく、月々の生活費や博士論文執筆に必要な資金を賄うのに十分な奨学金を受け取っており、ティーチングアシスタントや指導教員との研究活動に参加する際に給与が支払われることさえある(米国、韓国、シンガポールなど)。一方、ベトナムでは、博士課程学生は授業料を支払わなければならず、研修機関からの研究資金へのアクセスは限られている。
現在、国は、2019年から2030年にかけて高等教育機関の講師と管理者の能力を向上させるプロジェクトで選ばれた大学院生に対する財政支援メカニズムのみを設けており、これには論文執筆に対する財政支援(学生1人あたり年間1,300万~2,000万ドン、最長4年)、国際的な科学論文の出版に対する支援、国際会議、セミナー、海外での短期インターンシップへの参加に対する支援(研修プロセス全体を通じて1回)などが含まれます。
労働力の74.4%には予算の「パイ」の6.91%しか与えられていない
大学における研究開発活動への予算は依然として少なく、大学の能力や潜在力に見合っていない。全国の博士号取得者総数22,578人のうち、大学で研究開発に従事する博士号以上の学位取得者(16,810人)の割合は74.4%に上る。一方、大学・アカデミーにおける研究開発費は、この活動への総支出のわずか6.91%を占めるに過ぎない。
博士課程はエリート研修である
文化教育委員会によると、博士課程の教育の量と質を向上させるためには、博士課程の教育がエリート養成であるという観点を徹底的に理解することを含め、さまざまな方向づけ、課題、解決策を効果的に実行する必要がある。
博士課程教育の量と質の調和のとれた発展に留意し、投入の質を管理し、成果の質の水準を向上させる。産業化、近代化、ハイテク産業、コアテクノロジーの推進に直接貢献する産業・分野における博士課程教育を優先するためのメカニズムと政策を整備する。
提案されているもう一つの解決策は、品質保証のための条件を強化することです。特に、研究、応用、技術移転への公的投資をはじめとする投資資源の増強が不可欠です。財政メカニズムを改善し、研修・研究への資金配分方法を発注、入札、課題割り当てといった形式に変更する必要があります。
国家が質の高い人材を必要としているものの、学生の確保が困難な基礎科学分野および必要な研究分野への国家予算の投資を優先する。優れた研究成果と応用性の高いテーマ・論文を有する博士課程学生に対し、奨学金支援および科学研究費補助のための政策を策定する。国際基準に準拠した博士課程教育活動の質を評価するための基準と、各分野における博士論文の質を評価するための最低基準を策定・公布する。

優れた研究・学習成果と応用性の高いテーマ・論文を持つ大学院生に対する奨学金や科学研究資金を支援する政策を策定します。
文化教育委員会は、上記の評価に基づき、国会に対し、博士号取得者チームを優秀な人材チームの中の精鋭として構築・育成するための戦略目標と長期ビジョンに関する規定を含め、優秀な人材の育成の発展を促進・奨励するための政策方向付けに関する専門決議を採択すべきであり、博士号資格を持つ知識人チームを活用し、育成するためのメカニズムと政策が必要であると提案する。
同時に、決議では、高等教育への国家予算支出の対GDP比を地域諸国の平均水準まで引き上げ、特に博士課程教育、そして大学院教育全般への投資レベルを高め、高等人材育成の有効性と質を確保するためのロードマップを明確にする必要がある。特に、システムにおける潜在力と質の高い教育・科学研究能力を備えた高等教育機関への投資を重視し、特に複数の優先分野・分野において、国際水準の高等教育機関を複数設立し、先駆的な役割を担い、システムを主導し、科学技術発展と社会経済発展の推進力を生み出すことを目指す。
学位を重視するあまり、博士号取得への動機が依然として歪められています。
文化教育委員会の報告書によると、入学者構成は、約60~70%が教育訓練機関および研究機関出身で、約30%が管理・行政機関に勤務している(民間企業やその他の部署出身者はごくわずかである)。この数字は、博士課程の現状におけるいくつかの欠陥の原因を評価する上での根拠となる。文化教育委員会は、「職員の活用と管理において学位を重視する傾向は、多くの大学院生の博士号取得への意欲に偏りをもたらしている」と指摘した。
研修規模に関しては、2000年から2001年にかけて顕著な成長を遂げたものの、現在の入学状況は非常に厳しい状況にあります。合格率は目標を大きく下回り、近年の平均合格率はわずか32%程度にとどまっており、多くの入学枠で競争がなく、特に専門研究能力の面で入学選考の緩みが生じています。
教育の質に関して、文化教育委員会は、特に博士論文の質、そして博士課程教育全般の質の評価が、システム全体で均一ではないと考えています。論文評価委員会の設置において、審査が甘いという現象が見られます。また、実用的価値が低く、科学的内容が低く、影響範囲が狭い論文を優遇して承認する傾向も見られます。
論文再評価プロセスは依然として手続きや形式に追われており、実際には効果的とは言えません。特に報告書は、「研究倫理と学術的誠実性に関する一般的な規制が存在せず、教育、研究、科学論文や博士論文の出版における盗作を防止・撲滅するための共通ソフトウェアや十分な規模のデータベースが構築されていない」という現状を指摘しています。
[広告2]
ソースリンク





















































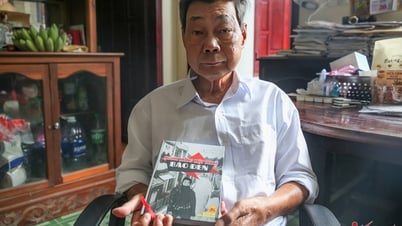


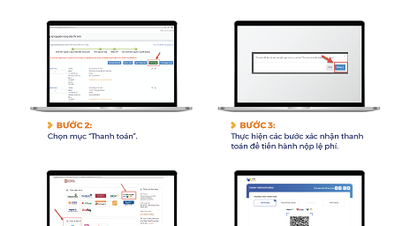







































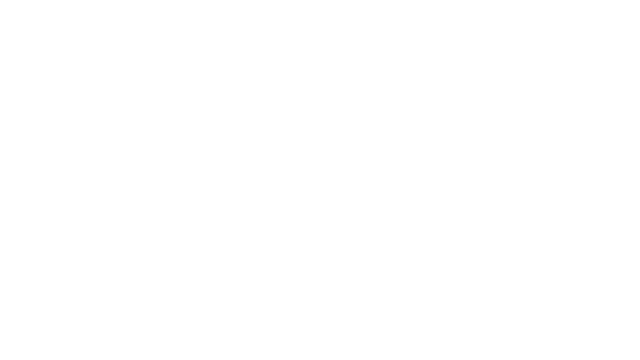


コメント (0)