
地震後、能登半島の一部が海に浸食された。
NHKスクリーンショット
NHKは1月6日、能登半島(石川県)で発生したマグニチュード7.6の地震により海岸線が最大175メートル拡大したとする日本の研究結果を引用して報じた。
広島大学の後藤英明准教授が率いる専門家チームは、中部日本にある石川県での地震と津波の影響後の土地の変化を調査した。
研究では主に、1月1日の地震後に撮影され、能登半島の北東海岸沿いの約50メートルの範囲にわたる航空写真が使用された。
調査の結果、地震の影響で地域の大部分で地盤が隆起し、沿岸部が海側に拡大したことが明らかになりました。珠洲市川浦区では、175メートルも拡大した地域もありました。
その結果、陸地面積は合計2.4平方キロメートル拡大したと研究者らは述べている。半島北岸のいくつかの港では海水がほぼ消失した。
1月2日にフランスの衛星が撮影した画像では、輪島市小沢地区の港から海水が消失している様子も確認された。後藤准教授は、これは地盤の隆起によるものだと述べた。
日本の地震救助、黄金期が尽きつつある
氏は、珠洲市宝竜地区で津波の高さが約3メートルに達したことも確認したと述べた。また、活動すると甚大な被害をもたらす活断層は日本各地に存在しており、人々は自分の住んでいる地域に断層がないか確認する必要があると指摘した。
共同通信社によると、地震による死者は98人に上り、依然として211人が行方不明となっている。
最も被害が大きかった地域の一つである輪島市の当局者は、倒壊した建物の下敷きになって救助を待っている人がまだ約100カ所あると述べた。
石川県では地震により道路が損壊し、31,000人以上が357か所の避難所に留まっているため、当局は依然として救援物資の輸送に苦慮している。
北陸電力によると、震源地に最も近い能登半島の志賀原子力発電所では、今回の地震による安全上の大きな問題はなかったという。
同発電所の原子炉2基は地震発生前から停止していた。同社は、敷地内4箇所に損傷が見つかり、外部電源システムの一部が依然として機能していないものの、使用済み核燃料は正常に冷却されており、放射性物質は安全に封じ込められていると発表した。
地震発生から約90分後、日本海西部につながる湖の水位が約3メートル上昇したが、原発は海抜11メートルを超える陸地にあるため、影響はなかった。
志賀原発は再稼働前の手順に則り、原子力規制庁によって安全システムの解析が行われている。
[広告2]
ソースリンク


















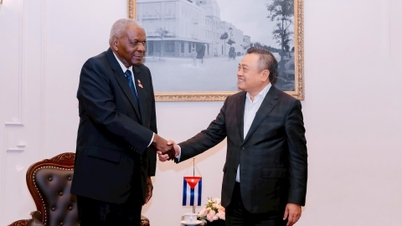
































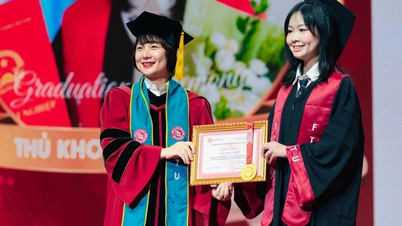















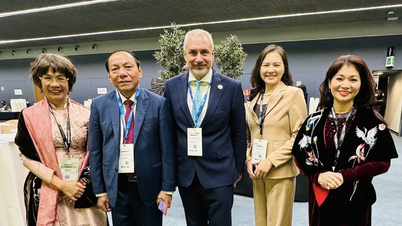








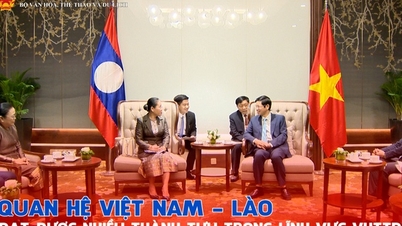



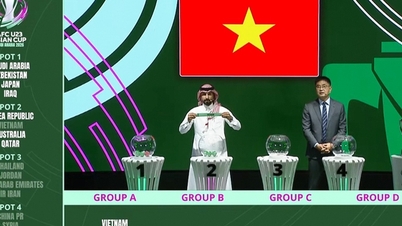






















コメント (0)