グエン・ハイ・チュン中将は、銀行部門における違反行為はより巧妙化しているが、国家銀行の捜査権限を強化する必要はないと述べた。
信用機関に関する法律案(改正版)は、現在の検査・監督の仕組みに加え、国立銀行の調査権限を補完するものである。
6月10日午後の議論において、 ハノイ警察長官のグエン・ハイ・チュン中将は、この権利は規制されるべきではないと述べた。チュン中将は、代わりに、大株主による権力の濫用を制限する国家銀行の権利と、信用機関の業務を管理・操作する権利を追加することを提案した。
同時に、大株主グループの名を騙って多数の個人が信用機関を経営するといった脱法行為を防ぐための措置も盛り込む必要がある。
チュン氏は、銀行における相互所有と操作の状況は、特に民間経済グループのエコシステムにおける企業間の融資のための資金動員において、依然として「懸念される」と評価した。
同氏によると、法案は個人の所有比率の調整を緩和し、銀行の株主構造の健全化に貢献する。しかし、現実には、取締役会に名を連ねているか否かに関わらず、経営、支配株の保有、銀行業務の運営を行う大株主が依然として存在する。

ハノイ警察署長グエン・ハイ・チュン中将。写真:ホアンフォン
ホーチミン市司法省のヴァン・ティ・バク・トゥエット副局長も、国家銀行の捜査権限の強化を慎重に検討する必要があると述べた。なぜなら、既存の機関は既に銀行業務における違反行為を捜査するための十分な手段を備えているからだ。
「国立銀行の検査・監督機関が監督過程で違反を発見した場合、専門の調査機関に移送する方が適切だろう」と彼女は述べた。
一方、国防安全保障委員会の常勤委員であるチン・スアン・アン氏は、信用活動を監視・検査するための独立機関のモデルを再構築する必要があると述べた。
彼は、相互所有は「誰もが知っているが、氏名や具体的な住所を特定するのは非常に難しい」という現実だと分析した。しかし、策定中の政策は依然として十分に強力ではなく、解決策は株式比率の引き下げや信用限度額の引き下げといった消極的なものにとどまっている。
「株式や資本の余裕を減らす必要はなく、むしろより高い所有レベルを認めることも可能だが、個人や組織が企業と相互に資産を利用できないような管理メカニズムを確立する必要がある」とアン氏は述べた。
アン氏は、昨年サイゴン銀行(SCB)で発生した大量引き出し事件や、強固な銀行システムにもかかわらず破綻が生じた米国の事例を想起した。そのため、今回の法案改正では、システミックリスクの防止に関する規制をさらに強化し、インシデント発生時にシステムが現状通りに耐えられるようにする必要があると述べた。
同氏はさらに、急速な発展期を経て銀行業務を「引き締める」ために、一時停止期間を経てこの機関を再開した国もあると付け加えた。

国防安全保障委員会常任委員、チン・スアン・アン氏。写真:ホアン・フォン
犯罪防止専門機関への情報提供については、法案では、管轄の政府機関が信用機関や外国銀行支店に顧客情報の提供を求めることを規定している。
しかし、ハノイ警察のグエン・ハイ・チュン署長は、現実にはハイテク犯罪、賭博、サイバー空間におけるマネーロンダリングは非常に複雑で、深刻な結果をもたらすとも述べた。事件後、警察は直ちに資金の流れを調査し、口座を凍結した。「しかし、現行の規制では、対象者はすぐに非常に迅速に資金を移動させているため、資金回収率は非常に低い」とチュン署長は述べた。
ハノイ警察署長は口座凍結期間の短縮も提案しており、 政府はこの内容に関する詳細な規定を検討することになるかもしれない。
しかし、ホーチミン市のチュオン・チョン・ギア氏は、この規制は、起訴・捜査中の事件に関連する顧客情報の提供のみを義務付けるべきだと述べた。提供される情報は捜査に必要な情報でもある。ギア氏は、これは顧客の権利とプライバシーを保護するためだと述べた。
[広告2]
ソースリンク










































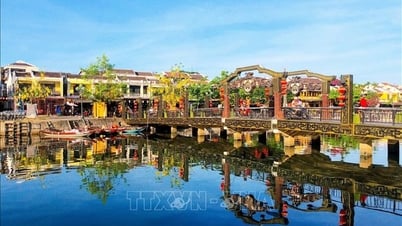



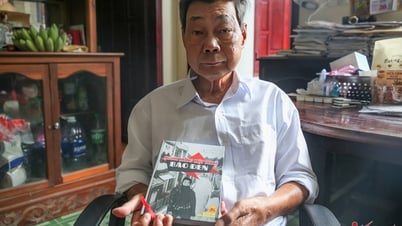





























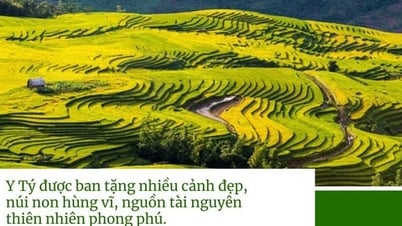
























コメント (0)