
米中間の関税停止決定は、一時的な休戦ではあるものの、多くの国に米国との貿易交渉へのアプローチを再考させるきっかけとなっている。ジャパンタイムズ(japantimes.co.jp)によると、中国の毅然とした姿勢は予想外の結果をもたらし、他の米国パートナー諸国は、不安定な世界貿易環境においてソフト外交が依然として有効であるのかどうか疑問を抱いているという。
中国が1ラウンド「勝利」、他の国々もそれに続くのか?
米中が貿易戦争の休戦に合意してからわずか1週間、中国の強硬姿勢は大きな驚きとなった。中国は依然として米国から平均50%近くの輸入関税(ジュネーブで合意した30%の関税を含む)に直面しているが、ドナルド・トランプ米大統領が中国製品に課していた145%の関税を撤回する意向を示したことは、韓国から欧州に至るまで、これまで関税による報復ではなく、米国政府の交渉要求に従ってきた各国政府を驚かせた。
「これは交渉の力学を変えるだろう」と、元米国貿易交渉官で、現在はシンガポールのISEASユソフ・イシャク研究所の客員上級研究員であるスティーブン・オルソン氏は述べた。「多くの国がジュネーブ協議の結果を見て、トランプ大統領は手札を使いすぎたことに気づき始めたと結論付けるだろう。」
中国が強硬な交渉戦術によって、たとえ一時的とはいえ有利な合意を成立させたという事実は、より迅速な外交アプローチを採用した国々に、その有効性に疑問を抱かせている。当局者は公に強硬姿勢を示すことに消極的だが、大国は以前考えられていた以上に多くのカードを持ち、交渉のペースを緩める余裕があることに気づき始めている兆候がある。
例えば、韓国の大統領選の有力候補である李在明氏は、暫定政権がトランプ政権と「性急に協力した」と批判し、米国との貿易交渉で早期合意に達することを急ぐ必要はないと述べた。
主要パートナーからのシグナル
トランプ大統領は、インドは米国製品に対するすべての関税を撤廃する用意があると述べているが、インドのスブラマニヤム・ジャイシャンカル外相は、交渉が進行中であり「この問題に関する判断は時期尚早だ」と述べ、この主張を否定した。インドのピユーシュ・ゴヤル商務相は協議継続のため米国を訪問すると予想されており、インド政府も譲歩を急いでいないことを示唆している。
BCAリサーチのジオマクロ部門チーフストラテジスト、マルコ・パピック氏は「トランプ大統領と交渉する正しい方法は毅然とした態度で、冷静さを保ち、降伏を迫ることだと中国から多くの国が学べるはずだ」と述べた。

米国の緊密な同盟国である日本でさえ、考え直しの兆しを見せている。首席交渉官である赤沢良生経済再生担当大臣は当初、米国との合意を6月までに実現したいと望んでいたが、国内メディアの最近の報道では、参院選前の7月になる可能性が示唆されている。「交渉に臨む誰もが、『なぜ自分は順番待ちなの?』と自問している」と、ナティクシスのアジア太平洋地域チーフエコノミスト、アリシア・ガルシア・エレロ氏は述べた。「この合意は中国を優先させるものであり、米国にとっても明確なメリットがないため、注視している他の国々にとっては二重に痛いものとなっている」
米国当局者も、協議には時間がかかる可能性を示唆している。スコット・ベセント財務長官は、欧州連合(EU)の結束の欠如が協議を妨げていると述べ、米国とEUの合意成立には「若干の遅れ」が出る可能性があると予測した。
一方、ブリュッセルの当局者は、米中休戦発表に懐疑的であり、これは複数の方面で高関税と制限を維持するための動きだと見ている。彼らは、米国にとっての交渉成果がわずかであり、90日間の猶予期間中に明確な成果が得られなかったことは、トランプ大統領が中国への圧力を強めたいという意欲が限られていることを示していると述べている。
欧州委員会の経済担当トップ、ヴァルディス・ドンブロフキス氏は「貿易環境はより細分化している」とし、「これまでに達した合意では状況が完全には解決されていない」と述べた。
ラテンアメリカでは、発展途上国が中国からの投資と米国市場への輸出アクセスの両方を維持したいと考えているため、指導者たちは慎重な道を歩もうとしている。ブラジルのルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバ大統領は北京を公式訪問し、30以上の協定に署名したが、中国との関係深化が米国の否定的な反応を招くという懸念を否定した。コロンビアのグスタボ・ペトロ大統領も中国の「一帯一路」構想に署名し、コロンビア外相は米国が引き続き重要な同盟国であることを強調した。
米中合意は、トランプ政権も関税による国内経済への打撃から逃れられないことを各国に示す可能性もある。「経済的な打撃は米国の方が深刻で広範囲に及んでいるため、今回の合意はトランプ政権によるその認識を示すものと捉えられるだろう」と、野村ホールディングスのグローバル市場調査責任者、ロバート・サブバラマン氏は述べた。
しかし、シンガポール国立大学の教授で、元世界銀行中国担当局長のバート・ホフマン氏は、強硬な姿勢を取る余裕があるのは経済力があり、米国との貿易依存度が低い国だけだと警告した。「ほとんどの国にとって、米国に対して強硬な姿勢を取ることは非常にリスクが高い」とホフマン教授は述べた。
経済的にレバレッジが低く、経済が米国との貿易に依存している国々にとって、選択肢は限られている。ムーディーズ・アナリティクスのアジア太平洋地域チーフエコノミスト、カトリーナ・エル氏は、大国が反撃したいと考えるなら、その動機付けとなる分野の一つはサービス分野だと述べた。EU、シンガポール、韓国、日本など多くの国が、米国とのサービス貿易で大きな赤字を抱えているからだ。
「中国は米国に対して強硬姿勢を継続する上で大きな影響力を持っているが、他の多くの経済国はそうではない」とエル氏は結論づけた。「私たちが忘れてはならないのは、その影響力と、誰がそれを持っているかだ」
出典: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-trung-dinh-chien-thue-quan-lieu-chien-thiat-cung-ran-se-lan-rong-toan-cau-/20250521080437755








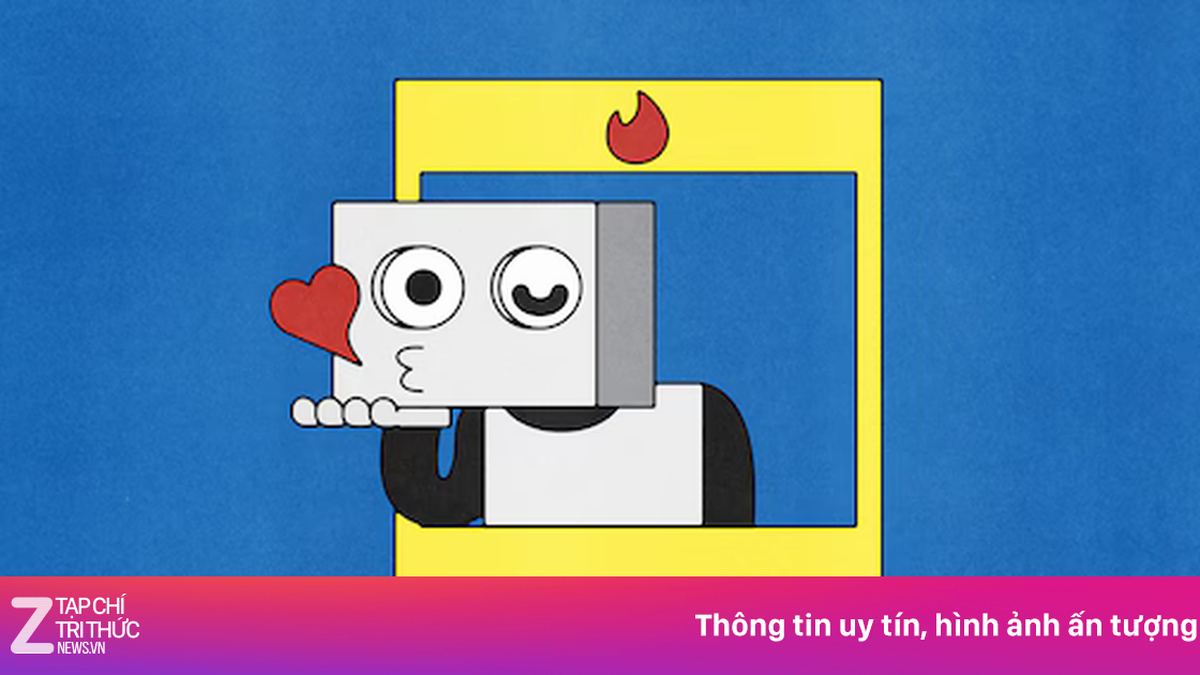
























































































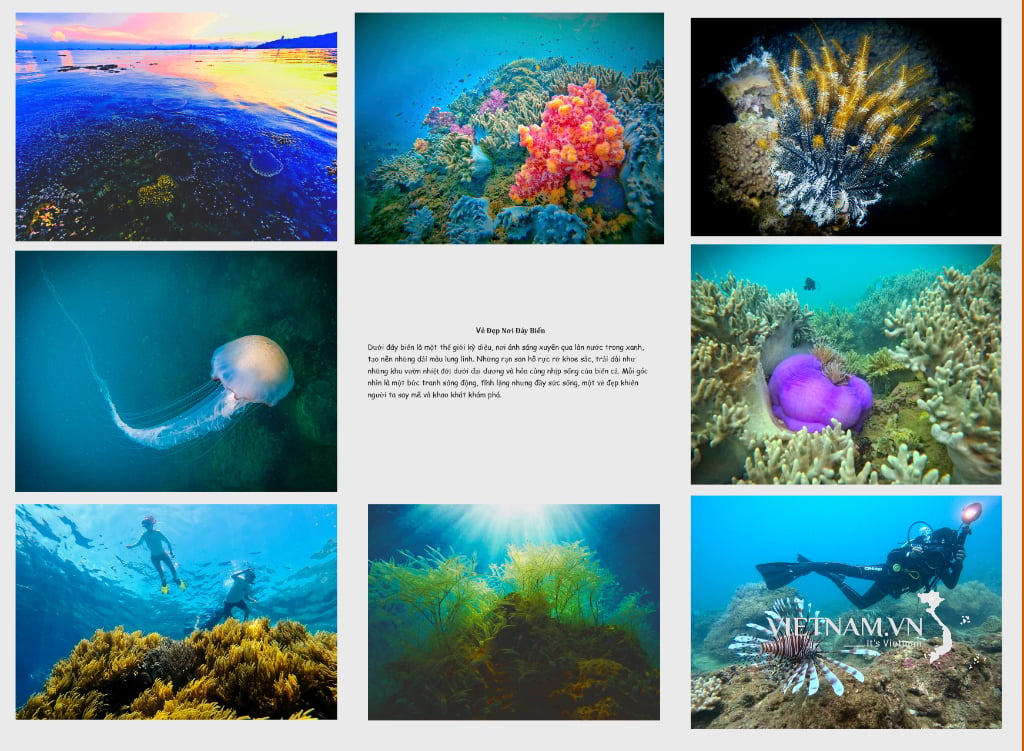



コメント (0)