グローバル化が進む中で、英語力は各国が人材獲得競争において重要な要素の一つとなっています。日本では、 政府はカリキュラム改革、明確な目標設定、試験への多額の投資を通じて、生徒の外国語能力向上に向けた取り組みを強化しています。
文部科学省の最近の調査によると、公立中学・高校の生徒の50%以上が、日本で広く認知されている英検英語能力評価フレームワークに基づく基礎的な英語力を達成していることが明らかになりました。具体的には、中学3年生の52.4%が英検3級以上、高校3年生の51.6%が準2級以上を達成しています。
調査では、これは前向きな兆候であり、英語教育政策の変更が当初は成果を上げていることを示しています。特に、埼玉、福井、福岡といった地域では、基準を満たす生徒の割合が非常に高くなっています。これは、より地域に根ざした柔軟な教育の実施が効果的であることを反映しています。
同様に、中等学校教師の約 46%、高等学校教師の 82% 以上が、英語で専門的に教えることができると期待されるレベルである Pre-1 相当以上の英語能力を達成しています。
しかし、統計には限界もあります。「合格」と評価された生徒の50%以上のうち、実際に英検に合格するのはほんの一部です。残りは教師の主観的な評価によって確認されています。
言うまでもなく、EF英語能力指数2024では、日本は116カ国・地域中92位と、韓国や中国といった多くのアジア諸国に遅れをとっています。この遅れは、英語に対するアプローチが依然として堅苦しく、実用的なスキルを伴う言語学習のトレンドに追いついていないことを反映しています。
根本的な理由の一つは、日本における英語学習が依然として試験のプレッシャーによって制約されていることにあります。子どもたちは、自然な文脈で英語を使うことを奨励されるのではなく、テストのために語彙や文型を暗記することを強いられています。これは学習への関心を低下させるだけでなく、生徒たちが英語をコミュニケーションツールではなく「合格するための科目」と見なすようにもなります。
2021年の調査では、小学生の約3分の1が英語学習を嫌っていることが分かりました。これは2013年と比べて8%増加しています。特に英語のカリキュラムが3年生から拡大されていることを考えると、これは憂慮すべき数字です。
さらに、地域や社会階層間の教育機会の格差も不平等を悪化させています。裕福な家庭の子どもたちは、試験対策コースの受講、補習授業の受講、留学といった機会に恵まれることが多い一方で、公立学校における英語教育の質は、人的資源、財政、施設の制約によって制限されています。
多くの生徒は、海外旅行を経験して初めて英語を本当に楽しめるようになります。これは、現地での語学学習体験に大きなギャップがあることを反映しています。ロールプレイング、演劇、英語スピーキングクラブ、ディベート大会といった体験学習形式は効果的であることが証明されていますが、標準化されたテストに押されて依然として見過ごされがちです。
英語教育団体「東京イングリッシュキッズアドベンチャー」の創設者、ジェイソン・ブール氏は次のように述べています。「没入型の体験は、子どもたちの自信を育み、語彙力を高め、英語を使う際により自然な反応を促します。楽しい学習環境、リアルなコミュニケーション、そして試験のプレッシャーの軽減が、子どもたちの言語への真の情熱を燃え上がらせています。」
出典: https://giaoducthoidai.vn/nhat-ban-no-luc-nang-cao-giao-duc-tieng-anh-post741234.html





![[動画] 殉教者の遺体識別技術の新たな進歩](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/26/ef0db1b91ceb445badc48179e7d272a1)





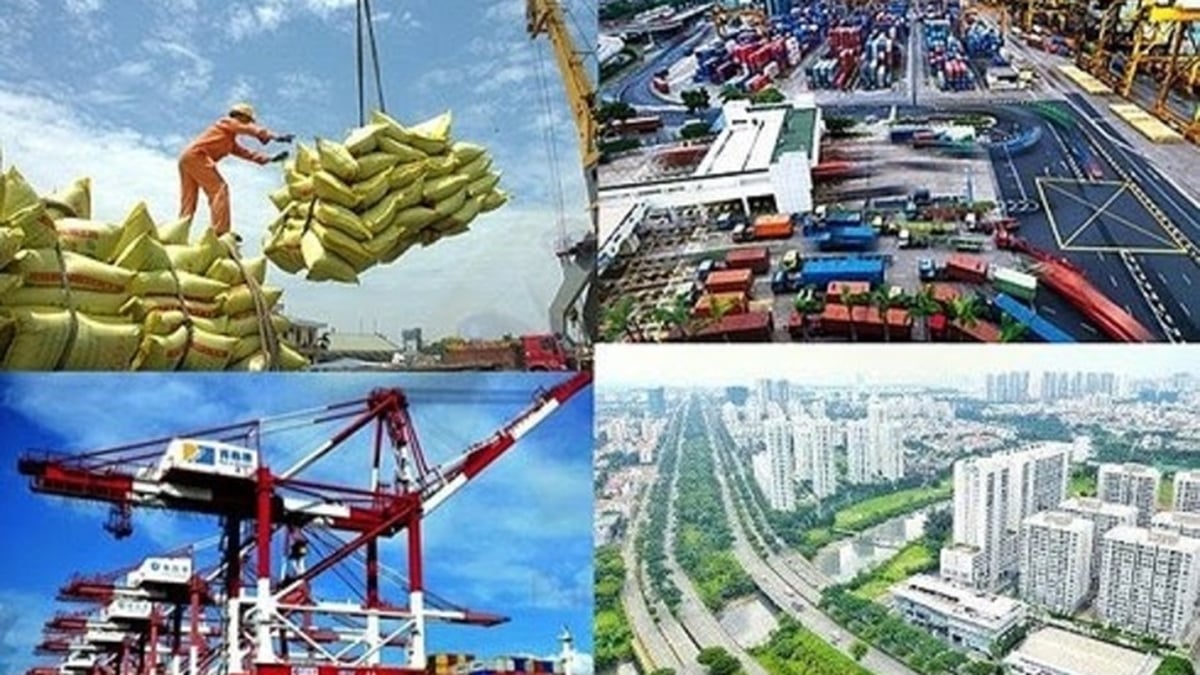















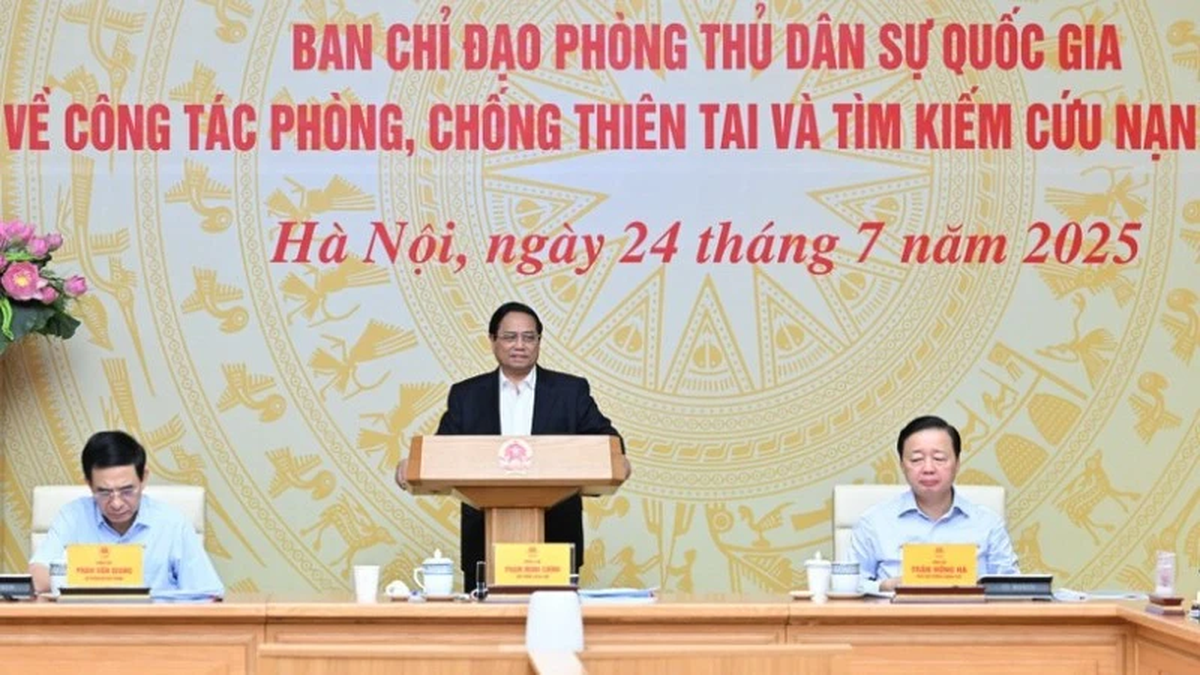

































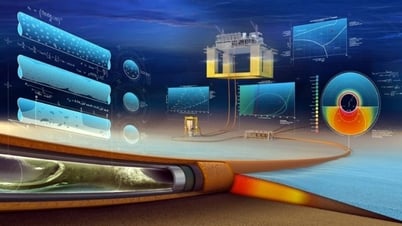

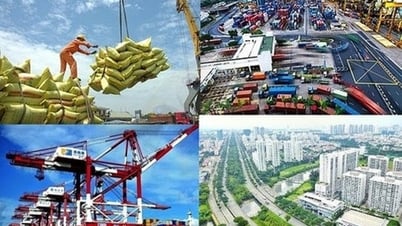
































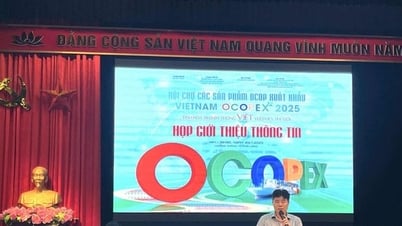






コメント (0)