かつては世界が羨む経済大国だった東京は、中国とドイツの経済が日本を追い越したこと、そして来年にはインドも追い越すのではないかと深く懸念している。
インドが2025年までに米ドル建ての名目国内総生産(GDP)で日本を追い抜くという発表は、東京に衝撃を与えた。ドイチェ・ヴェレ・インターナショナル(ドイツ)によると、東京は2010年まで世界第2位の経済大国だったが、現在では第5位に転落する見込みだ。
国際通貨基金(IMF)は4月下旬に発表した推計で、インドの名目GDPは2025年までに4兆3400億ドル(4兆3000億ユーロ)に達し、日本の4兆3100億ドルを上回ると予測した。インドが世界第4位に躍進したのは、主に円安の影響によるもので、IMFの前回の推計より1年早い。
 |
日本の世界経済における地位の低下は、政府が2023年までに日本がドイツに後れを取ると確認した後に起きた。来年インドが日本を追い抜く可能性があるという衝撃は、急成長を遂げた中国が日本に代わって世界第2位の経済大国の座についた2010年に匹敵する。
「日本にとって、これは大きな懸念事項だが、非常に恥ずかしく、対処が難しいため、公に話す人はほとんどいない」と富士通グローバル・マーケット・インテリジェンス・グループの主任政策エコノミスト、マーティン・シュルツ氏は語った。
経済学者シュルツ氏によると、日本が直面している問題は、安倍晋三氏が2012年に首相に就任し、日本の成長を促進するために「アベノミクス」と呼ばれる大規模な計画を発表した時点で認識されていたという。
そして、政策の「3本の柱」のうち、日本銀行による金融緩和と政府支出による財政刺激策の2本はある程度の成功を収めたが、3本目の柱である構造改革は成功していない。
「アベノミクスの本質は企業の成長促進ですが、生産性向上には構造改革も必要です。しかし、高齢化が進み、デジタル変革に抵抗する国では、それを実現するのは困難です。しかも、長期政権を担う人々は、従来のやり方を好んでいるだけです」とシュルツ氏は述べた。
他の国と同様に、新型コロナウイルス感染症のパンデミックとロシア・ウクライナ紛争は日本経済に依然として目に見える影響を及ぼしているが、他の指標はより深刻な問題を示している。
経済協力開発機構(OECD)は5月2日、世界経済の成長見通しに関する最新の報告書を発表し、日本に新たな圧力をかけた。
OECDは世界経済の成長率を前回の報告書の2.9%から3.1%に引き上げ、米国と中国はともに前回の予測を上回ると予想したが、フランスに拠点を置く同組織は日本の成長率予測を3か月前に予測した1%から0.5%に引き下げた。
日興アセットマネジメント(東京)のグローバルストラテジスト兼最高経営責任者(CEO)のナオミ・フィンク氏は、日本の経済不振の一部は30年にわたる経済成長の停滞に関係している可能性があると述べた。
「米国と日本はどちらも先進国市場であり、GDPに占める中流階級の割合が拡大している中国やインドなどの新興国市場ほどの急速な成長は期待できない。インフラ整備がまだ必要であり、要するに潜在能力がまだ十分に発揮されていないのだ」とフィンク氏は述べた。
フィンク氏は、人口増加はもはや経済成長の主な原動力ではなくなるため、日本の将来の成長の鍵は生産性向上(テクノロジー、人的資本、ビジネスプロセスの改善)への投資となるだろうと述べている。
しかし、日本はインフラ投資や中流階級の急成長という点でインドに追いつくことができず、一方でドイツは主に過去12年間の対ユーロでの円の急激な下落により日本を追い抜いた。
VNA/ティン・トゥック新聞によると
[広告2]
ソース






















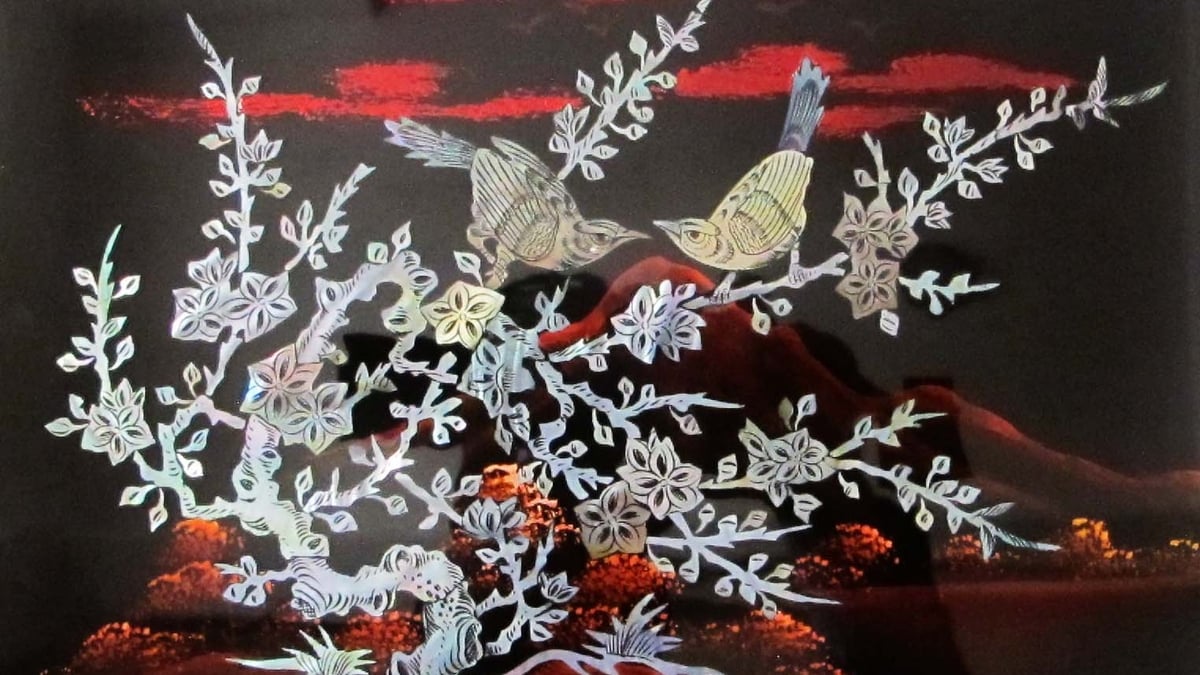








![[写真] ベトナムとセネガルの省庁、支部、地方自治体間の協力協定の調印](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/24/6147c654b0ae4f2793188e982e272651)


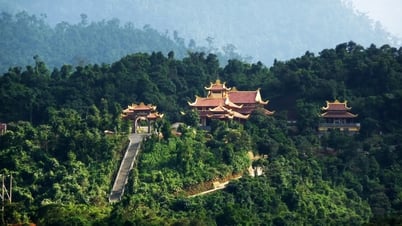

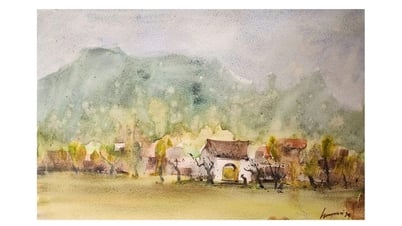







































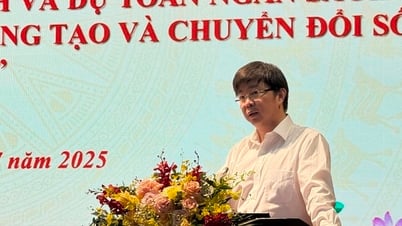

























コメント (0)