写真: アーティストのコンセプト。
科学者たちは、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)を用いて、地球から155光年離れた若い恒星HD 181327を周回するデブリ円盤を観測しました。その結果、結晶状の水氷が明確に存在することが明らかになりました。これは、太陽系の土星の環やカイパーベルト天体で見られる氷に類似した種類の氷です。スピッツァー宇宙望遠鏡は2008年にこの種の氷の存在を示唆していましたが、JWSTは今回初めて、前例のない分光データによってそれを確認しました。
ジョンズ・ホプキンス大学の主任研究者チェン・シー氏によると、発見された氷は通常の水氷ではなく、初期の太陽系における形成条件に類似した条件を反映している可能性のある特殊な結晶構造であるという。宇宙望遠鏡科学研究所の共著者クリスティン・チェン氏は、この発見により、太陽系だけでなく銀河系全体における巨大惑星の形成における水氷の役割について、研究者らがより深く理解できるようになると述べた。
HD 181327は、太陽の46億年と比べてわずか2300万年しか経っていない若い恒星です。この恒星の周囲には、初期のカイパーベルトに似た、非常に活発なデブリ円盤が広がっています。JWSTは、恒星とこの円盤の間に、塵のない大きな空間があることを明らかにしました。この空間では、氷の天体同士の継続的な衝突によって、JWSTが水氷を検出できるほど小さな粒子が放出されています。
データによると、HD 181327系の氷は不均一に分布しており、デブリ円盤の極寒の外側領域で最も濃度が高く(20%以上)、中心部では約8%まで低下し、中心星付近ではほとんど存在しないことが明らかになっています。これは、紫外線による蒸発、あるいは観測されていない小さな惑星に閉じ込められた氷によるものと考えられます。HD 181327は太陽よりも質量が大きく高温ですが、初期の太陽系に存在した可能性のある環境について貴重な知見を提供します。
天文学者たちは、JWST を使用した他のデブリ円盤の継続的な観測により、円盤の遠方領域で氷の高濃度が検出される傾向が、惑星系の形成における普遍的な特徴であるかどうかを判断するのに役立つと期待しています。
この発見は、惑星形成の理論モデルを強化するだけでなく、生命にとって不可欠な要素である水がどのように形成され、分布し、宇宙の生命居住可能な領域に運ばれるのかをより深く理解する希望をもたらします。これにより、この研究は数十億年前に地球上で生命が誕生した条件を明らかにすることに貢献します。
バオ・ゴック(編纂)
出典: https://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/nuoc-da-duoc-tim-thay-trong-mot-he-sao-khac/20250517030443984
















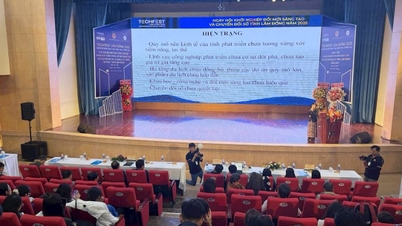



















![[動画] ドンホーの民画制作の工芸が、ユネスコの緊急保護が必要な工芸品リストに登録されました。](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/10/1765350246533_tranh-dong-ho-734-jpg.webp)











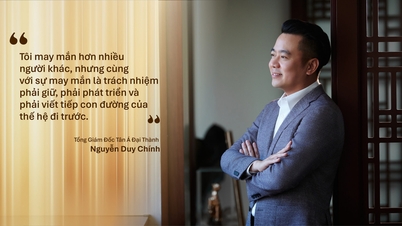



























































コメント (0)