ムスタファ氏とユウ氏は、 経済協力開発機構(OECD)加盟35カ国を対象に定量調査を実施し、研究開発(R&D)支出の1%増加が実質GDP成長の2.83%増加に寄与し、長期的な経済成長におけるイノベーションの極めて重要な役割を実証することを発見しました。
2024年の世界銀行の統計によると、ベトナムでは、GDPに対する研究開発費の比率が2013年の0.3%から2021年には0.43%に増加しました。これは前向きな一歩ですが、先進国の平均(通常はGDPの2%~4%の範囲)と比較するとまだ低いです。
ベトナムは依然として、技術の採用と習得の限界、企業と大学の連携の欠如、世界的な知的資源の有効活用の欠如など、多くの課題に直面しています。
AVSE Global(ベトナム科学専門家機構グローバル)はパリに拠点を置く非営利団体で、ニンビン省人民委員会と共同で「戦略的研究開発投資によるベトナムの未来の促進」をテーマにベトナム研究開発フォーラム2025(ベトナムR&Dフォーラム - VRDF 2025)を開催しています。
このイベントは、持続可能な開発と国家の地位向上の重要な要素である内発的イノベーション能力を強化しながら、知識基盤型経済への移行を促進するための戦略的ステップになると期待されています。
VietNamNetは、ベトナムにおける研究開発戦略について、ハミルトン・マン氏にインタビューを行いました。ハミルトン氏は国際的なテクノロジー専門家であり、現在タレスのグループ副社長を務め、防衛、航空宇宙、サイバーセキュリティの分野で世界をリードする同社において、グローバルなデジタル変革とAIプログラムの共同リーダーを務めています。

R&D は誰のために、何のためにあるのでしょうか?
ハミルトン・マン氏、国家、企業、研究所・学校、国際社会など、R&Dエコシステムの利害関係者間の長期的かつ持続可能な連携メカニズムを確立するための基本要素は何でしょうか?
重要なのは、R&Dで何をするかではなく、より根本的な問いに答えることです。R&Dは誰のために、そして何のために行われるのか?これが最初の基本要素です。R&Dの目的は、内発的な動機ではなく、繋がりの支点として再定義する必要があります。
研究開発は、プラットフォームモデル、つまり多次元での価値創造を可能にする構造として設計される必要があります。このプラットフォームの論理において、あらゆる技術研究開発活動の出発点は、本質的に「イデオロギー的研究開発」です。つまり、イノベーションがなぜ必要なのか、そしてイノベーションは誰に役立つのかを意図的に問うことです。
政府機関、民間企業、学術界、市民社会など、それぞれのグループには、それぞれ独自の優先事項、制約、そして能力があります。目指すのは、均質化ではなく、多様な貢献が全体の軌道を強化し、それぞれが単独で達成できる以上の成果を生み出す環境を創出することです。
しかし、意志と包括性だけでは十分ではありません。第二の根本的な要素は支援メカニズムです。R&Dプラットフォームモデルを発展させるには、関係者が2つの主要な障壁を克服する必要があります。アクセスコスト(情報、資金、インフラ、パートナーなど)と取引コスト(信頼、調整、実装を妨げる法的、技術的、文化的、組織的な障壁など)です。
これらのメカニズムはアクセスを提供するだけでなく、安定性、相互運用性、説明責任も確保します。
つまり、共通の目標と体系的なメカニズムという 2 つの要素が、持続可能な R&D エコシステムを開発するための基盤となります。
ヨーロッパとMITでの経験から、ベトナムが長期的な戦略的パートナーシップを構築するために学ぶことができる典型的なR&D協力モデルはありますか?
欧州とMITはどちらも、模倣を目的としたものではなく、状況に合わせて調整できる原則を導き出すことを目的としたR&Dモデルを提供しており、これは特に、ベトナムのようにイノベーションエコシステムを構築し、グローバルバリューチェーンにおける自国の地位を確立したい国にとって有用です。
フラウンホーファーモデル(ドイツ):フラウンホーファーモデルは、ハイブリッドな資金配分システムが特徴です。約30%は国家予算から、70%は企業との応用研究契約から拠出されます。フラウンホーファーの研究所は、多くの場合、地域の産業クラスターと密接に連携し、明確なミッション指向を持ち、商業化可能なイノベーションに重点を置いています。
ベトナムにとっての教訓は、組織モデルではなく原則、つまり研究能力を産業に貢献するという使命と結び付け、所有権とリスクを共有することです。
EIT および KIC モデル (ヨーロッパ):欧州イノベーション技術研究所 (EIT) と知識イノベーションコミュニティ (KIC) は、気候、健康、交通、デジタル化などの主要な社会的課題をめぐる欧州規模の官民学ネットワークです。
このモデルでは、ローカル実験とシステムレベルの学習の両方が可能になります。
ベトナムはこの論理を適用して、地域における卓越したセンターを構築することができる。これは、デジタルインフラ、スマート農業、気候変動への適応といった国家ミッションを中心としたエコシステムを開発するための基盤としてだけでなく、単独でも実現できる。
MIT 産業連携プログラム (ILP): ILP は、単に企業と教員を結びつけるだけでなく、スタートアップ、スピンオフ、応用ラボなどのグローバル企業と MIT イノベーション エコシステムとの長期的な戦略的関係を構築します。
MITジャミール・ワールド・エデュケーション・ラボ(J-WEL):このプログラムは、途上国の政府、大学、開発基金と連携し、イノベーション能力を単に移転するのではなく、共創することを目指しています。長期的なコミットメントと組織能力の構築に重点を置くという点で、他に類を見ないプログラムです。
教育とデジタル変革への投資に熱心なベトナムは、搾取ではなく構築を目的とした複数年にわたる能力開発プログラムの形で、このモデルから十分に恩恵を受けることができるだろう。
政策はアイデアを「投資可能なシグナル」へと成熟させる
発展途上国に共通するボトルネックの一つは、研究と市場のギャップです。ベトナムにおいて、研究成果の移転と商業化を促進する上で、政策はどのように機能するとお考えですか?
研究と市場のギャップは、しばしば技術力や起業家精神の欠如と誤解されます。しかし、実際には設計上のギャップ、つまり研究エコシステムのモチベーション、能力、そしてタイミングが市場エコシステムと合致していないことが原因です。
ここで公共政策が果たす重要な役割は、資金提供だけでなく、移転が持続可能な規範となり価値を生み出すための条件を設定することです。
公共政策は、次の 3 つの統合レベルで介入する必要があります。
ミッション・フレームワーク:例えば、英国のカタパルト・センターは、政府の資金援助を受け、戦略的産業ミッション(先進製造、エネルギー、細胞医療など)の遂行に取り組んでいます。この政策は成果重視ではなく目標指向であり、企業が「誰のために」そして「何のために」研究開発に取り組むべきかを理解するのを支援します。
プラットフォームの構築 - システムの摩擦を軽減:顕著な例として、フィンランドのVTTが挙げられます。VTTは研究機関であるだけでなく、学術界と産業界を中立的に統合する機関でもあります。VTTは共有ラボを提供し、知的財産の移転やプロジェクトの調整を支援することで、アクセスコストと取引コストを削減しています。
能力構築 - 仲介機関のギャップを埋める:発展途上国における大きなボトルネックの一つは、研究成果をビジネスモデル、プロトタイプ、あるいは法的戦略へと転換できる仲介機関とスキルの不足です。例えばイスラエルでは、イスラエル・イノベーション・オーソリティ(IIA)は研究開発への資金提供だけでなく、技術移転オフィス、アイデア検証プログラム、官民連携インキュベーターなどへの投資も行っています。
ここでの政策は、アイデアを「投資可能なシグナル」に成熟させるのを支援することです。これは、ベトナムが構築する必要がある重要な価値層です。
つまり、公共政策は、資金だけでなく、規範、共有インフラ、インセンティブ、社会的正当性を通じて、科学、市場、社会を結びつける接着剤として設計される必要があるのです。
公共政策は、研究開発のための構造を構築する必要があります。方向性、摩擦の軽減、そして能力の向上です。そうすれば、商業化はもはやボトルネックではなく、国家価値を創造するための戦略的原動力となるでしょう。
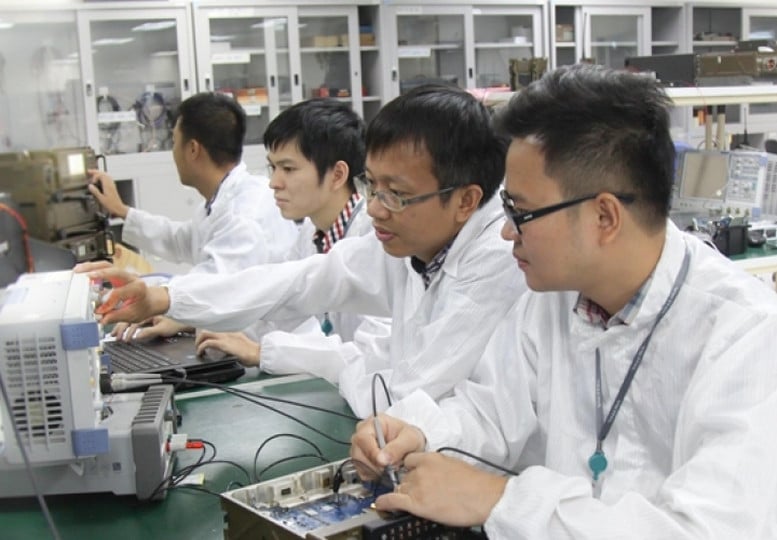
企業が「受け手」ではなく、学習パートナーとなるために
イノベーション・エコシステムにおいて、企業はしばしば「知識の買い手」となります。ベトナムの民間セクターは、どのようにすれば研究開発投資に積極的に参加し、学術セクターの研究成果を活用できるとお考えですか?
まず第一に、「知識購入者」という概念そのものに疑問を呈したい。
企業を「知識の買い手」と見なすのは、イノベーションを取引的に捉える見方、つまり学術界が知識を生み出し、産業界が知識を消費するという見方を反映しています。しかし実際には、イノベーションは単なる知識の移転ではなく、知識と需要の共進化から生まれます。
そのためには、民間部門が研究を吸収するだけでなく、研究が関連性、適用性、拡張性を持つための条件を積極的に整えることが求められます。
ベトナムにおいて、これは企業をイノベーション・エコシステムの「中心」に据えることを意味します。都合の良い時に資金を提供するだけでなく、初期段階から参画し、能力を統合し、イノベーションの道を共同で歩むのです。
デンマークのモデル: GTS先端技術研究所:この研究所は、大学と中小企業(SME)間の応用研究開発の仲介役を務めています。その強みは、特に中規模企業が、自力では開発できない技術プラットフォームに資金を投入することです。企業は単に研究を「購入する」のではなく、共同で課題を特定し、解決策を検証し、イノベーションのリスクを軽減します。
これは、ベトナムの企業が、特にハイテク農業、物流、グリーン製造などの重要な分野における応用研究のニーズを戦略的に収集するための効果的なモデルです。
シンガポールのモデル: A*STAR の技術アクセス イニシアチブ:ここでは、企業、特に中小企業は、政府の支援を受けて優遇価格で研究室や高度な機器を利用できるほか、技術アドバイス、サンプル テスト、トレーニングなども受けられます。研究はもはや「贅沢」ではなく、企業にとって「能力の発射台」となっています。
このモデルでは、民間部門は、学術的な成果が「流れてくる」のを受動的に待つのではなく、実際的な問題、製品開発のニーズ、イノベーションの目標をシステムに持ち込み、応用研究開発プログラムの共同決定者になります。
彼らはもはや「受益者」ではなく、学習パートナー、国の研究開発資産の増幅者であり、研究インフラを長期的な競争力のプラットフォームに変えています。
最も重要な戦略的転換は、考え方にあります。人材の育成、信頼の構築、長期的なビジョンは、知的財産権と同じくらい重要です。
企業は、「製品の収益率」という考え方から、人材、コラボレーション、エコシステムの要素を含む「参加の収益率」へと移行する必要があります。
企業が単なる「知識の買い手」ではなく「知識の創造者」になれば、自社のイノベーションを加速させるだけでなく、国全体の創造力を高めることにもつながります。
* パート2:研究開発投資は「国家使命」と結びつく必要がある
ハミルトン マン氏は国際的なテクノロジー専門家であり、ベストセラー作家でもあります。現在はタレス社のグループ副社長を務め、世界有数の防衛、航空宇宙、サイバーセキュリティ企業のグローバル デジタル変革および AI プログラムを共同で主導しています。
彼はINSEADとHECパリ校の講師であり、パリ工科大学エコール・デ・ポン校で人工知能の博士課程に在籍しています。また、プリシラ・キング・グレイ・センター(MIT)のコンサルタント、およびRetech Center(フランス)のシニアフェローも務めています。
2024年には『Technology Magazine』から「世界トップ10のテクノロジー思想家」に選出され、Thinkers50 Radarに選出されました。また、2025年にはWho Is Who International Awardsから「人類のためのデジタル&AIリーダー」の称号を授与されました。

出典: https://vietnamnet.vn/khi-doanh-nghiep-khong-chi-la-nguoi-mua-ma-la-nguoi-kien-tao-tri-thuc-2426559.html









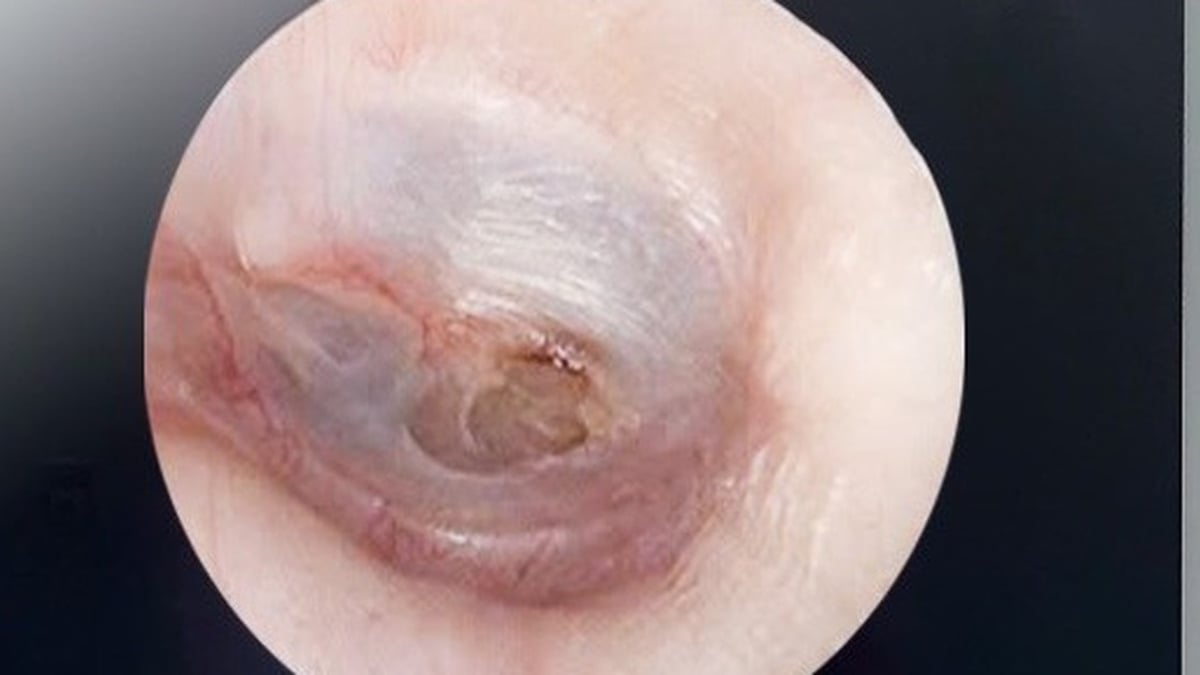
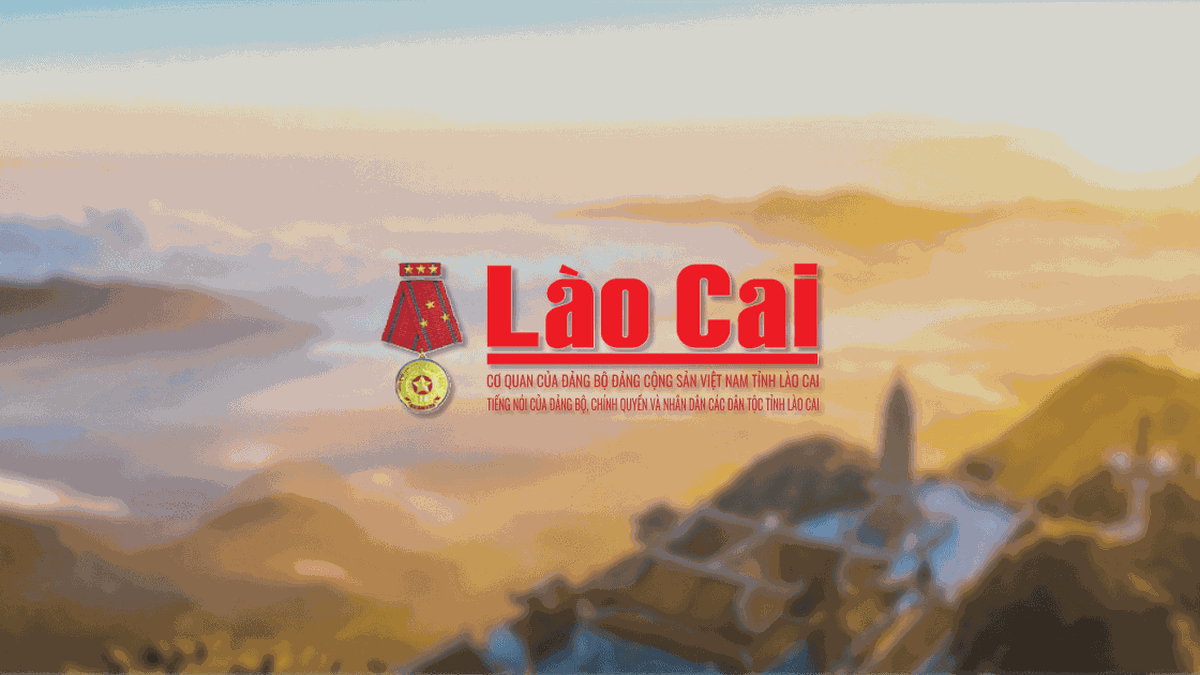










































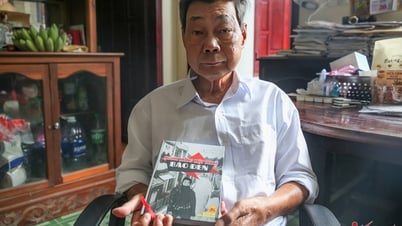


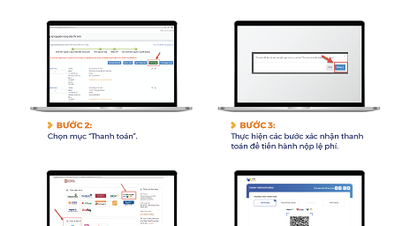






































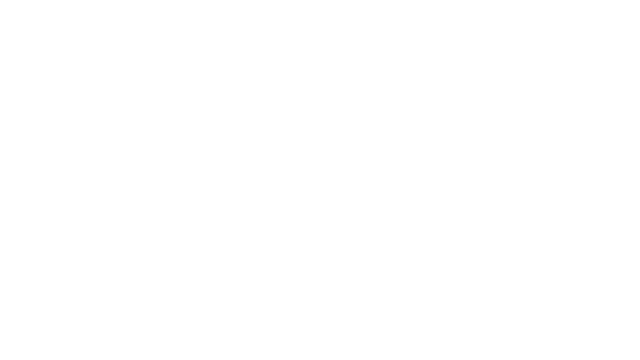

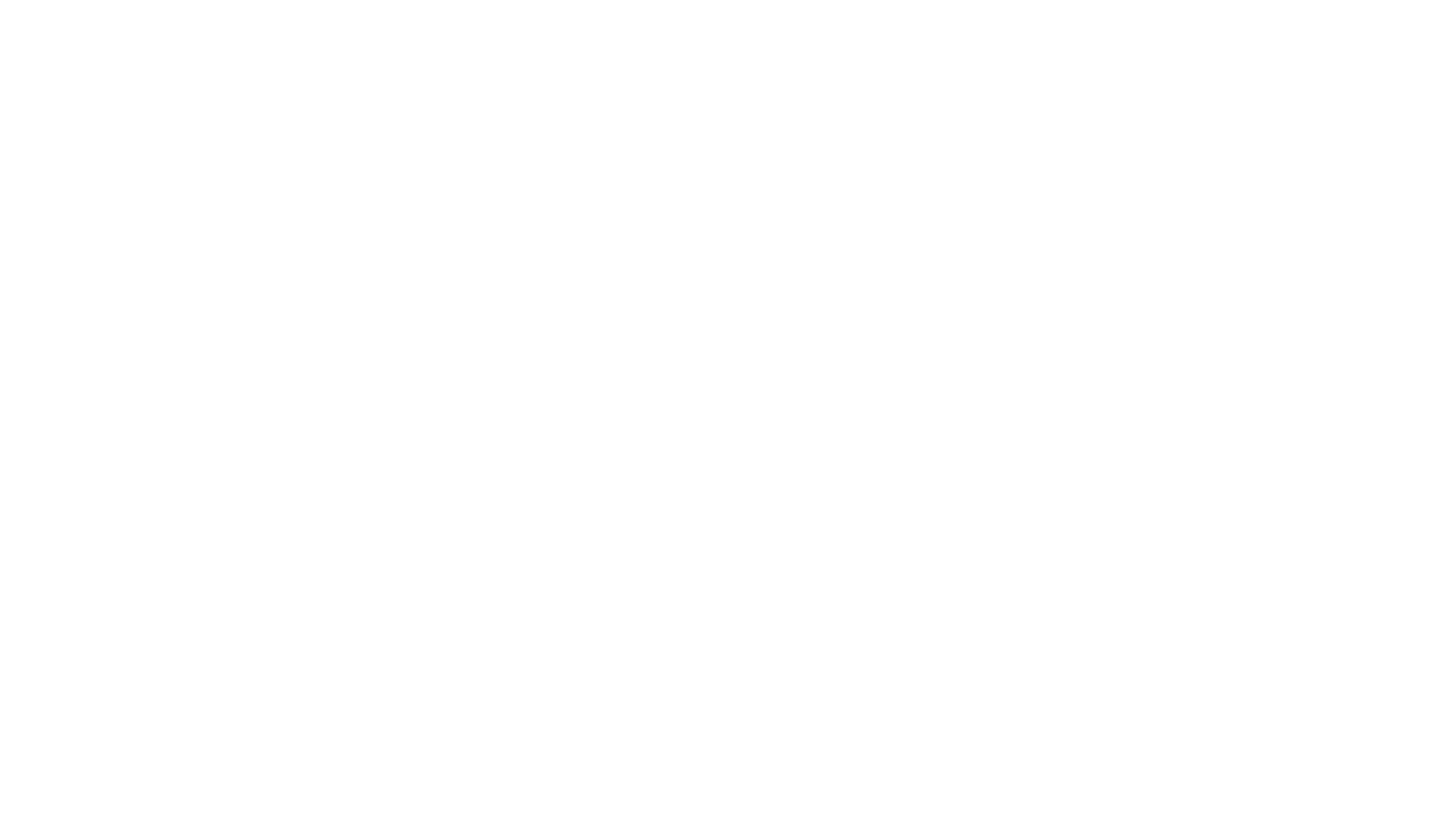
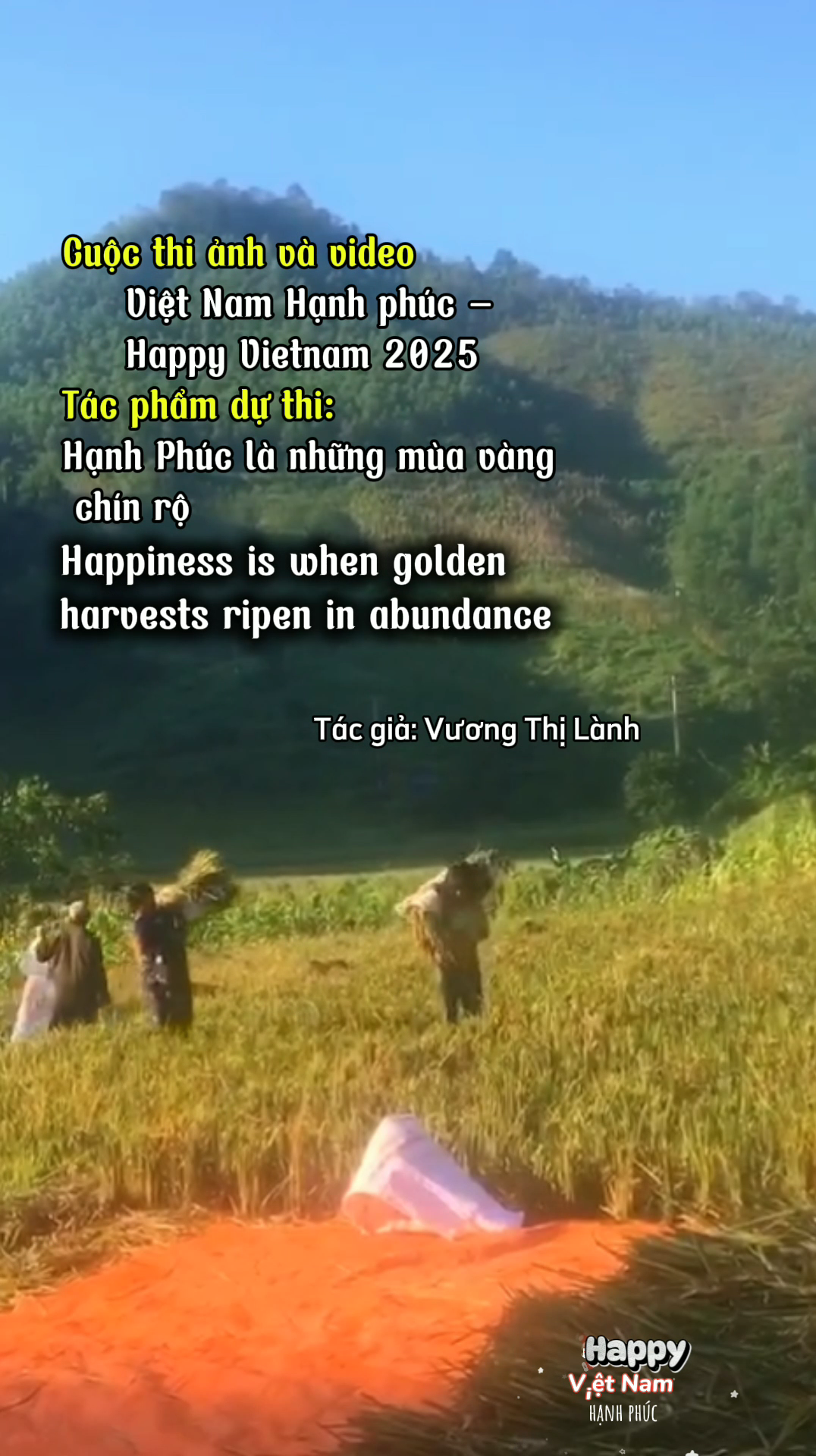
コメント (0)