テクノロジーを悪用し、ユーザーを第二の「機械」に変える
科学技術(S&T)の急速な発展に伴い、AIは世界的な現象となり、人類生活に包括的な影響を与え、各国・地域における科学技術の創造性と応用レベルを測る指標となっています。我が国では、AIの応用範囲がますます広がり、社会生活の様相を一変させています。技術の優位性は誰も否定しませんが、その優れた実用性に加え、社会生活や労働環境には深刻な懸念材料が浮かび上がっています。AIを支援ツールと捉えるどころか、AIに「錯乱状態」に陥り、自らを第二の「機械」と化してしまう人もいます。
 |
| イラスト写真:laodong.vn |
最近のカンファレンスやイベントで、思わず笑ってしまうような場面がいくつかありました。演壇に上がってスピーチをしたにもかかわらず、データを読み間違えたり、定型的な表現で話したり、「機械のように」読み上げたりして、聴衆をうんざりさせてしまった人がいました。原因は技術レベルではなく、依存度にあります。技術に詳しい人なら、こうした状況はAIが作成したものだと容易に見抜くことができます。講演者は怠惰で、依存的で、調査も編集も評価もせず、そのまま読み上げていました。その結果、スピーチは「機械語」のように、定型的で陳腐で、現実離れした内容になり、議論が間違っていたり、論点から逸脱したりしていました。
報道機関やメディア業界でも同様の状況が見られます。AIが作成した記事やメディア製品の中には、検証や評価が欠如しているものもあり、メディア関係者は、初歩的でありながら有害な誤りを絶えず発見し、指摘しています。中には、編集者が「本当に恥ずかしい!」と苦々しく叫ばざるを得ない原稿もあります。AIが作成したものなので、恥ずかしいと思うのは当然です。 政治的な出来事を振り返りながらも、現場の状況を「無関心」に描写し、「ナンセンス」を吐き出し、学生の作文課題のように陳腐で、嘘や下品なお世辞につながる記事も…。
この記事の筆者は、ある地方で党大会に提出する政治報告書の草案に意見を出し合う会議に出席した。それは地方向けの会議だったが、草案には国家レベルの内容と、現実離れした、全く実現不可能な目標が含まれていた。さらに調査を進めると、その報告書はAIによって作成されたことが判明した。AIは機械的に思考する。ユーザーの指示に基づいて結果を生成するが、その結果は往々にして、あらかじめプログラムされた言語の羅列に過ぎない。
AIへの依存を放棄し、AIに過度に依存する状況は、一種の「凍りついた」思考という非常に憂慮すべき事態を露呈しています。党の建設と是正、政治理論の研鑽、決議の徹底的な把握と実行の過程において、このような「凍りついた」思考は非常に有害です。AIに依存すると、主体は考えようとせず、考えるのを怠ります。その結果、報告書、演説、授業計画、文書の草稿といった成果物はすべて「工業製品」と化します。これらは「読むためだけに読む」だけの製品であり、人々の思考、魂、心に浸透する効果は全くありません。
公平を期すならば、学習、読書、研究における怠惰という病はAIの登場以前には現れず、むしろ長きにわたり存在していたと言えるでしょう。中央委員会(第12期)第4決議は、「一部の幹部と党員は政治思想の退廃の兆候を示しており、特に政治理論の学習と研究における怠惰、思考への恐れ、仕事の形式的、粗雑、非効率などが顕著である…」と明確に述べています。こうした状況の原因の一部は、主観的で自己満足に陥り、停滞した精神状態に起因しています。一部の幹部と党員は、学位、学歴、そして昇進の欲求を満たすための肩書きを十分に獲得した後、自己満足的な思考を示し、場合によっては「共産主義の英雄」症候群に陥り、傲慢で自己満足に陥っています。 ト・ラム書記長は「生涯学習」の記事の中で次のように指摘している。「多くの幹部、公務員、公務員は学校で学んだ知識に満足し、学位を追い求め、定期的に研究や勉強をして自分の資質を向上させることを望まない。それが保守化につながり、科学技術時代の速いペースの生活に適応できていない。」
AI技術の爆発的な発展という文脈において、既に学ぶのも読むのも研究するのも怠惰な官僚がAIを濫用すれば、その危険性は何倍にも増大するだろう。若い官僚にとって、思考に確固とした理論的根拠がなく、イデオロギーに強い政治的意志を持たず、技術を濫用すれば、彼らはただ第二の「機械」と化すだけであり、それ以上でもそれ以下でもない。
テクノロジーは単なる道具に過ぎません。どれほど力強く発展し、どれほど高いレベルに到達しようとも、それは永遠に単なる道具に過ぎません。人間の脳の思考に取って代わることは決してできず、人間の魂や心の感情を担うことも決してできません。しかし、怠惰で既成概念にとらわれた生活を送る多くの人々は、AIを「神格化」し、あらゆる課題を解決する「魔法の杖」と見なしています。公に露呈した誤りは、誰もが目にするごく小さな例に過ぎません。隠れた誤り、特に思考の衰退、魂の喪失、仕事の遂行と管理における無関心といった状態は、静かに進行し、世論が「名指しして非難」することを非常に困難にしています。そして、これは一種のイデオロギー的退廃の表れです。なぜなら、幹部や党員の政治的・道徳的資質を形成する基盤は、決して「プログラム」されたものではなく、定期的かつ継続的な学習、訓練、そして研鑽のプロセスを必要とするからです。思考が「凍結」されれば、官僚はテクノロジーの言語を繰り返すだけの「拡声器」と化してしまうことは容易に想像できる。国民は官僚の能力に失望するだけでなく、官僚の実生活への献身と責任にも信頼を失っているのだ…
テクノロジーに問題があるのではなく、ユーザーに問題がある
テクノロジーは不況の原因ではないが、それを通じて一部の幹部や党員の能力と思考力の弱点を露呈させている。したがって、現在の「デジタルリテラシー」の環境においては、AIはあくまでツールであり、決定権は人間にあることを明確に認識し、区別する必要がある。
テクノロジーを救世主とみなせば、私たちは危険な罠に陥り、創造性は固定観念に、主体性は受動性に取って代わられてしまうでしょう。あらゆるレベルの政治体制における指導、行政、管理…特に党の建設と改革の活動において、AIの濫用は明白な結果をもたらすでしょう。そうなれば、文書や報告書は味気なく陳腐なものとなり、現実の息吹を反映できなくなります。役人の発言は魂を失って信頼を得られず、世論の反発さえ招くでしょう。批判的思考力と創造的思考力――リーダーシップとマネジメントの中核的要件――は日々蝕まれていくのです。
第4期中央委員会(第12期)決議において、我が党は次のように警告しました。「一部の幹部と党員の政治思想、倫理、そして生活様式の劣化を阻止しなければ、予測不可能な危険を伴う「自己進化」と「自己変革」につながるだろう…明らかに、テクノロジーへの依存は悪習慣であるだけでなく、より深刻な劣化への「入り口」となる可能性を秘めている。この状況が広がれば、「思考のテクノロジー化」のリスクに直面することになるだろう。仕事は、人間の知性、洞察力、勇気、そして感情ではなく、魂のない機械のコピーによって解決されるようになるだろう。これは、ト・ラム書記長が2025年から2030年までの党大会を指導する中で強調した「文書は実践から、社会生活の息吹から、活力を持たなければならない」という精神に反する。
実践が証明しているように、テクノロジーは知性、能力、勇気、そして責任感を持った人々によって活用される場合にのみ、その価値を発揮します。逆に、役人が怠惰になり、すべてをアシスタントに「アウトソーシング」し、アシスタントがテクノロジーに頼るようになると、「教師」も「生徒」も自立した思考力を失ってしまいます。
デジタル時代において、テクノロジーの活用は避けられない流れです。しかし、リーダーシップ、マネジメント、そしてイノベーションという中心的な役割において、いかなるテクノロジーも人間に取って代わることはできません。テクノロジーに依存し、思考を軽視することは、我が党が警告してきた衰退の兆候です。
ル・ンガン
 |
出典: https://www.qdnd.vn/phong-chong-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/su-nguy-hai-cua-lam-dung-cong-nghe-coi-nhe-tu-duy-bai-1-bieu-hien-moi-cua-suy-thoai-tu-tuong-842326
































![[写真] 政治局はランソン省とバクニン省の党委員会常務委員会と協力する](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/20/0666629afb39421d8e1bd8922a0537e6)



















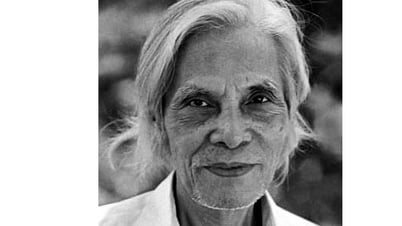





















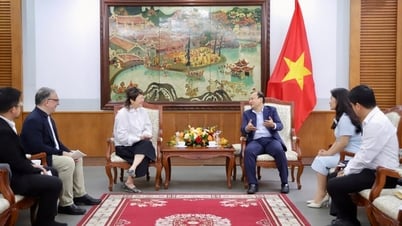






























コメント (0)