( クアンガイ新聞) - 小学4年生の夏、祖父が川の埠頭から私と同じくらいの年頃の、肌の黒い女の子を連れて帰ってきたのを今でも覚えています。祖母は「おじいちゃん、この子はどこから来たの?」と尋ねました。「埠頭から来たのよ、私が連れ帰ったの」祖父は驚いて声を落としました。「後で教えてあげるから、さあ、何か食べさせてあげなさい!」
 |
| MH: VO VAN |
祖母は台所に駆け込み、しばらくして冷めたご飯と煮魚の入った椀を持って戻ってきました。少女はご飯を椀に取り、美味しそうに食べました。その時、祖父が手を振って祖母を台所に呼び寄せ、ささやきました。その言葉が聞こえました。隣村の孤児だったその少女が、私の村に迷い込んできたのです。朝早くから川岸に行き、誰に頼まれても何でもして、廃墟となった草葺き小屋で寝泊まりしていました。祖父は彼女を哀れに思い、家に連れて帰りました。事情を話した後、祖父は祖母を慰めました。「我が家は裕福ではないけれど、可哀想だよ!」祖母はため息をこらえ、裏庭のポーチでシダを刈り始めました。それを見た少女は、祖母の手から包丁を取りました。「任せて!」不器用な見た目とは対照的に、優しく可愛らしい声でした。祖母は、彼女が野菜を切るのを見守るように座っていました。手は素早く動き、額のしわは緩んでいました。祖父は愛情を込めて彼女に言いました。「任せなさい。カムと遊んできて!」私はすぐに立ち上がり、少し憤りと傷を感じながら家の中に入りました。祖父母が愛していた唯一の孫娘が、今や別の孫娘に取って代わられてしまったのです。それを見た祖父は家に入り、私を慰めてくれました。「彼女は孤児で、苦しんでいるんだ。愛してあげなさい!」そう言うと、祖父は私を庭に連れ出し、彼女のところへ行きました。小さな女の子は浮き草を刈り終えると、今度は少し怯えた表情で立ち上がり、それからかがみ込み、苔むしたレンガの庭に足の親指を動かしました。祖母は振り返って尋ねました。「ええ、でもあなたの名前は?」「はい、シー」と女の子は優しく答えました。祖父はくすくす笑い、彼女の乱れた頭を撫でました。「これからあなたが私たちのところに戻ってくる時は、あなたの名前はナンよ」彼は私の方を向いて言った。「そしてこちらはサム・カム。孫娘には鳥の名前しか付けられないんだ」。ここで彼はまたくすくす笑った。「どうしてナンって呼ぶの?」と私は不思議に思った。「ああ…今日の午後、砂州にいた時に、白いアジサシが川から飛んできて、乾いた枝を口にくわえて川辺の小石に止まるのを見ました。その時、アジサシは薪の束を持って通り過ぎていきました」と彼は考え込むような顔で言った。
彼の目に同情の色が浮かび、祖母も感情を隠すように顔を背け、私に食事の配膳を促した。盆に椀と箸を並べ、振り返ると、ナンが藁にもたれかかり、シャツの裾をいじりながら、畑の方を向いていた。可哀想に思い、「ナン、箸を比べてみて!」と声をかけた。するとナンはようやく座り、箸を比べ始めた。食事の間、彼女は祖母の隣に座り、静かに食べていた。午後のご飯でまだお腹がいっぱいのようだった。食べている間、私はナンの姿をより鮮明に見ていた。汚れた顔に輝く瞳、口の端に愛らしいご飯粒が深くくっついている。着ている服は酸っぱい匂いがしていた。食事を終えると、彼女は急いで盆を水瓶に運び、体を洗った。まるで自分の立場を自覚しているかのようだった。日が暮れる頃、私は彼女に服を渡し、井戸で水浴びをするように誘った。お風呂上がりの彼女は服を着て、それをじっと見つめていました。レースの襟を下ろして眺め、胸元のリボンを撫でながら「なんて素敵な服なの、あなたがくれたのね!」と呟いていました。お風呂に入って他の服に着替えた後、彼女はずっと明るくなったように見えました。その夜、彼女は祖母と私と一緒に寝ました。私は真ん中に横になり、祖母を抱きしめました。「自分が 祖母であり、養子縁組された孫であることを確認」するためです。私は眠りに落ちましたが、真夜中にハッと目が覚めると、祖母はまだ寝返りを打っていました。朝、目が覚めると、台所で忙しそうに料理を手伝っていました。手を伸ばすと、枕が濡れていて、昨夜泣いていたことが分かりました。
夏休みの間、ナンはいつも私のそばにいました。街へ帰る準備をしていた日、祖父も急いで自転車で学校へ行き、ナンに勉強を頼みました。ナンはまだ綴りも分からなかったので、一年生から勉強し直しました。その夜、私はナンと一晩中話し、祖母は明日のバスに乗る体力をつけるために早く寝るようにと私に促しました。
ナンは高速道路まで彼を追いかけ、いつものバスに乗せて家まで送ってくれました。その日は空が澄み渡り、道の両側には野の花が散っていました。振り返ると、ナンの目に涙が溢れていました。彼は私がバスに乗り込み、姿を消すまでずっと私の手を握ってくれました。
* * *
ニャンが祖父母の家に来てから、一体何夏が過ぎたのか、もう思い出せない。中学生になると、実家に帰る回数は徐々に減っていった。私が帰ってくると聞くと、ニャンは村の入り口まで迎えに来てくれた。ニャンは私を後ろに乗せ、鉄の水牛のように重い自転車の上で揺らしながら、二人で軽妙な会話を交わした。
祖父の庭はますます緑が豊かになり、池のアヒルは皆ふっくらとしています。放課後、ニャンは一日中庭で野菜の列を一つ一つ手入れしています。祖父はもう機敏に動けなくなっていて、家の隅に座り、ぼんやりとした目で外を眺めています。私が帰宅するのを見ると、よく「ニャンを街に連れて行って、一緒に学校に行かせて」とささやきます。私がそう言うたびに、ニャンは目に涙を浮かべて微笑みます。「もうすっかり老衰しちゃったんだね。かわいそうに!」
祖父母はだんだん弱っていき、ニャンは家事全般を引き受けました。ニャンは高校に進学し、母は白いアオザイを作ってニャンに送りました。私は大学に進学し、アオザイを着ることはなくなり、それもニャンに持って帰りました。思春期に入ると、ニャンはすっかり変わりました。彼女の顔は優雅で魅力的になり、いつも太陽を浴びていましたが、肌は相変わらず白く滑らかでした。ニャンはアオザイを着たまま優雅にバッグを抱えて学校へ行き、村の男の子たちは彼女をチラチラと見ていました。故郷に帰るたびに、夜ニャンの隣に寝て、学校でのボーイフレンドの話をささやきました。ニャンは注意深く聞いてくれて、どんな恋をしても勉強に集中しなければいけないと言いました。私が何度もボーイフレンドのことを尋ねると、ニャンは首を横に振って「ない」と言いました。私がもう一度、ニャンに密かに好きな人がいるかどうか尋ねると、ニャンも首を横に振りました。私は困惑していました。ナンは美しく、毎日午後になると隣村の少年たちが私の村にやって来ては、こっそりナンを慕うのです。「ナン、君の心はなんて冷たいんだ!」と冗談を言ったら、ナンは笑って、遅くなる前に寝るように促しました。
大学卒業後、私は働きに出ました。ニャンも高校を卒業しましたが、大学受験を拒否しました。ニャンは毎日庭に出て、野菜畑や池のアヒルの世話をしていました。故郷に帰るたびに、ニャンの姿に驚嘆しました。ニャンはますます美しく魅力的になっていきました。祖母はニャンに何度も結婚を勧めましたが、ニャンはただ笑うだけでした。田舎のニャンと同じ年頃の女の子たちは、すでに赤ちゃんを腕に抱いていました。
…午後、仕事から帰宅すると、母が忙しく荷造りをしているのが見えました。母は顔を上げて私を見ると、「明日は休みを取って、実家に帰って両親とニャンの結婚について話し合って。おじいちゃんから連絡があったのよ」と促しました。「ニャンが結婚するの?」と私は驚きました。「ええ、それしか知りません」。家族全員が実家に帰ったのは、もう午後になっていました。祖母が路地裏から出てきて、両親の手を引いて家の中に引き入れてくれました。祖母はひどく動揺していました。「見てごらん、この村で一番美しい娘よ。毎晩、村の男たちが路地裏に列をなしているのに、彼女のことが好きじゃないのよ。今、ランと結婚しようと決めているのよ」。「お母さん、ランって誰のこと?」と父が尋ねました。「ランは家の裏に住んでいて、奥さんは5歳の娘を残して亡くなったのよ」その時になってようやく母はナンの肩に腕を回し、骨ばった背中を撫でた。「ランを愛しているのね。夫婦は運命よ、よくそう言うじゃない?」。「でも…ランの家はすごく貧しいから、ナンが将来苦しむんじゃないかと思う」。祖母はまだ落ち着きがなかった。
庭へ出てナンを探し、しばらくするとナンが池から出ようともがいていて、ズボンが膝までめくれ上がっているのが見えました。私を見ると、ナンは明るく微笑んで言いました。「今帰ってきたの?ちょっと待って、アヒルたちを囲いの中へ連れて行くわ!」 足早に去っていくナンの姿、柔らかな姿、優しく穏やかな表情を見て、私は密かに、ナンを飼っている男性のことを嬉しく思いました。
ニャンの結婚式は簡素で、両家の家族に数枚の料理が並べられただけだった。ニャンの希望通りだった。シンプルなピンクのアオザイをまとったニャンは、相変わらず驚くほど美しく、村の少年たちは惜しそうに顔を背けた。ニャンは夫の隣を歩き、明るく幸せそうな顔をしていた。小さな女の子は走り回り、時折立ち止まってニャンの手を握り、意味不明なことをささやいた。ニャンは優しく微笑んだ。「ママは知ってるよ!」
家族全員が街に戻った日、ナンと彼女の夫は私たちを幹線道路までずっと連れて行ってくれました。ナンの夫は田舎から母に届けるお土産を梱包するのに忙しく、時折ナンを見上げて愛情を込めて「手伝おう!」と声をかけていました。ナンは夫のところに舞い降りて、ささやくように言いました。
祖父母も家族全員を村の入り口まで連れて行ってくれました。夫が父と話をできるように、ナンは祖父を支えるために歩みを緩めました。祖父はすっかり歩みが遅くなり、見ているのが痛ましいほどでした。ナンは母の方を向いてささやきました。「夫と私は祖父母と一緒に暮らすことになるから、心配しないで!」母の目には感動が浮かんでいました。母はナンの手をしっかりと握りしめていました。
村の道の突き当たりで、祖父は突然立ち止まり、涙ぐんだ目で川を見上げた。朝日の中、シロアジサシの群れが川岸から戻って来た。細い翼を傾け、川面を旋回しながら、そして突然飛び去っていった。祖父は長い間耳を澄ませ、それから彼女の手を握り、さらに引き寄せた。「何か聞こえるかい?」彼女は困惑したように首を振った。「川がささやいているのよ…」祖父が何を言ったのかは分からなかった。ただ、彼女がくすくす笑いながら、雲間へと消えていく最後の鳥をキラキラと輝く目で見上げているのが見えただけだった。
ヴー・ニョック・ジャオ
関連ニュース:
ソース
















































































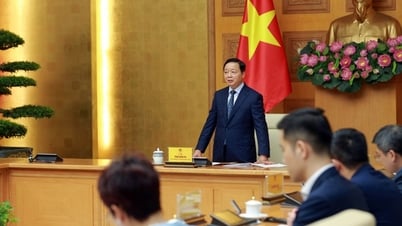
















コメント (0)