日本は2月14日、戦略米備蓄の米を放出することを決定した。スーパーマーケットなどの小売店での価格引き下げを目的とした国家備蓄米の放出は今回が初めてである。この前例のない介入の背景には、食糧危機を防ぐことを目的とした30年前の備蓄政策がある。
食糧危機に対処するための米の備蓄
2月14日、江藤拓農林水産大臣は、価格高騰の中、主要農産物である米の円滑な流通を確保するため、政府が備蓄している21万トンの米を活用すると述べた。
同省によると、米は昨年収穫分を中心に配布し、23年収穫分も少量配布するという。
日本政府はまた、価格暴落を避けるため政府が1年以内に同量の米を買い戻すという条件で、備蓄米を農業協同組合や他の卸売業者に販売する計画だ。
 |
| 2月14日、東京の米屋にて。写真:ル・フィガロ |
この前例のない介入の背後には、食糧危機を防ぐために設計された30年前の貯蔵政策がある。
備蓄政策は1993年に始まりました。当時、日本は深刻な凶作に見舞われ、政府は大量の外国産米を輸入せざるを得ませんでした。国産米の品質に常にこだわってきた日本人にとって、こうした輸入は大きな衝撃となりました。
それ以来、東京都は約100万トンの米備蓄を維持しており、これは国内消費量の10%に相当する。これまで、この備蓄は自然災害や農業生産量の急激な減少があった場合にのみ放出されてきた。しかし、米価高騰への対策として備蓄米が活用されるのは今回が初めてである。
米の消費量は減少しているが、価格は依然として上昇している
現在の米価格高騰には、いくつかの要因が考えられます。2024年夏の記録的な猛暑が米の収穫に影響し、供給量が減少しました。
この状況は、2024年8月に巨大地震が発生するとの警告を受けて消費量が増加し、特にパニック買いによってさらに悪化しました。その結果、2024年12月の米の価格は前年同期比で64.5%上昇しました。
政府の調査によると、1年前は5キロ入り米1袋が2,023円(約33万7,000ドン)で販売されていたが、現在は3,688円(61万5,000ドン)となっている。
一時は、日本への観光客が価格上昇の原因だと非難されましたが、実際には、彼らの消費量は総消費量のわずか0.5%に過ぎません。米価格危機における最も懸念される要素の一つは、依然として流通業者の役割です。農林水産省は、卸売業者と農家がさらなる価格上昇を見越して米を買いだめしているのではないかと疑っています。
政府は需要を刺激し、市場を安心させ、価格の急落を防ぐため、販売された量を相殺するために21万トンの米を買い戻す方針を示した。
しかし、この決定は転換点となる。自国生産米のほぼ100%を消費する日本は、長年にわたり生産者の保護を最優先に考えてきた。1970年代以降、歴代政府は農家の価格を高く維持するため、特定の水田の休耕に補助金を出してきた。例えば、近年では水田の40%が消失し、生産者は生産停止のための金銭的インセンティブを受け取っている。
皮肉なことに、この危機は数十年にわたる米消費量の減少の中で発生しています。1962年には日本人の平均年間消費量は118kgでしたが、2022年には51kgにまで減少しました。しかし、米は依然として日本の文化と経済の中心であり続けています。米の生産は依然として輸入障壁によって保護されており、国内価格はタイ米やベトナム米よりもはるかに高い水準に留まっています。
2月14日に戦略備蓄米の放出が決定されたことで、日本は農業政策を見直すべきかどうかという疑問が浮上する。一部の専門家は、食料安全保障を支えるために日本政府は価格の下落を抑制する必要があると指摘している。
NGOC MINH (ラ・トリビューン紙による)
* 関連ニュースや記事をご覧になるには、国際セクションをご覧ください。
[広告2]
出典: https://baodaknong.vn/vi-sao-nhat-ban-co-luong-gao-du-tru-khong-lo-242968.html








































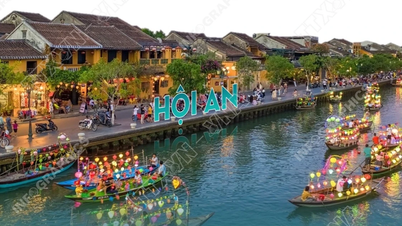

























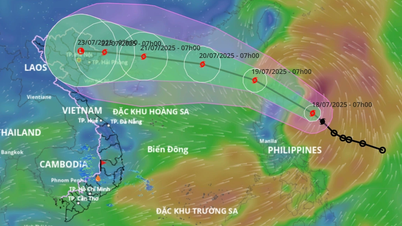



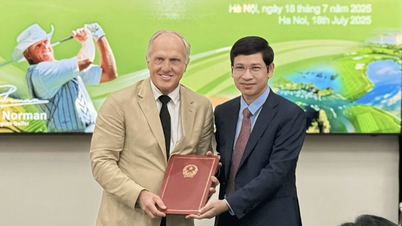



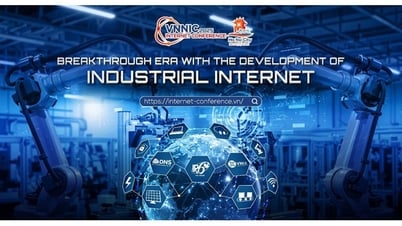




















![[インフォグラフィック] 2025年には47の製品が国家OCOPを達成する](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)







コメント (0)