合理化され、効果的かつ効率的な組織革命を実行するためには、政府組織法を含む国家機構組織に関するいくつかの法律を改正する必要がある。
この法律を改正することは必要ですが、問題は、短期間で再び改正しなければならないような事態を避け、改正された規定が現実に適合し、長期的に活力を持つようにどのように改正するかということです。
そうした精神で、今回の政府組織法(GOO)の改正に当たっては、5つの問題点を提起する必要があると私は考えます。
まず、政府の立場についてでございます。
実際、政府の立場は2013年憲法に規定されているため、政府の正しい立場を再規定する必要がある場合、それは憲法と関連することになる。今回の法律改正草案は、政府が最高行政機関であり、行政権を行使し、国会の執行機関であるという規定において、2013年憲法の条項を踏襲しており、この点は考慮すべき点である。
我が国の憲法は政府の立場をどのように規制しているのでしょうか?
1946年憲法は、ベトナム民主共和国政府が国全体の最高行政機関であると規定していましたが、政府が人民議会の執行機関であるとは規定していませんでした。1959年憲法では、政府評議会が最高国家権力機関の執行機関であり、ベトナム民主共和国の最高国家行政機関であると初めて規定され、根本的な変更が行われました。1980年、1992年、そして2013年の憲法は、引き続き政府が国会の執行機関であるという立場を定めています。
1980年憲法の制定当時、故ファム・ヴァン・ドン首相が、憲法改正案を議論する政府会議において、閣僚評議会(当時の概念では政府)に言及する部分について、閣僚評議会が国会の執行機関であるという規定は標準的ではないため、正確な内容に書き直す必要があると述べたことを、今でも覚えています。残念ながら、それは実現しませんでした。

2月5日の政府定例会議。写真:ナット・バック
これは、政府の機能と政府の地位の間に根本的な混同があるためです。我が国の政府は、世界の他の国々の政府と同様に、立法府、行政府、司法府という国家権力の三権分立によって構成されています。立法府が制定した法律は執行され、遵守されなければなりません。法執行と法執行は行政府の機能ですが、行政府の法執行機能から、政府が立法府の行政府であるという判断に至るまで、機能と地位が混同されています。
さらに、形式的な考え方として、なぜ最高人民法院と最高人民検察院は国会の執行機関として位置付けられていないのでしょうか。政府、最高人民法院、最高人民検察院の人事は国会によって選出または承認されるものの、これら3機関は憲法上の機関であることを明確に確認する必要があります。
政府の地位についてこのような規定を設けている国はあるでしょうか?ベトナムと政治体制に多くの類似点を持つ中国でさえ、そのような規定はありません。中国憲法は、中華人民共和国国務院(中央人民政府とも呼ばれる)を国家の最高行政機関と定めています。
第二に、政府の組織と運営の原則について
これは重要な内容の一つであり、正しく決定されれば、政府の効率的な運営を確保するための基礎となるでしょう。
TCCP法と地方自治組織法の二つの草案は、いずれも地方分権、権限委譲、権限付与といった問題を規定している。これらの問題が適切に規定されれば、制度上の大きなボトルネックは確実に克服されるだろう。
政府の組織と運営の原則は明確で、一般的なものではなく、特に達成すべき目標の方向性を規制するような、つまり真の原則とならないようなものを避けることが求められます。例えば、近代性、有効性、効率性を重視した国家統治の実施、統一性、円滑性、継続性、民主性、法の支配、専門性、近代性、科学的性、透明性、公共性、透明性、規律性を備えた行政規律の構築、国民と企業にとって好ましい環境の創出などが挙げられます。
もう一つの課題は、政府、首相、そして大臣間の責任と関係性です。この内容を規定する原則は何でしょうか?政府、首相、大臣、省庁レベルの機関の長の間の任務、権限、責任、そして省庁と省庁レベルの機関の間の管理機能と範囲を明確に定義するという考え方を踏まえると、政府の組織と運営の原則として首長の個人的責任を推進することも、更なる検討を要する課題です。なぜなら、これは実際には原則ではなく、達成すべき目標に向けた規制だからです。
参考となる事例の一つとして、ドイツ連邦共和国政府の運営原則が挙げられます。ドイツ連邦共和国政府のモデルは米国とは大きく異なります。米国政府は大統領による意思決定の原則に基づいて運営されており、政府の構成員は大統領の顧問に過ぎないからです。
ドイツ連邦政府は、首相原則、部門原則、そして集団原則という3つの原則に基づいて運営されています。首相原則は政策原則とも呼ばれ、首相が政府活動の方向性、指針、政策を決定することを意味します。
分野別原則とは、首相が定める指針及び政策の枠組みにおいて、各大臣が担当分野の管理について全面的に主導権を握り、責任を負うことを意味します。この原則に基づき、首相は、特定の職務に携わる大臣が首相が定める指針及び政策に違反する場合を除き、省庁の活動に介入することはありません。
合議制の原則とは、政府の権限に属する事項は集団で議論され、多数決で採決されなければならないことを意味します。首相は、政府の他の閣僚と同様に、1票しか投票権を持ちません。
第三に、地方分権と権限委譲の問題です。
我が国ほど地方分権と権限委譲の話題が盛んに取り上げられている国は他にありません。地方分権と権限委譲の強化と推進は、政府と首相の指示のもとで常に言及されており、国家行政機関が効果的かつ効率的に機能し、国の社会経済発展の要請に応え、それに応えるための条件と前提として位置付けられています。
TCCP法案と地方自治組織法はともに、地方分権、権限委譲、権限付与といった問題を規定しているため、これは非常に有用です。これらの問題が適切に規定されれば、制度上の大きなボトルネックを打破できるでしょう。
この短い記事では、基本的に「分散化」と「権限付与」という2つの概念についてのみコメントします。分散化の概念は標準化されておらず、私の個人的な意見では、分散化という概念は存在しません。
長らく、私たちは地方分権の概念を、中央機関が長年行ってきた業務の一部を地方に移譲し、「地方分権化」するという意味合いでのみ用いてきました。例えば、1962年8月27日付の内閣府決議第94-CP号(省及び中央直轄市の行政委員会への経済・文化管理の地方分権に関する規則を公布)、1989年11月27日付の閣僚理事会決議第186-HDBT号(予算管理の地方分権に関する規則)、2020年6月24日付の政府決議第99/NQ-CP号(部門別・分野別国家管理の地方分権化の促進に関する規則)などが挙げられます。
「地方分権」という表現が国家運営における地方分権と権限委譲の促進に関する決議第4号で初めて用いられたのは2022年になってからであるが、同決議では地方分権と権限委譲が何を意味するのか明確に定義されていなかった。なお、これら2つの概念については、2015年の地方自治組織法にも規定されていたことに留意すべきである。
TCCP法案の草案では、政府、首相、大臣は人民評議会、人民委員会、人民委員会委員長に権限を委譲し、その権限下にある1つまたは複数の任務および権限を継続的かつ定期的に遂行させるものとされている。ただし、分権化される機関、組織、部署、または個人は、分権化された任務および権限の遂行結果について全責任を負うという原則に従って、法律で分権化が許可されないと規定されている場合は除く。
問題は、分権化された事務と権限は、分権化された機関または組織に依然として帰属するのか、ということです。また、法案草案には、分権化の条件が保証されていない場合、分権化した機関および分権者には、分権化した事務と権限の執行結果に対する責任があるとの規定が追加されており、この法案草案における「分権化」の概念の曖昧さを示しています。私の意見では、分権化は分権化のみであり、分権化がなければ委任となるため、混乱を招き、実践が困難なこのような分権化の概念を導入すべきではありません。そして重要なのは、このような規定は、分権化、委任、分権化の順序を含め、各国の制度とも整合し、類似しているということです。
第四に、省庁および省庁レベルの機関について
省庁や省庁レベルの機関の概念は多くの変化を遂げてきたと言えますが、まだ完全に適切ではないようです。
1961年の内閣組織法では省庁の明確な定義は存在せず、「大臣、省庁レベルの機関の長は、その責任範囲内ですべての業務を統率する」とのみ規定されている。
1981年に閣僚評議会の組織法において初めて、大臣に割り当てられた部門または仕事分野の国家管理の責任が規定されました。
1992 年の TCCP 法第 22 条では、「省庁および省庁レベルの機関は、全国の部門または業務分野に対する国家管理の機能を実行する政府機関である」と定義されています。
2001年のTCCP法では、公共サービスにおける外国の経験を参考に、第22条に次のように規定されている。「省庁および省庁レベルの機関は、全国の部門または業務分野の国家管理機能、部門および分野の公共サービスの国家管理機能、および法律の規定に従って国有企業における国有資本の所有者を代表する政府機関である。」
14年後、2015年国家資本管理法第39条では、省庁および省庁レベルの機関を、全国で1つまたは複数の部門、分野、および当該部門または分野の公共サービスの国家管理機能を実行する政府機関と定義する際に、国家資本所有者の代表について言及されなくなりました。
このTCCP法の改正は、2015年省庁及び省庁級機関法の規定を維持するものと予想されます。もしそうであれば、以下のようないくつかの問題が生じます。
- 分野別公共サービスの国家管理を担当する省庁に関する規定は、実際には冗長である。なぜなら、分野別公共サービスの国家管理には、既に公共サービスの国家管理が含まれているからである。例えば、保健省が保健分野を管轄するということは、保健省が医療の国家管理を担当することを意味する。医療においては、公立病院が国民に医療サービスを提供しており、これは医療という公共サービスである。
- つまり、公的サービスの国家管理について言えば、保健省は民間医療サービスの国家管理を管理していないということですか?確かにそれは保健省の責務ですが、規制されていません。もちろん、広い意味では、民間医療サービスの国家管理は、保健省が管轄する全国の保健分野における国家管理の範囲内にあります。
省庁および省庁レベルの機関の重要な機能の一つは、公共サービスを提供する責任であるが、これは省庁および省庁レベルの機関という概念には反映されていない。保健省は、保健省に代わって国民への医療・診察・治療サービスを提供するため、複数の公立病院を管轄下に置いている。同様に、文化体育観光省は、文化、娯楽、芸術などの分野で社会に公共サービスを提供する複数の公共サービス機関を有している。
したがって、省庁のより明確で標準的な定義はまだ存在しないものの、1992 年の TCCP 法の規定が最も適切であることがわかります。省庁または省庁レベルの機関とは、全国規模で特定の部門または業務分野の国家管理機能を実行する政府機関です。
各国は省庁の機能をどのように規制しているのでしょうか?
私たちは長い間、地方分権化の概念を、地方分権化の意味合いに沿ってのみ使用してきました。つまり、中央機関が長い間行ってきた作業の一部を地方に移譲し、「地方分権化」するのです。
日本の運輸安全法では、省庁の責任を定義する際に、次のような一般的な公式を使用しています。省庁は、内閣の管理と統制のもとで行政事項を行うために設立されます。
韓国では、省庁の責任を定義する際に、様々な分野で「担当事項」という一般的な表現が用いられている。例えば、同国の経済協力法(TCCP法)第27条では、「財政経済部は、経済政策、通貨、財政、国宝、政府会計、内国税制、関税、外国為替、経済協力、国有資産の策定、総括検査及び調整に関する事項を所管する」と規定されている。
タイの2002年省庁再編法は、省庁の責任を定義する際に「各省庁は以下に関する権利と義務を有する」という一般的な表現を用いています。例えば、同法第10条は「財務省は、公共財政、資産評価、政府支援の管理、政府所有不動産および国宝に関する活動、税金、手数料等に関して権利と義務を有する」と規定しています。また、第14条は「観光スポーツ省は、観光産業、スポーツ、スポーツ教育の奨励、支援、発展に関して権利と義務を有する」と規定しています。
第五に、政府機関について
政府機関の定義が初めて提案されたことは評価に値します。省庁や省庁級機関という概念が存在するため、政府機関という概念を定めることは極めて重要です。TCCP法改正案では、政府機関を「政府によって設立され、政策の実施、国家運営への奉仕、公共サービスの提供といった機能を担う機関」と定義しています。
このように、この種の機関は、上記の3つの機能のいずれかを担っています。これを、ベトナムの声、ベトナム通信社、ベトナムテレビ、ベトナム科学技術アカデミー、ベトナム社会科学アカデミーの5つの政府機関に当てはめて、適切かどうか考えてみましょう。適切かどうかは一概には言えません。さらに、政策実施とは何かを明確にする必要があります。法律は、「政策実施」という一般的な概念を単純に規定し、後から好きに理解・説明できるようにすることはできません。国会は法律や決議を可決することで政策を公布します。政府も政令や共同決議を発布することで政策を公布します。では、どの政府機関がどの機関の政策を実施しているのでしょうか?そして、なぜ政府機関は法律を執行しないのでしょうか?
政策実施機関という概念は、1988年以降、公務員制度の改革と革新を目指して「執行機関」モデルを導入した英国での経験を参考にして生まれたと考えられます。「執行機関」とは、大まかに「執行機関」と訳される、政府省庁傘下の機関であり、公共サービス、研究、規制など、いわば「実施」を担当します。この種の実施機関には、組織、人事、そして特に財政において、かなりの自主性が与えられています。
したがって、英国の執行機関の重要な点は、執行にとどまるという概念ですが、私たちの行政法案では、政策の執行、国家管理への奉仕、公共サービスの提供という概念が追加されています。
[広告2]
出典: https://moha.gov.vn/tintuc/Pages/danh-sach-tin-noi-bat.aspx?ItemID=56873














































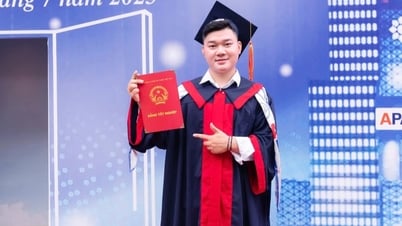




















































コメント (0)