産業フィルタリングか排出量削減かという現在の重要な問いに対する答えとして、トラン・ドゥ・リッヒ氏は次のように述べた。「私たちに残された道はグリーン経済だけですが、現在の重要な課題は排出量削減です。グリーン経済への移行という目標に向けた政策メカニズムが欠如しているため、あらゆる産業を排除することは不可能であり、産業フィルタリングか排出量削減かという問題を提起することは非常に現実的です。」
30年にわたる政策立案の経験を持つトラン・ドゥ・リック氏は、政府が企業に何かを求めるなら、政策と法制度を整備する必要があると結論づけました。企業は、その政策が有益だと判断すれば行動しますが、リスクがあったり有益でなかったりすれば、誰も実行しません。では、今最も欠けているものは何でしょうか? トラン・ドゥ・リック氏によると、最近開催されたグリーン経済、特にネットゼロに向けた循環型経済に関するフォーラムでは、ベトナムはグリーン経済政策の初期段階にあり、多くの行動計画が提示されていることが示されています。しかし、政策が不足しています。すべてのグリーン経済プロジェクトは、枠組みと方向性を確立するために法制化される必要があります。

ワークショップ「グリーン投資の誘致:産業フィルタリングか排出削減か」が本日5月12日に開催されました。
懸念事項として、欧米諸国は炭素証明書に非常に強く、こうした証明書の売買市場は非常に活発である。炭素証明書は非常に高価である。なぜなら、産業企業はこうした証明書の割り当てを受け、すべて使い切れない場合は他の企業に売却し、不足する場合は購入するが、これでは製品コストが上昇し、競争力がなくなるからである。したがって、企業は技術革新を行わなければならない。さもなければマイナスとなり、時間がかかればかかるほど、金銭的コストよりもマイナスの方が大きくなる。 天然資源・環境省のプロジェクトによると、ベトナムは2025年までに炭素市場を形成し、2028年までにこの市場を運営する計画である。これは早急に行う必要がある点だが、最も重要な問題は割り当てをどのように付与するかである。
トラン・ドゥ・リッヒ氏によると、2つ目の問題は、現在、排出量の最大の排出源がエネルギー部門であり、次いで農業、そして工業となっていることです。しかし、その見返りとして、ベトナムには森林が創出する炭素証明書の大きな可能性があります。現在、ベトナムには5,000万~7,000万トンの森林炭素証明書の埋蔵量があります。証明書1枚は、二酸化炭素換算で1トンの排出に相当します。これは国有資源です。これを活用すれば、国際的な交換となり、開発のための資源を生み出すことになります。森林は炭素証明書の非常に大きな供給源であるため、森林に影響を与えるものはすべてタブーです。
この精神に基づき、ホーチミン市はグリーン経済と循環型経済を強く意識し、主要な課題に取り組んでいます。まず、グリーン都市開発に伴うグリーン経済に重点を置いています。次に、この都市では温室効果ガス排出量、特に交通量が非常に多いため、バイクの削減を含む交通構造の改革を通じて、温室効果ガス排出量をどのように削減するかを検討しています。さらに、現在、17の旧式テクノロジーパークを輸出加工区に転換することを優先しており、5つの区をパイロットとして選定しています。エネルギーに関しては、付加価値単位あたりのエネルギー消費量の削減に重点を置いています。現在の統計によると、ベトナムはエネルギーを増やす必要はありませんが、30%節約できれば、温室効果ガス排出量を増やすことなく供給量を増やすことができます。ホーチミン市は、技術革新においてこの点に重点を置いています。
屋上電気についてですが、電力プログラム8は実施されていますが、太陽光発電などの再生可能エネルギーを増やすには蓄電池の設置が必須です。そうでなければ、気候や天候の変化によってすぐにバランスを崩してしまいます。これにはロードマップが必要であり、すぐに実現できるものではありません。さらに、市は廃棄物やバイオマス発電にも迅速に取り組んでいます。特に、決議98号は、ホーチミン市に炭素証明書の交換、排出量の寄与率の決定、交換のための予算投資を可能にするメカニズムを与えるものです。現在、市は政府からの法令と各省庁からの指示を待っています。法的根拠が確立されれば、政府の計画通り、2025年までに炭素市場が構築されることを期待しています。
「ホーチミン市にとって、グリーン経済、循環型経済、グリーン都市、あるいはもっと簡潔に言えば、グリーン経済、グリーントランスフォーメーション、そしてデジタルトランスフォーメーション以外に道はありません。これらはホーチミン市にとって極めて重要な2つの課題です。市は現在、国会決議98号を将来的に市の各分野に適用し、これらを推進しています」とトラン・ドゥ・リック氏は述べた。
[広告2]
ソースリンク









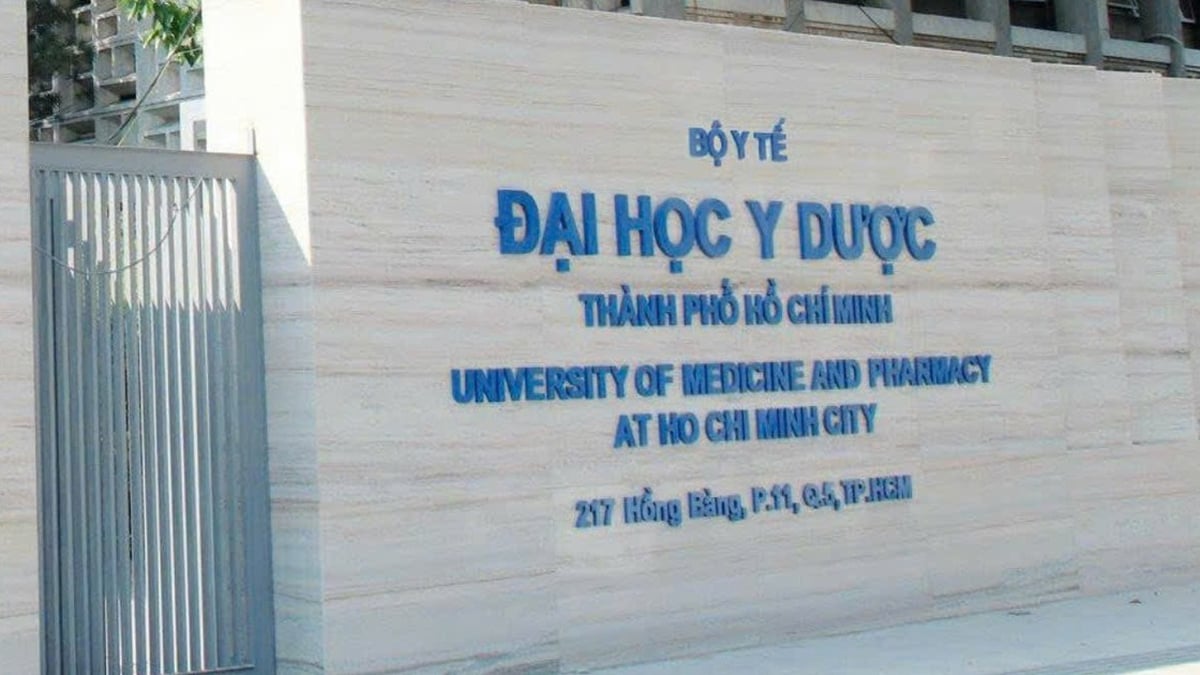

















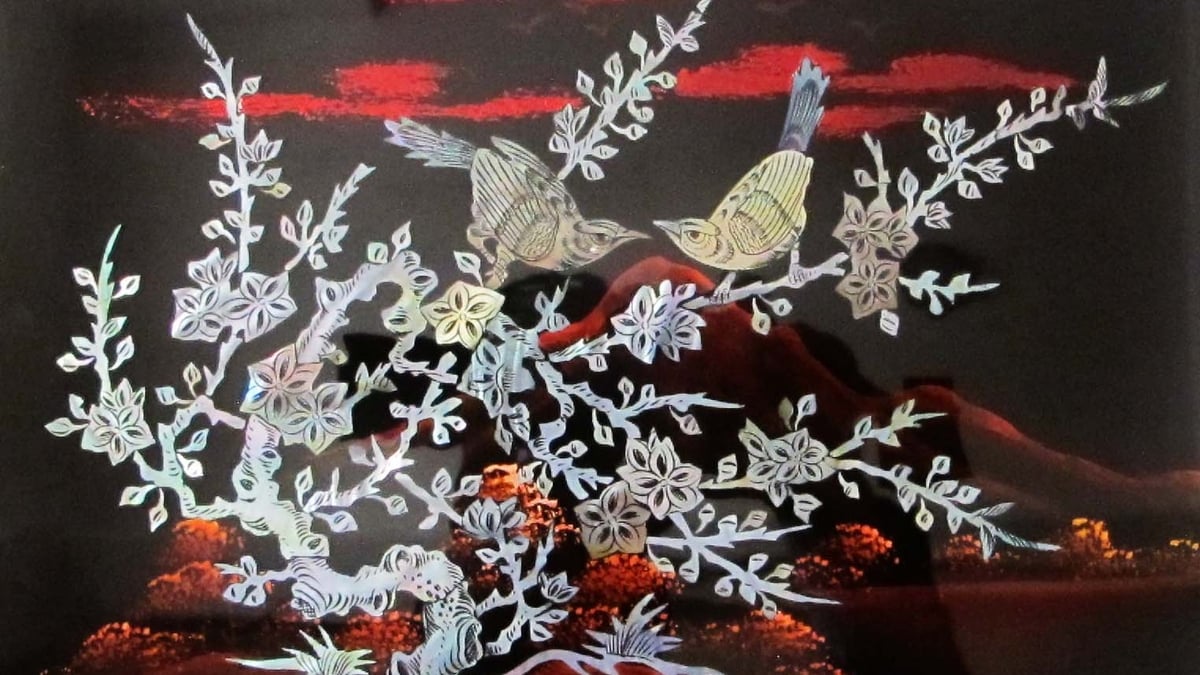






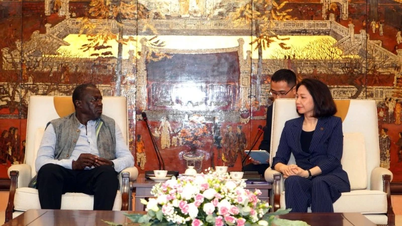



























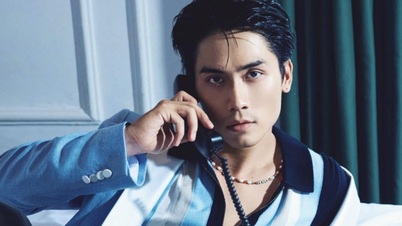



































コメント (0)