民衆が飢えに苦しんでいる中、彼は宣言した。「私は全国の民衆に提案したい。まず私が実行したいのは、10日ごとに1食断食、毎月3食断食することだ。貧しい民衆を救うために、1食につき1杯の米を摂取しよう。」
独立後、我が国は困難な状況にありました。この事態を解決するため、党と国家は人民の力に依拠し、大民族団結の力を奮い立たせました。特に、我が党は「抵抗と国家建設に関する指令」(1945年11月25日)を発布し、飢餓、文盲、そして外国からの侵略者と闘う大民族団結をさらに強化しました。

ホー・チミン主席は、 ハノイのルオン・イエン地区にある働く女性のための文化補習授業を視察した(1956年3月27日)。写真:アーカイブ
1949年10月15日に執筆され、真実新聞第120号に掲載された著書「大衆動員」の中で、 ホー・チ・ミン主席は次のように結論づけている。「大衆動員とは、国民一人ひとりの力を総動員し、一人たりとも取り残すことなく、人民全体の力に貢献し、なすべき仕事、政府と労働組合から与えられた仕事を遂行することである。」また、「大衆動員が巧みであれば、すべては成功する」とも指摘した。
「ゴールデンウィーク」は独立基金に寄付されます
1945年9月4日、内務大臣ヴォー・グエン・ザップはベトナム民主共和国臨時政府を代表し、「独立基金」設立に関する政令第4号に署名した。政令は、「ハノイおよび全国の各省に基金を設立し、国民の独立を支援するために政府に寄付したい金銭および物品を募る」こと、および「すべての募金活動および組織運営は財務省の管理下に置かれる」ことを規定していた。
政府は「独立基金」の枠組みの中で、1945年9月17日から24日までの「黄金週間」を計画し、国民、特に実業界からの支援を求めた。ホー・チ・ミン主席は、この件について明確にするため、全国の国民に手紙を送った。彼は次のように記している。「自由と独立を確固たるものにするには、全国の人々の犠牲と闘争が必要である。しかし同時に、国民、特に富裕層からの寄付も必要である。これが『黄金週間』の意義である」(『クー・コック新聞』第45号、1945年9月17日)

首都では、あらゆる階層の人々が「ゴールデンウィーク」を熱狂的に応援するために集まった。写真:アーカイブ
「ゴールデンウィーク」期間中、全国のあらゆる階層の人々から370kgの金と2,000万インドシナ・ピアストルが寄付されました。多くの研究者によると、当時の金の価格は1両400ドンだったので、2,000万ドンは5万両(約1,923kg)に相当します。つまり、「ゴールデンウィーク」には合計2,293kg、つまり59,618両の金が集まったことになります。
飢餓と闘う
1945年9月3日、ホー・チ・ミン主席は北部政府庁舎で政府評議会の初会議を主宰した。彼は6つの「最も緊急な問題」のうち、第一に「国民の飢餓」を挙げ、政府に増産キャンペーンを開始するよう提案した。
彼はまたこう提案した。「トウモロコシ、ジャガイモ、その他の食料が届くまでには3~4ヶ月かかりますが、その間、募金活動を行うことを提案します。10日ごとに、私たち全員が一食の断食を行います。節約した米は集められ、貧しい人々に分配されます。」
1945年9月中旬、政府は飢餓救済運動の開始を記念する式典を開催しました。式典はハノイのオペラハウスで開催されました。式典の議長を務めた愛国的な民族主義ブルジョワ階級のゴ・トゥ・ハは、飢えた人々を助けるために、すべての人々に食料と衣服を分け与え、各家庭で少量の米を分け与えるよう呼びかけました。
ゴ・トゥ・ハ氏は自ら荷車を引いて、ハノイのチャンティエン通りで飢餓救済運動に参加する人々を先導しました。どの家でも歩道には人々が並んでおり、米、トウモロコシ、お金を持った人がいました。一周もしないうちに荷車は米でいっぱいになりました。ホーチミン主席に会うためにオペラハウスに到着したゴ・トゥ・ハ氏は、荷車には赤米、白米、もち米、トウモロコシなど、あらゆる種類の米が混ざっていると報告しました。
当時のホー・チミン主席は、米の荷車を指差してこう言った。「これは大団結の米だ。我が国には美味しい米がたくさんあるが、今、これが最高の米だ。」
1945年9月28日付の救国新聞に掲載された全国の人民への手紙の中で、ホー・チ・ミン主席は次のように記している。「私たちがご飯を一杯手に取り、飢えや苦しみに苦しむ人々のことを思うと、心を動かされずにはいられません。そこで私は全国の人民に提案し、まず実行に移したいと思います。10日ごとに1食、毎月3食断食をしてください。そのご飯(1食につき1杯)を貧しい人々を救うために使ってください。」
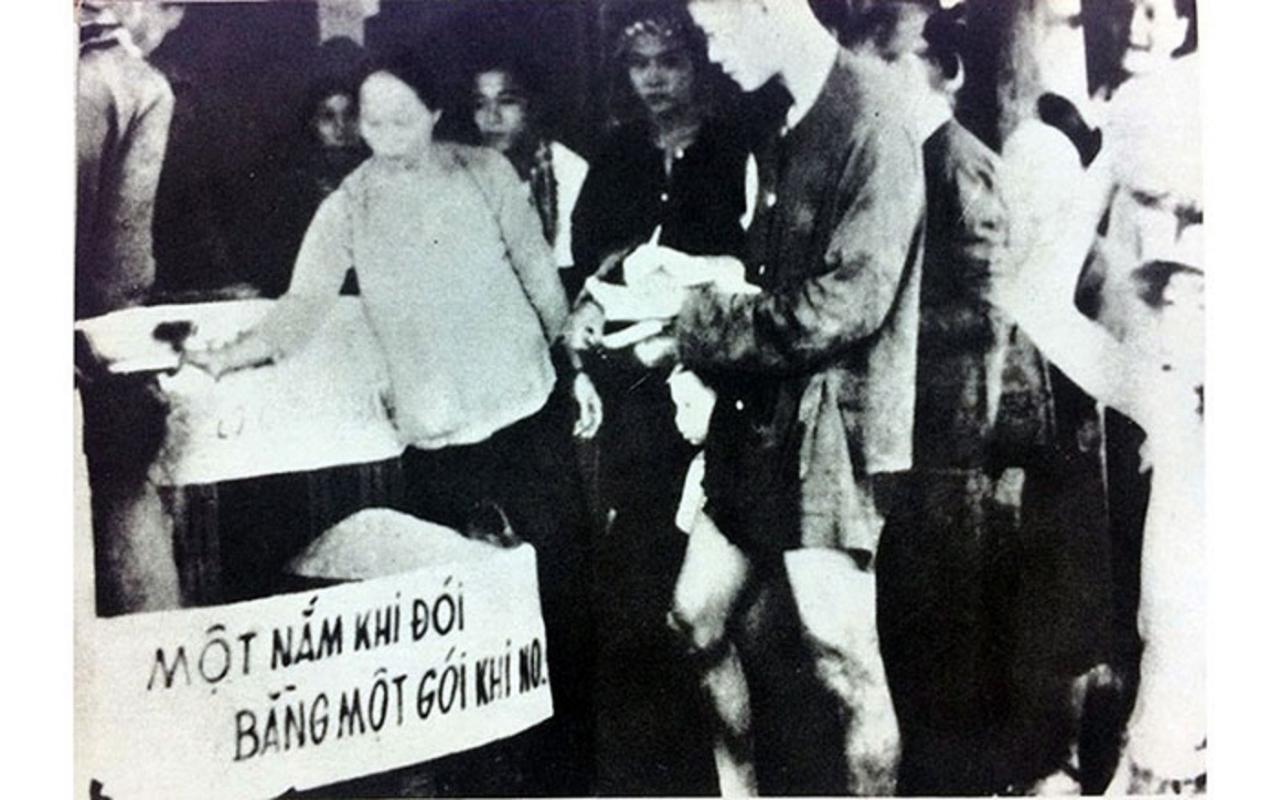
ホー・チミン主席の呼びかけに従い、各地の人々が飢餓対策のために米を寄付した。写真:アーカイブ
ホー・チミン主席の呼びかけに応え、我が人民は全国で「飢餓を救うための米壺」を設置し、「団結の日」を組織しました。それ以来、全国の人民から数万トンの米が寄付され、飢餓の災難に苦しむ同胞と分かち合ってきました。その後、ベトナム民主共和国政府は、投機や買いだめを行う者への厳重な処罰、ワインや菓子の製造など生活必需品以外の用途への米の使用禁止、米、トウモロコシ、豆の輸出禁止、南北間の米輸送を担当する委員会の設置など、一連の具体的措置を直ちに講じました。
1945年11月2日、グエン・ヴァン・トー社会救済大臣は飢餓救済協会の設立を決定しました。飢餓救済協会は村落レベルまで組織化されました。1945年11月28日、ホー・チ・ミン主席は最高救援委員会の設立を定める法令を発布しました。救援省に加え、他の多くの省庁も救援活動の任務を担いました。
1945年10月と11月、政府は洪水被害地域における地租を20%減額し、完全に免除する法令を発布した。国民経済省は、所有者不明土地、未耕作の公有地および私有地の申告、そして土地を持たない、あるいは土地が不足している農民への一時的な土地分配を規定する通達を発布した。
さらに、1945年11月19日、政府は生産を担当する中央委員会を設置しました。この時期には、生産指導のための新聞の発行、生産のための米や資金の貸付、家畜や家禽の世話をするための獣医の地方派遣、予算による破損した堤防の修復、堤防システムの強化、新しい堤防の建設など、多くの政策が同時に実施されました。
1945年12月、新聞「タック・ダット」に掲載された記事「ベトナムの農民へ」の中で、ホー・チ・ミン主席は生産増加の必要性を強調した。「食料が十分であれば軍隊は強くなる。耕作をすれば飢えることはない。『一寸の土地も一寸の金に値する』という格言を実践すれば、この二つの課題は必ず達成できる。生産を増やせ!」
今すぐ生産を増やそう!さらに生産を増やそう!これが今日の私たちのスローガンです。それが私たちの自由と独立を維持するための実践的な方法なのです。
1946年初頭には堤防工事が完了しました。堤防建設と並行して、各地域の当局と住民は、庭、歩道、堤防といった公共の空き地を、特に短期作物の栽培に適した土地として整備することに尽力しました。
そのおかげで、1945年11月から1946年5月までのわずか5ヶ月間で、主に穀物を中心とした食糧生産は米換算で50万6000トンに達し、1945年の食糧不足を補うのに十分な量となりました。飢饉はほぼ解消されました。1946年9月2日に行われた独立1周年記念式典(建国記念日)で、ヴォー・グエン・ザップ内務大臣は「革命は飢饉を克服した。これはまさに民主主義の偉業である」と宣言しました。
無知と戦う
1945年9月3日、臨時革命政府の初会合において、ホー・チ・ミン主席は国民の90%以上が文盲であることを指摘し、文盲撲滅キャンペーンの開始を提案しました。その後、人民教育局が設立され、6ヶ月以内にすべての村と町に「少なくとも一つの人民学級」を設置し、全国で国語の学習を義務付けることが定められました。
そして1945年10月4日、ホー・チ・ミン主席はすべての同胞に対し、文盲撲滅への闘いを訴えた。彼はこう記した。「独立を維持し、国民を強くし、国を豊かにするためには、すべてのベトナム国民が自らの権利と義務を理解し、国の建設に参加できる新たな知識を身につけ、そして何よりもまず国語の読み書きを習得しなければならない。」
人民教育運動により、250万人以上が読み書きを習得しました。これは、党と政府が非識字撲滅に向けた文化補習授業を継続していくための基盤です。ホー・チ・ミン主席が指摘したように、「社会主義とは、すべての人々に『学校に通わせること』です。」
グエン・ヴァン・トアン
ベトナムネット




![[動画] 100以上の大学が2025~2026年度の授業料を発表](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/18/7eacdc721552429494cf919b3a65b42e)




























































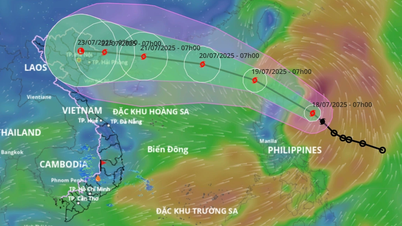



























![[インフォグラフィック] 2025年には47の製品が国家OCOPを達成する](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)





コメント (0)