
この出生促進策は保健省によって人口法案に盛り込まれており、6月12日まで審議されている。社会住宅は国が支援する住宅であり、複数の優先グループに低価格の住宅を提供することを目的としている。
上記の計画に加え、 保健省は、夫婦や個人が出産時期、子どもの数、出産間隔を決定できるようにすることを提案しました。女性労働者が第2子を出産する場合、産休を6か月から7か月に延長できるようにします。
同時に、各機関や団体は、結婚前の男女に対し、結婚生活、育児、子育てに直接関連するリプロダクティブ・ヘルスケアに関する知識を提供する責任を負います。各家庭が2人の子供を持つこと、子供を健全に育てること、そして不妊予防策に関する助言と指導を行うという価値観を強化します。人口政策や出生力維持のための施策の実施において、夫婦、個人、家族、そして社会の行動変容を促すため、広報、動員、コミュニケーション、 教育を推進します。
これらの解決策は、ベトナムの出生率が東南アジアで最も低い水準にあるという状況を踏まえ、保健省によって提案されたものです。ベトナムの出生率は現在、女性1人当たりわずか1.91人で、東南アジアで下位5位に入っています。地域平均(女性1人当たり2人)と比較すると、ベトナムの出生率はブルネイ(女性1人当たり1.8人)、マレーシア(女性1人当たり1.6人)、タイ、シンガポール(女性1人当たり1人)に次いで高い水準です。
出生率が人口置換水準を下回る省の数も急増しており、2019年の22省から2024年には32省に増加し、主に南東部とメコンデルタ地域に集中しています。ホーチミン市は依然として国内で最も出生率の低い地域であり、女性1人当たりの出生率はわずか1.39人です。ホーチミン市は5月初旬、35歳未満で2児を出産し、2024年12月21日から2025年4月15日までの間に第2子出産を予定している女性を審査・リスト化し、資金援助などの政策支援を開始しました。
保健省は、出生率が引き続き低下する中で、2039年までにベトナムの人口増加の黄金期は終わり、2042年には生産年齢人口がピークに達し、2054年以降は人口がマイナス成長に転じると予測している。
保健省は「長期にわたる低出生率は人口規模と構成に直接的に深刻な影響を及ぼし、労働力不足、人口減少、高齢化の加速、移民流入の増加など多くの結果をもたらすだろう」と述べた。
専門家らは、ベトナムの出生率が史上最低水準にまで低下しており、今後も低下し続けると予測している。この傾向には多くの原因があるが、主に経済的な圧力によるものだ。元人口総局(現人口局)通信教育局副局長のマイ・スアン・フオン博士は、インフレを背景に住宅や、ミルク、おむつ、教育、医療など一連の生活費への懸念が、多くの人々が子供を持つことを遅らせたり、拒否したりする原因になっていると分析した。例えば、ハノイでは住宅やアパートの価格が驚くべき速さで上昇しており、購入や賃貸は容易ではなく、住宅費は非常に高額である。
出生率の低下はベトナムだけでなく、中国、韓国、日本など世界各国でも問題となっています。各国は出産を促進するために様々な政策を変更しており、例えば世界で最も出生率が低い韓国は、出産促進プログラムへの予算を3倍に増額するとともに、子供を持つ家庭に多額の補助金を提供しています。ハンガリーでは、4人以上の子供を出産した女性は、生涯にわたって個人所得税が免除されます。
TH(VnExpressによると)出典: https://baohaiduong.vn/de-xuat-phu-nu-sinh-du-hai-con-duoc-ho-tro-nha-o-xa-hoi-412541.html



































































































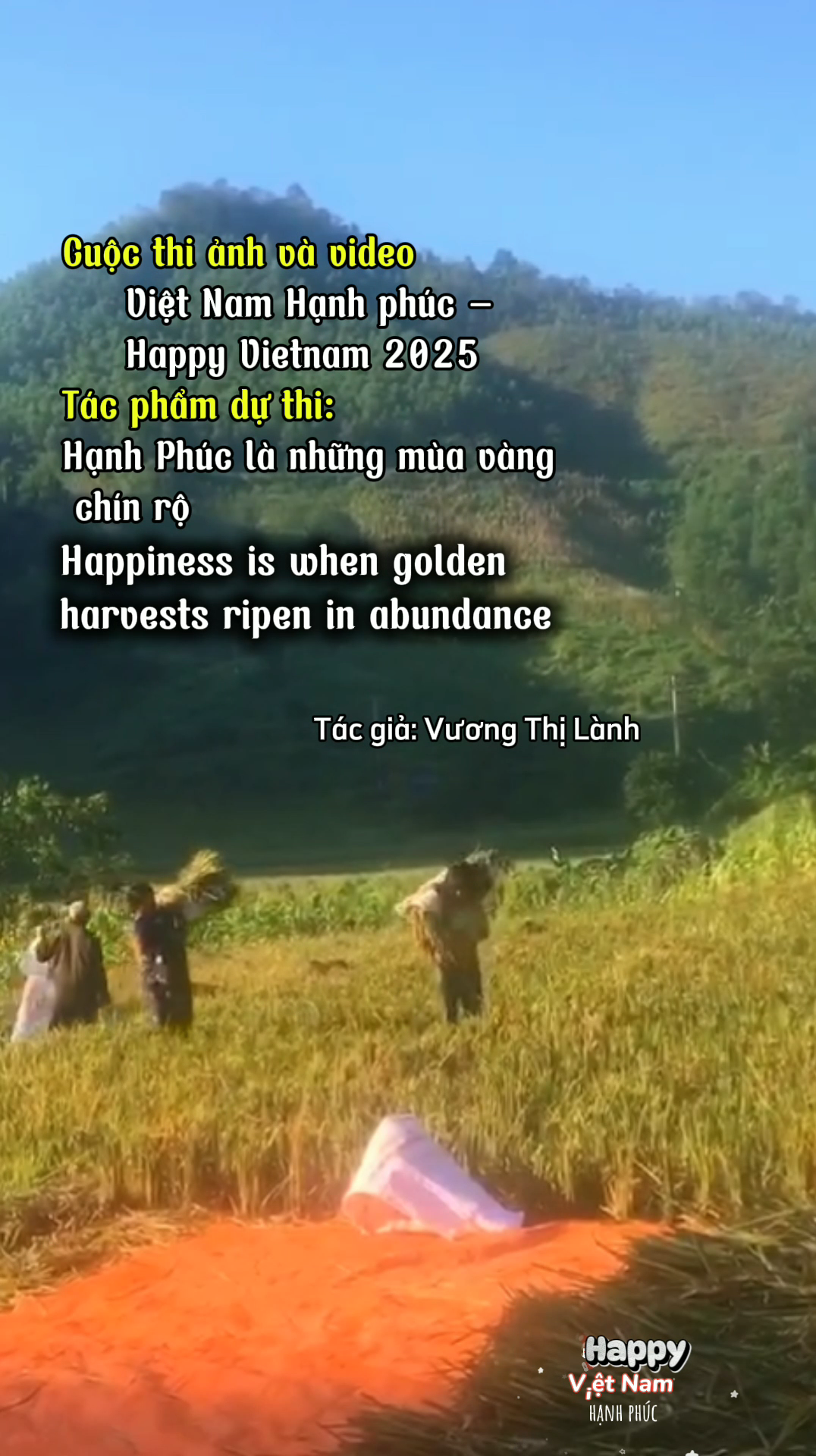

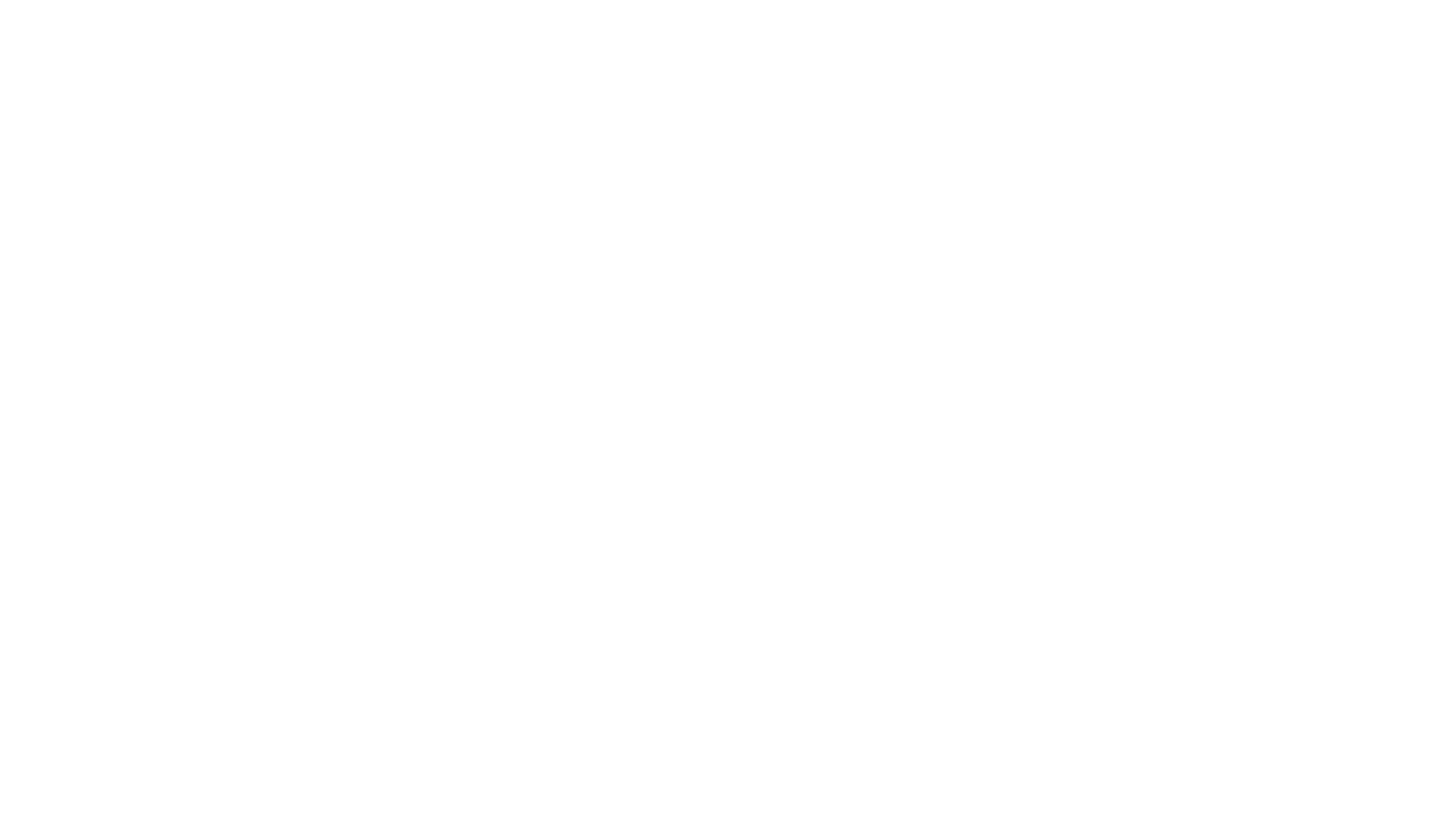

コメント (0)