
高い貧困率
ラーフー族はライチャウ省ムオンテ地区の 5 つのコミューン (パ ベ ス、パ ウー、カ ラン、ブム トー、ナム カオ) に集中して住んでいます。 2019年に行われた53少数民族の社会経済調査の結果によると、現在、ライチャウ省のラフ族は2,952世帯、12,113人を擁している。
数十年前、ラ・フ族は常に放浪の遊牧生活を送っていました。農業もあるが、自然に頼りすぎているため安定性がない。通常、農耕シーズンが終わって小屋の屋根を覆う葉がまだ黄色くならないうちに、彼らは別の地域へ移動し、新たな狩猟と採集のシーズンを始めます。
党と国家の注目により、ラ・フ族は徐々に深い森から抜け出し、密集した地域に居住し、村を形成した。これまで何年もの間、党と国家の投資政策、地方当局の配慮、苗木への支援、農業と畜産への技術支援のおかげで、ラ・フ族の人々の生活は貧困から抜け出し、以前に比べて改善されてきました。しかし現実から学ぶと、貧困と飢餓は依然として人々を永遠に悩ませ続けるのです。
ダー川を遡り、川に沿って進むと…ムオンテ県ブントコミューン、ピンコー村( ライチャウ省)に着きます。ピンコー村の地理的な位置は、上を見れば山しか見えず、下を見れば深い淵と鬱蒼とした森しか見えず、気候は極めて厳しいというものです。
村の幹部に続いて、私たちはフォン・キー・メさんの家を訪問しました。それは家と呼ばれていましたが、実際には小屋のようにいくつかの木のパネルが組み合わさっただけのものでした。中には、いくつかの古い家庭用品と薄暗い電球以外、貴重品は何も入っていませんでした。 50歳を超えているが、フン・チー・メ夫人は非常に厳格な印象を受ける。彼女の夫は早くに亡くなり、息子も亡くなり、彼女は2人の小さな孫を「育て」なければなりませんでした。長年にわたり、彼女の生活は国家の援助に依存してきました。 「私の家族は貧しく、家には何もないので、主に政府の支援に頼って暮らしています」とミーさんは打ち明けた。
ピンコー村はブン・ト村の中心地近くに位置し、165世帯が暮らしているが、そのうち140世帯が貧困世帯である。プン・チー・メさんの家族のような困難は、この村では珍しいケースではない。集約的な農業や生産の技術をどのように適用すればよいか分からないために人々が貧困や飢餓に陥っている理由に加え、社会悪が長年にわたって存在してきました。このコミューンには麻薬中毒者が90人おり、そのうちピンコー村だけで30人いる。
ピンコー村長のフン・ジョー・ソさんはこう語った。「村人のほとんどは麻薬中毒のため、いまだに貧困に苦しんでいます。中には家族全員が麻薬中毒になっている人もいます。そのため、土地や家屋はすべてアヘンと引き換えに売却されてしまうのです。」
ブム・トはラ・フ族の人口が多く住む集落で、860世帯以上、約3,600人が暮らしている。過去数年、コミューンは国から投資を受けた多くのプログラムやプロジェクトを受け入れましたが、それらは望ましい結果をもたらさず、貧困率は依然として80%を超えています。
ブントゥ村人民委員会のヴァン・フー・チョ委員長は、「ラ・フ族は、決定第449号に基づく特別保護政策の対象となる民族ではないため、ラ・フ族に対する一部の政策が削減され、特に学生支援やラ・フ族の文化保存といった政策に関して、人々の飢餓撲滅と貧困削減の実施が困難になっている」と述べた。

閑散期の「借りて返す」悪循環
毎年6月頃の収穫期になると、パ・ヴェ・スー村(ムオン・テ県)のラ・フ族の多くの家庭は「米が全部なくなる」という状況に陥ります。サピン村のジャン・ア・デさんの家族のように、2019年以降貧困からは脱したものの、食糧不足は依然として起きている。 「我が家には2サオ以上の米がありますが、夫と私にはそれほど多くの食料を育てているわけではありません。毎年、収穫期には米を借りて生き延びなければなりません」とデさんは言います。
約30平方メートルの簡素な家の中に座って話をしていた西鎮村の呂高胡さんは、彼の家族は現在両親2人と子ども3人の5人家族で、貧しい家庭で、家族全員が数枚の田んぼの稲作に頼っているが、食べるのに十分ではないと話した。毎年、農作物が収穫できない季節になると、胡さんの家族は飢えを避けるために国からの米の支援に頼らざるを得ない。
「資格が限られているため、安定した仕事に就けません。夫と私は、家族のために収入を増やすために必要なことを何でもして、誰かに雇ってもらえるのを待っているだけです」と胡さんは打ち明けた。

ソテン村長のリー・ガ・チュ氏は次のように述べた。「これまで、党と国家は人民を大いに支援し、飢饉期には米を配給することさえありました。人々の経済生活は主に稲作と畜産に依存しています。しかし、人々の教育レベルと意識が低いため、作物の生産性は低く、畜産も発達しておらず、生活は非常に困難です。」
現在、ソテン村には109世帯があり、そのうち81世帯が貧困層だ。多くの世帯は、農作物の少ない時期に飢えるだけでなく、新しい稲作が始まる前にも食糧が不足し、借金返済のために米を売らなければならないため、収穫直後に米がなくなることさえあります。
「米がなくなると、彼らは雇われて働いたり、借金をして米を買ったりするなど、生き延びるための他の手段を見つけなければなりません。こうした手段は日々の飢えをしのぐのに役立ちますが、一時的なもので、不安定なものです」とチュー氏は語った。
このように、借りては返すという行為は、国境のパヴェスー村だけでなく、ムオンテ県への取材旅行中に私たちが会う機会があった、ラ・フ族の人口が多い他の多くの村でも、ラ・フ族にとって悪循環となっている。

パヴェスー村の書記長、リー・ミ・リー氏は次のように述べた。「村全体では818世帯、3,084人が暮らしており、そのうち約70%がラ・フ族です。多額の投資にもかかわらず、ラ・フ族の生活は依然として非常に困難です。現実的に見ると、ラ・フ族は他の民族に比べてスタート地点がはるかに低く、さらに後進的な習慣を持ち、耕作地もほとんどなく、完全に自然に頼った生活を送っています。…そのため、現時点でラ・フ族を支援するには、少数民族全般に対する国の民族政策プログラムや投資支援に加えて、ラ・フ族が徐々に立ち上がり、生活を完全に変えられるよう、長期的な具体的政策が必要です。…」
特別な困難を抱える民族集団に対する投資政策の有効性




![[写真] クアンガイ省でのチャン・ドゥック・ルオン元大統領の葬儀](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/25/ccf19a3d8ea7450bb9afe81731b80995)
![[写真] ハノイ、「シャークジョーズ」ビルの解体をフェンスで阻止](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/25/1b42fe53b9574eb88f9eafd9642b5b45)
![[写真] エア・イエン村の入植計画が中止](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/25/57a8177361c24ee9885b5de1b9990b0e)
![[写真] フランスのエマニュエル・マクロン大統領夫妻、ベトナムへの公式訪問を開始](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/25/03b59c7613144a35ba0f241ded642a59)













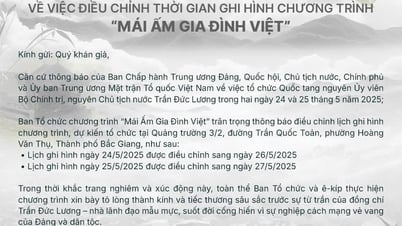











































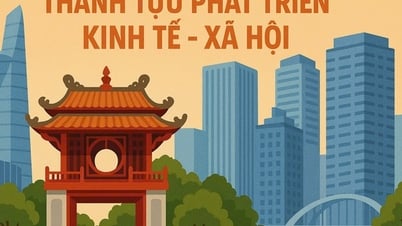


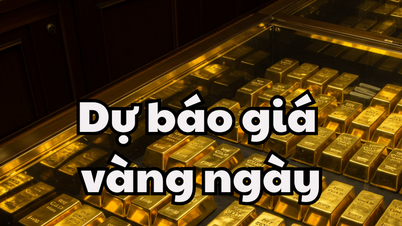
















コメント (0)