
このワークショップは、ファム・フォン・チ准教授が議長を務め、文学研究所が主催し、国立科学技術開発基金(NAFOSTED)が後援する国家プロジェクト「ポストコロニアル東南アジア文学と国家メタファー」(コード602.04-2023.01)の一環です。
ファム・フォン・チ准教授は序論報告の中で、ベトナムの学者にとって、東南アジア諸国における外部の文化や政治に支配されない、あるいは支配されない独立した文学の存在は、最も苦痛で悩ましい研究課題であるようだと述べました。
これらの作品で一貫して主張されているのは、民俗文学が先住民族文化とともに、外部からやってくる文化的・文学的力を受け入れ、相互作用するプロセスを方向付けるフィルターとして、基本的な役割を果たしているという主張である。

一方、東南アジア諸国の古代、中世、近代文学では、地元の芸術家が新しいものを吸収し、伝統を適用して独自の文体と自国の文学のテーマを創造する努力により、外国の勢力(東洋と西洋の両方)との衝突や、さらには支配が描かれることが多い。
東南アジア文学を研究するこのような傾向は、ベトナムの科学者の国民文学に対する責任を反映しており、それはまた国民文化に対する責任でもあります。
「このワークショップでは、植民地時代以降の国家建設の過程にある東南アジア諸国における近代化、階級分裂、人種対立、宗教対立、ジェンダー固定観念、環境・生態学的批判といった問題に取り組むことができる文学的表現とイメージとして東南アジア文学を取り上げます」とファム・フオン・チ准教授は語った。
彼女によれば、このアプローチにより、会議は、いまだに周縁的と見なされている東南アジア文学を世界の文学地図上でより明確に位置づけることに貢献したいと考えている。

さらに、このワークショップは、読者を「国家」という純粋に政治的または純粋に感情的なカテゴリーの概念を超えて、なぜ私たちは偶然同じ国に住んでいる人々に対して、他の国に住んでいる人々よりも愛着や親しみを感じられるのか、なぜ私たちは他の国で生まれた人々よりも同じ国で生まれた人々のイデオロギーに共感できるのか、一度も会ったことのない人々のために自らを犠牲にする人がいるのかなど、知的好奇心を喚起することができます。
本会議は、多様性に富み、様々なアプローチによって常に意味づけられてきた東南アジアの文学風景の様相や瞬間を明らかにすることを約束します。会議で取り上げられる事例研究は、西洋の理論家や批評家が提唱する文学・民族理論を裏付け、あるいは対話することになるかもしれません。
これは大規模で学際的かつ地域的な科学会議であり、特に文学、アイデンティティ、政治、国家建設のプロセスの相互作用において、東南アジアの文学研究における新たなアプローチを結集します。
学術会議は2つのセッションに分かれ、ホアン・ト・マイ博士が議長を務めた第1セッションでは、文学の観点から移民、都市化、脱植民地化の問題を探る研究成果が発表されました。
ド・ティ・フオン氏(文学研究所)のプレゼンテーションでは、作家ニック・ホアキン氏(フィリピン)の小説「二つのへそを持つ女」を例に挙げ、女性キャラクターがいかにして国境を越えたシンボルとなり、アイデンティティの葛藤と歴史的記憶の力を反映しているかが示されました。
ワークショップでは、非常に興味深い問題も取り上げられました。それは、現代東南アジア文学における都市の象徴的構造です。ハン・ティ・トゥ・ヒエン氏とレ・ティ・ンガー氏(フン・ヴォン大学)による現代ラオス短編小説の研究、そしてダン・レ・トゥエット・チン氏によるアルフィアン・サアット氏(シンガポール)とグエン・ティ・トゥ・フエ氏(ベトナム)の作品に関する研究は、都市のイメージがもはや静的な背景ではなく、ジェンダー規範、結婚制度、そしてポストコロニアル社会における個人のアイデンティティの変容を問う文学における意味論的なツールとなっていることを示し、都市の象徴性はもはや静的な背景ではなく、文学においてジェンダー規範、結婚制度、そして個人のアイデンティティの変容を問う意味論的なツールとなっていることを示しました。

もう一つの興味深い点は、ド・ハイニン(文学研究所)が「統一後50年におけるベトナム文学における国民意識」という問題を提起した点です。この研究は、特に戦後および現代文学において、国民的言説が集団的な英雄像からより私的で断片的かつ内省的な声へと大きく変化したことを明らかにしています。
ド・ハイ・ニン博士が議長を務めた第2セッションでは、研究対象が民族主義理論、歴史的伝統、そして近代以前の文学へと拡大されました。チャン・ドゥック・ユン氏(ハノイ教育大学)の発表では、リー・トラン文学における「正当化の方法」が論じられ、中世文学が単なるプロパガンダの道具ではなく、倫理基準、秩序、そして文化的権力を創造する手段でもあったことが示されました。文芸評論家のドアン・アン・ドゥオン氏は、20世紀初頭の言語と出版の近代化に向けた多くの取り組みの中で、グエン・ヴァン・ヴィンの問題を提起しました。
近現代文学研究の分野では、ルー・ゴック・アンが『ナム・フォン』誌について、そしてこの雑誌がE・ルナンやA・フイエをどのように受け止めたかについて論じ、翻訳、書き直し、国家建設とイデオロギー変容のプロセスとの複雑な関係を指摘している。
現代文学における記憶と国家的シンボルへのアプローチの選択。グエン・ティ・ホン・ハンは、レー・クアン・トランの短編小説の中で水牛のイメージを国家的メタファーとして用い、一方、レー・ティ・フオン・トゥイは、女性の髪の毛という問題を提起する。一見純粋に美的要素であるように見える髪の毛だが、ベトナム文化においては、その髪の毛はアイデンティティとジェンダーの層を内包している。
いくつかの論文は、グエン・フォン・アンとファム・フォン・チ(アユ・ウタミとグエン・カック・ンガン・ヴィの比較)、あるいはマイ・ティ・トゥ・フイエンとレー・ティ・ドゥオン(ベトナムの抵抗詩における感情的共同体に焦点を当てた)のように、非常に異文化・学際的な内容となっています。これらの論文は、涙が集団的な苦しみ、回復力、そして追悼の象徴であり、文学を通して国民的アイデンティティを構築する過程において不可欠な要素であることを示しています。
さらに、比較的観点からのカンボジア文学、ラオス文学、日本文学の研究(タン・ヴァン・トン、クオン・ヴィエット・ハなど)も、東南アジア文学の理論地図の拡大に貢献し、ブロック内のつながりと現代研究における学際的研究の重要性を強調しています。
ワークショップは、記憶、感情、象徴性という観点から、国家形成における文学の役割を浮き彫りにすることに寄与しました。東南アジア諸国はそれぞれ異なる歴史的、言語的、地政学的特徴を有していますが、いずれも複雑なポストコロニアルの現実を共有しており、文学は現実との衝突の中で絶えず自らを再定義していくことを求められています。
このイベントは、活発な学術交流の場を開き、文学は歴史の外にあるものではなく、情熱、思考、深い感情をもって歴史を書き換える方法であるということを証明するのに貢献しました。
出典: https://nhandan.vn/hoi-thao-ve-van-hoc-va-xay-dung-quoc-gia-o-dong-nam-a-post896943.html










































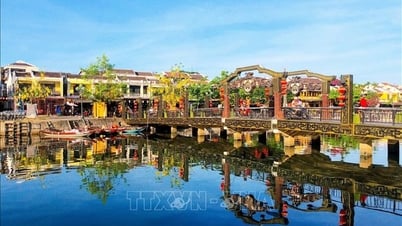



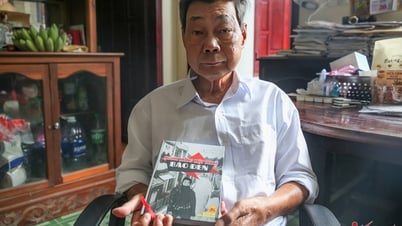




























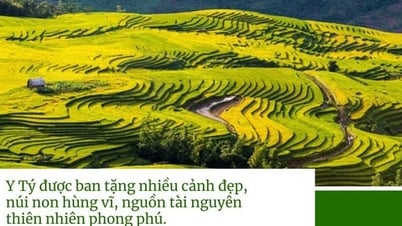
























コメント (0)